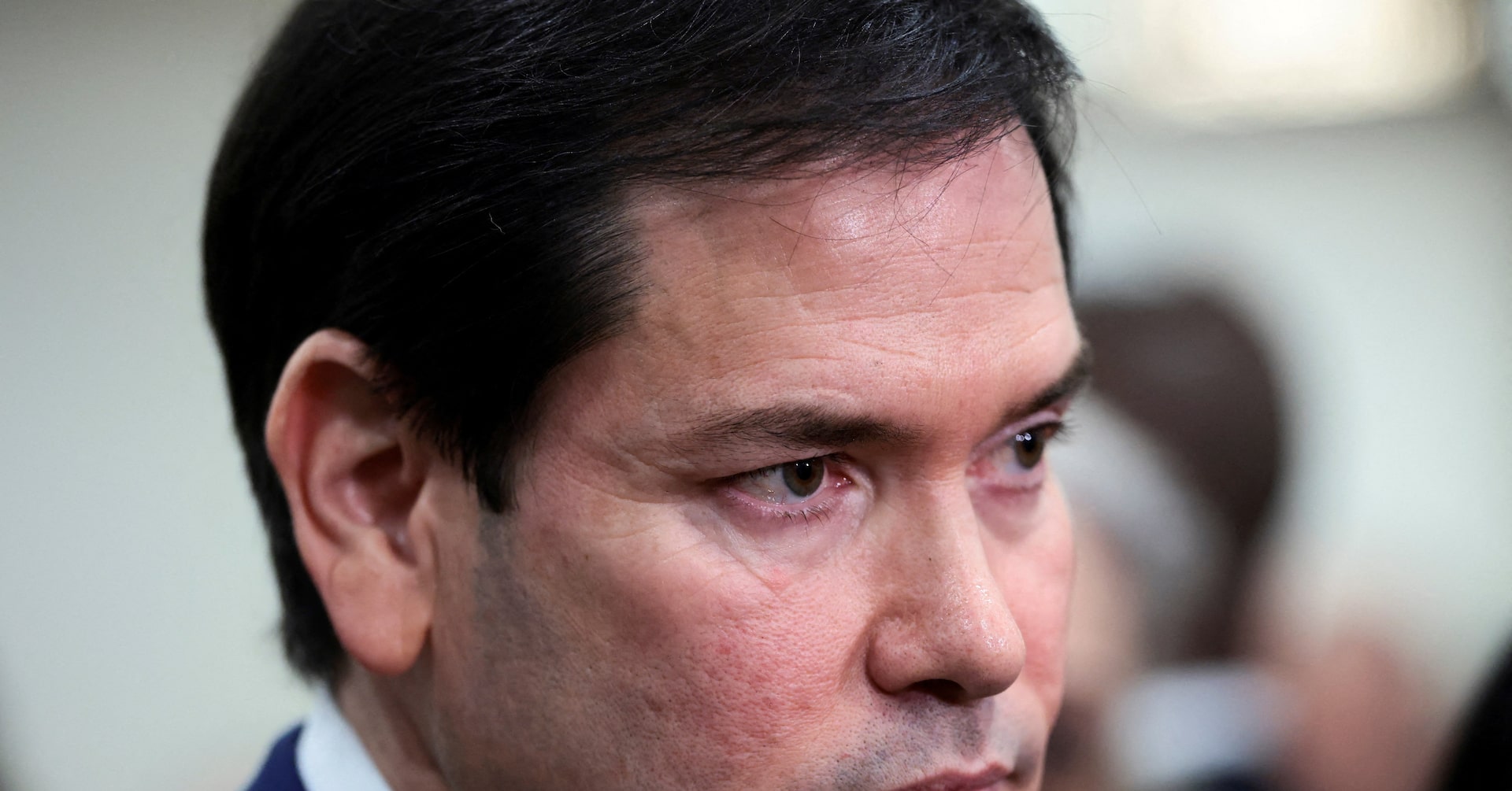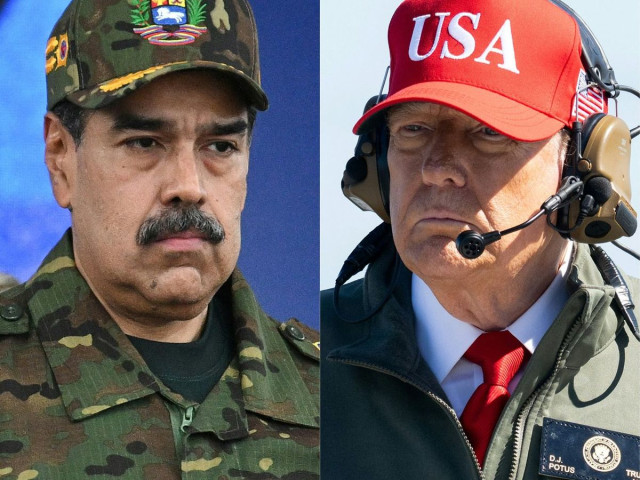アメリカは中国と何を争っているのか 対岸の火事とは思えない「グレー戦争」の行方 <潮流快読>中国系動画投稿アプリ「TikTok」巡る動向を読む

もしもスマートフォンを通じて自分の情報が収集され、行動を誘導されたら-。
安全保障上の懸念から、中国系動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の米国での利用禁止につながる新法が1月に発効したが、トランプ氏は大統領就任日に新法の執行を延期した。米企業や投資家が50%の所有権を持つことが望ましいという。
誰がサイバー空間を支配するか
ティックトックは、短い動画を公開できるアプリ。音楽に合わせて踊ったり料理をしたり、他愛のない動画を若者が楽しんでいる。だが、第2次トランプ政権の国務次官に指名された著者による『サイバー覇権戦争』ジェイコブ・ヘルバーグ著、川村幸城訳(作品社)では「アメリカ国内にサイバーセキュリティ上のリスクをもたらしている」と断定している。
『サイバー覇権戦争』(作品社)ユーザーが公開した動画が「顔認識アルゴリズムを改良するための材料になる可能性」を指摘する。また、親中的なコンテンツを優遇しているとみられる事例も挙げる。
著者は2016~20年に米グーグル社で偽情報・外国政府介入に対する方針作成に従事。本書では、16年の米大統領選を前にしたロシアのハッカーの活動を、先端テクノロジーを用いる「グレー戦争」の始まりに位置づけた。
帰趨は情報ネットワークや通信テクノロジーを誰が支配するかで決まるといい、端末画面の情報のコントロールを巡る「ソフトウエア戦争」と情報インフラを巡る「ハードウエア戦争」の2つに分けて詳説。ハード面は主に中国との間で行われているという。
『テクノ封建制』(集英社)ネット上の「地代」徴収権
ティックトックを巡る動向を経済面から説明するのが『テクノ封建制』ヤニス・バルファキス著、関美和訳(集英社)だ。著者はギリシャの経済学者。第1次トランプ政権が中国テクノロジー企業を締め出した措置の名目が、安全保障上の懸念とされたのは「偽装にすぎない」との見方を示す。
巨大テック企業が支配する「テクノ封建制」では、市場がデジタル取引プラットフォームという「封建領地」に変わり、利潤は「レント(地代)」に置き換えられたと主張。プラットフォームやネット上のデータ保管場所にアクセスするための場所代を「クラウド・レント」と呼ぶ。
ティックトックは、中国へクラウド・レントを吸い上げる。国境を越えてクラウド・レントが徴収される世界で、米国が覇権を維持するには中国のクラウド領主と対決するしかないというわけだ。
『SNS時代の戦略兵器 陰謀論』(ウェッジ)影響力工作に利用される陰謀論
日本のネット空間の現状はどうか。安全保障の観点からソフト面を日本の研究者が論じているのが『SNS時代の戦略兵器 陰謀論』長迫智子・小谷賢・大澤淳著(ウェッジ)。
陰謀論が国家による影響力工作に利用され、日本でも新型コロナウイルス禍やウクライナ戦争を背景に影響力を強めていると指摘する。ワクチンを巡る誤情報の発信と親露的投稿が重なっているという分析結果もあるそうだ。
安全保障を脅かした事例として、昨年2月に東京で開催された日ウクライナ経済復興推進会議の直前、真偽不明の情報がSNSで拡散されたことを挙げている。対岸の火事とは思えない。(寺田理恵)