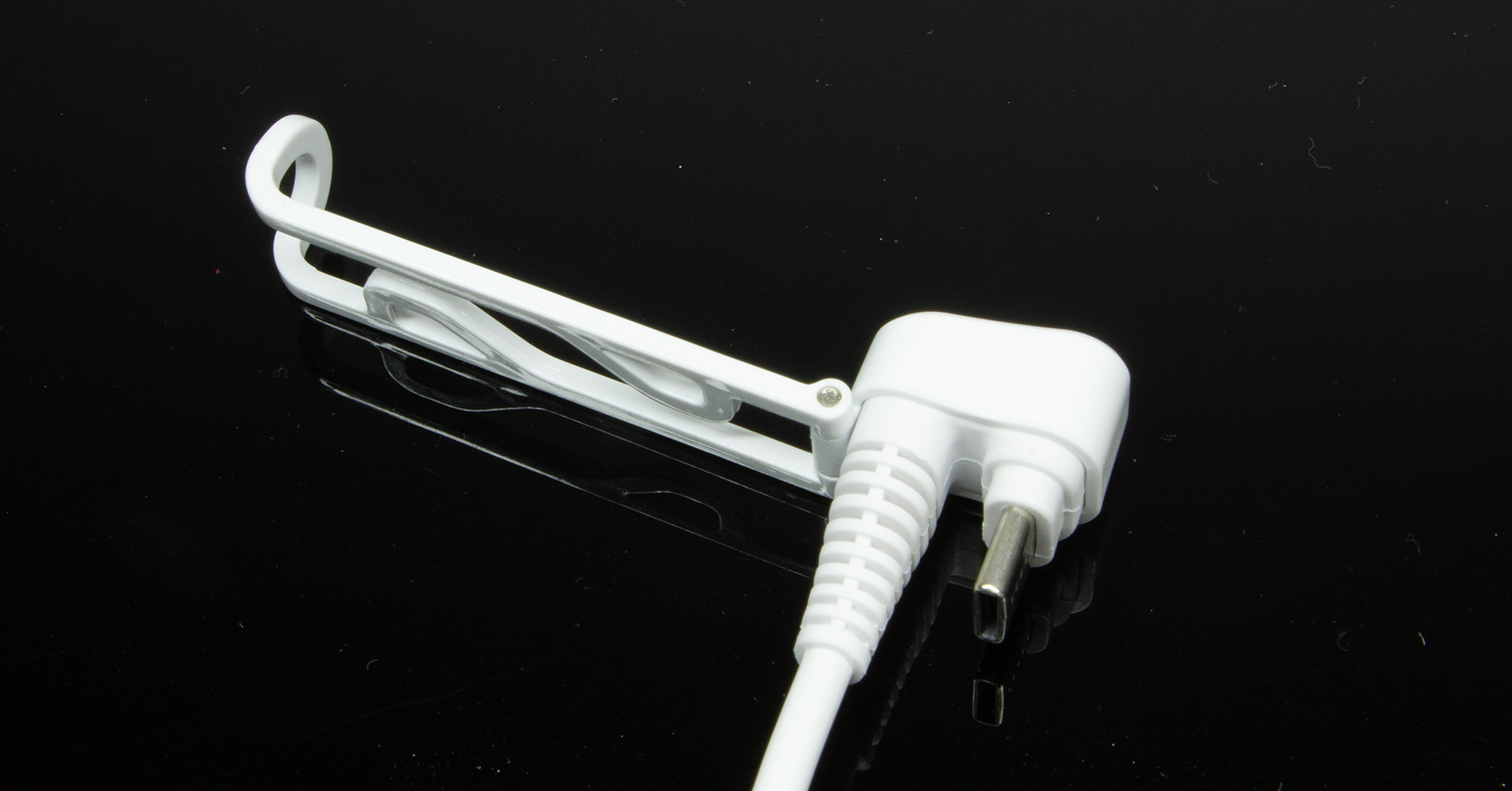これぞ「ものづくり大国日本」の再来だ…トヨタでも日産でもホンダでもない、世界の注目を集める自動車メーカー テクノロジー見本市で魅せた"日本の活路"

筆者の印象としては、CES2025において、最も存在感を示していたのがエヌビディア(NVIDIA)である。
基調講演に登場したエヌビディア創業者でCEOのジェンスン・フアン氏は、AI処理性能を大幅に高めた次世代GPU「Blackwell」の量産開始や、コンパクトなAIスーパーコンピュータ「Project DIGITS」、自律走行車やロボティクスなどの開発加速を支援するフィジカルAI(物理AI)プラットフォーム「NVIDIA Cosmos」といった新商品を発表した。最先端のAI開発・活用にはエヌビディアのテクノロジーが必須であるという景色が自然と見えてくる形になった。
筆者撮影
エヌビディア創業者兼CEO・ジェンスン・フアン氏の基調講演の様子
CES2025では、エヌビディアの存在が他社のさまざまな取り組みを見る際の“眼鏡”の役割を果たしたと感じる。つまり、各社が出展している技術や製品・サービスをエヌビディアが提示する世界観や、現実に提供しているサービスを基準として評価できるというわけだ。
この“エヌビディアの眼鏡”を通して筆者が感じたところでは、AI関連の出展のうち、4分の1以上は内容がすでに陳腐化しており、プロジェクト自体が頓挫してしまうだろうと思われた。
2025年、「AIエージェント」の時代がやってくる
エヌビディアの発表を見ていて確信したのは、いよいよ2025年には「AIエージェント」の時代がやってくるということだ。AIエージェントとは、簡単にいうなら、人間に代わってAIが自律的に判断・行動するシステムのことである。
AIは、人間と対話しながら文章や画像などさまざまなアウトプットを出す「生成AI(ジェネレーティブAI)」から、AIエージェントに代表される「自律型のAI(エージェンティックAI)」へと発展し、物理的な世界とデジタル世界を融合する「フィジカルAI」へと至る流れで進化している。
AIエージェントが普及すれば、企業では業務の目標や遂行に必要となる要素をAIみずから理解し、人間が介入することなく自律的に仕事をこなしてくれるため、効率化や生産性向上に大きく寄与する。一般消費者の世界でも、例えば旅行を計画する際、AIエージェントが適切な計画を編み出し、宿泊先や交通機関を選び、かつ予約や支払いまで自動で行ってくれるようになる。まさに「人間は旅に出るだけ」の世界観を実現できるだろう。
筆者撮影
「AIエージェント」の実例
これまで筆者が見てきたところでは、2022年頃までのCESは「3~5年後の未来の世界」を展開していたが、CES2023からは「現在進行形」へとシフトした。CES2025も引き続きその傾向を強めており、AIエージェントの分野でもマイクロソフトやアマゾン、グーグル、そして日本の富士通など多くの主要企業が参入している。そのため、筆者は2025年にAIエージェントがtoBを中心に普及する可能性が高いと予測していた。
Page 2
前述の「2025年の世界」5大ポイントのうち3、4点目はとりわけモビリティと縁が深い話だ。CES2025でもモビリティの3大トレンドとして「電動化」「コネクティビティ」「自動運転」が取り上げられた。
自動運転に関しては「Autonomous Vehicles : The Future is Finally Here(自動運転の未来がついにここに来た)」と題するセッションが行われていた。まさに“ここに来た”と表現している通り、アメリカでは自動運転サービスが現実にスタートしている。
自動運転といえば、ゼネラル・モーターズ(GM)傘下のクルーズ(Cruise)が開発した自動運転車両が路上に倒れていた女性をひいてしまい、世界的なニュースとなった。そのため、日本でも自動運転は難しいと考えている人は多いかもしれない。実際、この事故は一部で「クルーズ・クラッシュ」と呼ばれ、ゼネラル・モーターズはロボタクシー事業から撤退した。
その一方でグーグルの持株会社アルファベット(Alphabet)の傘下にあるウェイモ(Waymo)は、アメリカのサンフランシスコ、ロサンゼルス、フェニックスの3都市で無人自動運転のロボタクシーの商用運行を成功させ、その後も運行都市を拡大。2025年は地域をさらに増やす計画とのことだ。
筆者撮影
グーグル持株会社傘下「ウェイモ」の自動運転車
自動運転はいつ日本で実現するのか
日本でも、2025年からGo、日本交通とともに東京で自動運転実証を予定している。上記のセッションでもウェイモの話題が中心となっており、巨大な地球儀上に示された展開地域には日本もしっかり記されていた。2025年中の商用展開は難しいとしても、2026年には実現するのではないか。
筆者撮影
巨大な地球儀にはウェイモの日本展開が明記されていた
ウェイモのミッションは「Be the world’s most trusted driver」、すなわち世界で最も信頼されるドライバーになるということで、信頼性・安全性の実現に注力してきた。CES2025の基調講演に登場した共同CEOのテケドラ・マワカナ氏は、安全性の確保を最優先事項にあげていた。同社の展開地域を増やしている理由は、まさにその姿勢が評価されているからである。自動運転の仕組みにおいてもカメラ(映像)だけでなくLiDAR(光線)、レーダー(電波)と多様なセンサーを組み合わせ、信頼性と安全性を高めている。
こうした「安全性第一」の姿勢は、テクノロジーの成熟度、資金力、そして信頼構築における、ウェイモとクルーズの違いを如実に物語っている。
Page 3
ところが現実はその予測をさらに先回りし、1月24日、オープンAIがレストランや宿泊施設などの予約を自律的に行うAIエージェント「オペレーター」の提供を始めたとのニュースが飛び込んできた。今は試作段階で提供先もアメリカに限られるものの、すでに実用化のフェーズに入ったということで、日本でも2025年内に広まり始めることになりそうだ。
フアン氏は基調講演で「AIエージェントの時代がきた」と述べ、企業や組織がニーズに応じたAIエージェントをスピーディーに開発・展開できるフレームワーク「Agentic AI Blueprints」を発表した。そして、「企業のIT部門はAIエージェントのHR部門になる」と力強く宣言し、AIエージェントが職場生産性を支える中心的な存在になることを予測した。それはけっして何年も先の話ではないだろう。オープンAIの動きを見ても、2025年内には一部の日本企業でも個々の社員がAIエージェントを仕事の中で使うようになり、フアン氏が示した未来も近々実現するのではないか。
エヌビディアが描く「2025年の世界」とは
CES2025でエヌビディアが発表した内容を踏まえ、同社が描く「2025年の世界」を筆者が主な5つのポイントでまとめた。
まず、ここまで解説してきたように、AIが「知能化されたパートナー」としてビジネスや日常生活で普及していく。これは間違いのないところといえるだろう。
次に、ロボットやIoTデバイスがリアルタイムで物理的なタスクを実行し、環境と連携する新たな技術基盤である「フィジカルAI」がロボットなどを通じて製造・物流や医療、生活等の現場に入り始め、最適化に寄与するようになる。
3つ目が、NVIDIA Cosmosが自動運転やロボットの統合管理プラットフォームとして動き始める。
4つ目が、完全自動運転が実現して移動の民主化が達成される。
そして5つ目が、人間とロボットが共存する持続可能な社会が生まれる。
以上の5点である。
中国「ディープシーク」の衝撃
エヌビディアのビジネスに対するディープシークの影響を最後に考察したい。ディープシークは、従来よりも低コストで高性能なAIモデルを開発し、高価なエヌビディア製GPUに依存しない手法を採用している。このため、エヌビディアの株価は一時的に大幅に下落した。
写真=共同通信社
中国の新興企業「DeepSeek(ディープシーク)」が開発したAI新モデル=2025年1月27日
しかし、AI市場全体の拡大に伴い、エヌビディアの製品需要が増加する可能性も指摘されている。AI市場の成長とともに、エヌビディアのGPUが引き続き主要な計算資源として活用されるかどうかが今後の焦点となるだろう。
ディープシークの衝撃は、AI開発における巨額投資が必須であるとの従来の認識を覆し、米国の大手テクノロジー企業のAI投資戦略に再考を促す。同社のオープンソース戦略は、AI技術の民主化を推進し、世界中の開発者にとって新たな可能性を開くものだ。
もっとも、同社のAIが中国政府の検閲基準に従っている点は、技術の透明性と倫理性に関する議論を引き起こしている。今後に注目したい。
Page 4
このWaymoのすぐ隣に、日本のスズキがブースを展開していた。注目を集めるWaymoの真横では見劣りしてしまうかと思いきや、きわめて独自性の強い展示になっており、抜群の存在感を見せた。
スズキはCES2025のテーマに「Impact of the small」を掲げていた。CES2025向けサイトでは、このテーマの下に「小さなものづくりが、大きく社会を変える」というメッセージが加えられている。
会場で目を引いたのは、ブース内に掲示された「小」「少」「軽」「短」「美」の5つの漢字だ。意味するところは、コンパクトでシンプルかつ軽量・軽やかな製品を短期間で生み出し、その4要素の調和により美が生まれるということである。
さらに驚いたのは、「自動運転台車」を展示していたことだ。これは豪Applied EVと共同開発したもので、スズキの四輪駆動車「ジムニー」のラダーフレームをベースとしている。安全性とシンプルさを重視して設計されており、物流現場の効率化や人手不足に対応するソリューションとして、新たなモビリティの可能性を示した。
筆者撮影
スズキとApplied EVが共同で開発した自動運転電動台車
最新テクノロジーの世界で、日本企業は出遅れがちだといわれている。AIでも、また自動運転でも、プラットフォームづくりにおいては、先行するアメリカの巨大テック企業に太刀打ちできないだろう。
では日本企業の活路はどこにあるのか。今回のスズキの展示にこそ、そのヒントがあると感じている。スズキが示した「小」「少」「軽」「短」「美」、あるいは既存製品・サービスの繊細でかゆいところに手が届く改良といった、「日本の得意技」にさらに磨きをかけることで、今後のテクノロジーの世界でも日本が存在感を示し続けられるのではないだろうか。
筆者撮影
スズキが築き上げてきたものづくりの理念「小・少・軽・短・美」
(構成=斉藤俊明)