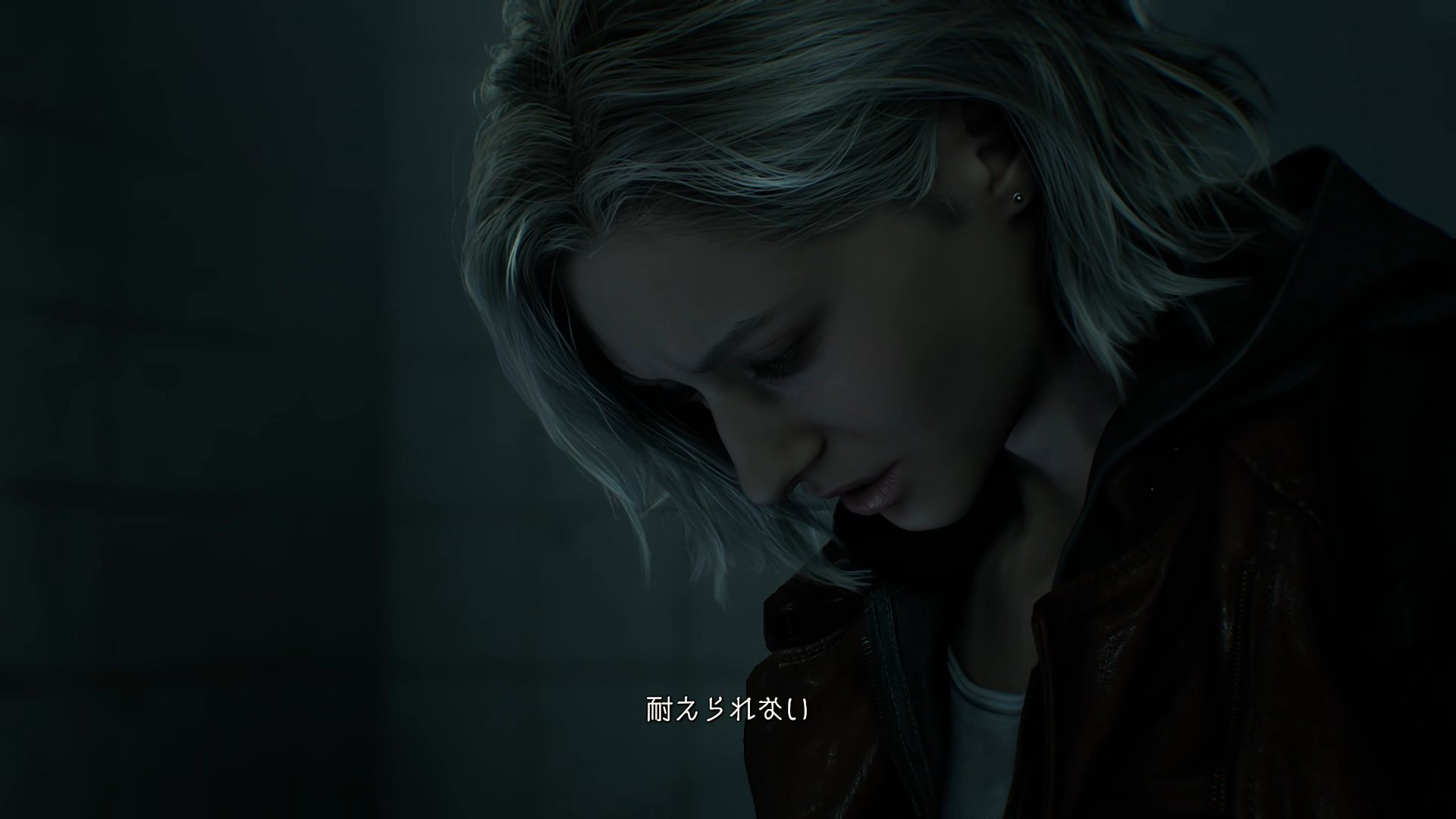【大河ドラマ べらぼう】第30回「人まね歌麿」回想 優れた治世、文芸に通じた白河藩の定信像 ドラマでは? 苦悩の歌麿を救った石燕のことば、「写生」が拓いた大作家への道

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の第30回「人まね歌麿」では、幕府の新たな権力闘争の構図と、真のアーティストへと脱皮しようとする歌麿の「生みの苦しみ」が並行して描かれました。
意次に陥れられた定信、敵意は強く
これからのストーリーのカギを握る人物として今回、改めて登場したのが、松平定信(1759∼1829、井上祐貴さん)です。今回のドラマで描かれた天明5~6年(1785∼1786)は、定信は26~27歳という若さです。田沼時代に続く「寛政の改革」を主導した人物として、教科書などでもおなじみの名前でしょう。8代将軍吉宗の血を引く御三卿の田安家の生まれで、ドラマの前半(第3回、第4回)では田安家を潰そうという田沼意次たちの権謀術数が功を奏し、本人の意に反して奥州の白河藩(現在の福島県南部)へと養子に出されてしまいました。
田安賢丸(のちの松平定信)を陥れる策略を意知と練る源内(第4回「『雛形若菜』の甘い罠」から)意次たちの企てを実現しようと、八代将軍吉宗の文書を偽造した平賀源内の大胆な計略を覚えていらっしゃるでしょうか。
「田安・一橋両家は跡継ぎがいない場合、お家断絶とする」とする将軍・吉宗の文書を偽造する源内。この文書の存在によって賢丸は田安家に戻れなくなりました。こうした経緯から意次への敵意が強かった定信。ドラマでは才気煥発で自信過剰気味。そして権力指向の強い人物としてまずは描かれていました。田沼側からは「癇癪小僧」と評されていました。
定信はのちに意次を追い落とし、老中だった際の寛政3年(1791)には、有名な筆禍事件で蔦屋重三郎(蔦重、横浜流星さん)と山東京伝(北尾政演、古川雄大さん)が罰せられます。禁制だった好色本の出版を咎められ、蔦重は財産の半分を召し上げられ、京伝は「手鎖50日」の罰を受けました。つまり幕府側、市中側双方で「べらぼう」のストーリーに大いに関わってくる人物です。
飢饉を乗り切り、公園を作り、「白河関」も見つけた
意次を牽制するため定信を引き立てて、幕政に関与させた一橋治済(生田斗真さん)は、折からの天明の大飢饉に触れて、「(定信は)見事な采配だった。奥州の他国が次々と飢えて死ぬ者を出すなか、白河では誰ひとり死ななかった」とその手腕を激賞しました。ドラマでは具体的に触れていませんでしたが、白河藩ではどんな君主だったのでしょうか。
定信の居城だった白河小峰城。大規模な石垣で知られ、盛岡城、会津若松城とともに石垣が有名ないわゆる「東北三名城」と言われます。定信が藩主当時、正確な図面を作成させており、戊辰戦争で焼け落ちたシンボルの三重櫓を復元する際に役立ちました。 豪壮な石垣が続く城内。みちのくににらみをきかせる幕府の重要拠点でした。白河藩主としての定信で、最も有名なエピソードはやはり天明の大飢饉にまつわるもの。天明2年(1782)から天明8年(1788)にかけて、東北地方で数十万人の餓死者を出したとされるこの飢饉では、定信はその最中(天明3年)に藩主に就任し、適切に対処したといいます。各地で米を買い集めたり、近隣の会津藩に米を融通してもらったり、裕福な商家や農家などに寄付を求めたりして食糧を確保。ひとりの餓死者も出さなかったと伝わっています。
そして彼の事績を巡る逸話はこれに留まりません。
南湖の湖水面積は17.7ヘクタール。周囲は約2キロ。那須連峰などを借景に、四季折々の景色が楽しめます。市民の憩いの場で、観光客にも人気の南湖公園。定信の命で享和元年(1801)に築造された大規模な庭園です。
身分の差に関係なく誰もが楽しめる「士民共楽」という理念のもと作られ、垣根はなく、武士も民も誰でも訪れることができました。当時としては画期的な庭園です。「南湖」という名称は李白の詩「南湖秋水夜無煙」に由来するといわれ、漢籍にも通じた定信の教養の幅広さを伺わせます。造成工事は領民の救済事業としての性格も持っていました。
「南湖十七景」といい、南湖に17か所の景勝地を定め、親しい公家や大名らにこれらを題名とした和歌や漢詩の作成を依頼して、名所としたのも定信です。文芸を深く愛する性格が現れています。
古典好きな方には歌枕としてお馴染みの「白河関」。能因法師の「都をば 霞とともに 立ちしかど 秋風ぞ吹く 白河の関」などで知られます。松尾芭蕉も「おくのほそ道」の序文で、白河の関を越えてみちのくへの旅をしたい、とその存在に触れています。また高校野球では東北勢が優勝に手が届きそうになると「優勝旗の白河関越えなるか」などとよく報じられます(2022年夏に仙台育英が東北勢として初優勝)。
みちのくへの出入り口として、古くから広く親しまれた白河関ですが、実質的な機能はかなり以前に失われており、江戸時代には場所もよく分からなくなっていました。定信は、領内にある名高い歌枕の場所が不明なままなのが残念だったのでしょう。調査を重ねて寛政12年(1800)、現在の史跡の場所を白河関跡と断定しました。
教育熱心で藩校の「立教館」を設立し、庶民が通える「敷教舎」も建て、町民らの子ども(女子も含む)に読書や算術を学ばせました。そのほかにも白河だるまや白河そば、南湖だんごなどの名物も定信由来とされるなど、「立派な殿様」に関するエピソードは枚挙にいとまがありません。今でも地元での人気は抜群です。
名物の「白河だるま」。こちらも定信公ゆかりと伝わります。白河の人たちの「べらぼう」への思いは?
定信を祀る神社まであります。南湖神社は大正11年(1922)に建てられました。地元の有志が活動をはじめ、その熱意にうたれて実業家の渋沢栄一らが多額の寄付をするなどして支援しました。渋沢が始めた数々の社会事業は、定信が寛政の改革で創設した積み立て制度「七分積金」の恩恵が大きかったことなどから、渋沢は定信を敬愛していました。
南湖神社 地元の有志や渋沢栄一らの尽力で建てられた南湖神社 定信の肖像画と中目公英宮司同神社の中目公英宮司は「一般的なイメージからすると、定信公は蔦屋重三郎を処罰するなど、当時の文化全般を弾圧して、庶民も締め付けたこわもての人、ということだと思いますが、当時の厳しい時代状況を考えると、ある程度社会に規律を求める方向に政治が動くのは致し方なかったと思います。定信公本人も好きでやっていた訳ではないでしょう」と言います。
その上で中目宮司は「白河で生まれ育った立場からすると、むしろ文化の大切さをよく知っている定信公だったから、蔦重は財産の半分を取られる処罰で済んだと感じます。他の人が幕閣の中心だったら、命を取られかねなかったのではないでしょうか。『べらぼう』でそのあたりの経緯がどのように描かれるのかが楽しみですし、ドラマを機会に定信公の真の姿を多くの方に知ってほしいです。ぜひ白河に遊びに来てください」と話していました。
「京伝先生は」と思わず口にしちゃう定信
文芸に通じた定信の特徴はドラマでもさっそく、表現されていました。冒頭、山東京伝(古川雄大さん)作の『江戸生艶気樺焼』を熱心に読んでいた定信。主人公の名前が「仇気屋」であることに引っ掛かり、「仇……。これは京伝先生は何かを穿っておるのか。仇…」とひとりごと。
町民の作家を「先生」と呼ぶところに、クリエイターに対するリスペクトが感じられました。先に触れたとおり、定信の老中時代に、京伝は蔦重とともに処罰されますが、そのあと定信と京伝とは交流するようになる、という複雑な経過をたどります。この場面はそうした一連の出来事への前触れの意味がありそうです。
定信を演じる井上祐貴さんは、「美術展ナビ」のインタビューに、「定信は文学の世界が本当は好きなのに、改革を進めなければならない。その葛藤も今後の見どころ。質素倹約政策を進める堅物な定信だけではなく、人間味あふれるシーンも森下さんが描いてくださった」と話しており、やはり深みのあるキャラクターに発展しそうです。これから森下先生やドラマ制作陣の描く定信像には大いに注目です。
定信は質素な「黒ごまむすび」をお弁当にクリエイターとしての歌麿の進化
今回のドラマのもう一人の主役は歌麿(染谷将太さん)でした。「人まね歌麿」として、世間にその存在が認知されてきました。
その大きなきっかけになったのは「狂歌絵本」。絵師が描いた絵に、狂歌師が歌を寄せる形式で、版元の企画主導で作られるタイプの狂歌本です。
天明6年(1786)の正月に発刊された「絵本江戸爵(えどすずめ)」は歌麿による絵本の初めての作品とされます。大胆な構図や印象的な身体の表現には、早くも歌麿らしい個性が見てとれます。
『絵本江戸すずめ』(江戸東京博物館所蔵) 天明六年刊(1786)出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100414287 『絵本江戸すずめ』(江戸東京博物館所蔵) 天明六年刊(1786)出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100414287 『絵本江戸すずめ』(江戸東京博物館所蔵) 天明六年刊(1786)出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100414287蔦重、いよいよ好機到来とみて、より作家性の強いオリジナルの作品を作るよう、歌麿に強く促します。
第4回「『雛形若菜』の甘い罠」から。磯田湖龍斎の原稿を汚してしまう事態に、唐丸少年(のちの歌麿)が寸分たがわず模写して、蔦重をピンチから救ってくれました。自分の内面と向き合わずに創作はできない
幼少期の唐丸にとてつもない才能を見い出した蔦重は、「おれが当代一の絵師にしてやる」と約束。ついにその宿願を実現するタイミングがきたのです。歌麿も蔦重の情熱にほだされ、覚悟の絵筆をとりました。ところが……。
歌麿、必然的に自分の過去と向き合うことになります。
歌麿の母、そしてその愛人のヤスの幻影に悩まされます。歌麿の筆舌にし難い半生が思い起こされます。
下級遊女の夜鷹だった母。堕胎しようとしてもおろすことが出来ず、生まれてきたのが歌麿でした。事あるごとに母から「なんで生まれてきたんだ」と罵倒され、生活のために年端もゆかぬ頃から男に身体を売る仕事までさせらました。傍らにいたのが母の愛人のヤス。母による暴力も年々、ひどくなる一方でした。
「このままじゃ殺される」と思っていた歌麿。明和の大火の時に建物の下敷きになった母を見捨てて逃げました。
自らの罪深さに火に巻かれて死ぬ覚悟をしますが、蔦重に助けられます。
しかし過去を知るヤスに見つかり、脅されて、せっかく築いた吉原の安住の地を手放さざるを得なくなります。
川にヤスを突き落し、自らも身を投げますが、死に切れませんでした。その後は蔦重がその存在に気付くまで、身分を隠した絵描きの仕事や、身体を売るなどして暮らしました。
どんな表現活動でも自らの内面と向き合うことは必要不可欠でしょう。歌麿も、こうした過去の出来事から逃れて筆を執ることはできないのです。
「人殺しならではの絵なんて誰が見てえんだ」と心の叫びを吐露する歌麿。蔦重、歌麿の過去を知るだけに、歌麿を追い詰めてしまった自分を省みます。
歌麿を救った石燕の存在
「人まね歌麿」の絵をみて、「これはあの子では」とピンときた人がいました。かつて、少年期の歌麿に絵を教えた妖怪画の巨匠、鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)です。居ても立っても居られず、著書の版元の耕書堂を訪ねてきたのでした。
「なんで来なかった。いつ来るか、いつ来るかとずっと待っておったのだぞ。けどよう生きとったな。生きとった!」。再会を心から喜ぶ石燕の様子に、歌麿はひたすら涙。視聴者も思わずもらい泣きだったでしょう。石燕が歌丸を呼ぶ「三つ目」は、最初の出会いのとき、母にぶたれて額に大きな傷のあった歌麿を、「三つ目小僧」と表現したことから始まっています。
人から大切に思われる、ということが、行き場を失っていた歌麿の心を溶かしました。「覚えていてくれたのですか?ちょいと遊んだだけのガキのことを」と驚く歌麿に、「忘れるか、あんなに楽しかったのに」と石燕。思えばこの時、弟子入りするよう促すほど、歌麿の才能に惚れ込んでいたのですから、一緒に絵を描くのもワクワクする思いだったはずです。
第18回「歌麿よ、見徳は一炊夢」から。たまたま出会った石燕が描く妖怪絵を真似するうちに、歌麿は絵の世界の魅力に取りつかれていきました。蔦重から、歌麿の書きかけの作品を見せられた石燕。ここから怒涛の名セリフ連発でした。「あやかしが塗りこめられておる。そやつらはここから出してくれ、出してくれ、とうめていおる。閉じ込められ、怒り、悲しんでおる」と。石燕の目には歌麿の母やヤスの事も見えているようでした。
「その目にしか見えぬモノを表せ。それが絵師の務めだ」
「三つ目、なぜ、かように迷う。三つ目の者にしか見えぬモノがあろうに。」
「絵師はそれを写すだけでいい。写してやらねばならぬとも言えるが。見える奴が描かなきゃ、それは誰にも見えぬまま消えてしまうだろう。その目にしか見えぬモノを表してやるのは、絵師に生まれついた者のつとめじゃ」。
画家に限らず、表現活動に携わるあらゆるジャンルに通じることばでした。素晴らしい脚本の冴え。そして自らも画家として活躍する片岡さん、さすがの説得力でした。
すべてを受け入れてくれた石燕の言葉に圧倒された歌麿。迷いがなくなりました。「おれ、俺の絵が描きてえんです」。石燕に弟子入りし、蔦重とは離れることになりました。爽やかな旅立ちのシーンでした。
あやかし絵を描く石燕石燕に「その辺のものを描いてみろよ。持ってりゃそのうちなんか見えてくるさ」といわれ、一心不乱に植物の写生に取り組み始めた歌麿の姿が、またホロリとさせました。真の作家となる道が、開けてきたようです。
「写生」に開眼、世界が開けた歌麿
ドラマの時間から少しあとの天明8年(1778)、歌麿の代表的な作品のひとつが世に出ます。「画本虫撰(えほんむしえらみ)」です。こちらも狂歌絵本です。見開きにそれぞれ虫を描き、それにちなんだ狂歌を添えていくもの。今回のドラマの展開は、こうした歌麿の作品世界の変遷を踏まえて創作されたものでしょう。フィクションを交えつつ、見事なストーリーの流れでした。
『画本虫撰』(国文学研究資料館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200014778歌麿というと、美人画をまず連想される方が多いと思いますが、こうした動植物を描いた作品の完成度も素晴らしいのです。昆虫図鑑のような精密な描写と、モチーフを自在に配置して、画面を構成する力にほれぼれします。展覧会などでぜひ実物を見ていただきたい作品です。
『画本虫撰』(国文学研究資料館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200014778この力が圧倒的な魅力を放つ美人画などへ発展していきます。
『画本虫撰』(国文学研究資料館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200014778のちに妻となる女性(きよ、藤間爽子さん)との不思議な出会いも描かれました。歌麿の波乱に満ちた人生の旅路、まだまだ続きます。
(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>
視聴に役立つ相関図↓はこちらから