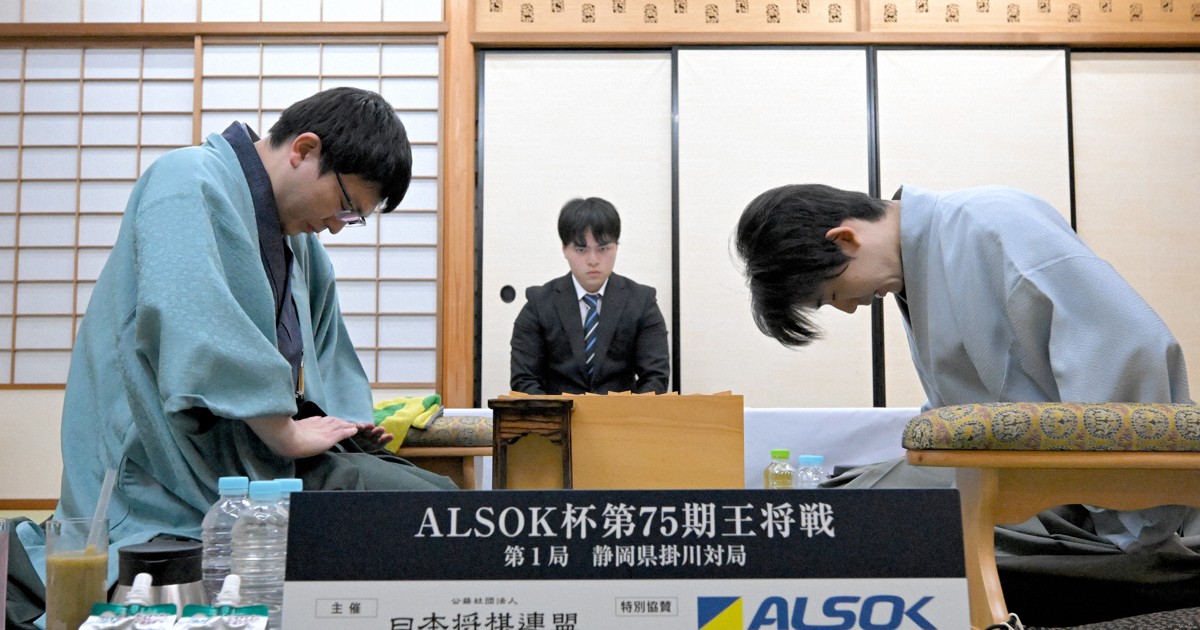飢えや寒さとの闘いだったシベリア抑留、やせ細って死んだ戦友…帰国後かぶりついた白米のおいしさ

東京都三鷹市 堀江弥太郎さん 104
東京都三鷹市の堀江弥太郎さん(104)は徴兵されて中国に渡り、24歳で終戦を迎えた。終戦後は旧ソ連のシベリアに抑留され、4年に及んだ抑留生活は厳しい飢えや寒さとの闘いだった。食事はわずかなパンとおかゆで、多くの仲間を栄養失調などで失った。
「死ぬ覚悟を決めて、頭を丸めた」。出征する時に使ったバリカンを手に振り返る堀江さん(東京都三鷹市で)戦前は東京で左官の仕事をしていました。21歳で徴兵後、中国北部に赴き、前線の警備などにあたりました。終戦の数日前、満州(現中国東北部)へ部隊が移動し、参戦したソ連軍の重戦車を迎撃することになりました。地面にたこつぼのような穴を掘っていた時、見習士官がやってきて、「戦争が終わった」と大声で告げました。ホッとして、手を止めました。
《1945年9月中旬、ソ連兵から「乗れ」と言われ、貨物列車に乗り込んだ。国境付近の日本軍の施設を取り壊した後、帰国すると説明を受けた》
車両に、すし詰め状態で乗せられました。毎朝1度、列車が止まるので、線路に下りて 薪(まき) を拾い、飯ごうでご飯を炊きます。それを3食に分けてちびちびと食べます。水をくんだ水筒に大豆を入れておくと、夕方には軟らかくなり、夕飯として食べます。その汁も豆茶のようで、甘く感じました。
それだけでは当然足りません。線路脇に現地の人がやってきて、時計などとパンを交換するのです。この時はまだ、「もうすぐ帰国できる」という希望を持っていました。
《10月1日、ソ連と中国との国境付近に到着し、大砲などを壊す作業にあたった。そこで帰国するはずだったが、列車は西へ進み、16日、東シベリア・イルクーツク州の駅に到着し、鉄条網が張り巡らされた収容所に着いた。経験したことのない寒さが待っており、炭鉱で作業する仲間は厳しいノルマを課された》
左官だった私は収容所の施設を建設する作業班となり、そうしたノルマはなく、左官の腕に助けられました。
朝は大きな洗面器に一度に3~4人分のおかゆが入れられます。他の人に取られないように急いで食べます。昼の分のパンも一緒に支給されるのですが、朝食が足りずに食べてしまう人もいました。翌日分を前日に配給された時、懐に入れて寝たのに翌朝盗まれていたこともありました。
雑穀のかゆと約350グラムの黒パン。「平和祈念展示資料館」(東京都新宿区)には、抑留者の証言を参考に再現した食事のレプリカが展示されているおなかが減るというのは本当に苦しいことです。馬のエサおけに入っていたおこげを取って食べる人もいました。厳しい作業ノルマと食料不足で骸骨のようになり、栄養失調で寝込む者が増えました。
中国にいた時の部隊から一緒で仲の良かった戦友もその一人でした。やせ細って部屋の隅に寝転がり、数少ない楽しみだったサウナ風呂の日に「もう行けない」と首を振るのです。翌朝、声をかけると返事がなく、すでに死んでいました。悔しくて涙が出ました。
初めての冬は毎日10人ほど死亡者が出て、死体置き場の遺体は天井まで届きました。この世の地獄でした。
《49年、いよいよ帰国することに。28歳になっていた》
帰国の船はナホトカから乗り、3、4日ほどかかって京都・舞鶴港に入りました。下船すると迎えの人たちが待っており、おにぎりと梅干し、たくあん、みそ汁を手渡してくれました。座って白米にかぶりつきました。その味は忘れられません。日本のコメは本当においしかった。平和な場所で食べるものほどおいしいものはありません。
60歳の頃に一度、旧ソ連へ行き、墓参りをしました。「俺はなんとか元気でやっているよ」。戦友たちに静かに手を合わせました。
戦後80年がたち、戦争のことを話す人も少なくなってきました。飢えに苦しむのが戦争です。皆さんに過去のことを一生懸命学んでほしい。それが私のお願いです。
◆ シベリア抑留 =第2次世界大戦後、満州(現中国東北部)や樺太にいた日本兵ら約57万5000人が捕虜となり、ソ連やモンゴルの収容所に連行された。劣悪な生活環境の下、鉄道建設などの重労働を強いられた。食事はわずかなパンと薄いスープの場合も多く、栄養失調で亡くなる人が続出した。飢えや寒さで約5万5000人が死亡したと推計される。抑留期間は数年から11年に及んだ。