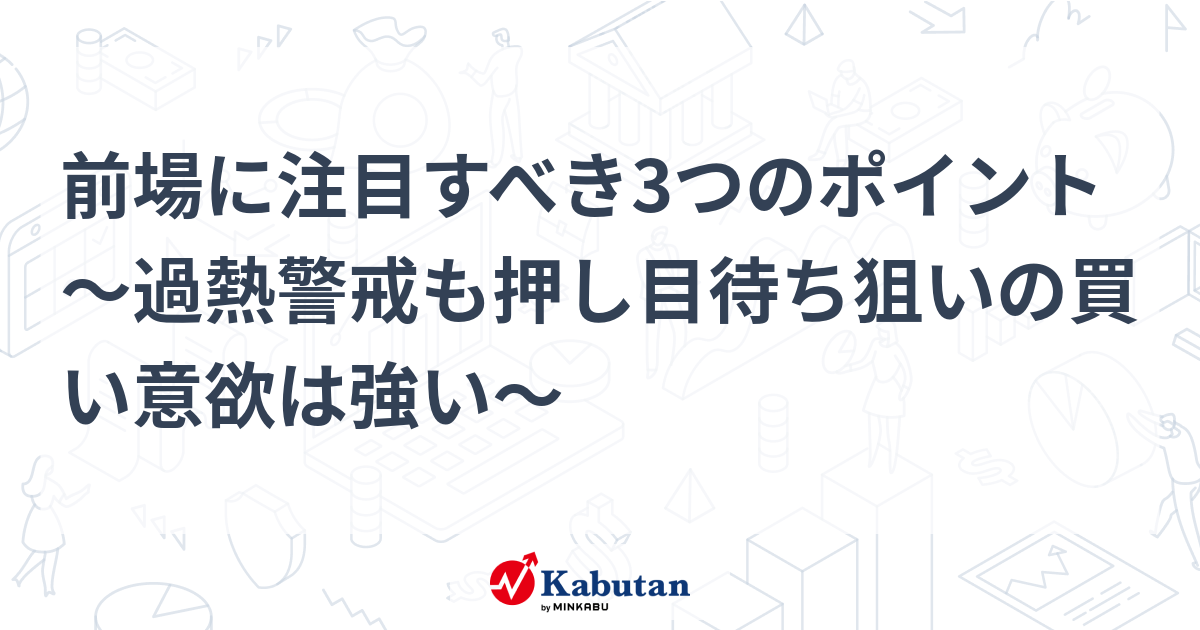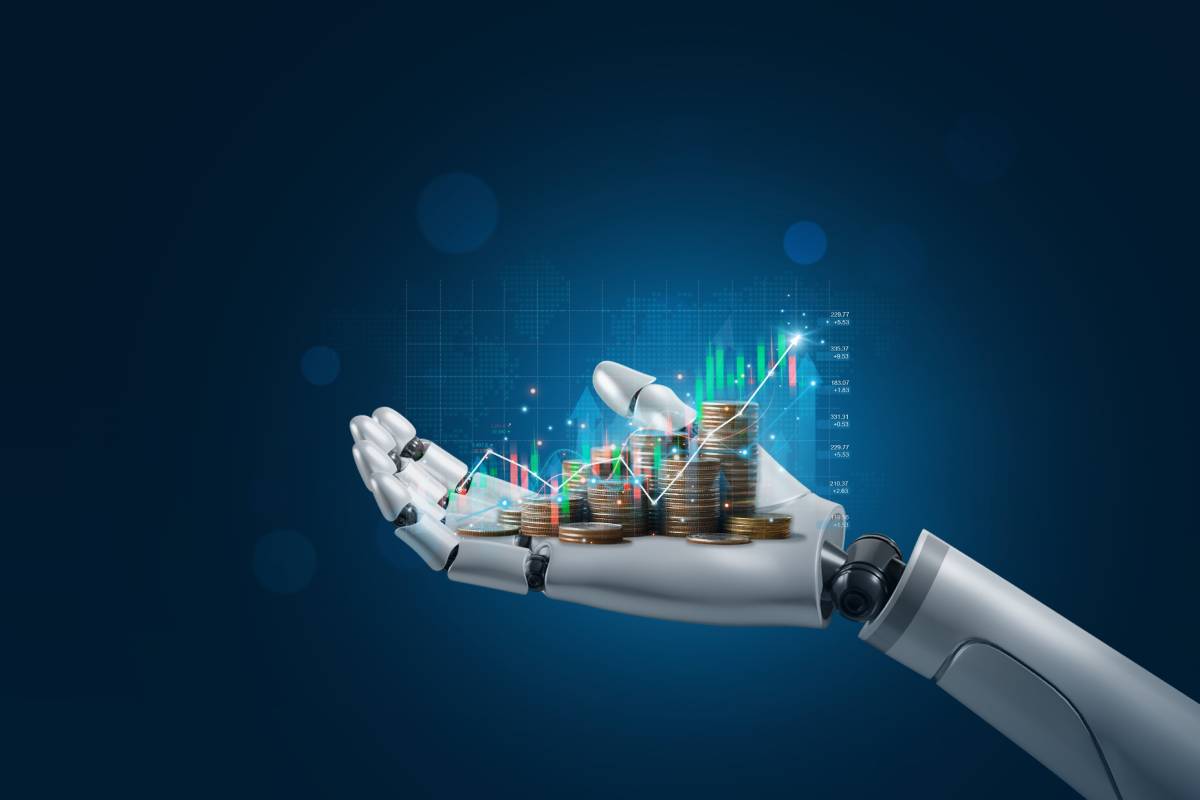金融庁が国内生保の再保険を調査、米ファンド系の活用増で-関係者

- 契約規模や形態など報告求める、引受先のバミューダ集中にも関心
- 元受け保険会社に影響も、「資産運用目的」の引き受け増加で実態把握
国内の生命保険会社が別の専門会社などと結ぶ再保険について、金融庁が実態調査に乗り出したことが分かった。再保険の引受先として積極的な資産運用を手がける米ファンド系などが増えている現状を踏まえ、関連リスクを事前に把握する狙いだ。
事情に詳しい複数の関係者が、情報が非公開であることから匿名を条件に明らかにした。アンケート形式で主要生保各社に現在の再保険の規模や契約形態などを報告するよう求めた。金融庁は引受先の再保険会社が租税回避地の一つである英領バミューダに集中していることにも関心を持っているという。
仮に多くの契約を引き受けた再保険会社が破綻した場合、国内生保の業績に影響が及ぶ恐れがあるほか、遠方で実態のつかみにくい引受先の資産運用に対するモニタリングが十分にできないことなどが懸念される。関係者らによると、金融庁は資産運用目的の新たな再保険引き受けが増えつつあることから、まずは実態把握に努める意向だという。
金融庁の担当者にコメントを求めたが、現時点で回答は得られていない。
国内生保は再保険を主に保険金支払いなどによる財務リスクの軽減に活用してきた。しかし、ここ数年は米KKRなど投資会社系列の再保険会社が、引き受けた資産をより高いリターンの運用に回そうと契約を増やしている。2025年度には国内で保険会社の新たな資本規制が導入される予定もあり、こうした流れが強まっている。
KKRやアポロ・グローバル・マネジメントなどの傘下にある再保険会社は、総額900兆円近くと世界有数の契約残高を持つ日本の生保から再保険契約を獲得し、再保険料として得た資金を比較的、流動性の低いプライベートクレジット(企業への直接融資)などに振り向けている。金融庁はこうした新たな動きに基づくリスクを注視している。
保険監督者国際機構(IAIS)は24年12月、元受け保険会社とファンド系再保険会社間の取引を含むクロスボーダーの再保険契約の増加などを例に挙げ、生保業界の構造的変化がリスクの一つとだ指摘した。3月にも再保険取引に関して論点整理して公表する予定だ。