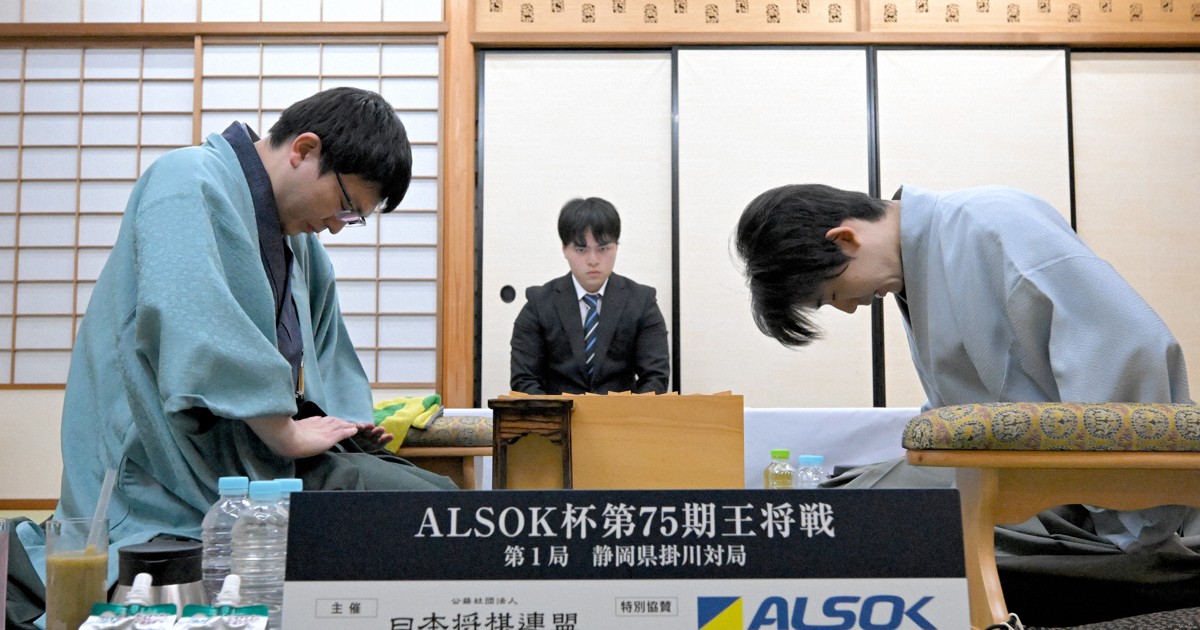今まで1度も降りたことがない「下総中山駅」に降りたら、歴史と芸術と美味しいものに出会える街とわかった

2009年8月から、当サイトで仕事をするようになって、早いもので今年で17年目に突入した。そんなにも長く仕事をしているにも関わらず、1度も降りたことのない駅が結構ある。このままその駅やその街を知らずに過ごすのはもったいないんじゃないのか?
ってことで、降りたことのない駅に降りてみることにした。私(佐藤)が以前から気になっていた駅のひとつが、総武線の「下総中山(しもうさなかやま)駅」である。できるだけ、新鮮な感動と驚くに出会うために、事前にほとんど下調べをせずに訪ねたところ、歴史を感じる味わい深い街であることがわかった。
・初めての下総中山
私は普段、総武線を頻繁に利用する。最寄駅が中野駅ということもあって、ほぼ毎日あの黄色いラインの入った電車に乗車しているのだ。主な下車駅は編集部のある新宿で、全線を通してほとんどの駅で下車しているといっても過言ではない。
だが、おそらく今まで1度も下総中山で降りたことはないはず。その特徴的な名前をいつも目にしていながら、今まで素通りしてきたのである。
もしかして何か発見があるのでは? と思い、今回下総中山駅に降りたのだった。
駅を出て北口を出ると、バスのロータリーがある。うん、やはりここに降りたことはない。1度でも訪ねた駅なら、駅前の雰囲気に既視感を覚えるのだが、それがないので初めてで間違いなさそうだ。
・中山法華経寺
駅前には上階に居住スペースを有する商業施設「ミレニティ中山」がある。スポーツジムやクリニック、アパレル・スーパー・雑貨屋が入っており、生活に必要な物事はここで完結するのではないだろうか。
少しだけ街の歴史を調べておいたのだが、この街は日蓮宗大本山の「中山法華経寺」の門前町である。とりあえず、その法華経寺へ向かってみるとしよう。
この道をまっすぐ進めば寺に着くだろう。それにしてもデカい看板だな。あの大きさから察するに、お寺もかなりデカいのではないだろうか。
この道は参道に通じているはずだが、その途中にいきなり踏み切り!? あれは京成本線の踏み切りだな。その先に立派な門が見える。
この門は「中山参道総門」という。門を境にして、向こうは「中山参道商店会」というのだとか。どことなく、古都の風情を感じる。そういえば、うちの地元(島根・松江市)の祖母の家の近くにも、市街地に唐突に立派な門があったっけなあ。初めて訪ねる街なのに、懐かしい気持ちになる。
さらに進むとさっきの門よりも、もっと立派な門が見えてきた。これは相当デカいぞ!
「中山参道山門」だ。中山法華経寺は鎌倉時代から続く日蓮宗の大本山だけあって、大変立派な門を構えている。その昔、この界隈はとても栄えていたのではないだろうか。この門から当時の繁栄の様子がうかがえる。
門の真横には高村光雲作の「日蓮聖人像」が立っている。そこかしこに歴史を感じる由緒ある街なのに、私は今まで少しも知らなかったなんて……。正直恥ずかしいな。
参道を歩いて行くと、この先に寺があるわけだが……。あれは! 五重塔!! なんか京都に来ている気分だよ。
お寺の手前に「額堂」という小さな喫茶があった。おでんと焼きそばの幟(のぼり)が見える。あとで寄ってみよう。この暑さではおでんを食べる気分ではないけど「太鼓焼き」という大判焼きみたいなのが名物らしい。
この景色も風情があっていいね。木々が色づく季節に訪ねると、一層風情がありそうだ。
ここが法華経寺か。白状すると、私はここを本院と勘違いして満足してしまって、次の場所へ行ってしまった。だがここは本院ではなく「祖師堂」という。国指定の重要文化財で、日蓮上人を祀る大堂である。鎌倉時代の1325年に創建されたのだとか。
本院はこのさらに奥にあるのに、本院を訪ねないまま帰ってしまった……。また次の機会に訪ねたいと思います。
平日ということもあって、観光している人の姿はない。きっと週末や年始はにぎわっているんだろうなあ。
間近で見る五重塔は迫力が違うなあ。江戸時代(1622年)に建築された約30メートルの塔で、池上本門寺(大田区)と寛永寺(台東区)の五重塔とほぼ同じ高さなのだそうだ。
そしてこちらは通称「中山大仏」と呼ばれる、「法華経寺銅造釈迦如来坐像」である。総高4.52メートル、像高3.45メートルで、1719年に造立されたという。
この先にある本院を中心に、寺・神社・石碑・像などが広範囲に点在しており、とても1日では見切れる気がしないので、あらためて時間を作ってじっくり訪ねたいと思う。
この近くに東山魁夷(ひがしやまかいい)の記念館があるそうなので、そちらに行ってみるとしよう。祖師堂の裏の道を抜けると、そこにあったのは「龍王池」である。一見なんでもない蓮池のように見えるけど、ここにも日蓮上人の逸話が残されている。
日照りに苦しむ農民のために、日蓮上人がこの池に八大龍王を祀って祈祷したところ、霊験があらわれて雨を降らせたそうだ。池の辺に「八大龍王堂」が設けられており、近年は商売繁盛の守護神として、参詣者が絶えないそうである。
うだるような日差しでも、亀は甲羅干しをしているな。暑くないのかねえ。干上がっちゃうよ……。
・東山魁夷記念館
法華経寺から7~8分歩いたところに、「市川市東山魁夷記念館」がある。東山魁夷は20世紀の日本を代表する日本画家で、生涯の大半を市川で過ごしたそうだ。2005年にゆかりのあるこの地に記念館を開館したという。洋風のモダンなこの建物で、魁夷の資料と作品を展示している。
私は芸術に明るくないのだが、「開運! なんでも鑑定団」でその名前を知っていたので、こちらを訪ねてみた。ちなみに入館料は大人税込520円である。
芸術の良し悪しはわからないけど、魁夷の描く作品の色使いの緻密さに圧倒された。なかでも「木枯らし舞う」という作品は秀逸で。山間の道で木枯らしに舞う落ち葉の描写が素晴らしい。
風を目で見ることはできないけど、魁夷は無数に舞い上がる落ち葉で、風を可視化している。一見不規則に見える風の向きの中に、ある種の秩序とでもいうべき一体感を描いているのだ。何でもない風のひと吹きを、高い感受性で捉えた魁夷の表現力に驚かされる。
・太鼓焼き
さて、再び参道に戻って先ほど通過した額堂でひと休み。往路で気になっていた、「太鼓焼き」(税込150円)のチョコレートを頂くことに。お店の人に、外は暑いから店内に入るように言われたけど、暑いなかでも外で食べる方が気持ちがいいと思い、ベンチで頂くことに。
この形状の焼きまんじゅうはいろいろ呼び方があるけど、私はやっぱり「大判焼き」と呼びたいなあ。たしかに太鼓の形をしてるけどね。
そんなに長い距離を歩いたわけじゃないけど、暑いから疲れちゃうな。そんな状態で食べる甘いモノはことのほかしみる~。
おお! チョコがぎっしり詰まってる! 甘味に癒されるわ~。
・深川伊勢屋 中山店
せっかくなのでお土産を買って帰ろう。京成本線中山駅の近くに、甘味処の「深川伊勢屋 中山店」というのがあった。少しシャッターが降りていたのでやっていないかと思ったら、ちゃんと営業してました。日除けでシャッターを下げているのかな?
持ち帰ったのは「焼きまんじゅう」と「どらやき」(各税込180円)と、「みたらしだんご」を2本(1本税込140円)だ。みたらしは注文ごとに、焼きたてを提供している。
食べてみると、だんごはモッチモチ! 焼き上げた香ばしいかおりと、濃厚なみたらしの甘さが相まって、濃いめのお茶が欲しくなってしまう。基本洋菓子派の私だが、歳を重ねるごとに和菓子の良さを痛感する次第。ショーケースに並んだおにぎりもウマそうだったなあ。
・海商寿し
そして最後に、駅近くの「海商寿し」でお昼を食べることに。店前に丸椅子がたくさん置いてあったので、きっと週末は行列ができるお店なのでは? と思い入ってみた。
平日ランチはいずれも1000円台。吸い物付きで大トロ1貫と赤マグロ1貫の入った、「特12貫ランチ」(税込1680円)を注文。昼時で多少混みあっていた都合で、提供に時間がかかるとのことだったが、思ったよりも早く出てきた。
こちらがその12貫です。
今日は寿司を食うつもりではなかったけど、図らずも良いお店に出会うことができた。どのネタも新鮮で味も良い。とくに大トロは悶えるほど美味かった! ふらりと入ってこんな上等な大トロに出会えるなんて幸せ!
ということで、下総中山は歴史と芸術、それから美味しいものに出会える街でした。今回、法華経寺を全部見切ることができなかったので、また時期をみて訪ねたいと思う。きっと紅葉の見られる晩秋の頃が良いのかも。下総中山、おすすめです!
参考リンク:中山法華経寺、市川市立東山魁夷記念館、Instagram @kaishou_sushi 執筆:佐藤英典 Photo:Rocketnews24