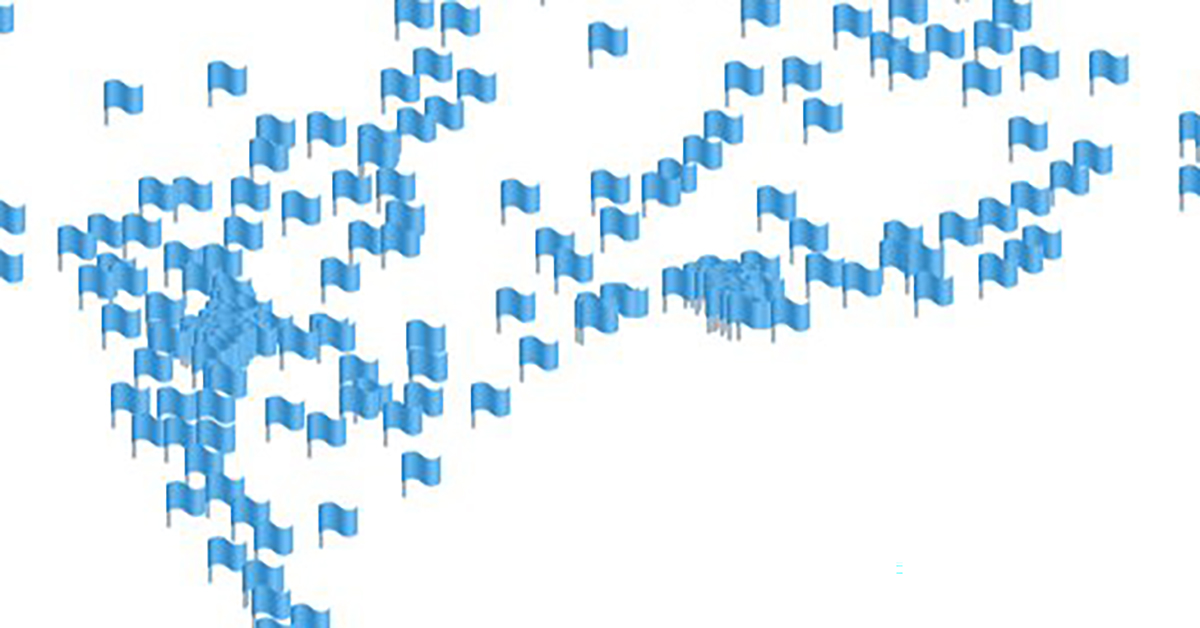免疫力をアップしても意味がない…小児科医が「ヨーグルトより高額サプリよりおすすめ」という花粉症の治療法 薬より食品やサプリが体にやさしいとは限らない

今、日本人の4割以上が花粉症で、しかも若年層ほど有病率が高くなっている。小児科医の森戸やすみさんは「目や喉のかゆみ、くしゃみなどの症状があると、つらいだけではなく、毎日の生活や学習にも差し支えるので、早めに治療をすることが大切」という――。
写真=iStock.com/PonyWang
※写真はイメージです
昔に比べて、子どもの花粉症が増えています。環境省の「花粉症環境保健マニュアル2022」によると、1998年から10年ごとの調査で、花粉症の推計患者数は約10%ずつ増加し、現在は42.5%です。全国民の4割以上が花粉症というのは、ずいぶん多いですね。
中でも若い人の有病率が上がっています。昭和58〜62年と平成8年の調査で一番多い年齢帯は30〜44歳でしたが、平成28年には15〜29歳が最多となり、3人に2人くらいの割合で花粉症です(※1)。
実際に小児科医として診察していても、小さな子が花粉症になることは増えていると感じます。以前だとまず風邪でしたが、両親にアレルギー歴があり、どうみても花粉症という子が3~4歳でもみられます。つらい症状があると、毎日の生活はもちろん、遊びや勉強やスポーツにも差し支えます。目をかきむしって腫れあがり、鼻が詰まってずっと口呼吸をし、夜によく眠れないなどということも。子どもは自分でどうすることもできないので、保護者が早めに対策を考えてあげてください。
※1 東京都健康安全研究センター「花粉症患者実態調査」
政府広報オンラインで情報収集
さて、花粉症を起こす花粉は50種類以上ありますが、遠くまで飛んで多くの人に症状を起こすのはスギとヒノキで、スギによるものが圧倒的です。なぜスギ花粉症が増えているのか、しかもなぜ若い人に増えているのかはわかりません。
環境省の調査によると、スギ花粉症の有病率には「スギ花粉の飛散量」と「両親のアレルギー歴」が関係していました。つまり、アレルギーになりやすい体質を持つ人がたくさんの花粉に接触することによって、花粉症になるということは間違いないようです。
スギは北海道南部から九州にかけて広く植林されており、次に原因として多いヒノキも北海道と沖縄を除く各地に植林されています。他に樹木の花粉では、シラカンバ、ハンノキなど、草本ではカモガヤ、ブタクサ、ヨモギなどがあります。どの花粉がいつごろ飛散するかを知っておくと、対策を立てやすいですね。
もはや国民病といえるほど有病率の高い花粉症は、政府も環境省を中心に気象庁、林野庁、厚生労働省などと共に対策しています(※2)。花粉の少ない杉の植林、花粉の飛散予測の情報提供などをしたり、リーフレットやウェブサイトに情報を載せたりしています。こうした資料を活用しましょう。
※2 政府広報オンライン「政府の花粉症対策」
Page 2
花粉症の治療では、症状を和らげる「対症療法」を行うことが多いでしょう。対症療法には、ヒスタミンやロイコトリエンといった炎症物質が作用しないようにする薬を使います。特に抗ヒスタミン薬は効果が高く、剤型がシロップ、粉、OD錠、錠剤など多数あり、1日1〜2回飲みます。小さな子どもの場合は、シロップや粉、口の中でとけるOD錠が飲ませやすいでしょう。
子どもによく使われるのは、五十音順にアレグラ、アレジオン、アレロック、クラリチン、ザイザル、ジルテックなどの第二世代抗ヒスタミン薬です。てんかんや熱性けいれんを何度か起こしたことのある子は、けいれんを誘発する恐れがある第一世代抗ヒスタミン薬は避けてください。
ただ、抗ヒスタミン薬は手軽で効果が高い一方、脳内でのヒスタミン受容体にも影響することで眠気が出る場合があります。小学生以下だと眠気の訴えは少ないですが、大事な試験があるなどで心配な場合は、医師に相談して薬を選んでください。
2024年改訂の『鼻アレルギー診断ガイドライン』で、初期治療としてこういった抗ヒスタミン薬の他にアレギサールなどの遊離抑制薬、オノンやシングレアなどのロイコトリエン受容体拮抗薬、プロスタグランジンD2・トロンボキサンA2受容体拮抗薬、アイピーディというTh2サイトカイン阻害薬が挙げられています。
内服薬を飲んでもまだ鼻の症状がつらかったら、点鼻薬をします。鼻噴霧ステロイド剤、抗ヒスタミン薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬、血管収縮薬といった種類があります。小児の場合、鼻に何かされるのを嫌がることが多いですが、説明をされてラクになることを実感すると毎日できるようになります。目の症状が強い場合は、点眼薬や眼瞼クリーム、ステロイドの軟膏を使います。
写真=iStock.com/MJ_Prototype
※写真はイメージです
根治を目指すアレルゲン免疫療法
一方、アレルゲン免疫療法は、原因物質を少量ずつ摂取する「舌下免疫療法」の効果が高いです。子ども(5歳以上)でも可能で、副作用が少なく、約80%の人に効果があるところが利点ですが、毎日の服用を3〜5年も続けなくてはいけないところがデメリットです。そして現在は、まだスギ花粉とダニに対する薬しかありません。同じ原理で少しずつアレルゲンを注射する「減感作療法」も昔から行われています。開始時には週2回、維持期には月1回通院して注射し、舌下免疫療法と同様に3〜5年間かかります。
その他に、IgEに結合することでアレルギー反応を抑える「オマリズマブ(商品名ゾレア)」を注射する抗体療法もあります。12歳以上で、毎月注射に通える場合は試してみてもいいかもしれません。
耳鼻咽喉科で花粉症を治す手術というものはありませんが、アレルギー性鼻炎を起こしにくい粘膜にしたり、鼻閉を起こしにくい構造にしたりするという方法が合っているかもしれません。鼻粘膜を縮小したり、レーザーで焼灼したりする方法があるようです。耳鼻科医に相談してみて下さい。
Page 3
さて、そもそも花粉症とはなんでしょうか。ひとことで表すなら「花粉によるアレルギー性鼻炎・結膜炎」です。
私たちの体には、ウイルスや細菌などの病原微生物やホコリなどの異物が入ってくると、体外に追い出そうとする仕組みがあります。そのため、スギ花粉が繰り返し体内に入ると、免疫細胞の一種「B細胞」が、スギ花粉に対するIgE抗体を産生。そのIgE抗体が免疫細胞である「肥満細胞(マスト細胞)」の表面に結合し、スギ花粉を感知するとヒスタミンやロイコトリエンなどの炎症物質を出すことで、くしゃみ、鼻水、鼻詰まり、目のかゆみや腫れ、喉のかゆみといった症状を引き起こすのです。
このIgEは、いろいろな物質に対して作られるので、スギ花粉だけでなく、ヒノキなどの樹木の花粉、ブタクサやハルガヤなど草の花粉、虫、ハウスダストやダニ、真菌、犬や猫など動物の毛、食べ物など、少なくとも数十種類について検査をすることができます。ただし、IgE値の高さと症状の強さは必ずしも相関しないので、アレルゲンすべての検査をする必要はなく、必要なものだけを検査します。また春だけ花粉症の症状の出る子の場合、血液検査はせず、問診と診察だけで治療薬を処方することが多いです。
写真=iStock.com/kororokerokero
※写真はイメージです
民間療法は安全とは限らない
「薬は体によくない」と思っている人が多いためか、花粉症にはいろいろな民間療法があります。たとえば「花粉症は食品で治せる」と言う人がいますね。レンコン、ヨーグルト、シソ、乳酸菌、甜茶など、花粉症対策によいとされる食品はさまざまですが、医学的な根拠は少ないのです。以前、花粉症に効くというお茶にステロイドが混入されていた事件がありました。食品やサプリメントが安全とは限りませんし、薬より高額になることもあります。一方、市販薬や処方薬は成分が明らかで、効果と安全性が確かめられているのです。
「免疫力をアップすると花粉症が治る」と言う人もいます。免疫力は確かに存在するものの、測ることはできません。「体力」や「忍耐力」だって存在しますが、一つの指標で測ることはできないし、その力を格段に上げる一つの方法はありませんね。また、花粉症は免疫が働きすぎて起こるもの。本来、あまり害のない花粉に対して抗体を作って炎症物質をたくさん放出するからこそ、つらい症状が起こるわけです。そんな免疫力は少しダウンしてほしいくらいで、わざわざアップする必要はありません。
子どもの頃から花粉症だったという知人が、大人になって初めて抗アレルギー薬を飲み、「薬は体に負担だと思っていたけど、こんなに効くなら早く飲めばよかった」と言っていました。サプリメントのほうが体にやさしいと思い込んでいたり、医療不信があったりしたのかもしれません。でも、本当は薬を使わず症状を我慢するほうがずっと体に負担がかかると思います。
Page 4
最後に、花粉を物理的に避けることも大切です。環境省の「花粉症環境保健マニュアル2022」をもとに説明しましょう。
花粉の多い日に外出しない 晴れて気温が高い日、空気が乾燥して風が強い日、雨の翌日や気温の高い日が2〜3日続いたあとは、花粉の飛散量が増えるので外出を控えましょう。
マスク・メガネを装着する どちらもしない場合に比べて、ガーゼマスクだけで70%の花粉を減らすことができ、不織布だと84%減少する効果がありました。メガネも同様で、普通のメガネ、花粉症用のメガネともに粘膜に付着する花粉を減らすことができます。
服に付着しないようにする 衣服の繊維に花粉が付着すると、家の中に持ち込んでしまいます。ウールが一番花粉が付着してしまい、化繊、綿の順に減っていきます。家に入る前に服についた花粉を払うのも効果的です。
うがいと洗顔をする うがいをしたり、鼻を生理食塩水で洗ったり、洗顔・洗髪をしたりすると、花粉を完全ではないものの洗い流すことができます。
換気と掃除をする 換気のときに部屋の窓を全開にするのではなく、10cm程度開けてレースのカーテンを通すことで花粉の流入を4分の1程度に減らすことができます。拭き掃除とカーテンの洗濯もしましょう。
薬による治療、また生活の工夫によって、少しでもラクに過ごせるといいですね。困ったことがあれば、耳鼻科や小児科で相談しましょう。