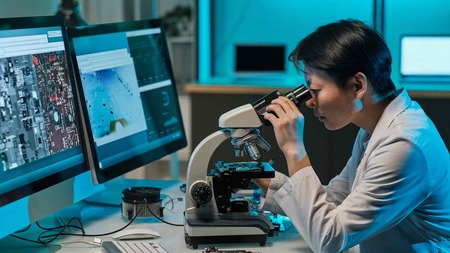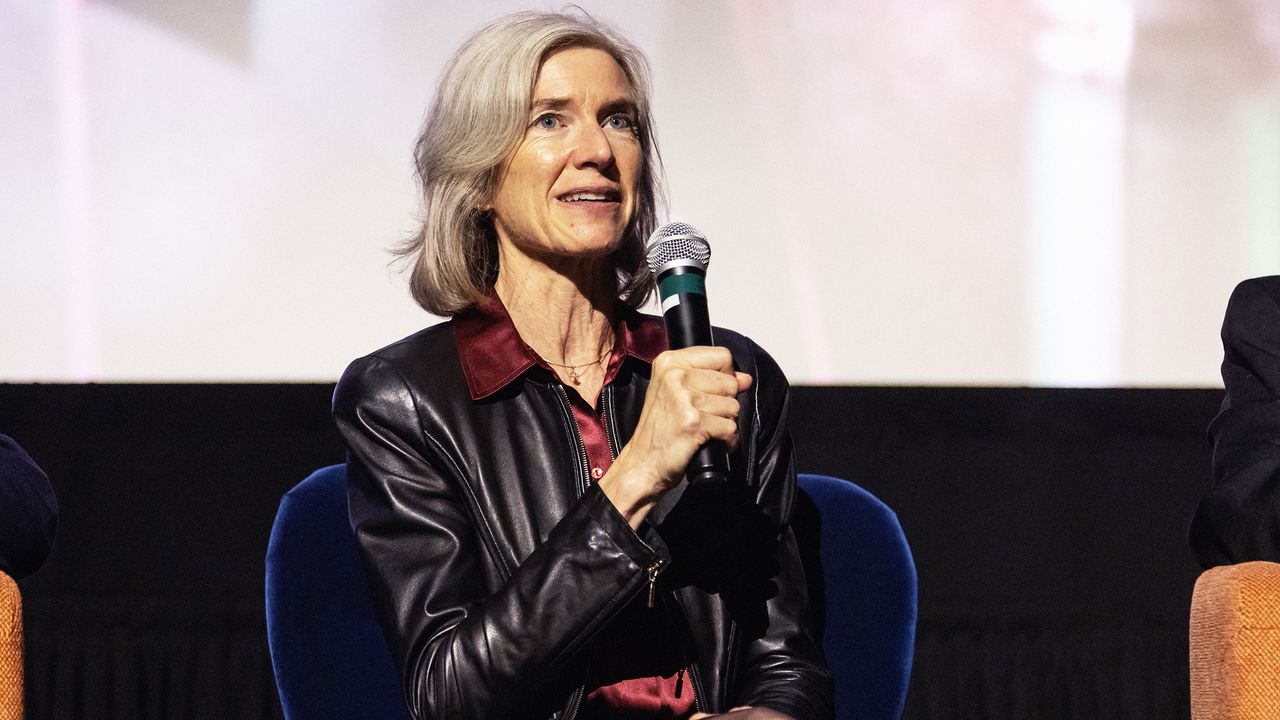「仕事ができるかどうか」よりも重要…11年間、上場企業の受付をしていて分かった「評価が低い人」の共通点 「感情的な人はダサい」という時代に変わった

ちょっとしたアイデアを思いついた時、上司に相談したくても、不機嫌な対応をされるのではないかと思うと、「やめておこうかな」と思ってしまいます。
緊急の報告ならともかく、思いついたアイデアを話さなかったからといって怒られるわけではないからです。
「これを言ったら怒られる」という地雷がわかっていればまだいいのですが、いつ何がきっかけで怒り出すのかわからない人には、なるべく近寄りたくありません。
たとえ革新的なアイデアだったとしても、発言しづらい空気があることによって、埋もれていってしまうのです。
安心して発言できない組織では、意思決定の質も下がっていきます。
「本当はこっちの方がいいと思うけど、怒られるかもしれないから黙っておこう」と考える人が増えるからです。
たとえ理路整然と発言する人がいても、感情的に反応されたら、そもそも議論になりません。
その結果、みんなが発言を控え、上ばかり見て仕事するようになります。そのような組織では、新しいアイデアが生まれづらくなり、生産性も下がってしまいます。
そんな組織は、正しい判断ができなくなっていきます。
自分の組織をチェックする7つの質問
チームの心理的安全性というのは、ハーバードビジネススクールのエイミー・C・エドモンドソン教授が提唱した考え方です。
心理的安全性があるかどうかを考える時、このような状況かどうかを質問するそうです。
7.このチームのメンバーと一緒に仕事をしていると、私にしかないスキルや才能が評価され、活かされる。
不機嫌な人がいる組織では、こんな状況とはほど遠くなるはずです。
写真=iStock.com/maroke
※写真はイメージです
さらに、アメリカで提唱されている「エモーショナル・リーダーシップ」では、リーダーが自分の感情を認識して、適切に出力するための行動モデルが示されています。
つまり、自分の感情に振り回されてしまう人はリーダー失格である、どう感情を出すかを身につけなければいけないといわれているのです。
これからの社会では、「感情の出し方」が成果と評価と信頼につながっていくのです。
では、どう出していけばいいのか。
これこそが、私がこの本でお伝えしたい「感情の作法」です。
Page 2
それは「感情」にヒントがあります。
端的にいうと、感情が安定している人(この本では、感情が安定しているように「見える」人のことを指します)は、信頼され、評価される傾向にあるのです。
この数年ほどのあいだで、その傾向はどんどん強くなり、職場で「感情」が評価に直結するようになってきました。
「あの人は感情の起伏が激しい」 「好き嫌いや感情に任せて発言する」
「不機嫌を人にぶつけ、当たり散らす」
そう判断されると、たとえ優秀で魅力的な一面があったとしても、大きなマイナスになってしまうのです。
それはなぜかというと、「パワハラ」「フキハラ(不機嫌ハラスメント)」などの言葉が広まってきたことと関係しているのではないでしょうか。
たとえ正しいことを言っていても、言い方をまちがえるとすぐに「あの人、パワハラだよね」と評価されてしまう。
機嫌が悪い姿を見せてしまうと「フキハラだよね、あんな人といっしょに働きたくない」という声が広まってしまう。
そんな風潮になってきています。
写真=iStock.com/kuppa_rock
※写真はイメージです
「威厳がある人」→「ダサい人」
これまでの働き方の歴史を紐解いてみると、過去数十年は「仕事の成果さえ出せば、感情的でもかまわない」という水面下の常識がありました。
たとえ、不機嫌になり部下に怒鳴り散らす上司がいても、成果さえ上げていれば、大きな問題にはなりませんでした。それどころか「ちゃんと叱り、育てている」と言われることすらあったように思います。
特に役職者の場合、むしろ「あの人は威厳がある」と尊敬の念で受け止められていることも多くありました。
ところが、その常識はものすごいスピードで変わっています。
「感情を出す人は信用できない」「感情的なリーダーにはついていけない」「感情的な人はダサい」という見方をされる社会に変わってしまったのです。
では、まったく感情を出さなければいいのかというと、そんなわけにもいきません。
能面のような顔で、一日中喜怒哀楽をまったく出さない人が職場にいたら、その人を信頼できるか、評価したいかというと……そんなことはありませんよね。
Page 3
データ上だけでなく、本当に「感情」が評価や出世に響いてしまった例があります。
私は企業の受付という仕事を通して、120万人以上のビジネスパーソンと接してきました。
受付には、さまざまな人がいらっしゃいます。
役員、部課長などの役職者や入社したばかりの新入社員など自社の人々はもちろん、商談や採用面接のために来社される他社の方々もいらっしゃいます。
受付とは、多くの人が「素」になる場所です。
笑顔でお客様を送り出した瞬間、豹変する人。
受付には名刺を投げ出すようにして「取り次いでよ」という態度なのに、やってきた上司や重役にはひたすら低姿勢な人。
どなたにも同じ距離で接する受付という仕事を通して、どういう人がどう評価されていくのかを客観的に見ることができました。
そして9年前に起業してからは、経営者として、信頼を集めるのはどのようなタイプの人か、どんな上司のもとでは人が去っていくのかを見てきました。
その結果わかったことは「不機嫌は『見えないキャリアの天井』を作る」ということです。
実力者なのに出世コースから外れた部長
こんなことがありました。
ある会社で、社内でも主力とされる事業部の部長がいました。誰もが認める実力のある人で、役員への昇進も噂されていました。
でもその方は、感情的にふるまうことで有名だったのです。
お客様をお見送りしてから受付の前を通って会議室に戻るあいだだけでも、強い口調で部下を叱責していることが多くありました。
会議室や執務スペースに戻ってからならまだしも、会社のエントランスで、その場にいるほかの社員やお待ちになっている来客から丸見えであっても、自分の感情のままにふるまっていました。
その方はずっと仕事の成果を出されていたはずですが、いつしか出世コースから外れてしまいました。
仕事の成果的には昇進してもおかしくないのに、なぜ?
その答えは「感情の作法」にありました。
その方が出世コースから外れてしまったのは「部下がいつかないから」「部下からの信頼が足りないから」という理由だったそうです。
橋本真里子『感情の作法』(サンマーク出版)
大きな組織になるほど、部長から役員への昇進は、数十人から選ばれるような狭き門です。
部長や課長のポジションまでは、業績や功績で昇進できたとしても、役員への昇進ともなれば、経営陣は、人間性や周囲からの評価を注意深く見ているものです。
上司だけでなく同僚や部下からも評価される「360度評価」を取り入れる会社も増えてきています。これも「上から見えている評価だけでなく、全員がどう思っているかを評価の対象とする」という意思の表れです。
周りの人からの信頼がなければ、いくら仕事の成果を出していたとしても出世はさせられない。そう評価されてしまうのです。
- 1981年三重県生まれ。トランスコスモス、USEN、ミクシィ、GMOインターネットなど、複数の上場企業にて受付として勤務。11年間で、のべ120万人以上の来訪者対応を経験する中で、現場の非効率に課題を感じ、2016年にディライテッド株式会社(現・株式会社RECEPTIONIST)を設立。来客対応のデジタル化を推進するクラウド受付システム「RECEPTIONIST」は、現在では年間400万人が利用。業界売上シェアNo.1を獲得し、導入企業を拡大している。<この著者の他の記事> 元受付嬢が教える"相手を虜にする"話し方