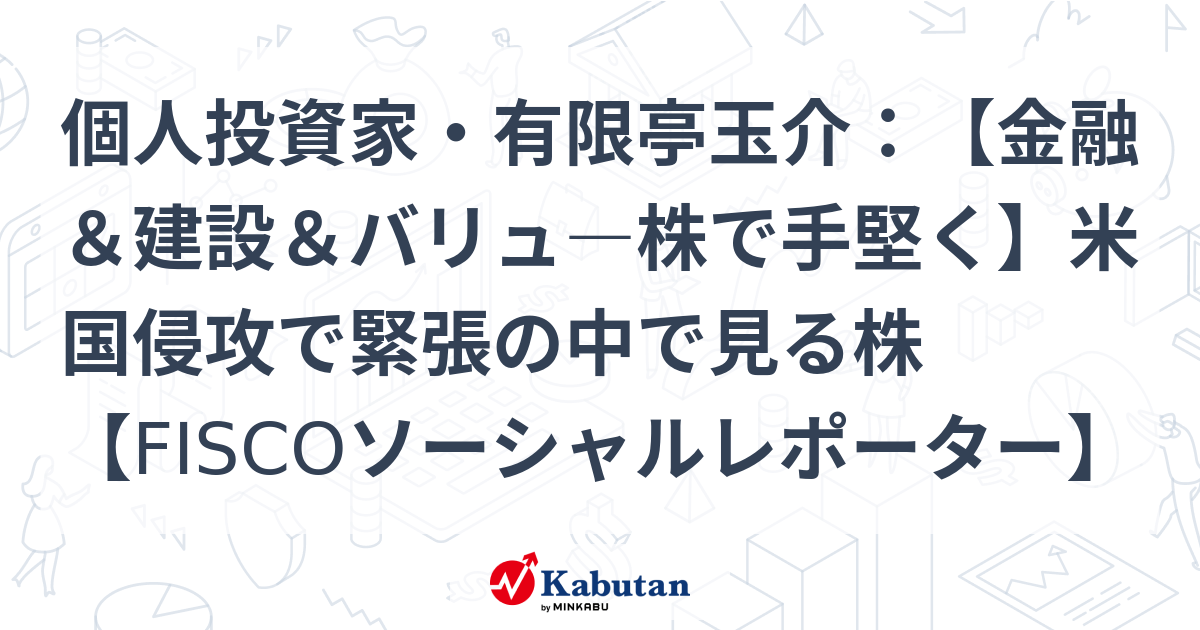専門家がタブーに切り込む「安楽死を導入したら国家はいくら“節約”できるのか」

Photo: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images
Text by Jérôme Cordelier
安楽死や自殺幇助に関する議論で、誰もが意識しつつも、誰も口に出そうとはしないタブーな話題がある。それは、安楽死が持つ経済的な影響だ。厄介なのは、それが議論で外せない重要な論点となっていることだ。 そんな状況のなか、シンクタンクのフランス政治刷新研究所が、この問題を正面から取り扱う思い切った報告書を公表した。その報告書『人生の終末期に関する議論で語られない経済的・社会的側面』の著者パスカル・ファーヴルに話を聞いた。
──なぜ人生の終末期における社会的・経済的側面に関心を抱いたのですか?
私は医者ですが、いまは博士課程に籍を置き、安楽死の問題を研究しています。医者が安楽死にどう関わるのか、そのとき医者にどんな責任があるのか、ということに関心を持っています。
研究のなかで、安楽死が合法化されたときにどんなことが起きるのか、他国の事例を調べることになります。ベルギーとオランダでは2002年から、ケベック州では2015年そしてカナダでは2016年から安楽死が合法化されています。これらの国々では、それなりの量の記録が蓄積され、安楽死の社会的・経済的側面が研究されるようになっています。
──フランスの「人生の終末期」に関する法案を見ると、この安楽死という言葉ではなく、「死への積極的援助」という言葉が使われています。この言葉遣いには、どのような意味があるのですか?
そこは、私が非常に問題視しているところです。2024年、フランス政治刷新研究所で「人生の終末期に関する用語」という文章を書き、この議論で使う用語に曖昧さがあってはならないと論じました。医者にとって、言葉遣いは正しいものでなければなりません。 「死への援助」という言葉を使うとき、私たち医者の頭に思い浮かぶのは緩和ケアです。これは患者が人生を最後まで生きるのを助けることを指します。医師の使命に含まれるものだと言っていいでしょう。
一方、安楽死は、まったく別物です。これは致死薬の投与です。ほんのわずかな時間で人を死なせる薬物を注入するわけです。安楽死とは別に自殺幇助というものもあります。これは患者を死なせるところは安楽死と同じですが、致死薬を患者本人が摂取するので、安楽死とは別の扱いになります。こういったものは、私たち医者にとって、どんな場合も、医療とはみなせません。医師の使命とは相容れないビジョンです。
──いまの話は、あなたの活動家としての意見にすぎないと言う人もいるかもしれません。その人たちには、どのように答えますか?
まず言いたいのは、私は活動家としてではなく、医療従事者として発言しています。言葉遣いを明快にするのは本当に大事なのです。「死への援助」という表現は、大きな混乱をもたらす原因になっています。 私は医師のジャン=マリ・ゴマと『人生の終末期──人は自分の死を選べるか』(未邦訳)という本を書いたのがきっかけで、シンポジウムや討論会に何度も登壇してきました。そこで毎回、議論に出てくる基礎用語の意味を取り違えている人が多いのに気がつきました。 私が、安楽死とは「その場で患者をすぐに死なせることだ」と説明すると、多くの人が驚いて、「私が望んでいるのは、それではありません。私は苦しみながら死ぬのが嫌だと言っているのです」と言うのです。
苦しみながら死ぬのが嫌なのは、誰もが同意できると思います。ただ、フランスの問題は、毎日、500人が緩和ケアを利用できずに亡くなっていることです。
緩和ケアとは、それ専門の病棟を用意するだけの話ではありません。痛みを和らげたり取り除いたりするのに加えて、介護や看取りのケアも含まれます。いまのフランスで、痛みの緩和や除去ができているとは全然いえません。緩和ケアを専門とする医療従事者の不足が深刻な問題となっています。その結果、多くの人が、あってはならないような条件で命を終えているのです。
──人生の終末期をめぐる議論を経済の側面から、いうなれば冷徹に実利重視で考えることは可能なのですか?
残り: 2681文字 / 全文 : 4414文字
無料会員になると記事のつづきが読めます。 さらに有料会員になると、すべての記事が読み放題!
\新生活応援キャンペーン中/