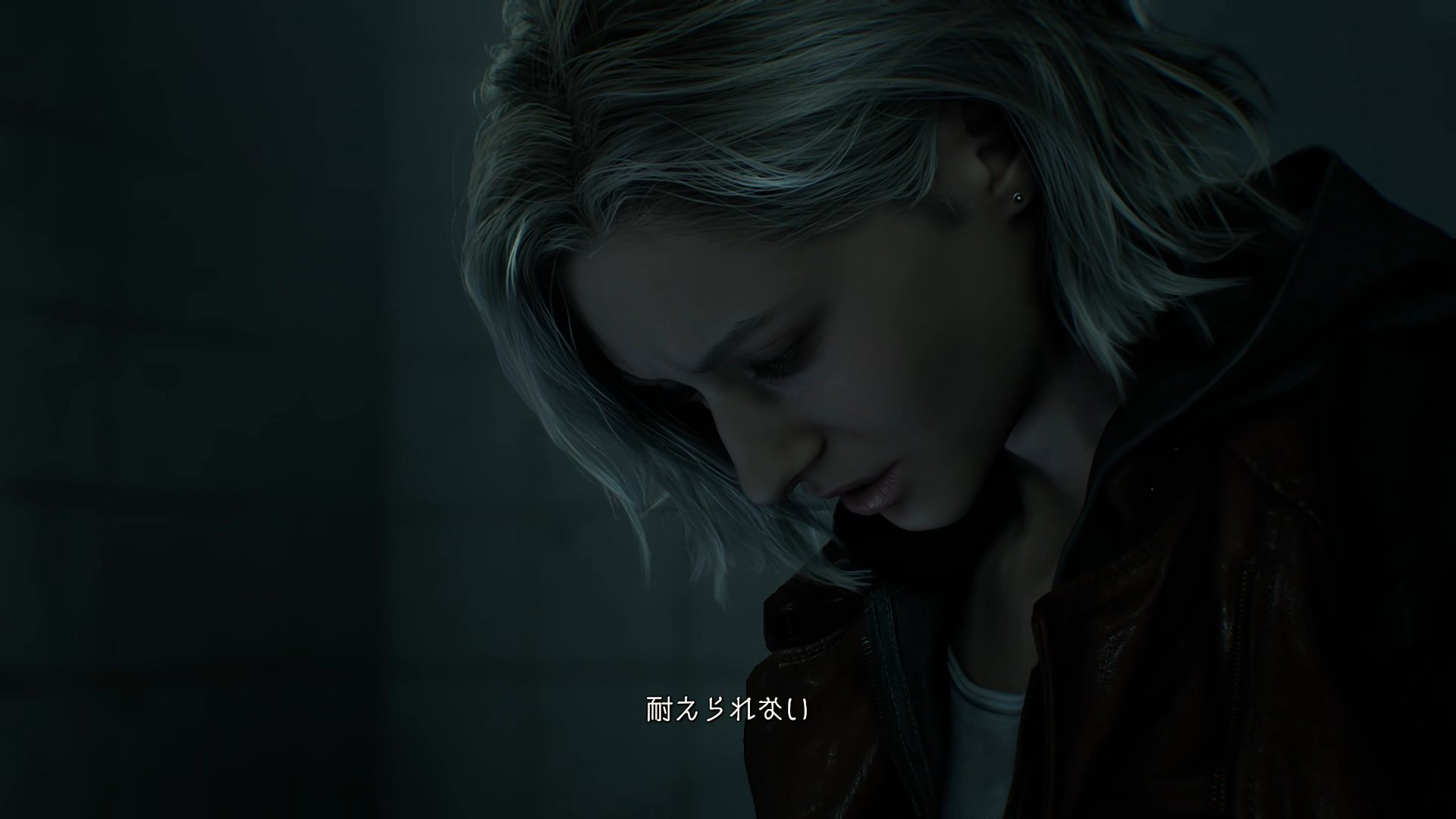【大河ドラマ べらぼう】第11回「富本、仁義の馬面」回想 「わっちは籠の鳥」太夫の心を動かした女郎の涙 大奥女中も必修の富本節、「追っかけ」が物語になる過熱人気

真の芸術との出会いに涙した「籠の鳥」たち
「こんな涙を見せられて、断れる男がどこにいる」。浄瑠璃の太夫の牛之助(寛一郎さん)はそういって、蔦屋重三郎(蔦重、横浜流星さん)たちが懇願していた吉原のお祭り、「俄にわか」への出演を快諾しました。太夫と相棒の歌舞伎役者の市川門之助(濱尾ノリタカさん)が、お座敷のほんの座興で自作の富本節「都見物彩色紅葉」を一節、披露したことがきっかけでした。
黒木売り(京の町に薪などを頭に乗せて売りに来る大原女)の小琴と、都見物左衛門の彦総の濡れ場などが描かれる艶っぽいストーリーです。
「彦惣頭巾小琴帽子/都見物彩色紅葉」明和8年(1771年)初演 東京大学教養学部国文・漢文学部会,黒木文庫それまで、江戸の大スターと楽しい宴を共にして大喜びしていたかをり(稲垣来泉さん)ら女郎たち。
ところが、この浄瑠璃が始まったとたん、シンと静まり返ってしまいました。感極まって涙を流すもの、鼻をすするもの…。
あまりの反応に「こんな座興で」と太夫たちが戸惑っていると、蔦重が彼女たちの涙のわけを説明しました。
「座敷芸で芝居や浄瑠璃に親しむものの、幼い頃より廓で育ち、まことの芝居は見たことがない者がほとんど。この江戸にいながら一度も芝居を見ず、この世に別れを告げる者もおります」。宴席で太夫と女郎を引き合わせ、太夫に吉原に関心を持ってもらおうというアイデアも、かをりが「わっちは駕籠の鳥。まことの芝居など見たことありんせん。いつかわっちの手を取り芝居町へ」と蔦重にせがんだことが発端でした。
外出は厳しく制限された女郎
吉原の出入りを厳しく制限される女郎たち。実質監獄のようなもので、原則として10年とされる年季が明けるか、身請けされるか、受診や病気療養以外に大門を出ることは許されませんでした。ただし例外はあり、遣手の監視付ながら馴染みに連れられて芝居見物したり、神社にお参りしたり、遊郭を挙げて飛鳥山や向島に花見見物に行ったりするケースはありました。ですから今回のように大挙して向島に出かけることも、遊郭の主人や女将が付き添っているのであれば、不自然ではなかったでしょう。いずれにせよ、性病などの重い病や貧困で吉原からあの世に旅立った女性は決して珍しくありません。蔦重の脳裏にはこういった過去のシーンが浮かんでいたことでしょう。
蔦重たちの恩人、非業の死を遂げた花魁の朝顔姐さん(愛希れいかさん)も芝居を見る機会は果たしてあったのでしょうか。吉原に暮し、女郎の真実をよく知る蔦重であれば、「本物の芝居を見たい」「浄瑠璃を聞きたい」という彼女たちの悲痛な思いに深く同情するのも当然です。
アーティスト魂を震わせた
知識や教養は豊富でも、本当の芸術の凄味を初めて肌で感じた女郎たちの涙。恵まれない境遇の中で、自分たちの芸に心から感動してくれる人がたくさんいるという事実は、太夫のアーティスト魂を奮い立たせました。「吉原には太夫のお声を聞きたい女郎が千も二千もおります。救われる女がおります。どうか女郎たちのためにも、祭りの場でその声を響かせてはくださいませんか」という蔦重の思いが太夫たちに伝わったのです。次回、牛之助改め豊前太夫は、「俄」の舞台でどんな歌声を響かせてくれるでしょうか。
大奥女中の必須教養でもあった富本節
馬面太夫の芸である浄瑠璃とは室町時代にはじまり、江戸時代に完成した語り物の総称です。伴奏楽器は三味線。国史大辞典(吉川弘文館)などによると、三河国の長者の娘浄瑠璃姫と牛若丸との恋物語を描いた『浄瑠璃物語』が大いに人気を博し、やがてこの種の語り物が浄瑠璃と総称されるようになったといわれています。義太夫節、豊後節など様々な流派が起り、操り人形と結びついて高い芸術性を獲得した人形浄瑠璃が名高いですが、歌舞伎と結びついたもの、座敷芸として発展したものなど様々な形態で演じられました。
鳥橋斎栄里筆「富本豊前太夫」 1795年頃 メトロポリタン美術館蔵富本節は太夫の父、初世豊前掾(1716‐1764)が寛延元年(1748年)に独立したのがはじまり。二世となる太夫(1754‐1822)は10歳の時に父と死に別れましたが、天性の美声の持ち主で、富本節の全盛時代を築きました。顔が長く、「馬面豊前」「馬面太夫」などと言われたそうです。代表曲『浅間』などでその美声で江戸じゅうを沸かせました。
あの不昧公も絶賛
支配層にもその名は知られました。松江藩主で大茶人として当代きっての文化人だった松平不昧ふまい公(治郷)からその才能を讃えられ、「七重八重 野辺のにしきや 桜草」という俳句を賜ったので、それまでの鶴の紋所を桜草に変更したという逸話さえあります。また江戸城の大奥女中の採用にあたっては、富本節の教養が問題になったといい、当時の社会でいかに大きな影響力を誇ったかが分かります。
「馬面太夫」の追っかけ話が黄表紙に
その人気ぶりを映す一冊があります。「桜草野辺錦」という黄表紙で、豊前太夫が主人公です。「江戸の声ー黒木文庫でみる音楽と演劇の世界ー」(発行・東京大学大学院総合文化研究科教養学部美術博物館、編者・ロバート・キャンベル)によると、黄表紙らしい誇張はあるにせよ、現代の「アイドル推し」を思わせる熱狂的なエピソードには驚かされます。
宿屋飯盛 [作] ほか『桜草野辺の錦 : 3巻』,[天明3(1783)]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892499子どものころに親から伝えられた浄瑠璃で天下一になった豊前太夫。中村座の歌舞伎「八百屋お七恋の江戸染」で「文月笹の一夜」という曲で出演。大評判になりました。もともと旅籠を営んでいた太夫、これをやめて煎餅店を出したらこちらも大当たり。アイドルが運営に携わる公式ショップのようなものでしょうか。「推し」の熱の高まりは留まるところを知りません。太夫が料理店に立ち寄れば入口で騒ぎ立て、裏口から逃げると追いかけ、船を出して川向こうに渡ると、女たちは川を渡って後を追います。道成寺の清姫も顔負けです。
ライバルの流派が稽古本を鎧の形につけて押し寄せてきますが、ファンの女性たちが三味線を振り上げて応戦。蹴散らします。
ライバルとのバトルも制し、世の中はすべて富本節になったので、たくさんの鶴に門弟たちの名札をつけて放しましたーー。という筋です。荒唐無稽ではあるものの、富本節の隆盛を雄弁に物語る黄表紙です。またアーティストとファンの関係性の表現は、この時代と現代の社会との近さも伺わせます。
固い経営基盤を得た蔦重、ドラマ作りの妙
これほどの人気を誇った富本節だけに、ファンは争って関連の出版物を求めました。太夫と強い信頼関係で結ばれた蔦重は、浄瑠璃の歌詞をまとめた直傳の「正本」などを独占的に販売していくことになります。蔦重のビジネスにとって、これは大きな前進でした。
これまで『一目千本』や『青楼美人合姿鏡』など、吉原の女郎をテーマにした出版物で世間の耳目を集めてきた蔦重ですが、こうした書籍はドラマでも描かれたように当たりはずれが大きく、リスクを避けることはできません。現在からみると、歌麿や写楽らと取り組んだ新機軸の仕事がクローズアップされがちな蔦重ですが、実際は堅実派で、浄瑠璃関連書籍や、寺子屋などの初等教育で用いられるテキスト(往来物)などを扱い、安定した収入を確保した上で大胆な企画に挑戦していたのです。蔦重にとって重要な太夫との関係構築の過程を、想像を交えて印象的なエピソードにまとめたドラマ作りの妙でもありました。
瀬以と蔦重の関係に嫉妬する検校
「俄」を盛り上げて、吉原に人を呼び込むためにはスターの馬面太夫を呼ぶのが一番、と大文字屋(伊藤淳史さん)が発案。ところが太夫は以前、吉原の遊郭で役者と間違われて出入り禁止をくらい、吉原にいい感情を持っていないことが判明します。浄瑠璃の元締めは鳥山検校(市原隼人さん)の率いる「当道座」であることから、口添えを期待して大文字屋と蔦重は検校邸を訪ねます。
妻の瀬川改め瀬以(小芝風花さん)と、蔦重との親密なやり取りを耳にした検校。その関係性にただならぬものを感じ、嫉妬の感情を募らせます。今後のストーリーの上でも重要なエピソードになりそうです。複雑な思いを抱えつつ、検校は妻の願いを聞き入れて太夫の浄瑠璃を聞き、その技量に納得。「豊前太夫」の襲名を認めます。
とはいえ、瀬以への「そなたの望むことはすべて叶えると決めた」という検校の言葉の裏側には、明らかに蔦重への対抗心が見え隠れしました。何やら不穏なものを感じてしまう展開です。
音楽の発展に不可欠だった目の不自由な人たち
「日本盲人史」(成光館出版部)、「日本盲人史考ー視覚障害者の歴史と伝承 金属と片眼神—」(米子今井書店)などによると、三味線音楽の発展に際しては、目の不自由な人々が大きく貢献しました。琵琶を用いて「平家物語」を語っていたような人たちも浄瑠璃に移り、その基礎を築いたと考えられます。ドラマでも描かれたように、江戸時代になると浄瑠璃などの芸能が広く庶民にまで普及し、三味線の担い手も健常者が増えましたが、そうした音楽の基礎を作ったのは目の不自由な人たちである、という概念は広く社会に受け入れられていました。また三味線の手ほどきを受ける際は、やはり目の不自由な人から教えてもらうことが多かったとみられ、「当道座」の力はそうした音楽や浄瑠璃の分野にも引き続き及んでいたとみられます。
吉原を華やかに彩った「俄」、本物の芸を間近に
今回、テーマになった吉原の「俄」は九郎助稲荷の祭礼に合わせて催されたといわれる吉原芸者衆の余興です。8月の朔日(一日)から晴天の日に限って30日間、開催されました。雨の多い年は10月まで行われることもあったそうです。火災による中断などを経て、1775年(安永4年)に再興されてから年々、盛んになったということなので、ドラマの前年から盛り上がったということになります。客寄せのイベントとして、忘八たちに力が入っていたのも納得です。
礒田湖龍斎筆「青樓藝子俄狂言盡・玉屋弥八内三味線こん、きくぢ、こきう いその」 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)吉原の芸者衆は別格中の別格
「大吉原展」図録などによると、俄の出し物は茶番狂言や舞踊、所作事などを引手茶屋や妓楼の前で披露し、練り移っていくもの。吉原の俄が何と言っても特別なのは、トップクラスの芸者衆がその技を披露する点です。踊りや三味線、唄などで高い技能を持つ人物しか吉原芸者にはなれず、在野の芸者衆とは扱いが全く別物で、その地位は高かったのです。吉原の場合は男芸者も存在感があり、義太夫節や富本節などを語る太夫衆が中心だったといいます。また幇間や人形遣いもいました。
喜多川歌麿筆「青樓仁和嘉・花の田植廓の賑ひ」江戸時代・寛政10年(1798) 東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)そうした一流の芸を庶民が見ることは難しかったのですが、この吉原の俄では足さえ運べば気軽に間近で観られるということで、非常に人気が高かったのです。ここに大スターの馬面太夫まで加わるとなれば、どれほど盛り上がることでしょう。次回が楽しみです。
「日光社参」、その桁外れのスケールの光と闇
忘八たちが「俄」に注力した背景として、日光社参をモチーフにしたのが史実の使い方として巧みでした。家康の命日(4月17日)にあわせて将軍が日光東照宮に参拝することいい、1776年(安永5年)4月に行われた第10代将軍家治の日光社参は、1728年(享保13年)の8代吉宗の社参以来で実に48年ぶりの挙行。久々の大スペクタクルになりました。
行列の先頭が夜半に江戸城を出てから、最後尾が出発するまで12時間もかかったという桁外れのスケールです。
見物客が押し寄せ、社参に参加した大名らの顔触れを紹介したガイドブックも売れました。田沼意次が経済政策の一環として重視した南鐐二朱銀の流通拡大にも貢献したことでしょう。一定の「経済効果」を挙げたはずです。「やはり街を盛り上げるには非日常のイベントが必要」と忘八たちに確信させました。
<日光御成街道ルート>
鈴木理生・鈴木浩三『ビジュアルでわかる 江戸・東京の地理と歴史』(日本実業出版社刊)105Pと107Pから著者の許可を得て転載将軍の通る街道も整備されました。日光社参全体では、幕府の年収の7分の1にあたる22万両もの費用が掛かったといいます。一方、人馬などの提供を求められる関東各地の農村に掛かる負担は極めて大きく、地域の荒廃を進めたとされます。その後、意次、定信の命運も大きく左右する浅間山の天明の大噴火(1783年)、天明の大飢饉(1782∼1787)という国家的な危機も迫ってきます。幕府パートも徐々に緊迫の度を加えてくるでしょう。
喜三二と春町、いよいよドラマの前面に!
何度もクレジットで登場、「尾美としのりさんはどこに映っている?」と話題になっていました。いよいよ蔦重と会話を交わしました。
遊び慣れた風体で、蔦重の制作した「青楼美人合姿鏡」に対する批評も「志津山が琴を弾くなんていいねえ」とやたらに具体的。相当な事情通のようです。
琴に向かっているのが志津山。北尾重政・勝川春章筆「青楼美人合姿鏡」から 江戸時代・安永5年(1776) 東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)この人の平沢常富という男の正体は出羽・秋田藩の江戸留守居役という立派なお侍。ただしこれまでの行動でご覧になったとおり、吉原の常連で「宝暦の色男」の異名で知られた存在でした。
のちに平沢常富(朋誠堂喜三二)が文章を考え、蔦重が出版した黄表紙朋誠堂喜三二 作 ほか『亀山人家妖 3巻』,[蔦屋重三郎],天明7 [1787]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/8929457のちに朋誠堂喜三二の名前で流行作家になり、絵師の北尾重政とともに蔦重の最大の協力者として蔦重の成功を支えることになります。今後、ドラマでも大いに活躍すること間違いない人物です。鱗形屋(片岡愛之助さん)が手掛け、大ヒットになった黄表紙「金々先生栄花夢」の作者、恋川春町も初めて登場しました。鱗形屋の息子に絵を教えていたとおり、文章も絵画も高いレベルでこなすマルチクリエーターです。こちらも素顔は武士。駿河・小島藩の倉橋格です。自らが仕える小島藩の都合で鱗形屋をピンチに陥れたことを気にかけ、現在は鱗形屋に肩入れしている春町ですが、のちには蔦重と深くつながることになります。春町は喜三二とも縁が深く、「喜三二の文に春町の絵」という形で協働する場面も出てくるでしょう。ストーリーのカギを握るこの2人にはぜひ注目ください。(美術展ナビ編集班 岡部匡志)
本記事で使用した一部の地図は、鈴木理生・鈴木浩三『ビジュアルでわかる 江戸・東京の地理と歴史』(日本実業出版社刊)から、著者の許可を得て掲載しました。購入はアマゾンなどで。