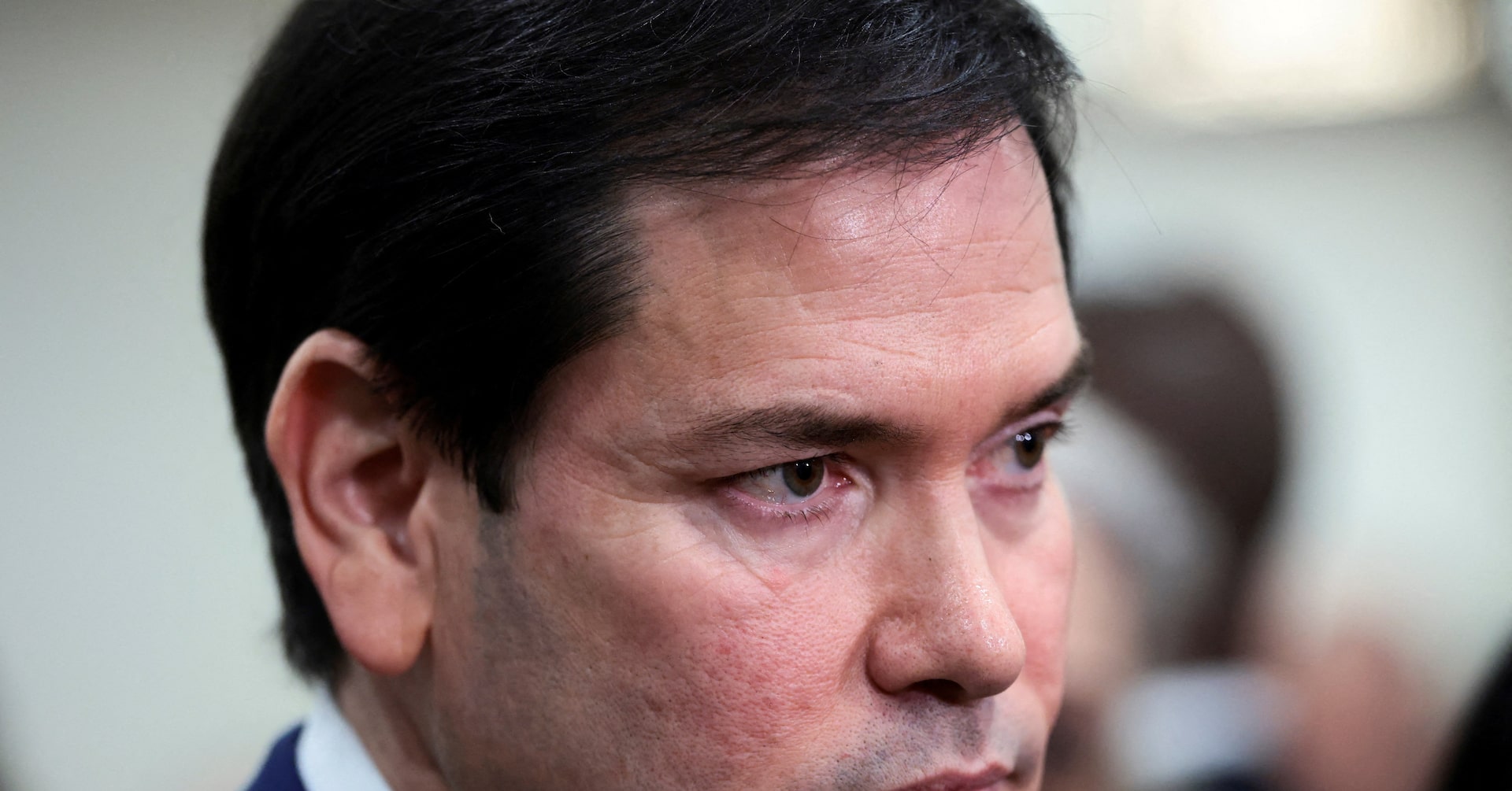中国がアフリカの大統領府を作った ソファに「龍」の彫刻 OECD加盟国なら〝禁じ手〟

公に目にする記者会見の裏で、ときに一歩も譲れぬ駆け引きが繰り広げられる外交の世界。その舞台裏が語られる機会は少ない。戦後最年少(50歳)で大使に就任し、欧州・アフリカ大陸に知己が多い岡村善文・元経済協力開発機構(OECD)代表部大使に、40年以上に及ぶ外交官生活を振り返ってもらった。
「中国進出」どころか「中国席巻」
南アフリカのラマポーザ大統領(左)と握手する中国の習近平国家主席=北京の人民大会堂(新華社=共同)《外務省有数の〝アフリカ通〟として、ここ十数年のアフリカ大陸での中国の伸長ぶりには驚かされてきたという》
東アフリカ、西アフリカ、南部地域を問わず、アフリカへの中国の経済進出には目を見張るものがあります。「中国進出」どころか、「中国席巻」の状態。以前、アフリカにとって最大の貿易相手はフランスや英国などの旧宗主国や米国などでした。しかし今は全部、中国。アフリカのどの国も第1位は中国です。
私たち先進国の中で「常識」と思っていることは、アフリカでは「常識」ではない。たとえば携帯電話でいうと、私たちはアップルやサムスンが世界を支配していると考えています。しかし、アフリカにそれらはほとんどない。試しにアフリカ人に「スマホを見せてくれ」と言ってみれば分かります。アフリカ人のスマホはほぼ全て、中国製なのです。
アフリカのスマホ、中国が支配
(ロイター)《中国製の性能は先進国並みに高くない。しかし、技術的に工夫し、ツボを押さえた仕様だという》
私たちは、アフリカ人が中国のスマホを買うのは、「安かろう、悪かろう」だから、と考えます。最先端の半導体を使わず安いようですが、決して「悪かろう」ではない。
アフリカ人はよく不満をこぼします。「アップルやサムソンを使うと、自分たちの顔が映らない」と。確かに、アフリカ人の顔を撮影すると、真っ黒になり、きちんと映らない。ところが、中国製のスマホだと、鼻や口、目などが奇麗に写り、表情が出る。色彩を考えた「アフリカ仕様」なのです。そういう製品は、市場では強いわけです。
先進国は甘いと思います。アフリカのスマホ市場を中国が支配するとは、どういうことか。ソフトも中国製であり、購買履歴やGPSの位置情報をはじめ、アフリカの人々の行動の情報がみな中国に流れるということです。こうして、中国が着々と支配力、覇権を確立しつつあるのです。
中国が作る舗装道路は10倍も長い
OECD閣僚理事会の関連会合「炭素緩和アプローチに関する包摂的フォーラム」閣僚対話で、演説する岸田文雄前首相=パリ(共同)《中国がアフリカで有利な地位を占めるのは、〝先進国スタンダード〟に縛られないことも理由だという》
中国は経済協力開発機構(OECD)に加盟していません。このため、OECDのルールに縛られることはない。OECDには、インフラを整備する際、社会的影響や環境を考慮したさまざまなルールが存在し、加盟国はみんな、安全・開発基準面でお互いを縛っています。しかし、中国は全く縛られない。
たとえば、同じ資金で道路を建設する際、10キロしか作れない〝先進国基準〟があるとすれば、中国は100キロぐらい簡単に作ってしまう。アフリカにしてみれば、基準がどうのこうのより、とにかく100キロの舗装道路ができた方がよっぽどいいのです。だからどんどん、アフリカが中国になびくのです。
中国の大建造物、〝アフリカの首都〟に
エチオピアの首都アディスアベバにある「アフリカ連合」(AU)の本部。中国の資金で堂々と立つ(ロイター)《アフリカを訪れると、大統領府や国会議事堂、スタジアムなどの多くを中国が作っているという現実を突き付けられる》
有名なのが、〝アフリカの首都〟ともいわれるエチオピアの首都アディスアベバにある「アフリカ連合」(AU)の本部です。ニューヨークの国連本部のような建物が、中国の資金で建設され、堂々と立っている。
私が2008年、西アフリカのトーゴとベナンの大使として、両国の大統領に信任状を捧呈するため大統領府を訪れたとき、大変、驚かされました。
どちらの大統領府も、中国が建設し、寄贈していたのです。廊下を歩いていると、消火栓の施設が漢字で「消火栓」と書かれてあった。現地の人が読めない文字で、火事の時に大丈夫なのだろうか、とも思いました。
〝人気取り〟はタブー
大統領府の待合室に入ると、高級ソファがあった。肘掛け部分には、竜の彫り物が施されていました。そうした大統領府、スタジアム、国会議事堂を建設する〝人気取り〟の建設を「してはいけないよね」というのが、OECDに加盟する先進国の良識あるルールです。ところが、中国はそんなものに縛られず、各国で建設をどんどん進めている。
OECDは、加盟国がアフリカに開発協力の融資を行う際、さまざまなルールを設けていますし、世界銀行も融資に際し、アフリカ側に厳しい政治・財政の条件を突き付けます。
ところが、OECDに加盟していない中国は難しいことを言わない。アフリカの国々は、借りやすい中国の資金を借りることになるのです。
中国は、相手国が多額の債務を返済できない場合、港湾施設など重要なインフラ権益の譲渡を迫る「債務の罠(わな)」をつかうのだと悪口を言われます。しかし、中国がアフリカ各国を罠にはめようとして資金を貸し出すわけではない。中国の資金のほうが使いやすいから、進んで中国の資金を借りるのです。
アフリカ各国が中国になびき、結果として欧米や日本などに排他的になるわけではありません。それでも、中国がアフリカでのビジネスを席巻すれば、中国の企業やビジネスマンたちも根を広げ、いい意味でも悪い意味でも関係を深化させ、「中国なしにアフリカは成り立たない」ということになる。そうした状況になることを私は大変、危惧しています。(聞き手 黒沢潤)
〈おかむら・よしふみ〉 1958年、大阪市生まれ。東大法学部卒。81年、外務省入省。軍備管理軍縮課長、ウィーン国際機関日本政府代表部公使などを経て、2008年にコートジボワール大使。12年に外務省アフリカ部長、14年に国連日本政府代表部次席大使、17年にTICAD(アフリカ開発会議)担当大使。19年に経済協力開発機構(OECD)代表部大使。24年から立命館アジア太平洋大学副学長を務める。