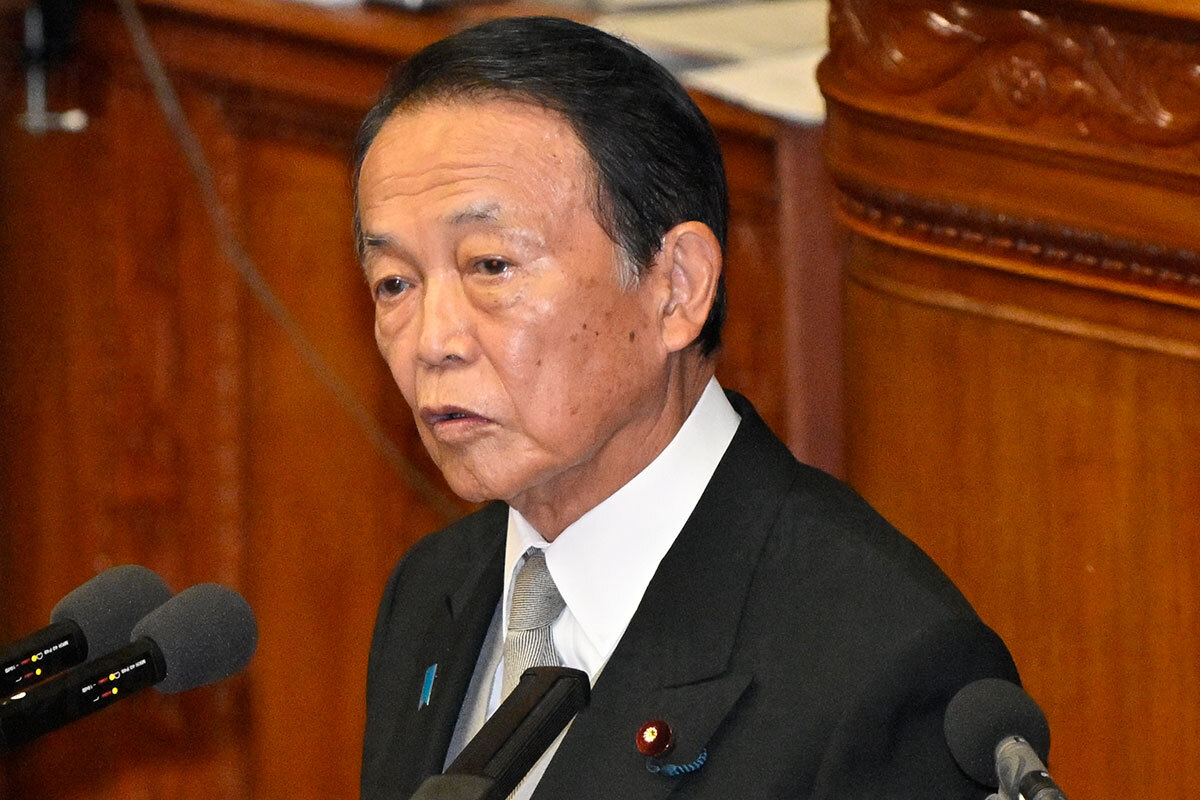日本学術会議、監事が活動を監査 法人化法案を閣議決定

- 記事を印刷する
- メールで送る
- リンクをコピーする
- note
- X(旧Twitter)
- はてなブックマーク
- Bluesky
政府は7日、日本学術会議を2026年10月から国の特別な機関から特殊法人に移行する新たな法案を閣議決定した。国が財政支援した上で首相が任命する監事を置き、業務や財務を監査する。民生・軍事両用の「デュアルユース」技術の研究の推進につながる期待がある。
政府は今国会での法案の成立をめざす。現行法は廃止する。
学術会議は幅広い学問の分野の学者が集まる組織だ。20年に当時の菅義偉首相が推薦候補6人の任命を拒んだことがあり方を見直すきっかけになった。
新法案は「学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする」と明記した。研究と社会での成果の活用の両立をはかる。国は運営の自主性、自律性に配慮しなければならないとも規定した。
大きな論点となっていた会員選考について、学術会議の推薦をもとに首相が任命するしくみをやめ、新法人は学術会議総会が会員を任命する。外部有識者からなる選定助言委員会が意見を述べる。会員数を現行の210人から250人に増やす。政府への勧告権限は維持する。
会員任期は6年で1回に限り再任できる。定年は現在の70歳から75歳にする。幅広い研究分野から人を集めて年齢や性別などに偏りが出ないように努めるとした。
学術会議は6事業年度ごとの中期的な活動計画とともに毎年度、計画を定めて公表する。首相が会員以外の人から任命する監事を置く。監事は必要に応じて首相と会長に意見を提出する。
首相は内閣府に置く評価委員会の委員も任命する。委員会は同会議が出す自己点検評価について審議する。
政府は23年の通常国会で現行法の改正案の提出をめざしたが、同会議が「独立性が脅かされる」などと反発して見送った経緯がある。同年8月に会議のあり方を議論する有識者懇談会を設置し、24年4月からは会員選考や組織・制度について2つの作業部会で話し合ってきた。
学術会議は1950年と67年に戦争目的の科学研究は絶対にしないとする声明を出した。科学技術の軍事利用がかつて戦争の一因になったとの考えが背景にある。
22年に軍民両用と軍事に無関係な研究を明確に分けるのは難しいとの認識を示した。23年にはこの考えを維持する見解を出して研究を事実上容認したものの、かつての姿勢がデュアルユース技術の研究の遅れにつながったとの指摘がある。
デュアルユースは海外で推進が先行する。米国では国防総省の研究機関「国防イノベーションユニット」(DIU)が中心となり、民生技術を安全保障でも活用するために企業との橋渡しを担う。装備品の試作などを通じて、先端技術を用いた装備品の量産を狙う。
日本は防衛省と経済産業省がスタートアップとの連携機会を伺う。意見交換会を開いたほか、スタートアップが出展する展示会を開催してきた。企業も自衛隊装備や政府の支援策を把握し、参入や協業を探る。
デュアルユースの活用はトランプ米政権へのアピールポイントともなり得る。先端技術を取り込んで防衛力をさらに強化することは、地域の安保で責任を担うとの証左となる。米軍も日本企業の技術に関心を示しており、連携が進めば米側の利益にもなる。
安全保障に先端技術を活用することは懸念もある。政府は新興技術の軍事利用に関して「人間中心の原則を維持し、責任ある形で行われることを重視する」との立場をとる。人工知能(AI)など人間の判断を介さずに攻撃する兵器が使われるようになれば安全保障上の脅威になる。
林芳正官房長官は7日の記者会見で「社会課題の複雑化・深刻化が進み、国民生活や政策立案に学術的な知見を取り入れていく必要性がこれまで以上に高まっている」と指摘した。「学術会議の機能が強化され、国民の期待にしっかりと応えていくことを期待している」と述べた。
学術会議の光石衛会長は2月27日、法案について「懸念を払拭するものとなっていない」とする談話を出した。監事の設置や会員選考の自主性などの面に懸念があるという。「学術会議のより良い役割発揮のためには、政府との相互の信頼関係が重要だ」と指摘した。
- 記事を印刷する
- メールで送る
- リンクをコピーする
- note
- X(旧Twitter)
- はてなブックマーク
- Bluesky
こちらもおすすめ(自動検索)
操作を実行できませんでした。時間を空けて再度お試しください。
権限不足のため、フォローできません
日本経済新聞の編集者が選んだ押さえておきたい「ニュース5本」をお届けします。(週5回配信)
ご登録いただいたメールアドレス宛てにニュースレターの配信と日経電子版のキャンペーン情報などをお送りします(登録後の配信解除も可能です)。これらメール配信の目的に限りメールアドレスを利用します。日経IDなどその他のサービスに自動で登録されることはありません。
入力いただいたメールアドレスにメールを送付しました。メールのリンクをクリックすると記事全文をお読みいただけます。
ニュースレターの登録に失敗しました。ご覧頂いている記事は、対象外になっています。
入力いただきましたメールアドレスは既に登録済みとなっております。ニュースレターの配信をお待ち下さい。