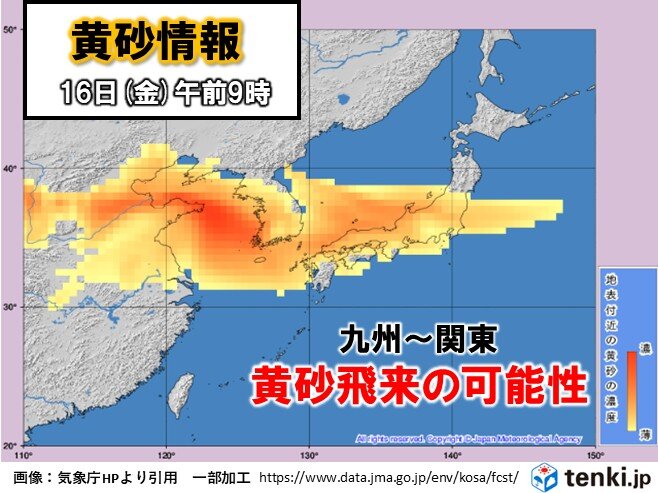流動化する日本政治はどこへ行くのか

参議院議員選挙が始まる前に、「日本政治はいよいよ本格的な流動化の時代に入ったか」という題名の記事を書いた。
参照:日本政治はいよいよ本格的な流動化の時代に入ったか 篠田 英朗
参議院選挙の結果は、ほぼ予想通りとなった。多数派を形成する安定した連立政権も組めない諸政党が乱立する現状は、先行きが読めないものだ。
野党支持者と思われる方々が、「石破辞めるな」の運動を熱心に開始したことが話題だ。もともと石破首相は、「党内野党」と言われていた時期から、世論調査では首相候補として一番人気だった。これは当時から、自民党支持者以外の間で、他の自民党の首相候補と比して人気が高かった、ということを意味していただろう。したがって今の状況は、予測されていたことだ。
自民党の政治家たちは、当然、複雑な心境だろう。一方では、非自民党支持者の間で人気が高いからといって、それを理由にして石破首相を支え続ける気がしないとすれば、それはわからないでもない。
しかし、現状は、連立相手の公明党や、野党第一党の立憲民主党を中心にした大連立に可能性を視野に入れる必要性がある。石破首相という選択肢には合理性がある、ということだ。老舗の政党である立憲民主党には、自民党側から見て顔なじみの議員が多く、政策ごとの協力は、計算が立つところもあるだろう。
石破首相ではない人物を選ぶ場合、特に右派のイメージが強い高市氏を選ぶ場合、石破首相を消極支持する野党との協力関係を築けない恐れが出てくる。安倍首相の時代には、右派の政党の台頭を許さず多数派を獲得できていたが、現状は全く異なる。野党との協力が必至だ。石破首相以外の人物を首相に据えて、野党とうまくやっていけるのかは未知数の度合いが高いだろう。
石破首相がトランプ大統領との間で達成した関税交渉も、「文書化しない」状況で、日米で全く異なる解釈が表明されている。先行きの不透明感の強さを象徴する事例であると言える。
米国の関税措置に関する日米協議についての会見する石破首相 首相官邸HPより
「本来のあるべき政党政治は・・・」、といった切り出しで、様々な方々から、異なる色々な意見が出てきそうである。しかし日本は今、現実の現状の中で、このような状況になっている。むしろ焦りは禁物である。まずは現状の停滞感・焦燥感に耐える覚悟を定めるしかない。
■
国際情勢分析を『The Letter』を通じてニュースレター形式で配信しています。
「篠田英朗国際情勢分析チャンネル」(ニコニコチャンネルプラス)で、月2回の頻度で、国際情勢の分析を行っています。