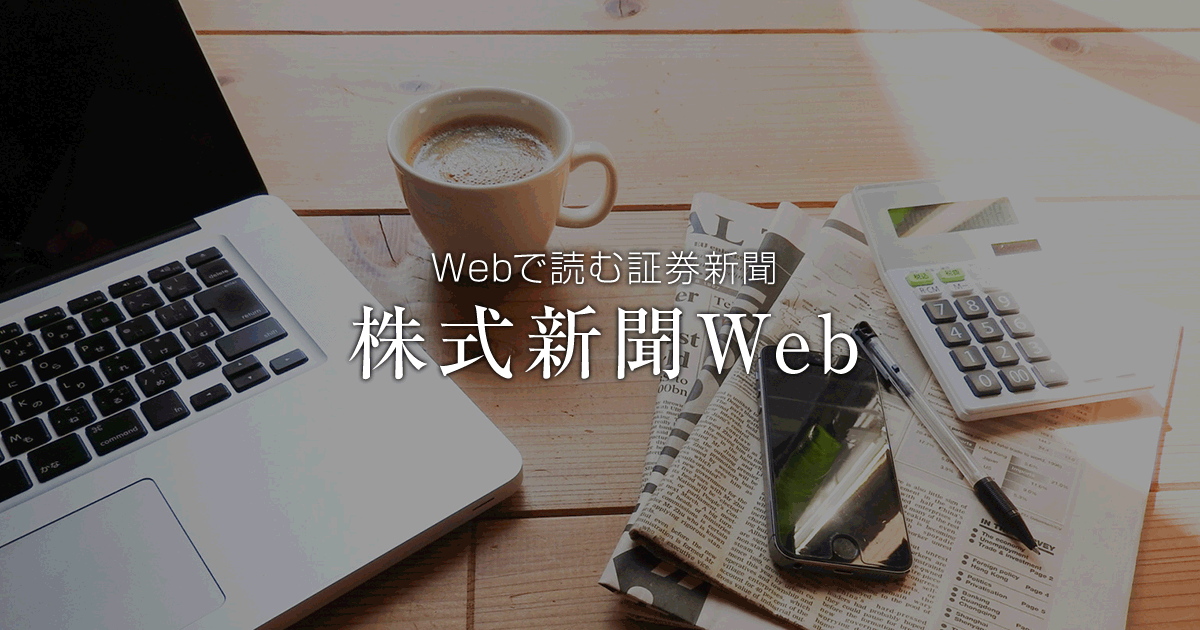コラム:金急騰と米国債の波乱、背後に巨大プレーヤーか

[ロンドン 16日 ロイター] - 過去2年間で初めて、米国の超大型ハイテク株は「世界で最もポジションが集中する取引」の座を失った。代わりにその座に就いたのは金で、中国による驚くほど大量の金現物購入がその一因だ。
バンク・オブ・アメリカ(BofA)が世界のファンドマネジャーを対象に実施した直近の月間調査では、貿易戦争の激化に伴って投資家の懸念と取引パターンが変化していることについて、非常に興味深い詳細がいくつか浮かび上がった。
世界の投資家は、今後1年間の最大のリスクに貿易戦争をきっかけとする景気後退を挙げ、過去2カ月間にかつてない規模で米国株の保有を減らした。その結果、ファンドの36%は米国株をアンダーウェートにしている。これは過去約2年間で最も弱気な米国株ポジションだ。
保有削減の規模があまりに大きいため、「マグニフィセントセブン」と呼ばれる超大型ハイテク7銘柄を筆頭とする割高な米大型ハイテク株は、過去2年間で初めて、最もポジションが集中する取引の座を明け渡した。
金価格は年初から23%も上昇して1オンス=3200ドルを超えた。世界のファンドの正味42%は、今年最も大きく上昇する資産が金になると予想しており、現金もしくは米国債を挙げた割合の2倍以上に達した。この予想には一理ある。金以外の資産が、年初来の金の上昇率にこれから追い付くのは難しいだろう。
From crisis hedge to record setter: Gold hits $3,200 milestone<米国債の売り手は>
長年にわたり、世界の外貨準備やソブリンファンドから安全資産と見なされてきた米国債が乱高下する中、投資家は金に殺到し続けている。先週だけ見ても、30年物米国債利回りは過去40年余りで最も大きく上昇した。しかも米国株が大幅下落する中での出来事だ。
米国債波乱の原因について数多くの仮説が出回っており、その1つが中国による米国債の売却だ。おそらく多くの代理保有者を通じて売ったとみられている。トランプ米大統領が中国以外の国々について関税の脅しを和らげる中でも、中国に対しては貿易障壁を引き上げ、報復合戦に発展していることから、中国による売却説が浮上した格好だ。
何が米国債相場下落の引き金を引いたのかを示す明確な証拠はない。しかし中国は過去2年間に米国債保有を減らし続けている一方、外貨準備における金の保有を大幅に増やしている。
China has been ramping up its gold purchases, along with countries such as India,中国の外貨準備に占める金の割合は現在8%と、新型コロナ禍の直前に比べて約3倍の割合に増えた。
ソシエテ・ジェネラル(SG)のストラテジストらはこの状況を分析した上で、11日に公表された英政府の輸出データにより、2月もまた、中国が英国から50トンもの金を輸入したことが確認できたと指摘している。
SGは英歳入関税庁のデータに基づき、過去2年間に中国が英国から輸入した金が700トンと「驚異の」規模に上ったと推計。「その多くが中央銀行に向かった」と指摘している。
ワールド・ゴールド・カウンシルが14日発表したデータを見ると、金現物を裏付けとする中国の上場投資信託(ETF)への資金流入が、今月初めから現在までに第1・四半期全体の額を既に超えていることも注目される。この額は、米上場ETFへの流入額を上回っている。
なぜ英国なのか。イングランド銀行(英中央銀行)は安全な保管庫と信頼の置ける金融サービスで知られ、多くの外国顧客のために金を保管しているからだ。
なぜ中国なのか。中国政府は近年、米国債の保有削減を加速させている。特に、ロシアがウクライナに侵攻し、欧米でロシアの外貨準備が凍結されて以来、そのペースは速まっている。金の現物は、同様の制裁を科されにくい数少ない保有資産の1つだ。
金相場の急騰、米中貿易戦争、足元の米国債波乱という3点を結びつける1つの「ひも」はあるだろうか。SGは間違いなく、これらの関連について検討に値すると考えている。SGは「米国債から金への資金移動には、おおまかな相関があり、ある程度追跡可能だ。そして米国債の売却が、中国への金の輸出と一致することには注目せざるを得ない」と指摘する。
それが決定的な証拠とは言えないまでも、少なくとも注目すべき兆候かもしれない。
Dollar is down 8.2% versus a basket of other top currencies this year(筆者はロイターのコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています)
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
Mike Dolan is Reuters Editor-at-Large for Finance & Markets and a regular columnist. He has worked as a correspondent, editor and columnist at Reuters for the past 30 years - specializing in global economics and policy and financial markets across G7 and emerging economies. Mike is based in London but has also worked in Washington DC and in Sarajevo and has covered news events from dozens of cities across the world. A graduate in economics and politics from Trinity College Dublin, Mike previously worked with Bloomberg and Euromoney and received Reuters awards for his work during the financial crisis in 2007/2008 and on Frontier Markets in 2010.