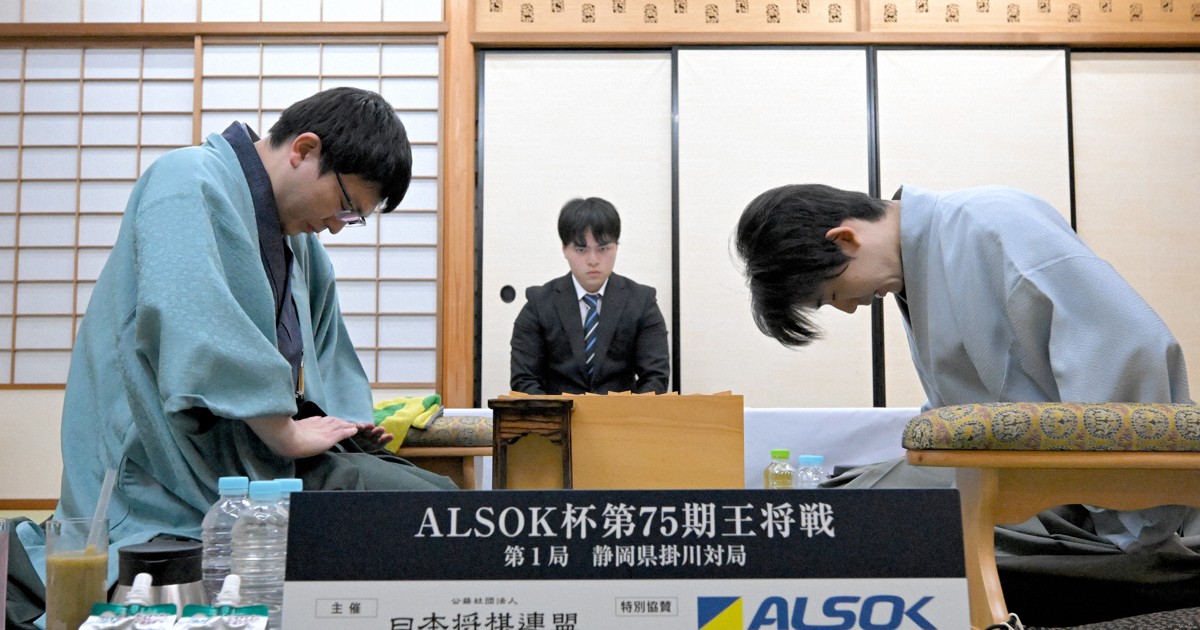アニメ産業崩壊リスクに国連も警鐘-低賃金や長時間労働の是正急務

「声優という職業では、とても食べていけない」。首都圏に住む柴田由美子さん(60)は20代のころ、人気アニメに声優として出演する傍ら、夜は六本木や銀座のナイトクラブで働いて生計を立てていた。
「聖闘士星矢」の春麗役などの人気キャラクターを10年ほど演じた後も平均的な報酬は変わらず、1日5000円程度だった。所属事務所への手数料10%を差し引くと手取りはわずか。報酬はその後、多少上がったものの、現在は主に整理収納アドバイザーとして働いている。
「鬼滅の刃」や「呪術廻戦」などの世界的なヒットが続き、日本動画協会によるとアニメ産業市場は2023年に約3兆3000億円と過去10年間で2倍超に拡大した。海外ファンドからの投資や、企業の合併・買収(M&A)も活発化。東宝は24年に米国でジブリ作品などを配給する米GKIDSを買収すると発表し、ソニーグループはKADOKAWAの筆頭株主になるなどコンテンツ事業の強化を図っている。
一方、利益は多くの声優やアニメーターらクリエーターの手には届いていない。日本アニメーター・演出協会による22年の調査では、20-24歳のアニメーターの平均年収は約197万円と、東京都の同年代の平均約350万円を下回る。コンテンツ需要の高まりで18年の約155万円からは増加したものの、米労働統計局が示す米アニメーターの平均年収の半分以下にとどまっている。
ブルームバーグ・ニュースが取材した20人以上のアニメ業界の関係者からは、低賃金のほかにも長時間労働や給料の未払い、書面を交わさない取引など厳しい労働環境について指摘する声が上がった。こうした現状について、1月に公正取引委員会が調査に乗り出し、変化の兆しが表れ始めている。
ガバナンス意識
資本市場でガバナンスへの意識が高まる中、労働環境の改善や法令順守は、活況なアニメ産業への投資を継続させるための鍵となる。24年11月に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)によって保護の対象が広がり、委託元にはアニメ制作者の大半を占めるフリーランスへの対応の改善が求められている。
マッコーリーキャピタル証券の山科拓アナリストは「アニメは日本が世界で圧倒的優位を獲得し得る数少ない産業の一つだが、業界の労働慣行は周回遅れ」と述べ、業界のガバナンスの弱さが将来的に海外からの投資機会を奪う可能性があると指摘する。
24年5月には、国連人権理事会の作業部会が日本のアニメ業界では過剰な長時間労働や低賃金、不公正な請負関係などの問題があると指摘した。調査を指揮したピチャモン・イェオファントン氏はブルームバーグ・ニュースの取材に対し「搾取的な労働慣行に断固として対処しなければ、アニメ産業が崩壊する可能性は現実的なリスクだ」と警鐘を鳴らした。
製作委員会方式の功罪
日本の本格的なテレビアニメの始まりは、1963年に放送を開始した手塚治虫氏の「鉄腕アトム」だった。専修大学非常勤講師の長谷川雅弘氏らによると、毎週30分の放送を限られた資金で継続し、版権を利用して関連グッズなどで収入を得る事業モデルがこの作品以降、浸透した。
現在は、出版社や放送局、おもちゃメーカーなどの出資者から成る「製作委員会」を通じてアニメ制作の資金調達が行われ、参加企業が版権収入を得るケースが多い。
この製作委員会方式は作品が不人気で終わった際の損失リスクが軽減される一方で、収益が分散されることにより高収益化を阻害する一因だと指摘されている。また、多重下請け構造により、アニメーターや声優などのサプライチェーンの末端まで報酬が届くには半年以上を要することもある。
音響制作の仕事に従事しながら声優のマネジメント会社を約10年経営していた子吉信成さん(47)は、声優が報酬を得るまでに6カ月以上待たされることも多かったと語る。作品が利益を上げられなかった場合には、未払いで終わることもあったという。
「制作会社はクライアントから支払いがあるまで声優に報酬を出さない」と指摘。「末端がリスクを取らされているし完全に下請法違反だが、皆無視している」と話した。子吉さんの声優事務所の売り上げは低迷し、昨年解散を余儀なくされた。
問題解決の障壁
また、フリーランスの間では口頭やSNSのメッセージ機能で曖昧な仕事の依頼を受けることも多く、下請法やフリーランス新法で禁じられている、条件を明記した書面を交わさない契約が業界で慣行化しているとアニメーターらは話す。
フリーランス新法では、従来の下請法の対象に含まれなかった小規模の委託事業主もフリーランスに仕事を委託する際に、書面での取引条件の明示や、物品等を受け取った日から60日以内に報酬の支払日を設定するよう義務付けている。公取委は1月に、国内のアニメや映画の制作現場における取引慣行の調査を始めたと発表。年内に報告書を取りまとめる予定だ。
公取委フリーランス取引適正化室の武田雅弘室長は、「フリーランスの労働者が不利な立場に置かれている」とし、「多くが仕事を失うことを恐れ、報酬など基本的な労働条件すら発注元に確認するのをためらっているケースが多いということは認識している」と述べた。
アニメーターや声優の多くが労働組合に加入していないことも、低賃金問題解決の障壁になってきたと、30年以上東映アニメーションに勤務した沼子哲也さん(63)は話す。同社で「ドラゴンボール」や「ワンピース」の制作に関わった沼子さんは、業績面から「客観的に見て単価を上げられる環境にある」にもかかわらず、「上げるための組織づくりと運動を誰も考えられていない」と指摘する。
制作スタジオ間やクリエーター間での競争激化も低賃金の一因になってきたと業界関係者はみている。日本動画協会の20年の調査によると、アニメ制作会社は811社と、16年の622社から30%増加した。競争激化で一部の制作会社は赤字が続いており、賃上げに踏み切ることができていない。
一方、志望者の多い声優業界では、役を勝ち取るため、声優が進んで低賃金を申し出たり、逆に金銭などを支払ったりする慣習が常態化。仕事を失うことを恐れ、キャリアがある声優でも賃金交渉をためらっている現実がある。
「もっと報酬を上げてくれなんて言った日には、じゃあ別の誰かに依頼すると言われるだけ」と子吉さんは話す。
AIの台頭
政府の規則強化に加え、今後予想される国内アニメーターの減少が待遇の改善につながる可能性があるとの見方もある。日本総合研究所は、人口減少の進行でアニメ制作者が30年には19年比で約1割減少し、制作分数も約1万分減少するとみている。また、声優業においても、生成人工知能(AI)の台頭で簡単な仕事は機械が担うようになり、労働人口の適正化につながる動きが見え始めている。
帝国データバンク情報統括部の飯島大介副係長は、小規模なアニメ制作スタジオの間で統合が進み、1社当たりの収益性の改善が期待されると話す。労働環境改善のためにも「現状の会社数から少なくとも半分程度にならないと到底業界として持続可能ではない」と述べた。
新人アニメーターの労働環境も改善し始めている。杉澤あいなさん(24)は、トムス・エンタテインメントの奨励金を受け取りながら現役アニメーターから指導を受けることができるプログラムに所属。アニメ業界について「これから環境が良くなるのではという希望的観測を持って入った」と話す。
労働条件について声を上げる業界関係者はごくわずかだが、声優の柴田さんは23年に発売されたテレビゲームに自分の声が無許可で使用されたことを知り、抗議した。ゲームを制作した出版社は柴田さんに謝罪し、補償金の支払いに同意したという。
「業界について否定的なことを言うと干されてしまうので、声優はどんな仕事でもしがみ付くしかない。皆、泣き寝入りするしかないと諦めている」と話す。
フリーランス保護に詳しい山田康成弁護士は、フリーランスも事業者なので、自分の身は自分で守るという意識を持つ必要があると指摘。法律を活用し、おかしいと思ったら自分で声を上げていくべきだと述べた。