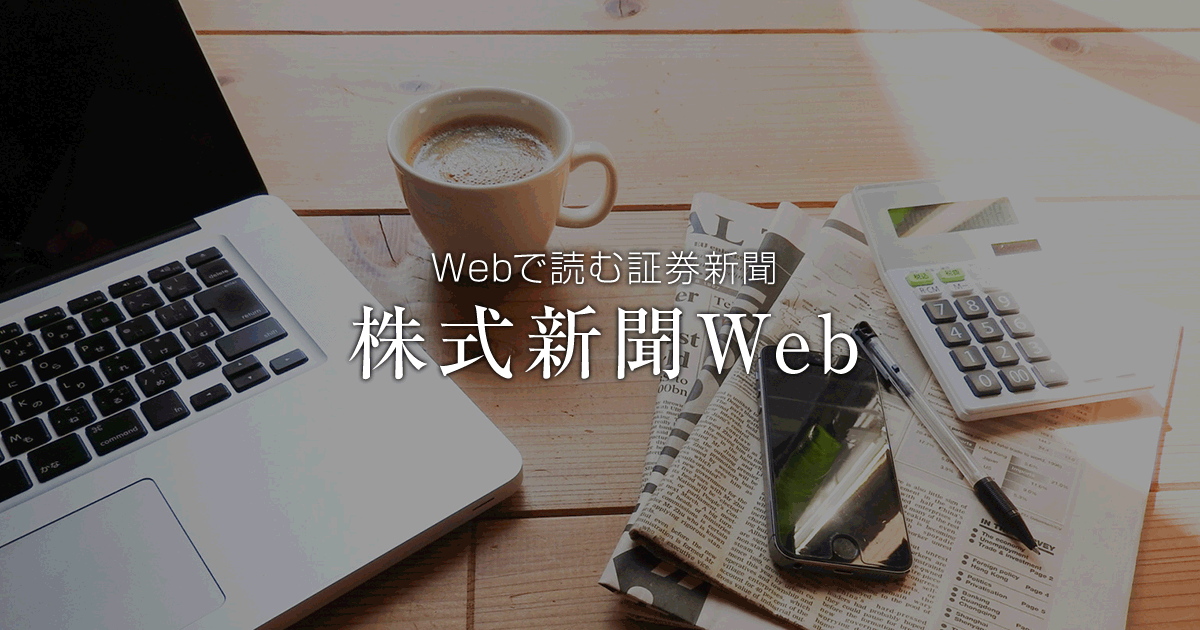コラム:米中デカップリング、「引き返し不能点」越えたか

[香港 15日 ロイター BREAKINGVIEWS] - 「デカップリング(切り離し)」はもはや単なる政治的スローガンではなくなっている。過去10年間、米国の政権は中国がパートナーになれる可能性を声高に提唱し、敵だと言及することを控えてきたが、そうした楽観論はほぼ消え失せた。トランプ大統領は米国に輸入される中国製品に懲罰的で広範囲の関税を課し、前政権まで採用されてきた「small yard,high fence(重点分野だけ強固に守りを固める)」政策は放棄されている。こうした政策の下では、特に戦略的に大事なハイテク産業に的を絞って障壁を設けつつ、他の領域では中国との協力を模索していた。
中国の習近平国家主席は、明確なゴールのない米国との交渉を無理強いされるいわれはないとして貿易戦争を「最後まで戦い抜く」と表明。これは、今まで緩やかに進行していた世界の2つの経済大国のデカップリングが加速することを意味している。ロイターのBreakingviewsが米中の貿易、金融、企業、教育、地政学それぞれの面での結びつきの方向性を調べたところ、単に言葉上の問題だけではない、急速な関係悪化を示す証拠が多く集まった。
<貿易の抜け穴>
まずは伝統的に米中関係の根幹を成してきたモノの貿易に目を向ける。トランプ氏が1期目の2018年に仕掛けた最初の貿易戦争は米国の中国製造業への依存を解消できなかったが、今月発動した関税措置によって中国製品に適用される税率は最低でも145%に高まった。この動きは、昨年5820億ドルに達した米中の二国間貿易の大部分を崩壊させる恐れがある。トランプ政権はスマートフォン、コンピューターを含む一部電子機器を課税対象から外したものの、中国のサプライチェーン(供給網)に大きく依存することによる安全保障上のリスクを調査している。同調査が示唆するのは、分野別関税が近く発動される展開だ。
The bar chart shows China's share of US imports from Asia is shrinking一方でトランプ氏は、中国以外の国にも7月上旬まで10%の関税を課しており、中国がベトナムなどの第三国経由で米国に輸出する道も険しくなっている。米商務省国勢調査局によると、2017年から24年までに米国の輸入全体に占める中国の比率は8ポイント下がって13.4%になった。18年にはアジアからの米国の輸入の半分は中国だったが、現在は3分の1程度に過ぎない。ただ国連貿易開発会議(UNCTAD)のデータに基づくと、世界全体のモノの輸出に占める中国の比率はこの間に12.7%から14.2%に上昇している。つまり中国が第三国を迂回して米国に輸出している可能性が浮かび上がってくるが、その比率も今後は低下に転じてもおかしくない。
<金融と投資>
金融分野でもデカップリングが起こっている。23年の中国に対するストックベースの米国の直接投資は1270億ドルだったとはいえ、年間のフローは縮小中だ。逆に米国に対する中国の直接投資のストックも23年は440億ドルと、19年以降で16%減少した。年間ベースの中国から米国へのフローは20年からマイナスで、中国の投資家が米国のプロジェクトから資金を引き揚げている様子がうかがえる。
国際決済銀行(BIS)のデータを見ると、米国の銀行が中国向けに保有する債権総額は昨年9月時点で1500億ドル弱と過去最高を記録し、米金融業界が中国から撤退している兆しは乏しい。しかしウォール街の有力金融機関トップは非公式の場でBreakingviewsに、対中国の投融資は以前よりも換金が容易になっていると明かし、必要なら素早く撤退する態勢にあると示唆している。
The chart shows position and flow of Chinese FDI into US and Us FDI into ChinaThe area chart shows the trend of global funds allocation to Chinese assets. Global equity funds' average allocation to China assets peaked at 3.13% in April 2015The line chart shows consolidated total claims of US banks in all currencies with residents of China on a guarantor basis.次に問題となるのは、外交問題評議会のブラッド・セスター上席研究員の推計で1兆1000億ドルに上る中国保有の米国債で、恐らく米中の金融的な関係において最も解消が難しい事案になる。中国政府にとってドルを持っていることは人民元の管理に役立つし、中国が米国債を売却した場合にどういった資産を買うのかもはっきりしない。さらに売却益で人民元建て資産を買えば、当局が債務デフレからの脱出を目指す中で、人民元高という望ましくない事態をもたらしかねない。
<企業行動>
中国企業はこれまで決して米国に強固な足場を築いてこなかった。しかしロジウム・グループのデータによると、中国企業が米国に保有する資産の規模も頭打ちが続いている。特にトランプ政権が、動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の米事業売却を中国の親会社に受け入れさせることに成功すれば、この流れは加速するだろう。ベッセント財務長官は、中国企業の上場廃止も辞さない姿勢だ。今年3月時点で米国の証券取引所に上場されている中国企業は286社で、合計時価総額は1兆1000億ドルに上る。
<学生交流>
米中の人的交流はしばしば軽視されているが、両国関係の行方を占う上で有力な指標になり得る。米教育省の下部機関によると、22-23年に中国で単位取得修のために勉強していた米国人学生はわずか469人と、過去20年の最低水準に近かった。これは米国の中国理解が今後大きく弱まることを示している。
The line chart shows the trend of US tudents study in China, Hong Kong, Taiwan一方中国人学生にとって米国の魅力は根強いものの、米国の大学で学ぶ外国人学生の比率で言うと現在はインド人よりも低い。
The line chart shows % of US students studying in China.<台湾問題>
米中関係は台湾問題に左右されるケースも少なくない。米国側の「1つの中国政策」に対する立場は、中国の主権が台湾に及ぶとの主張を認識したものだ。しかし中国が台湾に軍事侵攻すれば、大規模な制裁を科すか、武力さえ行使するかもしれない。
ゴールドマン・サックスが算出する「中台リスク指数」は、トランプ氏が「相互関税」の詳細を発表した今月2日以降、上昇傾向をたどっている。背景には、米国が仕掛けた貿易戦争が金融戦争に発展し、最終的には台湾を巻き込んだ軍事衝突に至るのではないかとの観測が高まっていることがある。ただ台湾株の値動きからは、今のところ強い警戒を要するとの根拠は乏しい。
A double line chart showing that the news-based measure of Taiwan risk has risen to historically high levels in recent months.<結論>
米国が貿易赤字解消を目指し、安全保障上の懸念から中国に行き着くサプライチェーンの調査に乗り出すにつれ、じわじわとしたペースだった米中関係の悪化は加速しそうだ。データから察せられるのは、企業や金融機関、さらには大学生までもデカップリングの速度を上げるような行動をしているという現実だ。そう考えると、トランプ氏の第2次対中貿易戦争の扉は最初から開け放たれている。
(筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています)
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
Una Galani is Asia Editor of Reuters Breakingviews, based in Mumbai, overseeing a team of columnists across the region. She was previously in Hong Kong, Dubai and London. Breakingviews is the global financial commentary brand of Reuters delivering agenda-setting insight in real time on the most important events impacting global markets and companies.