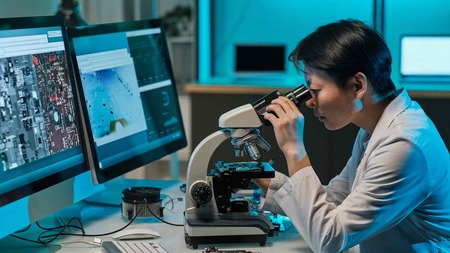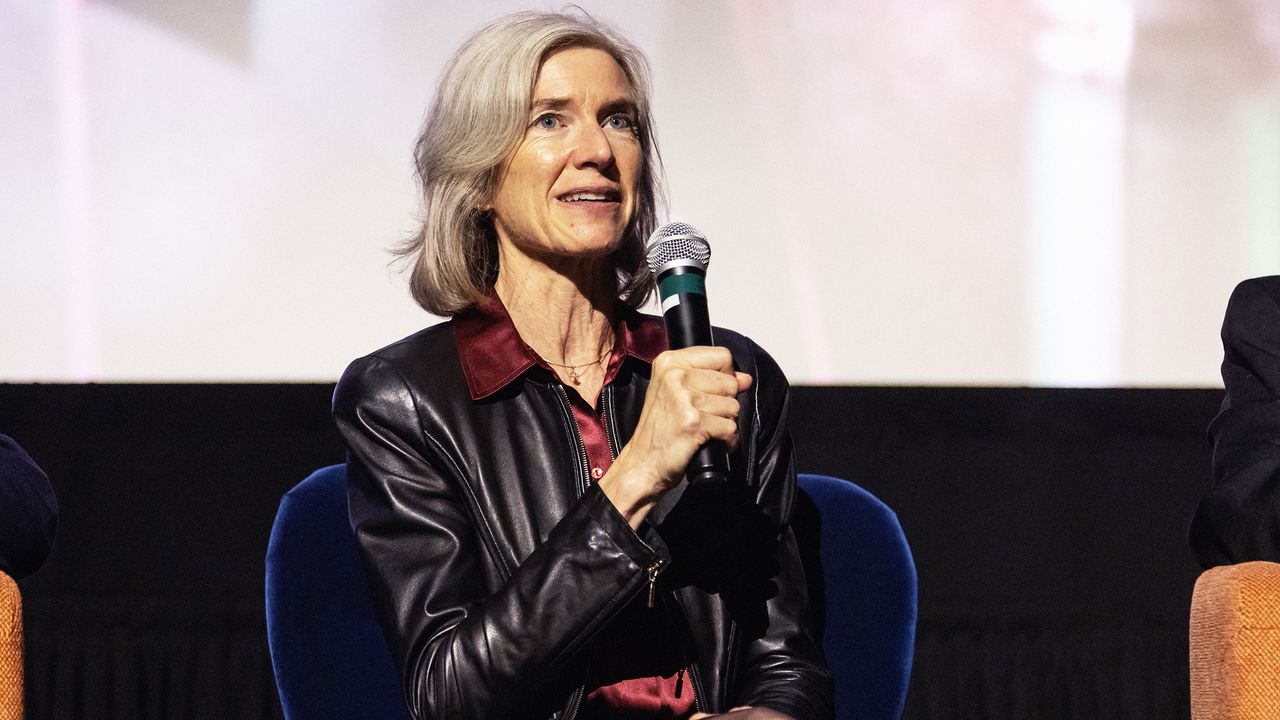セリフも動きもない「静止シーン」が1分以上も続く…現代のエンタメでは不可能な「90年代有名アニメ」の名前 余白とは、「情報がないムダなもの」なのか

曖昧さについて、こんなことがわかっています。
たくさんの顔写真のなかから、「喜怒哀楽が明確にわかるもの」と「やや表情はあるけれど喜怒哀楽に分類不可能なもの」を見せたとき、それぞれの脳の活動には違いがあります。
はっきりと怒っている顔や、見るからに悲しい顔など、喜怒哀楽が明確にわかる表情を見せたときは、扁桃体などの感情ネットワークに関連する一部の部位が活動していました。
しかし曖昧な表情のときは、前頭回の中部や下部という言語やイメージを使って何か想像しているときによく働くところなど、比較的多くの高次の部位が活動することがわかりました。
曖昧さの中にある意味を自分の中で一義に定めるための活動が行われているのかもしれません。
美術史学では、「偉大な芸術は、曖昧で多義的なものを包摂できる表現になっている」と言われます。
たとえばフェルメールの『真珠の耳飾りの少女』という有名な絵画があります。青いターバンを巻いてこちらを振り返った少女の顔は、かすかに唇を開けてこちらを見ていますが、彼女が何を思っているのかはよくわかりません。
人によっては、八つくらいの感情に見えると言われています。わたしは八つには見えませんが、でも四つくらいには見える。
悲しげに見えるときもあれば、薄く微笑んでいるようにも見える。なんだか誘っているような表情に見えるときもあるし、無表情な顔のときもある、というように。
3時間、ずっと見続けてみたら
わたしはこの絵の実物を見に、オランダのデン・ハーグという都市にあるマウリッツハイス美術館に行ったことがあります。
この作品の前は、通常は大勢の観覧者でにぎわっているのですが、わたしが訪れた2020年の3月はコロナ禍が始まったところで人がほとんどいませんでした。
だからその絵の前に座って、3時間くらい見ていたのです。するとやはり印象がいろいろ変わりました。
これも少女が曖昧な表情をしているからです。
記憶に残るものというのは、必ずしも明確に意味づけられたものではありません。
むしろ、「これってどういう意味だったんだろう?」「あのときの気持ちは、何だったんだろう?」と、受け手の中に引っかかりを残すものこそが、長く心に残りやすいのではないでしょうか。
曖昧な表現には、それをどう受け取るかという「余地」があります。
「こういうことを言いたいのかな」「でも、こうも解釈できるな」と、自分の中で何度も意味を探ろうとする。そのプロセスが、自然と心の動きを引き出し、感情の幅を広げてくれます。そして大きく心が動いた記憶は、情報としてではなく、体験として長く残りやすくなるのです。
Page 2
もしあなたが、商品を作る側、物語を届ける側にいるのなら、大切なのは「安心して感情を動かせる設計」をすることです。
石津智大『泣ける消費 人はモノではなく「感情」を買っている』(サンマーク出版)
それはつまり、以下の三つを掛け合わせるということです。
①安心できる「予測」(こういうものなんだろうな、という入り口) ②ほんの少しの「ズレ」(思ったより○○だった、という意外性)
③ちょっとした「余白」(すぐには説明しきれない、あとを引く感じ)
この三つがそろったとき、人は「これは特別な体験だった」と感じ、またその世界に戻ってきたくなります。
それは、「体験してよかった」という深い満足へとつながる感情設計のかたちなのです。