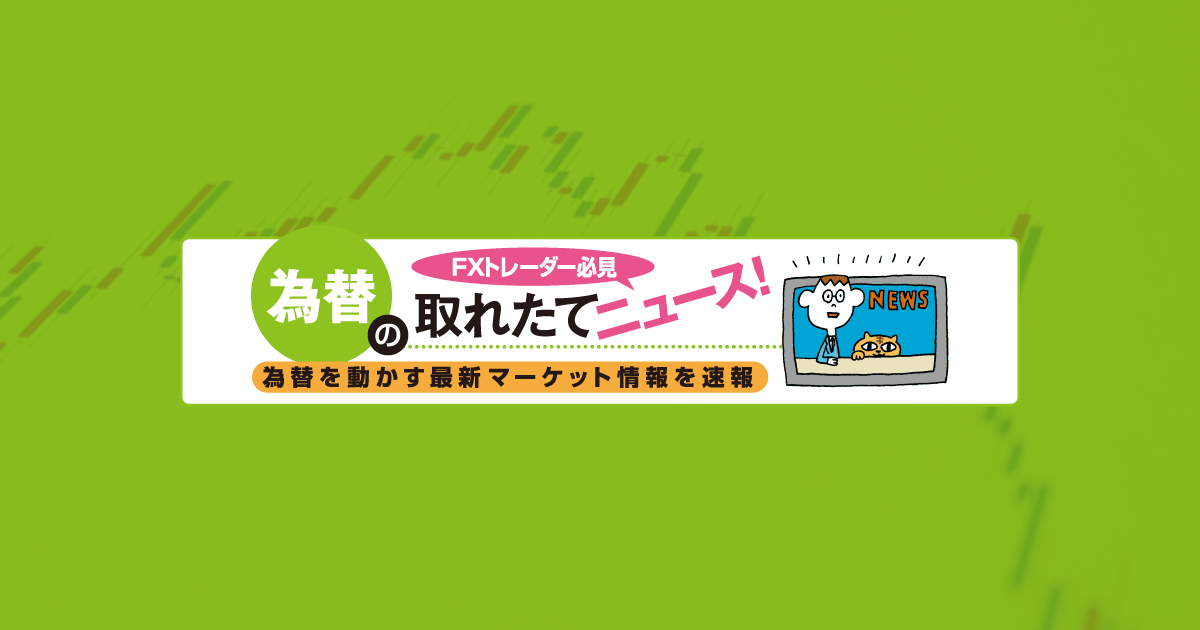生体情報に結婚歴まで…万博の前売り入場券、個人情報に懸念 販売目標未達で焦点は開幕後

2025年大阪・関西万博の開幕まで1カ月に迫る中、1400万枚を掲げた前売り入場券の販売目標の未達成が確実となっている。5日時点の販売枚数は約806万枚にとどまり、当初計画していなかった当日券の導入を発表するなど、機運醸成の焦点はすでに開幕後に移った。ただ、予約なしの来場者が急増すれば交通インフラに問題を抱える人工島の会場に大きな負荷がかかり、運営の混乱も懸念される。
100万枚売るのに5カ月
「東京に行くたびに万博について誰も何も知らないことにがく然とする」。万博にパビリオンを出展する関西企業の関係者はこう嘆く。大阪市内と会場を結ぶシャトルバス運営会社の関係者も「予約が埋まったのは初日だけ。あとは埋まらない」と明かす。
万博への関心の低さは、前売り入場券の販売ペースを見れば明白だ。割引幅が大きい前売り券が販売されていた昨年10月初旬までは約700万枚まで伸びたが、その後増加ペースは急激に鈍化。万博を運営する日本国際博覧会協会がPRを強化しても、その後に約100万枚を売るのに5カ月かかった。
また前売り入場券は経済界が700万枚の購入を推進しており、販売された大半は企業の購入とみられる。1400万枚の販売目標について協会の石毛博行事務総長は2月、「非常に野心的だ」と発言し、達成が困難な状況を事実上認めた。
海外政府が怒りの声
販売が低迷した要因は多く考えられるが、海外パビリオンの建設遅れなどを背景に万博の具体的な内容の情報提供が進まなかったことに加え、来場日時やパビリオン、イベントの訪問先まで事前予約を求められる複雑なシステムを協会が導入し、多くの人が敬遠したことが大きい。
複雑な予約システムを導入した理由としては、交通インフラが脆弱(ぜいじゃく)で会場の面積も限られた未整備の人工島・夢洲(ゆめしま)を会場に選んだため、来場者の流入を厳しくコントロールする必要があったことがある。
来場を呼びかけながら流入する人員を制限するこの施策に対しては、海外政府も怒りの声を上げる。欧州の政府関係者は1月、「私たちは知っている。協会は夢洲に人を入れたくないんだ」と怒気を込めて話し、他の国々とともに改善を要求したことを明かした。
こうした流れを受け協会は2月下旬、来場当日に会場で購入できる「当日券」の導入などを発表。期日前の販売から会期中の販売を重視する姿勢にシフトした。
ただ、当日券の利用が拡大すれば来場者の流れを整理することはより一層困難になり、問題が深刻化する懸念がぬぐえない。大阪・関西万博は、多くの矛盾を抱えながら開幕に向かっている。
SNSのパスワード情報も
大阪・関西万博の入場券では、オンラインで購入する際に提示される個人情報の扱いの規約も問題視されている。入場券購入に必要とは思えない内容も多く含まれる上、「第三者に提供される場合もある」と記されているためだ。
入場券購入やパビリオン予約には「万博ID」を取得する必要がある。その際に同意を求められる「個人情報保護方針」には、日本国際博覧会協会が収集する情報として、名前や生年月日などに加え、顔画像や指紋などの生体情報▽SNS(交流サイト)のアカウントやパスワードに関する情報▽結婚しているか▽子供の有無▽趣味―などが羅列されている。さらに「第三者に提供される場合がある」とし、対象として外国政府、SNS事業者、広告関係会社などが含まれる。
この問題は2月に国会質問でも取り上げられた。協会の担当者はこれらの記載の背景として「来場者からスタッフまで、幅広い個人情報をさまざまなケースで扱うことを想定して策定されたため」と説明。制定当時はどのような情報が必要か具体的な検討ができなかったことから、弁護士とも協議して幅広い記載になったとしている。
その上で「SNSのパスワード情報を把握することはない」と強調。現在は「実際に取り扱っていない個人情報の有無の確認作業を進めている」とし、文言が修正される可能性にも言及した。
ただ、開幕直前までこれらの記載が残っている状況にSNS上では「怖すぎる」などの声が広がる。来場意欲をそいでいるのは確実で、前売り入場券販売のさらなる足かせになっている。(黒川信雄)
来場者満足度高める取り組みを 日本総研の藤山光雄氏
藤山光雄氏前売り入場券の販売が低迷した理由は、万博で何を見て体験できるかが人々に伝わらなかったことと、入場券の購入や予約のシステムが使いづらかったことに尽きる。
パビリオンのPRも個々に任せられていた印象だ。万博全体で、どうアピールしていくのかといった方向性も感じられなかった。予約システムに対しても、使いにくいという指摘は当初からあったと思うが柔軟に見直す姿勢が欠けていた。対応が遅れたのは、日本国際博覧会協会の内部で誰が何をするのかという役割分担が明確でなかったからだろう。
開幕直前のタイミングで当日券の導入が決まったが、ここからはもう開幕後の機運醸成をいかに図るかという視点に切り替えるべきだ。ただそれも各パビリオンに任せるのではなく、来場者の興味に合わせてルートを提案するなど、来場者の満足度を上げるきめ細かい取り組みが必須だ。
そうでなければ来場者が否定的な情報を発信して、事態がさらに悪化する可能性もある。開幕後の継続的な改善も不可欠だろう。