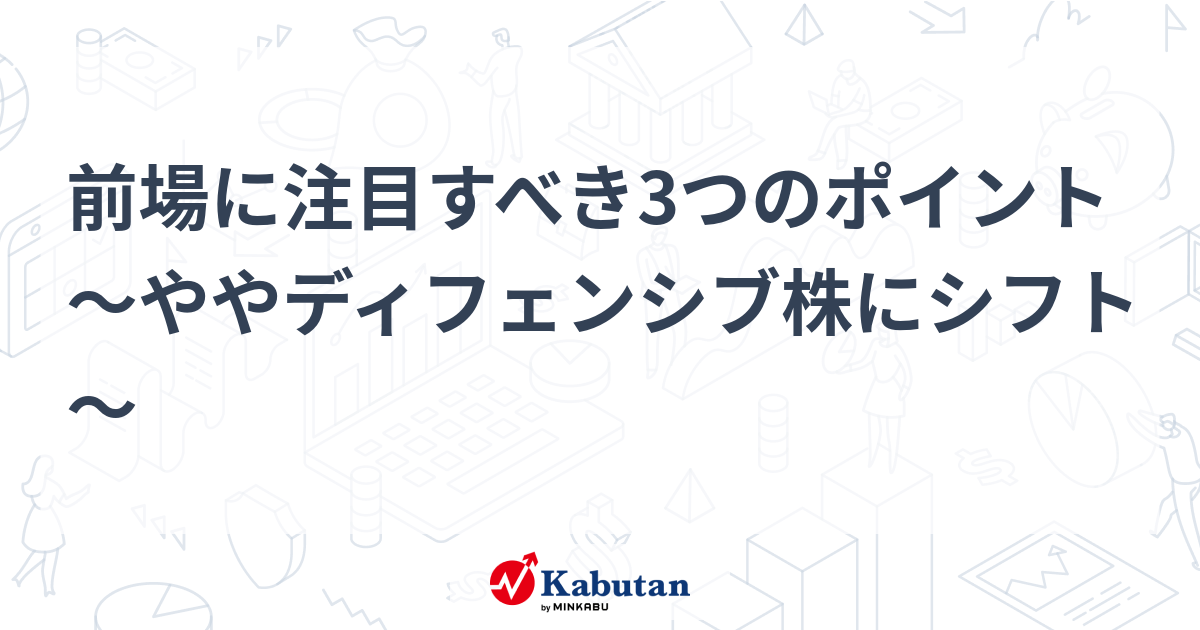試されるFRB、リスク志向のウォール街が金融政策の影響力問う

マネーの価格、つまり米連邦準備制度理事会(FRB)の政策金利は普段、ウォール街で注目の的だ。引き締めの気配はリスク選好を冷やし、緩和の兆しは相場を押し上げる。
しかし、連邦公開市場委員会(FOMC)が16、17両日開く会合は、この古典的なロジックが今も有効なのかを試す場となる。最近の相場サイクルが従来のパターンを裏切り続けているためだ。
今年の市場は、パウエルFRB議長の意向を確かめることなくリスクを取りに行っている。株価は過去最高を更新し、社債市場は活況だ。上場投資信託(ETF)には年初から8000億ドル(約118兆円)余りが流入した。
このうち株式向けが4750億ドルを占め、同時にミューチュアルファンドからは資金が流出。年間のETF流入額は1兆ドル超えの勢いで、過去最大となる見込みだ。
幅広い株価指数から暗号資産(仮想通貨)や高リスク債券に至るまで、資金流入は4月の株価調整や新たな関税摩擦の局面でも止まらなかった。
ゴールドマン・サックス・グループのデービッド・ソロモン最高経営責任者(CEO)は最近、「リスク選好の状況を見ると、政策金利が極端に制約的だとはとても感じない」と述べた。
関連記事:ゴールドマンCEO、利下げ急ぐ必要ないと示唆-金融緩和圧力と一線画す
市場はすぐにその見方を裏付けた。労働市場に一段のひび割れが見える新たな統計が公表されたにもかかわらず、S&P500種株価指数は11日に再び最高値を更新した。
FOMCが17日に広く予想される利下げを実施したとしても、中央銀行の協調があろうとなかろうと、投資資金はリスク資産に突き進んでいるという事実が確認されるだけになるかもしれない。
過去1カ月だけで1200億ドル超がETFに流入し、主に大型株や債券に資金が向かっている。
こうした強靭(きょうじん)さは長年の積み重ねのたまものだ。米国の労働者は給与の一部を退職年金に拠出してきたが、その資金の行き先が変化した。
ターゲットデート型ファンドやモデルポートフォリオ、ロボアドバイザーを通じて、退職資金が自動的にパッシブ運用に振り向けられる割合が増えている。運用業界ではこれを「オートパイロット効果」と呼ぶことが多い。
経済や市場の動向ではなく、カレンダーに沿って流れ込む安定資金を強調する「非弾力的需要」という言い方もある。
投資カルチャーの変化
ストーンXフィナンシャルのグローバルマクロストラテジスト、ビンセント・デルアード氏は「われわれは永久機関を発明した」と言う。要するに「バリュエーションやセンチメント、マクロ環境とは無関係に、GDP(国内総生産)の約1%を毎月、インデックスファンドへ振り向ける」状況だということだ。
金融政策が無意味になったわけではない。リスク志向の市場が利下げ観測を先取りするのは理由がある。
政策金利は債券やバリュエーション、レバレッジを左右する。ただし、リスクを指揮するのがFOMCだけという見方は単純過ぎる。資金フローは今や、経済データが逆転しても楽観を後押しし得る。
雇用統計が悪化する中、市場では年内3回の利下げ観測が強まり、17日の0.25ポイント利下げが確実視されている。それでもS&P500種は12日、小反落ながら史上最高値圏で引け、週間では1.6%上昇した。
アカデミー・セキュリティーズのマクロ戦略責任者ピーター・チア氏は「市場が『金融緩和は株にプラス』という思考にすっかり慣れており、緩和方向の道筋は明確だ」と述べ、「人々は利回り低下に賭けており、低下が景気を下支えし、政策不透明感を打ち消すとみている」と指摘した。
投資カルチャーの変化も同じくらい重要だ。多くの投資家は今やETFを現金に近い存在と見なし、レバレッジをかけたり流動性の低い資産を組み込んだりしていても、流動的かつ売買しやすいと考えている。
当初は取引上の利便性に過ぎなかったものが習慣となり、その習慣が確信へと変わった。
数字にもその変化が表れている。投資信託協会(ICI)のデータによると、米国人の確定拠出年金残高は1-3月期末時点で12兆ドルを超え、このうち401(k)プランが8兆7000億ドルを占めた。
モデルポートフォリオの運用資産は2024年末に2兆5000億ドルに達し、調査会社セリュリによれば、ETF資産全体の約4分の1がそうしたモデル経由での流入だとETF発行体は報告している。
原題:Wall Street Rides a $1 Trillion Money Wave as Fed Test Looms (抜粋)