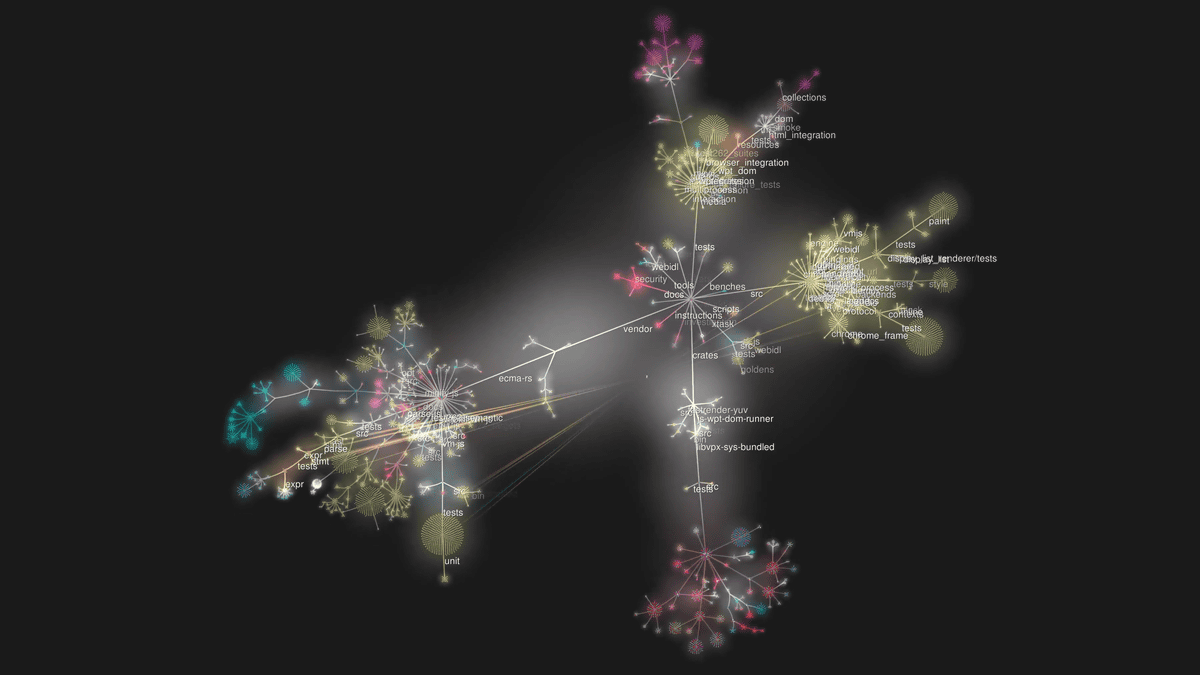高性能な自社製チップの登場で、アップルは商品の「差別化に苦労」している(Forbes JAPAN)

MacBook Proのようなノートパソコンを一般消費者にどう売り込むか。ハイエンドのコンテンツクリエイターや開発者なら、Appleシリコンの上位チップであるProやUltraを選ぶ理由がはっきりしている。しかし、一般消費者向けのMacBook Proは、同じくアップル製品であるMacBook Airが突きつけてくる大きな課題と向き合わなければならない。 ■「インテル搭載」時代にあったMacBook Proの優位性 Macがインテル製チップを採用していた時代は、製品間の性能差を明確につけやすかった。世代ごとのチップ性能の開きによって、低価格なMacBook Airモデルは、高価格なMacBook Proモデルと比べて明らかに非力だったからだ。インテル製チップを搭載することで、アップルは自然に差別化を図れていたのである。 Appleシリコンへの移行後、ティム・クックたちは新たな強みを打ち出せるようになった。2020年後半に登場したM1チップ搭載のMacBook Airは、同年初頭に発売されたインテル搭載モデルと比べて、ベンチマークで2〜3倍という大幅な性能向上を記録した。 ところが、M1 MacBook AirとM1 MacBook Proの性能差はおおむね15〜20%程度にすぎなかった。特にM1 MacBook Airの性能が、インテル搭載の同クラスのノートパソコンを大きく凌駕していたため、一般ユーザーには両モデルの差を体感しにくくなったのだ ■AirがProと肩を並べるように その後アップルは、プロユーザー向けにAppleシリコンのProやUltraというより高性能なチップを投入して性能差を広げようとしたが、すでに重要な分岐点は過ぎていた。エントリーレベルのMacBook Airであっても、平均的な消費者には十分すぎるほどの処理能力を備えていたからだ。 Appleシリコンが年々改良され、買い替えを検討する消費者が増えるなか、アップルは1つの問題に直面した。2020年時点ですでに高性能だったエントリーモデルがその後4年間アップデートを重ねてきた中、どのようにして999ドル(日本では税込16万4800円)のベースモデルから、より高額で利益率の高い製品へ買い替えを促すかという問題だ。 その解決策としてアップルは、差別化要因として「性能」ではなく「時期」を選択した。 当初のM1世代では、MacBook AirとMacBook Proは同タイミングで発売された(Mac miniも同時)。ところがその後の世代では、Airの発売をProよりも遅らせるスケジュールを組む方針に変わった。現行のM4チップでも、リリースからほぼ1年を経て、ようやくM4 MacBook Airが登場している。さらにややこしいのは、「タブレットと呼ばないでほしい」とされているiPad ProにまずM4が搭載され(2024年5月)、その6カ月後(2024年11月)にMacBook Pro、そして4カ月後(2025年3月)にMacBook Airが発売されるという順番が組まれた点だ。