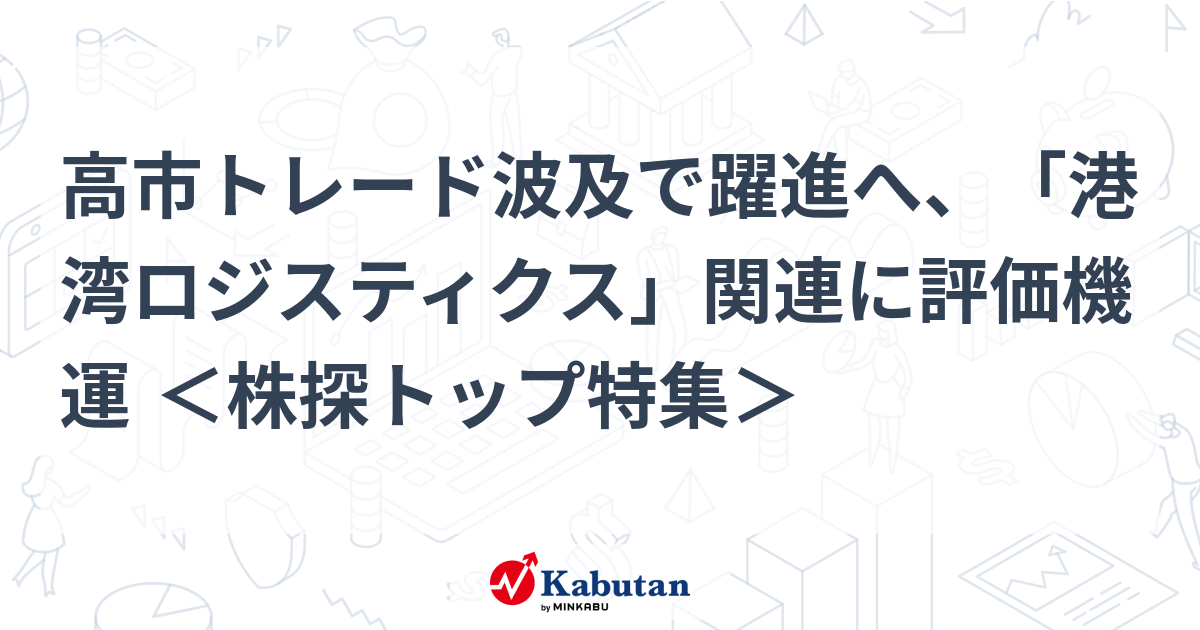名目賃金の伸び鈍化、不透明感増し先行き慎重な声-実質3カ月連続減

3月の名目賃金は前月から伸びが鈍化し、プラス幅は市場予想を下回った。トランプ米政権の関税政策の影響で世界経済の不確実性が高まる中、賃金動向の先行きに慎重な見方が広がる可能性がある。物価高が続く中、実質賃金は3カ月連続で前年を下回った。
厚生労働省が9日発表した3月の毎月勤労統計調査(速報)によると、名目賃金に相当する1人当たりの現金給与総額は前年同月比2.1%増だった。前月は2.7%増。市場予想では2.5%増が見込まれていた。プラスは39カ月連続。所定内給与は1.3%増と前月から横ばい。物価変動を反映させた実質賃金は2.1%減とマイナス幅が拡大した。
エコノミストが賃金の基調を把握する上で注目するサンプル替えの影響を受けにくい共通事業所ベースでは、名目賃金は2.4%増だった。所定内給与は1.8%増加。
日本銀行の植田和男総裁は、金融政策の維持を決めた1日の決定会合後の会見で、深刻な人手不足などを背景に賃金と価格が相互に影響し合う意味での好循環は継続していくとの見方を示していた。ただ、経済成長率の鈍化を予想する中で、結果として物価と賃金の「上昇率はやや下振れ、あるいは伸び悩みの状態に入っていく」と分析。企業の賃上げ機運の持続が今後の鍵となる。
関連記事:植田総裁、通商政策や海外経済巡る不確実性「極めて高い」-政策維持
みずほ証券の片木亮介マーケットエコノミストは、1月以降の数字は「サンプル替えやうるう年の影響など特殊要因で少し振れが大きいようにみえる」と指摘。賃金の基調判断では今春闘の結果が反映される「4月から夏にかけてのデータを見ていく必要がある」と語った。懸念材料としてトランプ関税の影響が企業収益に及び、今年よりも来年の春闘を押し下げる可能性を挙げた。
連合が8日公表した今春闘の第5回回答集計(2日午前10時時点)によると、平均賃上げ率は5.32%。前回集計(5.37%)から低下したものの、最終集計との比較で34年ぶりの高水準を維持している。中小組合も4.93%と高い水準を保っている。
厚労省は名目賃金の伸び鈍化について、賃金の締め日が事業所で異なるため昨年がうるう年だったことに伴う労働時間の減少が3月分に反映された可能性があると説明。2月の押し上げ要因となった特別給与の効果が弱まったことも考えられるという。
実質賃金は、3月分から従来の「持ち家の帰属家賃を除く」消費者物価指数からの算出に加え、「総合」から実質化した数値の公表が始まった。総合での実質賃金は1.5%減と、「持ち家の帰属家賃を除く」と比較してマイナス幅は小さい。
実質賃金の算出では、米国や英国、ドイツで総合が使われており、他国と比較しやすいという利点がある。3月の経済財政諮問会議では、民間議員から、実質賃金をしっかり上げていく上で、実質賃金を適切に把握するためにも、「国際比較ができるような統計情報の整備が重要だ」との意見が出ていた。
消費支出は増加
総務省が9日発表した家計調査によると、3月の消費支出(2人以上の世帯)は物価変動の影響を除いた実質ベースで前年同月比2.1%増加した。2カ月ぶりのプラスで、市場予想(0.2%増)を上回る伸びだった。私立大学の授業料や電気代など光熱・水道、パソコンを含む教養娯楽用耐久財の支出が増え、全体を押し上げた。
SOMPOインスティチュート・プラスの小池理人上級研究員は、実質賃金が改善して消費が強くなっていくという日銀のシナリオに対して、「少なくとも今回のデータを見る限りネガティブ」と指摘。米関税の影響で不透明感が強い上、円高や原油安など物価への下押し圧力も出てきており、利上げは相当難しいとの見方を示した。
日銀は、経済・物価見通しが実現していけば利上げで金融緩和度合いを調整する方針を維持している。一方、トランプ関税で高まる世界経済の不確実性を踏まえ、1日の会合で2%の物価安定目標の実現時期を1年程度先送りした。各国通商政策の今後の展開やその影響を受けた「海外経済・物価を巡る不確実性は極めて高い」とし、丁寧に見極めて適切に政策判断をしていく考えを示している。