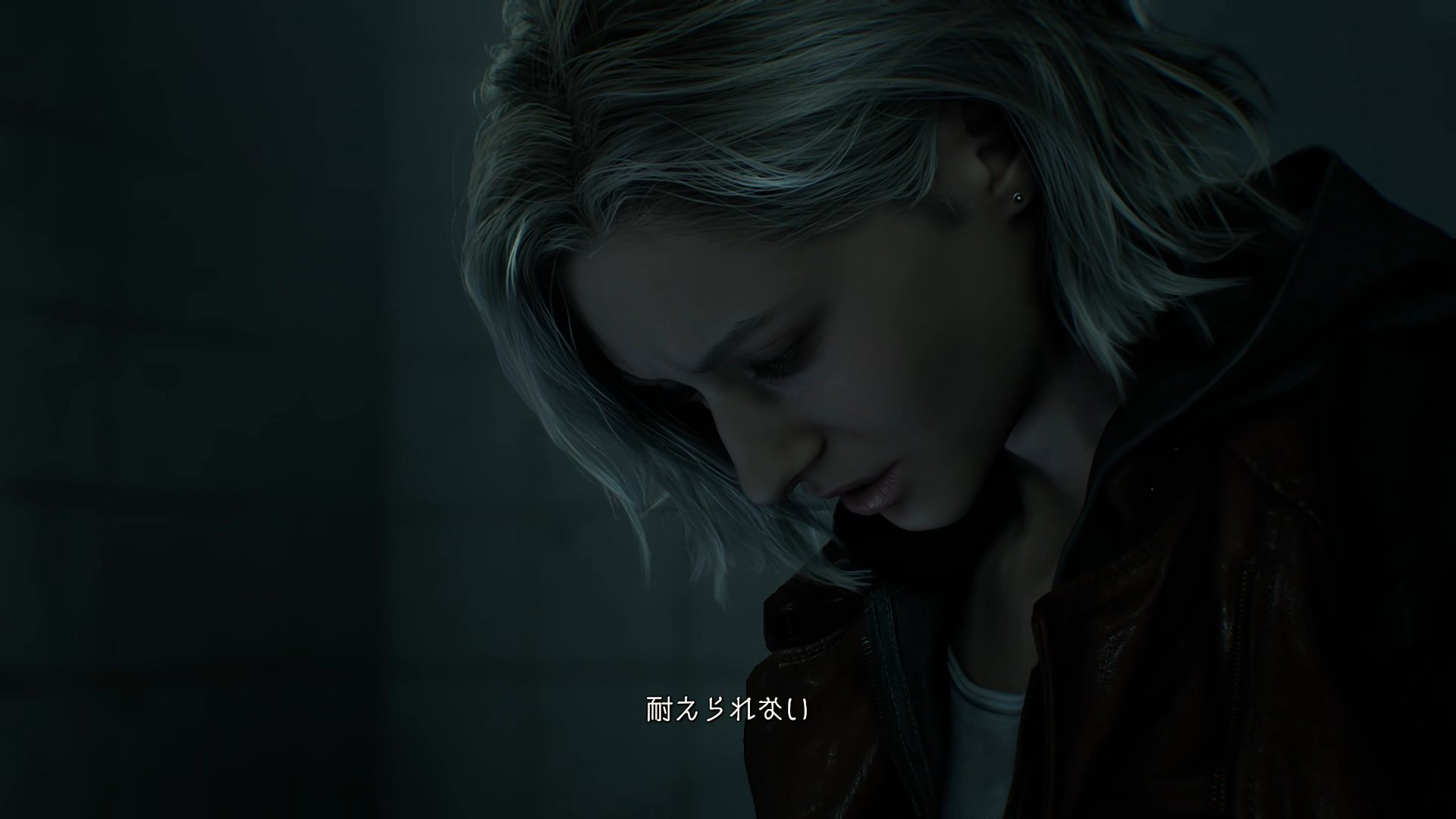【大河ドラマ べらぼう】第33回「打壊演太女功徳」回想 「エンタメは世を変え、人を救う」を問いかけた骨太のストーリー 本懐を遂げ妻子の元へと旅だった新之助 打ち壊しを徹底調査した治済の思いとは

「エンタメは人を救うのか」を問うストーリー
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の第33回は「打壊演太女功徳(うちこわしえんためのくどく)」。歴史的な天明の打ちこわしの大騒動をモチーフにしつつ、この意味深なタイトルが象徴したのは「エンターテイメントは世を変え、人を救うのか」という、「べらぼう」全体を貫くテーマでしょう。前回に続き、一年間の放送のちょうど3分の2、という節目にあたる第33回では、中盤から後半へと突入するストーリーに、ドラマの中心主題を浮き彫りにする重要なシーンが畳み込まれました。(場面写真はNHK提供)
新さん、悔い無き最期の笑顔
「蔦重、俺は何のために生まれてきたか分からぬ男だった。貧乏侍の三男に生まれ、源内先生の門を叩いたものの、秀でた才もなく、おふくと坊のことも守れず」。
「丈右衛門を名乗る男」(矢野聖人さん)に斬られる寸前だった蔦重(蔦屋重三郎、横浜流星さん)をとっさの動きでかばい、毒を塗られた刃やいばの切っ先が腰に入ったのが新之助(井之脇海さん)でした。
「蔦重を守れてよかった」 本懐を遂げた新さん
蔦重に抱きかかえられた新さん。毒が身体に回る中、虫の息で自らの人生を振り返りました。「蔦重を守れてよかった。俺は世を明るくする男を守るために、生まれてきた」。そこまで語って事切れました。愛する妻子の元へと旅立っていった新さん、いい笑顔でした。蔦重の慟哭がいつまでも耳に残りました。涙なしでは見られないシーンでした。
誠実に生きる庶民の象徴だった新さん
新之助はドラマの前半からずっと登場している数少ないキャストのひとり。ストーリー上も徐々に重みを増したその歩みでした。
源内さんに連れられて吉原へ。女郎のうつせみ(のちのふく、小野花梨さん)との運命の出会いでした。激しい恋に落ちます。
学識があり、字も上手。蔦重の仕事をよくサポートしました。締め切り間際に工程を度外視した蔦重から無茶な修正が何度も入り、ブチ切れていた場面も懐かしいです。それでも蔦重の熱意にほだされ、最後まで付き合う人でした。
恋しいうつせみと足抜けを試みたものの、あっさり捕まってしまいます。この頃は、侍のくせして吉原の男たちにボコボコにされてしまう、ちょっと頼りない新さんでした。
吉原を挙げてのお祭りの日。祭りの神様に導かれるように再会を果たしたうつせみと新さん。「べらぼう」屈指の名場面でした。
農村で野良仕事の傍ら、子どもたちに読み書きを教えるなど、慎ましいながらも落ち着いた暮らしを築いたのもつかの間。浅間山の噴火に遭遇。
餓死寸前まで追い込まれ、すんでのところで蔦重の店にたどりつきました。なんとか生き延びることができました。
子供が生まれ、平穏な日々が戻って来たと思う間もなく。
天明6年(1786)7月の利根川洪水に見舞われます。浅間山の噴火によって氾濫しやすくなった利根川。大規模自然災害に政権の無策が重なり、江戸の多くの庶民が貧困のどん底に突き落とされます。そこでは、蔦重の支援があって、ほんのちょっとだけの余裕があった新さんの家までもが標的にされました。乳飲み子に乳さえやれない、最底辺の暮しを強いられていた妻子持ちの男の凶行でした。
社会の貧しさの犠牲になった妻と子。哀しみの果てに権力の無策、世の不条理に目を背けるのを止めた新さんでした。「おかしいものはおかしいという。この世は正されるべきと俺は訴える」と覚悟を決めました。妻子の無惨な死に報いなければならない、自分にはその責任がある、という思いだったでしょう。
派手な道楽は無縁。誠実に、地に足を付けて生きようとしても、様々な苦難から逃れられない当時の庶民を象徴するキャラクターでした。幼少期に吉原へ売られたであろう、妻のふくも同様の人でした。成功者である蔦重や、権力者の意次らの目線では語りようがない、あの時代の現実を私達に見せてくれました。
エンタメは人の心を動かす 太夫の美声とリズム
新之助ら名もない庶民が立ち上がった打ちこわしのクライマックスで、エンターテイメントの力を表現した一つ目の場面がありました。江戸の町全体を巻き込む激しい抗議活動に驚愕した幕府。とにかく金を配り、それを米に確実に替えられると保障することで、難局を乗り切ることにします。意次から頼まれ、その政策のPR役を任された蔦重。一刻も早くニュースを市中に広めて事態を収束させたいのですが、読売(かわら版)を配っても、この狂騒状態ではまともに読んでもらえるとはとても思えません。そこで一計を案じました。
富本節の名手、富本斎宮太夫(新浜レオンさん)が美声を響かせます。「天から恵みの銀が降る~」「三匁二分、米一升、声は天に届いた」。
次郎兵衛(中村蒼さん)たちの力強いリズム隊がそれに続きます。
目を輝かせる江戸の庶民たち。美しい歌とダイナミックな音楽に支えられて「自分たちの力が幕府を動かした」という感触を確かめることができたのでしょう。
芝居、歌、舞踊、アート……。いつの時代も変わらぬエンターテインメントの力ではないでしょうか。世の中を変えることは難しいかもしれませんが、世を生きる私たちに何らかの力を与えてくれるのです。蔦重、さすがのセンスでした。そしてドラマの作り手の強い信念も込められていました。
「エンタメが起こした奇跡の瞬間」
クランクアップした井之脇海さんが「美術展ナビ」などのインタビューに応じて、この場面を振り返っています。「蔦重率いる隊列が来たとき打ちこわしが止まるシーンがあります。その台本のト書きに『それはエンターテイメントが起こした奇跡の瞬間だ』と書いてありました。僕の大好きなト書きで、この一行にドラマのメッセージが凝縮されていると思います。エンタメが世の中を変え、影響を与えていく様子が今後も描かれていくと思います。」
まさに今回のタイトルである「エンタメの功徳(人のためになるよい行い)」を具現化した瞬間でした。
500軒以上が打ち壊された江戸
「天明の打ちこわし」(新日本新書)、「一揆打毀しの運動構造」(校倉書房)を参考にドラマで描かれた打ちこわしの状況を詳しく振り返ります。天明7年(1787)5月の打ちこわしは7日の大坂を手始めに、燎原りょうげんの火のごとく各地へ波及しました。この月だけも長崎、熊本、博多、下関、広島、尾道、尼崎、堺、奈良、和歌山、福井、駿府、甲府、神奈川などで発生。江戸にその動きが波及するのは時間の問題でした。
鈴木理生・鈴木浩三『ビジュアルでわかる 江戸・東京の地理と歴史』(日本実業出版社刊)から転載。著者の許可を得て一部加工。「天明の打ちこわし」(新日本新書)を参考に作成。地図上の黄色の枠の地名が打ちこわしが大規模に起こった地域です。ほぼ江戸全域に広がっているのが分かります。江戸では5月中旬から散発的に打ちこわしが始まり、本格化したのは20日から。赤坂の街が発火点に。新之助のいた深川などもそれに続きました。
統制の取れた行動、「社会的制裁」が目的
ドラマで描かれていたように、打ちこわしは主に米商人を狙い、多くは統制の取れた行動をしていました。米が買えないからといって米を奪って分配するのではなく、俵を引き裂き、道に巻き散らかし、溝に投げ込むなどして、米を商品として使い物にならないようにしました。建物の一部や建具、家財道具などを壊しはしましたが、家そのものを壊した例は見当たらないということです。ドラマに出て来た「作兵衛」は実在の米屋で、意次の米を預かっていると評判だったため、特に狙い撃ちにあったようです。
打ち壊しが拡大する中で、盗賊行為やお金の紛失の届け出もあり、打ち壊し勢をなだめるために店の前に置かれた酒に酔いつぶれるなどのケースもありましたが、基本的には高値を狙って米を売り惜しみする商人への社会的制裁、という色彩が濃い抗議行動でした。20日から24日の間に、500軒以上の米屋などが打ちこわしの対象になりました。
蘭徳 画『新建哉亀蔵 : 2巻』,刊. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892650 打ちこわしを風刺した黄表紙も色々と出ました。こちらはすっぽんが打ちこわしをする奇想天外なストーリー米価高騰、鈍い公儀の対応 庶民の怒り頂点に
打ち壊しの発生の理由は物価の高騰でした。この天明7年の正月、米の小売価格は銭100文で6~7合が買えました。ところが4月に入ると100文で3合5勺、5月では3合、さらに2合5勺、2号2勺と日に日に上昇し、年明けから3倍になりました。この間の玄米相場の上昇より小売価格の上がり方が急だったといい、便乗値上げもあったのかもしれません。米以外の物価も軒並み上がっていました。続いた米の不作に加え、江戸などの都市人口の増大に伴って食糧の需要も拡大したのに、流通システムが追い付かないという問題もあったようです。当時の江戸では行き倒れて死ぬ者、川に身を投げる者が相次ぎました。幕府の統治能力の欠如は明らかでした。
「犬を食え、とお侍から言われた」と広め、民衆を扇動した治済と丈右衛門と名乗る男。「犬を食え」発言は実話だったかもしれません。(前回の「新之助の義」のシーンから)「犬がいるうちは飢えることもない」
その幕府側の対応は常にちぐはぐ。公儀から米の売り出しがあっても高値の時価相当で、「高くても有難く食え」と言わんばかり。「米の代わりに大豆を食べなさい」とお触れを出し、ご丁寧に食べ方の指南まで広めたので、「大豆だって高いし、そもそも品薄」とかえって庶民の怒りを買いました。当時の風評では、町奉行から「田舎では猫まで食っているというではないか。江戸の町には犬がたくさんいる。犬がいるうちは飢えることもあるまい」と言われたという話もあります。幕府側の危機感の無さ、対応の悪さを知れば、打ちこわしになるのも当然、という状況でした。ここにも明確な時代の転換点を感じさせます。
蔦重のピンチを助けた長谷川平蔵が現場に派遣されたのも史実通り。しかしこちらも投入の判断が遅かったのです。すべてが後手後手の幕府でした。
治済のチーム、打ち壊しの市中を徹底調査
今回のドラマも、影の主役は一橋治済(生田斗真さん)でした。
前回、流民に偽装して江戸市中を視察。蔦重を自らの陣営に敵対する重要人物と確認した上で、「丈右衛門と名乗る男」に殺害を指示したのでしょう。あらゆる手段を使って権力を自らの手に握ろうとします。
打ちこわし勢に盗みを働かせ、事態を悪化させようとする「丈右衛門を名乗る男」ドラマでは、江戸の町を一層の混乱に陥れる陰謀を企てた治済ですが、江戸の町の状況に治済が注目したのは事実なのです。
『劫粟記事』(筑波大学附属図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100352601「劫粟記事(きょうぞくきじ)」という文書が残っています。一橋家では12人の小人目付という幕府のスタッフを打ちこわしの最中の市中に派遣して、被害状況を調査させました。その記録をまとめたものです。
『劫粟記事』(筑波大学附属図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100352601「赤坂」「青山」などお馴染みの地名が次々にでてきます。打ちこわしの発生地でした。丹念な記録で、被害地域の拡がりなどを知る上で、貴重な資料になっています。治済がなぜ江戸市中の様子を調べさせたのかは分かりませんが、息子の家斉が将軍になったばかりの時期です。混乱がさらに広がれば、将軍の権威に傷がつきかねないとも考えらます。息子の事を心配して調べさせた、と想像すると「親心」を感じさせる対応でもあります。いずれにせよ治済本人が市中に出たり、「丈右衛門を名乗る男」が暗躍したりしたドラマの展開は、こうした一橋家をめぐる事実からそれほどかけ離れていないことも分かります。文献などから想像力を働かせたエピソードだったのしょう。
「毒」をもって政治を動かす治済
市中では「丈右衛門」を失い、工作に失敗した治済ですが、江戸城中では巧妙に目的を達成しました。幕政全体に隠然たる影響力を誇る大奥総取締の高岳(冨永愛さん)に面談したのは、治済抱えの非公然工作員の顔も持つ大奥の重鎮、大崎(映美くららさん)です。大崎は、治済から渡された手袋を「このようなものが私のところに送りつけられてきたのですが」と意味深な問いかけをしつつ、高岳に見せつけます。
指先の色が変色していることにわざわざ言及し、「調べてみましょうか」とまでいう大崎。明白な脅しです。
この手袋は高岳が意次に頼んで誂え、種姫の名前で、先代の将軍家治の世継ぎだった家基(奥智哉さん)に贈ったものです。この手袋を使った家基は死亡。この手袋に不審点あり、と察知した老中の松平武元(石坂浩二さん)も急死し、手袋は武元の手元から無くなっていました。そうした一連の経緯は高岳も把握していたでしょう。
治済に屈した大奥
その「死を呼ぶ手袋」を高岳に突き付けた大崎の真意は「手袋を誂えたあなたが疑われるかもしれませんよ」なのか、あるいは「あなたも毒を盛られるかもしれせんよ」なのか。その両方なのでしょうか。いずれにせよ、恐るべき陰謀が過去の要人の死の背景にあることを知った高岳。治済=大崎のラインに屈するほかありません。倹約一点張りで、大奥としては避けたかった「老中・松平定信」の人事案を呑まされることになりました。
「首座ならば」、「10万石を差し出せ」 定信と治済の駆け引き
大奥が定信を老中とする人事を受け入れ、これで治済サイドは全て上手くいったかと思いきや、当の定信が思いもがけない条件を付けてきます。「首座にするなら老中を引き受ける」。満年齢でまだ28歳の若さ。自信家ぶりを伺わせるエピソードです。
寝耳に水の要求を聞いた治済も丸のみしません。「田安家の10万石を差し出せば、そなたの忠義を示し、いかにも首座に相応しい、ということに」。狐とタヌキの化かし合いのようでしたが、さすがに治済のほうが一枚上手だったようです。
今は反意次で連携している治済と定信ですが、歴史を見る通り、その蜜月は意外なほど長くは続きませんでした。お互いに個性の強い者同士。早々に難しい関係になることを予感させるやり取りでもありました。
この人事で追い詰められたのが意次です。打ちこわし対策に奔走するなかで「忘れておった。城中の魔物たちのことは」。大奥が「老中・定信」の人事を呑んだのが想定外でした。老中を退いてからもしぶとく立ち回ってきた意次ですが、いよいよ退路を断たれたのでしょうか。これからの意次の身の処し方、生き方が見せ場になるのでしょう。
慟哭の蔦重を救った歌麿の「画本虫撰」
幕切れが、「エンタメは人を救う」という、このドラマ全体のテーマを描いたもうひとつの重いシーンでした。
「おれは墓穴掘って、この人たちを叩きこんだんだって」。自分をかばって新之助が死んだ事実は、蔦重にとってあまりに苦しい出来事でした。新さんやふく、とよ坊が葬られた土まんじゅうの前で、蔦重は抜け殻のよう。これまで、母や母の愛人の死を背負ってきた歌麿にとっても、大切な人である蔦重の苦しみ、そして苦楽と共にした新さん一家の悲劇は、自分のことのように辛いものだったに違いありません。
ここで歌麿が「これが俺の『ならではの絵』さ」と差し出した原稿が、蔦重の心をいくらか動かしたようでした。蔦重は「生きてるみてえだな」とぽつり。
「絵ってなあ、命を写し取るようなものだなって。いつかは消えてく命を紙の上に残す。命を写すことが俺のできる償いなのかもしんねえと思いだして。近頃は少し心が軽くなってきよた」。歌麿の言葉に思わず涙する蔦重。
まさに「生きている」かのような細密な絵画。そして自在な画面構成。歌麿の本領が発揮された作品の原稿です。まもなく、歌麿の代表作へのひとつへと結実していくものです。
「新さん、いい人生だったと思うよ」と歌麿
歌麿、絵だけでなく、言葉も奮っていました。「新さん、いい人生だったと思うんだよ。さらいてえほど惚れた女がいて、その女と一緒になって、苦労もあったんだろうけど、きっと楽しい時も山ほどあって、最後は世に向かって、てめえの思いをぶつけて貫いて。だから、とびきりいい顔しちゃいなかったかい?」。のちに、世界的超一流アーティストとして評価される絵師、まるで最期の新さんの顔を見ていたかのような見立てでした。
「歌麿に写してもらいたい、いい顔だった」
蔦重、歌麿の作品と言葉に導かれて、ようやく自分の心を開くことができました。「いい顔だったよ。いままでいちばんいい顔で、男前で。おめえに写してもらいたかった」。
とめどなく流れる涙。歌麿の1枚の絵が、蔦重の心を危機からすくい上げてくれたようでした。同じように1枚の絵に救われた経験のある方、決して少なくないでしょう。優れた絵の持つ力は計り知れないものがあります。
歌麿の「画本虫撰えほんむしえらみ」、翌天明8年(1788)、蔦重とのコンビで発刊されました。今日に至るまで、歌麿を代表する作品とひとつとして高く評価されています。今回のストーリーの象徴に相応しい名作、ぜひ展覧会で実物をご覧ください。
(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>
視聴に役立つ相関図↓はこちらから