リモートワークは限界なのか。完全出社、急成長企業に見る現実
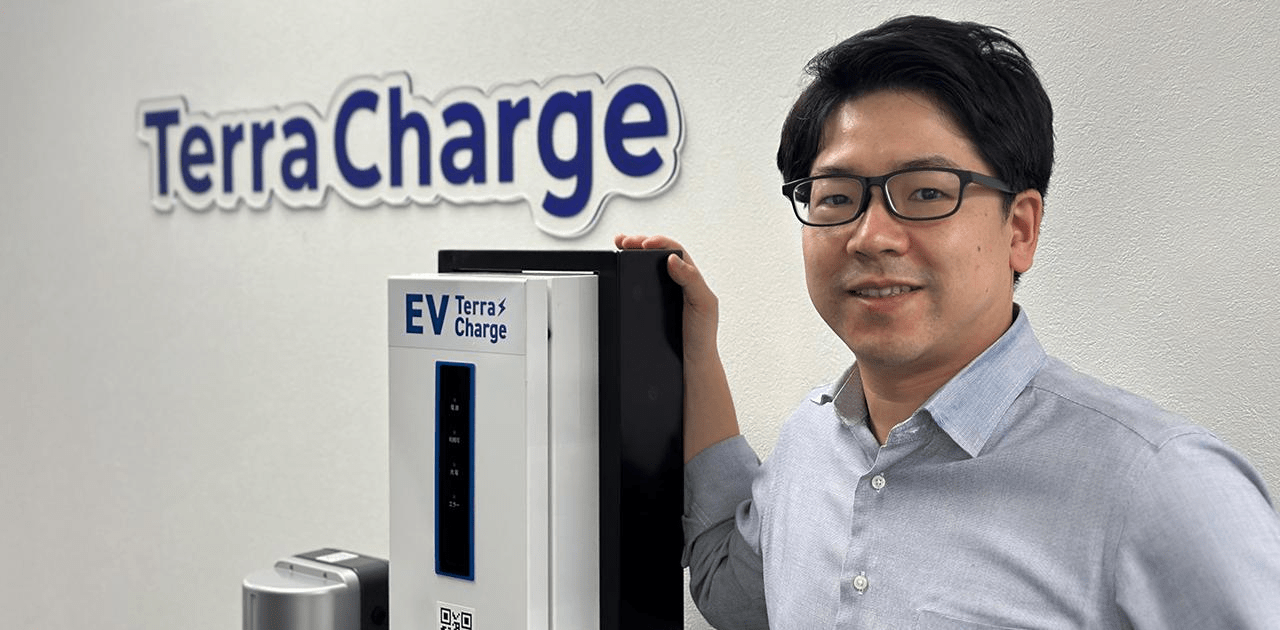
テラチャージの中川耕輔COO。インターン時代から徳重徹社長と共に働いてきた。
撮影:三ツ村崇志
出社勤務に回帰すべきか、リモートワークやハイブリッドワークを維持すべきか……。アメリカのビッグテックをはじめ出社回帰の流れが加速している中、悩ましい選択を突きつけられている企業も多い。
そんな中、「スタートアップが生き残る上で、とにかくカルチャーが大事。企業文化は戦略に勝る」として、週5出社前提で業界内で勢力を急拡大しているベンチャー企業がある。
EV用の充電サービスを提供する、テラチャージだ。
テラチャージは2022年に充電インフラ事業への参入を表明すると、初年度こそ設置数は約50基にとどまったものの、3年目にあたる2024年度には累計1万5000基に達する見通し。事業としては投資フェーズで黒字化はまだ先ではあるものの、収益基盤のインフラ設置の「面の拡大」で大きくリードし、業界のトップランナーの1社へと成長を遂げている。
テラチャージのCOOを務める中川耕輔さん(32)は働き方にも多様なあり方を求める若手世代でありながら、「スタートアップが勝つため、やり切るためには、そこまでやらないと行動量が生まれない」と週5完全出社の現状を語る。その意図を聞いた。
成長の鍵は経営者との「シンクロ率」
テラチャージは、2022年4月に当時テラモーターズとしてEV充電器事業へ参入を発表すると、そこから急成長を遂げている。2024年2月には、社名をテラモーターズからテラチャージへと変更している。
撮影:三ツ村崇志
「週5出社で勤務時間は昔ながらの9時〜18時。かなり昭和的な働き方だと思います。昭和のことは知らないんですが(笑)」
中川さんは、テラチャージの働き方を「昭和的」だと自ら語る。
一方で、「万人ウケはしないかもしれませんが」と前置きした上で、
「世の中には本気で仕事をやりたいのにやりきれない人たちは一定数いると思うんです。そういう方たちからすると、すごい刺さる会社だと思う」
とテラチャージの独特なカルチャーを説明する。
少数精鋭で始まるスタートアップ企業において、事業成長は経営者や創業メンバー(経営幹部)の突破力に依存するところが大きい。ただ、事業が成長し、従業員が増えて組織化していくにつれて、その突破力や熱量の「濃度」はどうしても薄まってしまうものだ。
「(従業員に対して)経営者から一つのことを伝えたときに、10の情報が入るような会社になることがスタートアップが成長するためには極めて大事だと思っています。これをやるには、やっぱり一緒に仕事をしないと。『シンクロ率』が低いのは課題だと思っているんです」
カルチャーは戦略に勝る。
スタートアップがスピード感を持って成長するためには、従業員一人ひとりが経営者と同じレベルの熱量や意識を持つことが理想だと、中川さんは指摘する。週5出社は、そういったカルチャーを醸成する手法の一つになっているというのだ。
当たり前の基準を上げる
テラチャージのアプリ。
撮影:三ツ村崇志
「リモートでもしんどいことを乗り越えられるとは思うのですが、乗り越えられる量が違うのではないでしょうか。自分の家で勉強すればいいのに、塾に行くのと近い感覚かもしれません。会社に来たら、少なくとも周りが仕事をしている。そうなったら、やらざるを得ない。ある種の強制力がある」
中川さんは週5出社するメリットの前提をそう話す。その上で重要なのが、いかに組織として「当たり前」の水準を高めるかだという。
もちろん、リモートワークでも自律的に仕事を進められる人はいる。ただ、特にパフォーマンスが上がらない社員がいる組織や、テラチャージのようにマーケットとプロダクトがはっきりしていて組織的に営業していく必要があるような事業領域では、社員が顔を突き合わせて進めていくことで最大限スピードが上がる場合もあるという。
テラチャージが行うEV充電器の設置事業では、設置先を確保する営業活動や、政府の補助金を押さえる仕事、設置工事の計画を詰める作業など、かなり地道に一つずつ進めていかなければならない業務が多い。
テラチャージの充電スポット。
撮影:三ツ村崇志
営業先とどんな話をするのか、そのときどんな表情をしているのか —— 。組織として高いレベルで方法論を統一することは、成果を出す上で非常に重要だ。単に成功事例を共有するだけでは、どうしても全員を高いレベルに引き上げることが難しい。
「できる社員は勝手に修正できるのですが、中にはうまくいかない社員も出てくるものです。やっぱり『横で見てこうした方が良い』と膝を詰めてやらないと成長しない」
「ロジカルの先」に行かなければ勝てない
テラチャージの徳重徹社長。中川さんは、社長の熱量を社員にいかに伝えるかが強い組織になる上で重要だと話す。写真は2023年12月に撮影したもの。
撮影:三ツ村崇志
技術的な側面だけではなく、出社による「熱量の伝播」も勝てるベンチャーになる上では重要だと中川さんは話す。
「横でガンガン営業かけている社員が数字(成果)を出してきたら、『自分も頑張らないとな』と思いますよね。それが組織全体でできるようになると、事業は勝手に伸びていくはずです」
朝、会議が終わった瞬間に営業社員が電話をかけ始める。ガチャガチャとした音がオフィスに響く。周囲の社員が仕事をしている音や空気、緊張感がある。オンラインでは決して感じられない雰囲気だ。
昭和的な考え方かもしれないが、それを社員全体に伝えることが週5出社の一番のポイントなのだという。
「No.2として、社長の熱量と共に戦うメンバーを増やさないと、ロジカルな事業で終わってしまう。ロジカルを超えた先に行かないといけない」
テラチャージのオフィス入口には簡素な形でミッション、バリューが掲げられていた。華美な装飾をせずに、事業に集中するコスト意識・ストイックさも徳重流だ。
撮影:三ツ村崇志
しかし、いくら社員に熱量高く仕事に打ち込んでもらおうとしても、企業文化はそう簡単に醸成できるものではない。
実際、テラチャージでは人員が160人規模にまで膨らんでいた2023年の冬頃に、部門ごとにカルチャーがずれ、全体のマネジメントに膨大な負荷がかかっていた時期があったという。中川さんは当時、「これではだめだ」と限界を感じ、組織を作り直してカルチャーの浸透を進めてきた。
改革の中では当然離れていく社員もいた。ただそれでも、理解を示し残ってくれる社員もいたという。結果的に社員数は約3分の2になった一方で、事業成績(設置数)は昨年から4倍に伸びた。
どうすればカルチャーの浸透が図れるのか。中川さんは、経営トップに熱量があることはもちろんのこと、その「ブレなさ」と「素直さ」が重要なのではないかと話す。
「私は10年間、徳重社長と一緒にやってきたのですが、彼はブレない。それはかなり大事です。加えて、数年前から素直さにもこだわろうと彼(徳重社長)が言い始めたんです。10%でも悪い部分があるなら、言い訳せずにその10%をしっかり反省しようと。それが今、社内に伝播していて」
何かミスがあると、人は思わず言い訳をしたくなるものだ。ただ、責任がある部分を素直に振り返り続けていくうちに、「彼(徳重社長)の言ってることがすごくよく分かるようになっていった」(中川さん)という。社長と経営陣の視座が揃っていったわけだ。
テラチャージが実現したいのは、これを社員一人ひとりのレベルにまで浸透させることだ。
オフィスには、徳重社長の仕事に対する考え方を示す資料などが掲げられていた。
撮影:三ツ村崇志
週5出社で仕事のレベルを高い水準で同期させた上で、経営陣同士だけではなく、中間管理職や一般社員までの目線を合わせる。こうして、激しい競争環境の中で120%の力を発揮して成長し続けられる企業文化ができるのだという。
「世の中の流れからすると、僕らは逆行しているところも正直あると思うんです。でも、勝つためにはここまでやり切る必要があるのではないかとも思います」
改革を進めていく中で、テラチャージのファイナンス的にも多少余裕が出てきた。当然その分、従業員への還元策も整備している最中だ。
「それができれば、もう1段階も2段階もみんな頑張ってくれると思います」
勘違いしてはいけないのは、テラチャージは確かに週5フル出社での勤務が前提ではあるものの、深夜残業やパワハラまがいの無茶な働き方・指導を奨励しているわけではないということだ。
「企業文化として、ベクトルを間違えないように気をつけています」
ただ、課題もないわけではない。例えば、週5完全出社で気になるのは、子育てとの両立や、男女問わず産休・育休の取得といった従業員生活との両立だ。
中川さんによると、現時点で両親やパートナーの助けを借りて個別に解決できている事例が多く、表面化した問題はないという。ただ、自社で負うべきリソースを社員のパートナーが働く企業や親世代に肩代わりさせて成り立ってるだけとも取れる。それでうまく回る事例は限られる。
今後企業として成長し、社会的な責任が大きくなっていく上では、単に「昭和的」な働き方に回帰するだけではなく、令和版「企業戦士」を生み出す仕組みも必要かもしれない。



