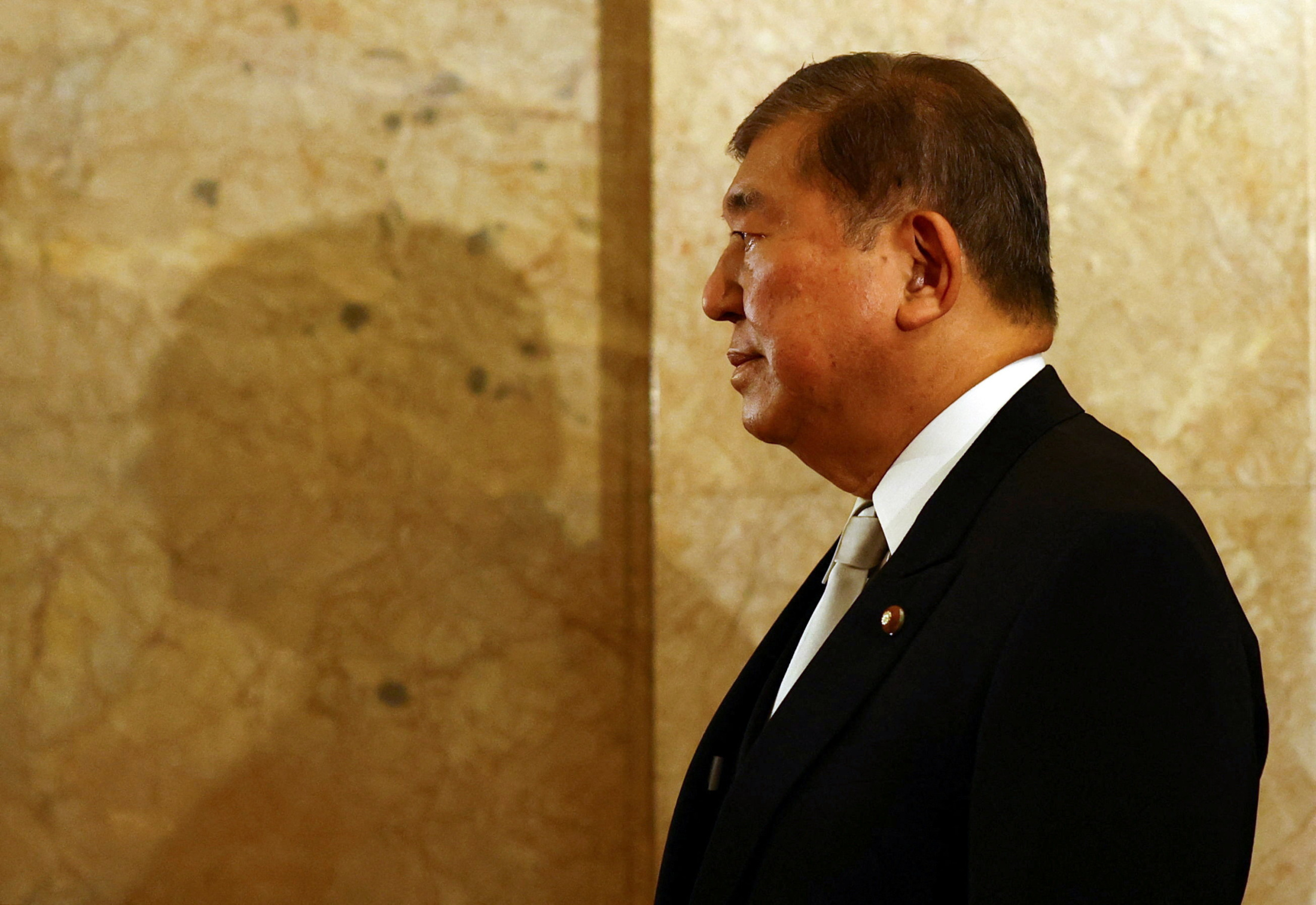フィジーのイグアナは3000万年前にイカダで太平洋横断していた

植物でできたイカダに乗って海を漂うイグアナの群れ。想像したらめちゃくちゃかわいい。
米国科学アカデミー(National Academy of Sciences)に掲載された論文には、フィジーイグアナ属は海の上を漂いながら、北米から南太平洋まで8,000kmを移動してきたのではないかと記されています。
アメリカから海を渡ったイグアナ
ガラパゴスのウミイグアナから熱帯のカメレオン、砂漠のトカゲまで約2,100種の爬虫類を含むイグアナ科の系譜に関する新たな調査により、フィジーイグアナ属はアメリカ南西部のトカゲに最も近縁であることが分かりました。
両者の地理的な距離は遠いですが、遺伝的には比較的近いことから、研究者チームは太古の昔、アメリカ南西部の砂漠に生息する爬虫類の群れが漂流物に乗って、およそ1年ほどで海を渡ってフィジーまでたどり着き、そこで約3400万年生き延びたと結論付けています。
火山活動によりフィジー諸島が形成されたのも、約3400万年前とされています。
サンフランシスコ大学の爬虫類学者兼古生物学者で、論文の筆頭著者であるSimon Scarpetta氏は、
フィジーイグアナの系統がその祖先から分岐したのは、比較的最近の3000万年近く前のことでしょう。フィジー諸島を形成した可能性のある火山活動があった後か、それとほぼ同時期だと考えられます。
と、カリフォルニア大学バークレー校のリリースで述べています。
イグアナたちの太平洋横断の旅にかかった期間は、4〜12カ月と推定されていましたが、最近のシミュレーションでは2.5〜4カ月と示唆されています。
さらに、Simon氏は米ギズモードのメール取材に対し
分散したメカニズムは、植物でできたマットのようなもので海上を浮遊できたことです。北米からフィジーに渡ったイグアナは、太平洋を横断する途中でその浮遊物から食料を得ることができたかもしれません。また彼らは、途中で直面した水の不足や高温などの条件にも耐えられるほどの回復力もあったと考えられます。
と、述べています。
研究チームの結論が正しければ、フィジーイグアナ属の祖先は、植物の漂流物と偶然の海流、そして夢に乗って、アメリカ南西部からフィジーまで8,047km(5000マイル)もの距離を移動してきたことになります。この移動は、陸生脊椎動物の海洋横断移動としては最長記録です。
長年の論争「漂流 vs 徒歩」
さらに同リリース内では
イグアナが北米から直接、フィジーに到達したというのは、ちょっとイカれた話みたいに聞こえますが、隣合う陸地からの植民地化を含む代替モデルは、3400万年以内に到着したという時間枠に当てはめて考えるとうまく合いません。
と、カリフォルニア大学バークレー校の爬虫類学者で共著者のJimmy McGuire氏は述べています。フィジーやトンガ以外の太平洋にある島のどこにもフィジーイグアナ属の化石は見つかっておらず、McGuire氏も直接北米からたどり着いた可能性が高いと考えているようです。
以前から、もともとアメリカ大陸に生息するイグアナが、どうやって飛び地で南太平洋の島々に分布したのか議論されてきました。徒歩説では、まだフィジー諸島が大陸と陸続きだった6000万年前ごろに分布したのではなどと言われています。
最後にScarpetta氏は
検証は難しいものですが、私たちの研究に関して指摘する価値のある疑問です。イグアナが一度に太平洋の島々を渡りフィジーまで移動したのではなく、北米からフィジーまで飛び移ったかどうかということです。
と、付け加えています。
フィジーやトンガに生息する4種のイグアナは、離島に隔離されているにもかかわらず、生息地の喪失や捕食、エキゾチックペットとしての取引などにより、絶滅の危機に瀕しています。
フィジーイグアナに限ったことではありませんが、生き物が困難を乗り越えてなぜ子孫を残してきたのか、そして今日まで生き延びてきたことを考えると、人間の身勝手な行動の愚かさが醜く感じられますよね。