コラム:トランプ氏の発言に振り回されるドル/円相場=尾河眞樹氏
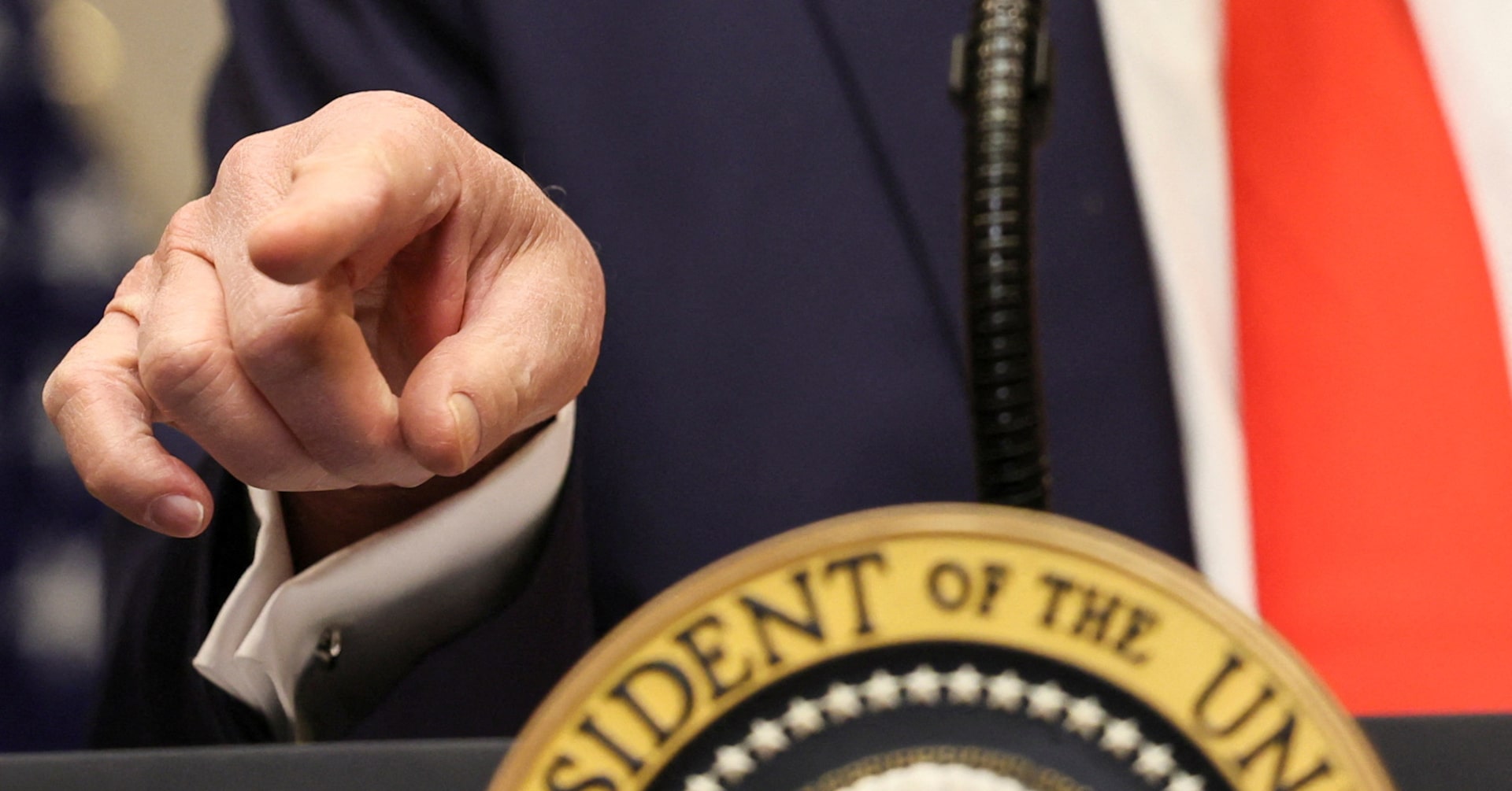
[東京 7日] - 3月3日、トランプ米大統領が日本と中国の通貨政策に言及したことで円が急騰し、一時148円台を付ける展開となった。ホワイトハウスのイベントで記者団に対して述べたもので、「中国の習主席や日本の首脳たちに電話して、通貨を切り下げ続けることはできないと言った」、「我々にとって不公平だ。日本や中国やその他の国々が通貨を押し下げれば、キャタピラーが米国でトラクターを作るのは難しくなる」、「この問題の簡単な解決方法は関税だ」などと述べた。何事も「関税(タリフ)」の一言で解決しようというのがトランプ氏のスタイルで、自称「タリフマン」の本領発揮というところか。
しかし2月7日の日米首脳会談後の共同記者会見では、石破首相は為替を巡る問題に関して「第1次トランプ政権時と同様に、専門家である日米の財務相の間で、緊密な議論を継続させていく」と発言していた。また報道によれば、加藤財務大臣とベッセント財務長官は首脳会談前の1月29日のビデオ会談で、為替については緊密に協議していくことで一致していたという。
今回のトランプ氏による「円安けん制」は、政府の大臣レベルで適切な関係を構築し、両国の認識に齟齬はなかったとしても、トランプ氏の一言で全てがひっくり返される可能性があることを示していると言えよう。今後も、このように突如繰り広げられる不規則発言が市場に影響を及ぼすと思うと頭が痛い。
興味深いことにドル/円相場は、トランプ1.0の時と類似の値動きをしている。2016年と24年の大統領選を挟んで、それぞれ前後半年程度のドル/円相場を重ねてみると、1ドル=110円台がレンジの中心であったトランプ1.0と、150円台を中心とした今回のトランプ2.0では、水準こそ全く異なるものの値動きはほぼ同じであることが分かる。異なっているのは、トランプ1.0では、大統領選でトランプ氏が勝利した後に、米株高・ドル高の「トランプ・ラリー」が起こったのに対し、トランプ2.0では、投票前の24年10月頃から早くもラリーが始まっていた点である。これは、当時のハリス民主党候補が「1億人以上に減税・医療費の借金帳消し」をうたい、トランプ共和党候補もトランプ減税の恒久化を公約に掲げるなど、両者の景気刺激策に対する期待もあっただろう。加えて、米経済も予想外に堅調で、米利下げ観測が後退していたことなどがドル高の背景にあったと思われる。
しかし、一度大幅なラリーが起こった後は、ドル/円はいずれのケースも年明けにいったん反落している。17年1月31日、トランプ氏はホワイトハウスで行われた製薬業界幹部との会合で、米国の貿易赤字や企業流出の要因は「他国の資金供給と通貨切り下げだ」と述べたうえで、「中国や日本は何年も通貨安誘導を繰り広げている」などと批判した。これを受けてドル/円は翌日にかけて115円台から112円台に下落した。
振り返れば16年3月、大統領選で共和党の候補指名を争っていたトランプ氏は、「キャタピラーは円安でコマツとの競争が難しくなっている」などと発言、その後も「メキシコ国境の壁はキャタピラーの建機でつくる」などと述べており、キャタピラーはトランプ銘柄とされていた。今回の発言は当時と同様の観点であり、為替を巡る問題について、トランプ氏は9年前と全く認識が変わっていないようだ。しかし、決定的に異なるのは、今やどの観点からも「日本が円安誘導している」とは言えないことだ。日本の政府・日銀が実施した介入は、22年以降、円安を是正するための「円買い介入」であり、23年、24年の介入も含めると、これまでに約25兆円もの円買いが実施された。加えて日銀は24年7月、25年1月とそれぞれ0.25%の利上げに踏み切っており、「異例の金融緩和」からの出口に向かいつつある。
トランプ氏の通貨政策を巡る認識が事実と異なることに加えて、もう一つの問題は、同大統領は「関税」であらゆる問題に対応しようとしていることだ。既に、カナダ、メキシコからの輸入品に対する25%の関税を発動し、中国からの輸入品にもさらに10%の追加関税をかけた。また、鉄鋼・アルミニウムに対する関税政策に加え、自動車関税も検討。新たに検討されている「相互関税」については、貿易相手国との関税率を「揃える」だけでなく、付加価値税や補助金に加え、米国企業に対する参入障壁などあらゆるものを関税率に換算し、ペナルティー的に賦課するという。
足下米国のインフレの抑制が足踏み状態となるなかで、これらのトランプ関税が米国に輸入インフレをもたらせば、市場では米金利先高観が高まり、むしろ為替はドル高・円安に振れる可能性も考えられる。
日本経済にも影響を及ぼしかねないトランプ政権の政策リスクが高まるなかで、トランプ1.0における「日米経済対話」は参考になる。安倍晋三首相(当時)が17年2月に行われた日米首脳会談で提案したもので、同年の4月18日に初会合が開催された。麻生太郎副総理兼財務相(当時)とペンス米副大統領(当時)をトップに据え、財政、金融などマクロ経済政策の連携、インフラ、エネルギー、サイバー、宇宙などの協力と2国間の貿易に関する枠組みについて協議する会合となった。当時の報道では、先述したトランプ大統領の突然の円安けん制を受けて、日本の金融緩和の正当性を理解してもらうことを念頭に設定されたということだが、トランプ氏の為替に関する認識が当時と変わっていないのであれば、こうした丁寧な日米間の協議や説明が改めて必要になるかもしれない。
一方、同大統領の円安に絡む発言は、国内の製造業等、単に米国民向けのアピールという可能性もある。2月25日に公開されたロイターによる世論調査では、トランプ大統領の支持率は44%と、就任時の47%からわずかに低下している。ただし、トランプ1.0の支持率が平均で40%前後だったことを思えば、当時よりまだ高水準であり、バイデン政権の終盤(37%付近)を大きく上回る。
一方で、同氏の経済政策に対する支持率も低下している。19日発表の同調査では足下39%と、バイデン政権終盤の35%より高水準ながら、トランプ1.0の平均(50%付近)よりも大幅に低い。さらに、「米国経済は間違った方向に向かっている」との問いについては、就任時の43%から足下53%に急上昇している。これらが今回のトランプ大統領のリップサービスに繋がったのかもしれない。ただ、国民の不満はインフレの抑制が遅れていることや、これに伴い国民の実質所得が徐々に低下していることなどが背景にあるのではないか。その観点では円高・ドル安は米輸入物価の上昇につながるため逆効果だ。また、「化石燃料を掘ればインフレは減速する」というのがトランプ大統領の主張だが、米コア消費者物価指数(CPI)は財が前年比マイナス0.1%とすでにマイナス圏である一方、サービス価格が4.3%と高止まりしている。したがって、「インフレ抑制」はエネルギーを増産すればすぐに低下するとは考えにくい。仮に今後、関税引き上げによる輸入インフレに対する懸念などから支持率の低下が進むようなら、トランプ大統領の「タリフマン」ぶりも徐々に勢いが萎むかもしれない。
トランプ大統領は2月27日、メキシコ・カナダに対する関税を3月4日から導入すると発言した。その前日、26日に4月2日に発動と表明したばかりだ。このように、トランプ大統領のこれまでの発言には一貫性がない。市場参加者も同氏の言動1つ1つに、あまり一喜一憂しないほうが良いかもしれない。とはいえドル/円相場は当面、ボラティリティーの激しい展開が続きそうだ。トランプ政権の政策の見極めがつく6月末頃までは、146-158円程度のレンジ内を、ニュース次第で右往左往する展開を予想している。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*尾河眞樹氏は、ソニーフィナンシャルグループの執行役員チーフアナリスト。米系金融機関の為替ディーラーを経て、ソニーの財務部にて為替ヘッジと市場調査に従事。その後シティバンク銀行(現SMBC信託銀行)で個人金融部門の投資調査企画部長として、金融市場の調査・分析を担当。著書に「〈最新版〉本当にわかる為替相場」、「ビジネスパーソンなら知っておきたい仮想通貨の本当のところ」などがある。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。



