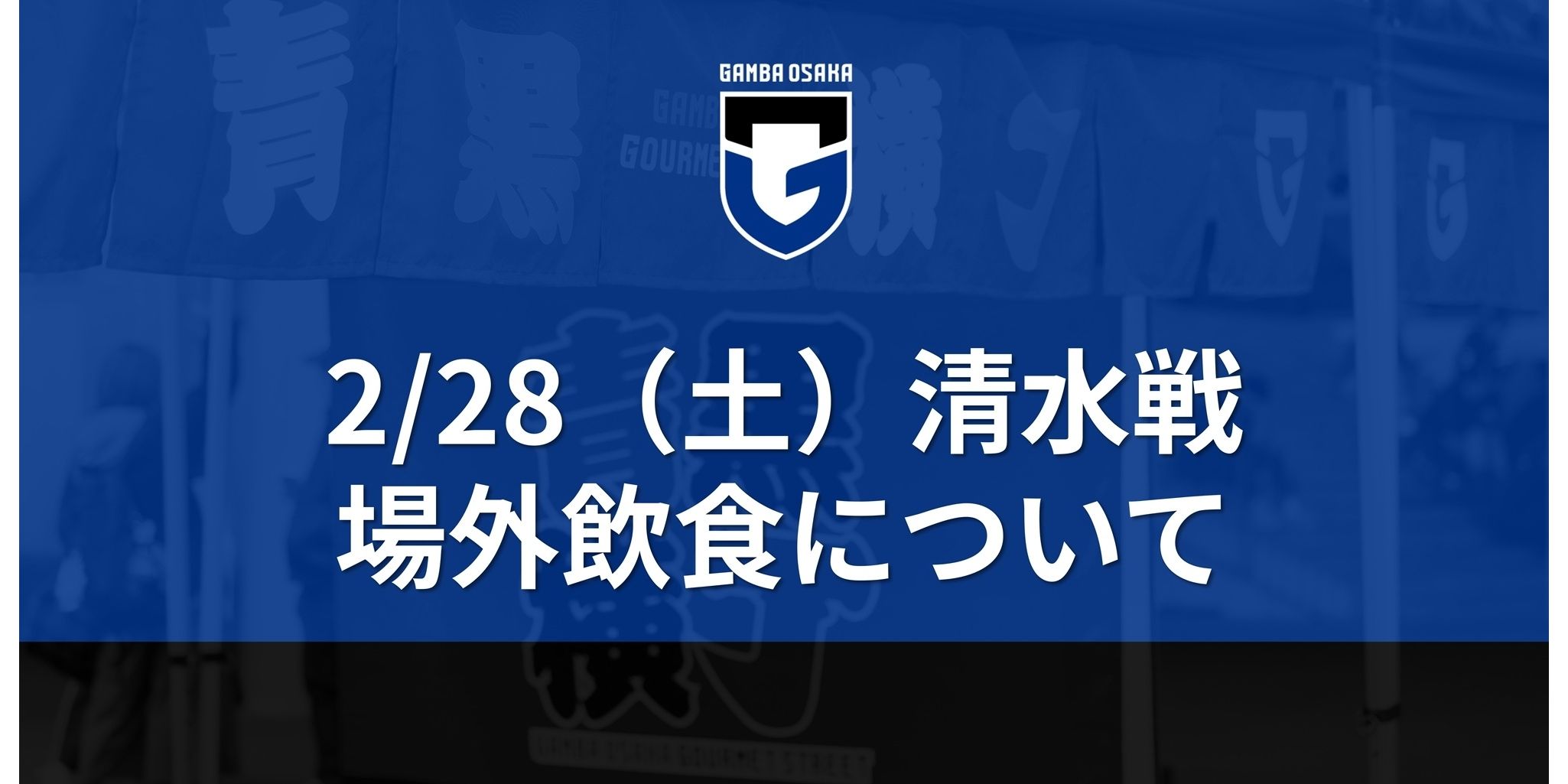「お母さんの体がもたないからクラブをやめて」と子どもに…負担増で保護者に限界 部活動の地域移行で「格差は進むばかり」

公立中学校の部活動を地域の民間クラブなどに委ねる「地域展開(地域移行)」について本紙「声のチカラ」(コエチカ)取材班は、当事者を中心にアンケートを行った。アンケートは5月30日~6月8日、通信アプリLINE(ライン)を通じて実施した。
長野県長野市の女性会社員(43)は、子どもが中学校のバスケットボール部から地域のクラブに移行し、遠征が増え、送迎、月謝、体育館の場所取りと、負担が格段に増えた。平日の帰宅時間は午後9時過ぎで、部活の時よりも2時間ほど遅くなり、勉強する時間は削られ、睡眠時間も親子ともに減ったという。
小学生と高校生の子がいる同県松本市の自営業の女性(48)は「どうしてもやりたければ考えるが、『ちょっとやってみたい』程度では送迎してまでやらせてあげられないかも」と戸惑う。周囲には、移行に伴って競技をやめた子もいる。「お金のない家や送迎できない家は何もできなくなり、教育格差は進むばかり」と感じている。
一方、子どもが中学校で卓球部に所属する松本市の女性会社員(50)は「部活でなくても、子どもだけで放課後すぐに行けて、体を動かせる場所が必要」と提案。同県北安曇郡池田町の男性会社員(48)は「勝ちや技術向上を目指す場と、生涯活動の基礎となるような楽しむ場を、良い形で両立できたらいい」とする。
負担感については、ソフトテニスを指導する女性公務員(54)から「土日は旅費も自腹で大会引率し、平日も仕事を抜けて指導してまた仕事に戻る生活。時間、体力、金銭の面で負担が大きい」との声も寄せられた。こうした課題の解決に向けては「教育委員会の主導で、学校、行政、企業、外部コーチが集まってワークショップを行い、地域に合ったクラブチームづくりに向けて動き出すことが必要」とする意見もあった。
同県大町市のアルバイトの女性(61)は「子どもたちの意見を大切にしてほしい」と訴えた。「生徒の意見が置いてけぼりになっている」「保護者や子どもの意見が反映されることなくクラブ化された」との声も複数あった。地域展開を良い形で進めるには、やはり一番の当事者である子どもたちの思いを優先しながら、進める姿勢が欠かせない。