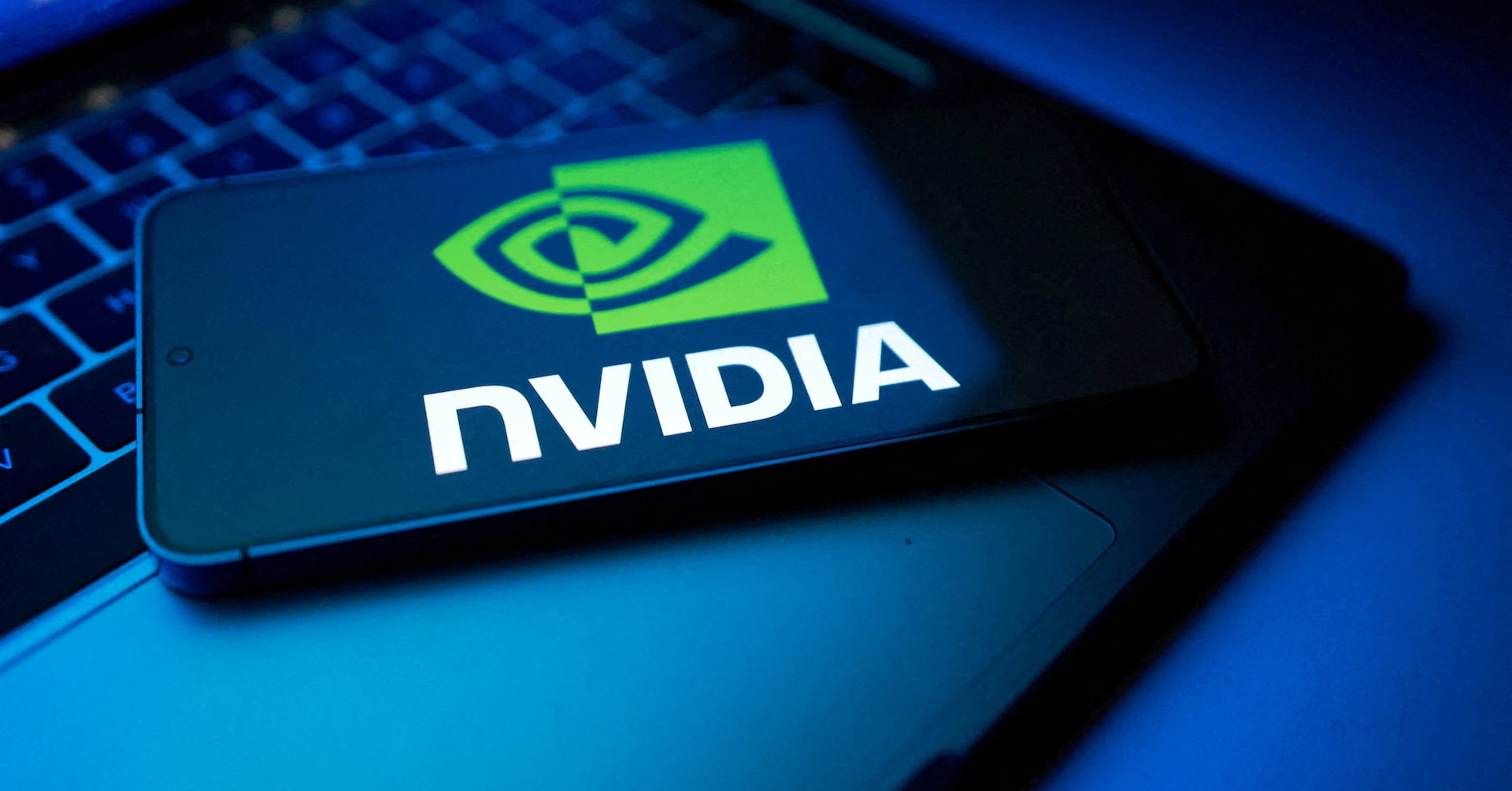交通手段限られる夢洲を会場にした理由は何か、万博誘致担った松井一郎・前大阪知事に聞く…開幕まで2か月

大阪・関西万博は13日、開幕まで2か月となった。遅れが指摘されていた海外パビリオンの建設にはめどがついたものの、入場券の売れ行きは低調で、誘客が課題になっている。(梅本寛之)
大阪府と大阪市が誘致を正式に表明したのは2014年8月。日本維新の会を率いた松井一郎知事(当時)らが旗振り役となり、18年11月、ロシア、アゼルバイジャンとの誘致レースを制して開催地に決まった。
会場の人工島・ 夢洲(ゆめしま) では、23年4月に起工式が開かれ、工事が本格化した。しかし、建設資材や人件費の高騰を背景に、海外パビリオンの建設遅れが表面化。日本国際博覧会協会(万博協会)が一部の建設を代行するなどてこ入れを図った。
万博協会によると、今年1月末時点で、自前で建設する「タイプA」の47か国42棟のうち5棟が完成した。残る37棟も大半は3月中に完成検査を受ける見通し。
目下最大の課題は、機運醸成だ。入場券の販売は、前売り目標1400万枚に対し約774万枚(2月5日時点)にとどまる。
万博協会は「並ばない万博」を掲げ、来場日時などを予約するシステムを導入。夢洲は鉄道が1本、道路が2本とアクセスが限られることが背景にある。購入・予約手続きの複雑さが入場券の販売不振の一因になっている。
「ベイエリア発展大阪に絶対必要」
万博を誘致した経緯について語る松井一郎氏(大阪市北区で)=宇那木健一撮影万博はなぜ開催されることになったのか。交通手段が限られる夢洲を会場にした理由は何か。誘致の中心を担った松井一郎・前大阪府知事(61)に聞いた。
――万博を誘致しようと思った経緯は。
2013年秋、大阪・北浜のすし店で、橋下徹さん(元大阪市長)と、(1970年大阪万博で企画を担当した)堺屋太一さんと話したのが始まりだ。堺屋さんが「展示型ではなく、お客さんに参加してもらい、世界の課題を解決する新しい万博をやる」と言った。
ただ、その時は俺自身はまだ懐疑的だった。ネットで何でも見られる今の時代にマッチしないんじゃないかと。15年にミラノ万博を視察した時、博覧会国際事務局(BIE、パリ)のロセルタレス事務局長(当時)から「すごくいいアイデアだ」と言われ、具体的な検討を始めた。大阪を成長させるために、仕掛け作りが必要だと思っていた。
――その年の12月、橋下氏とともに当時の安倍首相や菅義偉官房長官に協力を要請した。
安倍さんも最初は懐疑的で、「うーん、今から万博なの?」と。日本が直面している超高齢化という課題を解決する新しい万博を作りたいと言ったら、安倍さんも「それはやりがいのあるチャレンジだね」と。
大阪は再生医療の中心で、江戸時代から創薬が盛んで研究機関も多い。その頃、おやじが認知症になり、老化で人生を楽しめなくなった。何とか解決せなあかんとプライベートでも思っており、「健康・長寿」をテーマに選んだ。
――府の候補地案は、りんくうタウン(泉佐野市など)や万博記念公園(吹田市)など6か所だったが、夢洲は入っていなかった。
上海やニューヨークなど世界の都市はベイエリアがにぎわいの中心になっているのに、大阪は五輪招致に失敗してから見向きもされなくなった。ベイエリアの発展は、大阪の成長には絶対に必要だ。だから夢洲を入れるよう、菅さんにお願いした。
万博は半年間の開催だから、それだけでは不十分だと思っていた。だから(カジノを含む)IRだ。もともとはIRを先に決めて、IRの施設や展示場を使いながら(万博を)やりたかった。万博とIRをセットにするのはおかしいと言われたが、そうしないと夢洲の価値は上げられない。
――18年11月のBIE総会で、加盟国による決選投票の末、ロシアに勝った。なぜ勝てたのか。
やはり国家としての信頼だ。安倍首相の外交力は大きかった。誘致活動では、行く国々で「アベは元気か」「アベに自分の国を訪問してほしい」と言われた。世界の首脳にリスペクトされていたのだろう。
――会場建設費は2度増額され、当初の2倍の2350億円に膨らんだ。
物価や人件費が上がっており、仕方がない。万博だけやってその後は空き地なら問題かもしれんけど、万博の跡地も使いたいという民間企業が出てきている。
――「並ばない万博」を目指して入場予約を徹底しているのは、夢洲へのアクセスが限られるためだ。この結果、入場券の購入手続きが複雑になっている。
健康に一番悪いのはストレスだから、ストレスフリーな万博にしようと言った。夢洲には鉄道や道路があり、海からも行くわけで、それほどアクセスが悪いとは思っていない。予約手続きの煩雑さは、この前、万博協会の石毛さん(石毛博行事務総長)にも何とかしてくれと電話で伝えた。