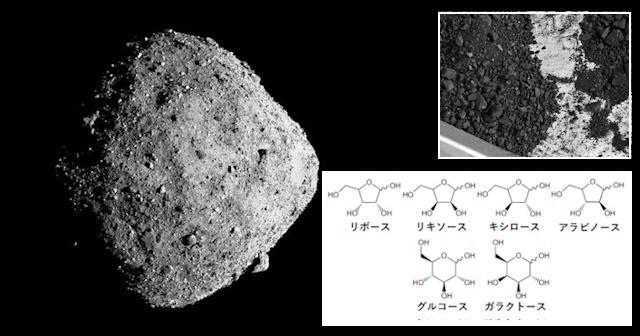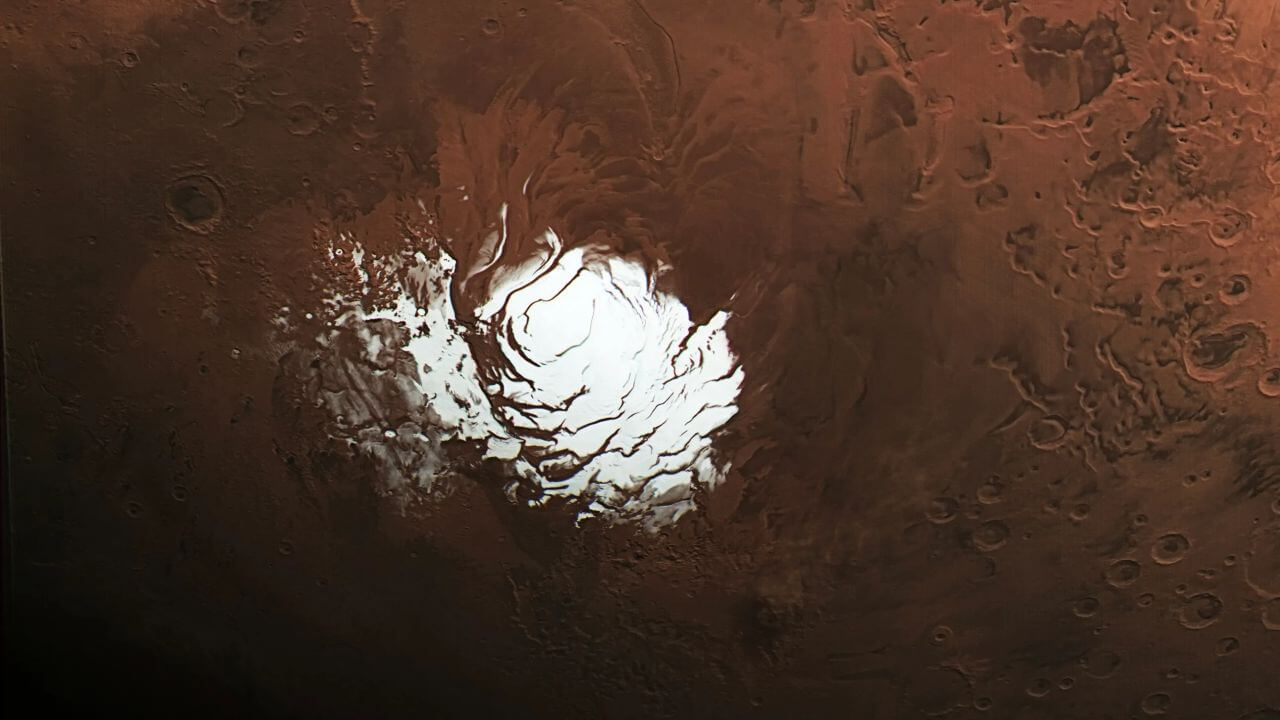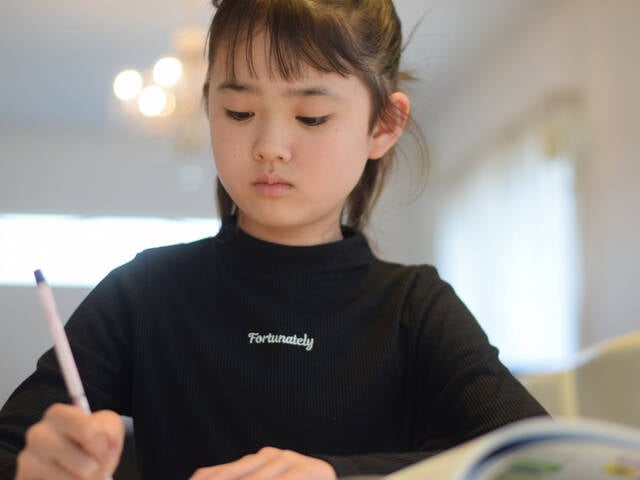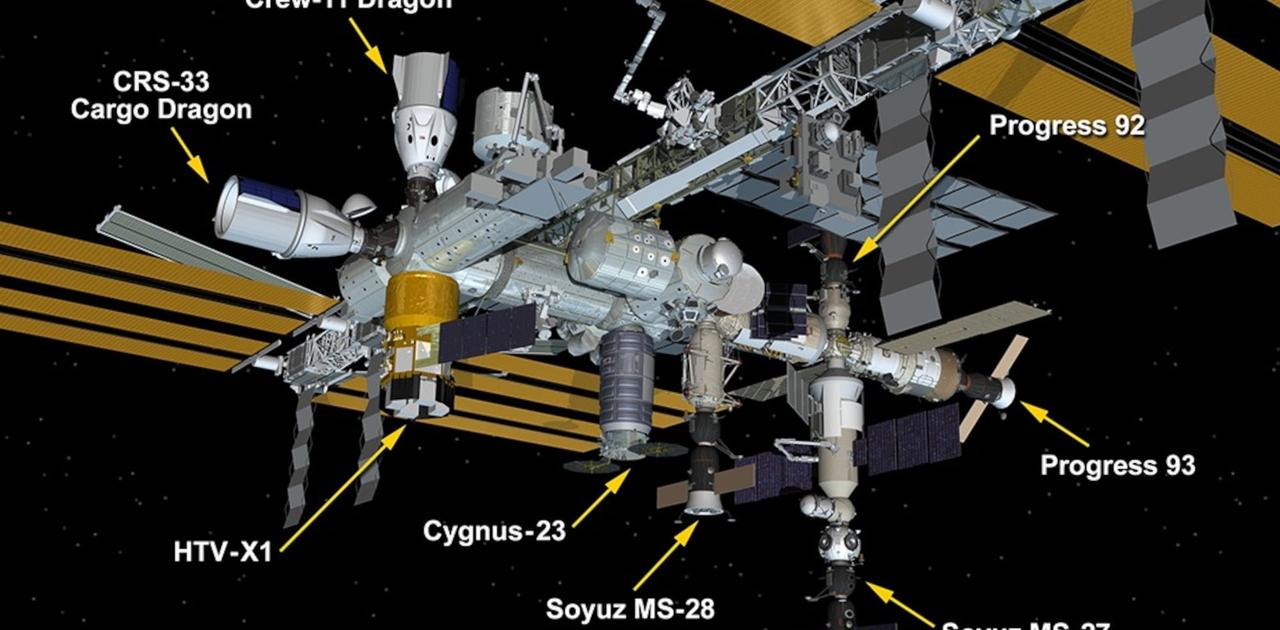『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は科学的にアリ? タイムトラベル映画を実証分析

だが一般相対性理論では、もうひとつ、興味をそそられる可能性が浮上する。ワームホールだ。ワームホールは一般に、空間内を移動する近道と考えられているが、それが空間内のみに限られると考えなければならない理由はない。時空内と考えてもかまわないのだ。ワームホールを作って安定させ、移動(あるいは情報を伝達)できれば、それを使って時間を前後に好きなだけ移動することができる。条件が整っていれば、強力な数学的解としてループ、つまり時間的閉曲線を作ることもできる。 たとえば、一般相対性理論の文脈のなかでは、過去の特定の場所に戻る方法もある。ただし、ちょっとした準備が必要となる。 物質から巨大ブラックホールを作り、その横に負の質量からできたブラックホール(論理的に存在すると仮定して)を作ったら、そのふたつのあいだにワームホールを作ることができる。 好きなだけふたつを離し、ワームホールの一方の端を光速近くまで加速する。その加速された端とともに移動するかぎり、好きなときにワームホールを通り抜けて、無傷のままもう一方の端までたどり着ける。その場合、一番面白いのはどこか? 光速に近い速度で移動しているため、時間の進み方が変わる。逆向きにワームホールを進むと、元の場所に戻ったとき、時間が進んでいないも同然になる。何百年という時間を旅したあとに、出発してからほんの数秒後の出発点に戻ることができるのだ。 そういう意味で、時間をさかのぼることは物理的に実際に起きても不思議はない。 ◾️タイムトラベルの文脈で映画を評価する 可能性はいくらでもあり、だからこそタイムマシンと想像力豊かな物語を組み合わせた映画が数多く存在する。だがもちろん、科学をいい加減に扱っている映画もある。 『タイムコップ』、『オフロでGO!!!!!タイムマシンはジェット式』、『ビルとテッドの大冒険』といった映画を、信じられないくらい正確にタイムトラベルやタイムマシンを描いた作品として記憶している人はいないはずだ。 『26世紀青年』は、不活性状態の物(あるいは人)が不活性であるあいだも時間は進むという意味でしかタイムトラベルを描いていない(タイム"マシーン”だけは正確に描かれているが)。 『スーパーマン』では、スーパーマンがロイス・レーンの命を救うために時間を巻き戻すが、これは科学ではなく超人的な能力によるものだ。最近の『ドクター・ストレンジ』、古典的カルト映画の『ワーロック』『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』にも同じことがいえる。 タイムトラベルの仕組みに魔法を使っても、科学的には高得点を得られない。多くの映画で、タイムトラベルは科学的な正しさよりも、話を進めるための道具としての役割に重きが置かれている。『キャプテン・スーパーマーケット』も、作品自体は楽しいのだが、そこで描かれているタイムトラベルの仕組みは実現可能ではない。『ネクロノミコン(死霊秘法)』の呪文を唱えて過去に放り出されるというのは、映画として魅力的だが、科学のにおいはしない。 だが、なかには、その仕組みについて語ったり、くわしく描写したりしていなくても、どうすればタイムトラベルが可能になるかをうまく描いている映画もある。 未来へのタイムトラベルは簡単だ。光速に近い速度で進み、出発点に戻れば、遠い未来にいることになるからだ。これが、『猿の惑星』で、人類をはるか未来のディストピアに変じた地球に送る方法であり、一方で、『スター・ウォーズ』で描かれるハイパードライブ(超光速航法)が満足のいくものでない理由でもある。 高速での移動は、時間の経過に実際に影響を及ぼすものであり、何をしようと未来に運ばれてしまうのだ。