ネット上の誹謗中傷を監視…池下議員らの名誉回復に向けた取り組み
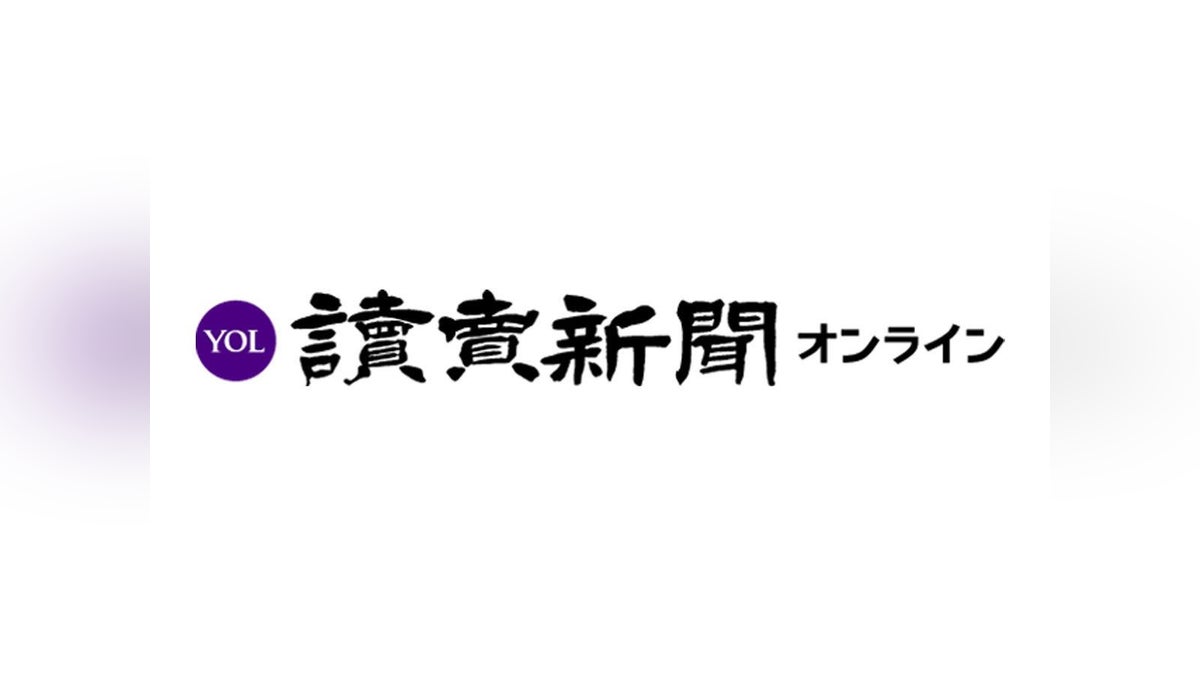
読売新聞は、今回の誤報により、インターネット上で池下卓衆院議員や2人の元公設秘書に関するデマや誤情報、 誹謗(ひぼう) 中傷の書き込みがないかについて監視を続け、名誉回復に向けた取り組みを進めてまいります。
今回の誤報をもとに、池下議員らに関する誤った情報などがネット上で拡散されていることを確認した場合には、事実と異なる情報であることを指摘し、池下議員らの名誉回復に努めてまいります。
また、誤報を掲載した新聞紙面やオンライン記事がネット上で拡散されていることを確認した場合には、当該記事が誤報であることを発信し続け、適切に対処してまいります。
再発防止へ記者教育徹底…記事の事前審査を強化
読売新聞は、今回の誤報の反省を踏まえ、記者教育の研修強化などの再発防止策を実施します。
社内では、iPS細胞を巡る誤報の反省として、2013年4月、編集局長をトップとする記者教育の専門部署「記者教育実行委員会」(記者塾)を設け、若手記者を中心に年間を通して研修を実施してきました。
しかし、今回、思い込みによる取材や確認不足が明らかになりました。改めて裏付け取材の徹底など、取材の基本動作を見つめ直すプログラムの導入を図るとともに、研修の対象も拡充します。これまでも、若手のほかにデスクや支局長、シニア記者らを対象に研修を実施してきましたが、本社の第一線で働く中堅記者やキャップ級記者への研修も強化します。
また、誤報を防ぐための専門部署である「適正報道委員会」は、調査報道など1面トップで展開するような重要な記事について、内容が適切か、裏付け取材が十分かなど、記者経験が豊富なベテランの委員が、第三者的な目で記事を掲載する前に審査、アドバイスしています。
ただ、今回の記事は審査に諮られず、誤報の一因になりました。このため、さらなる審査機能の充実を図ります。
さらに、取材上の留意点や報道のあり方に関して独自に作成している「取材報道指針」について、今回の誤報を教訓とするために改訂も行います。



