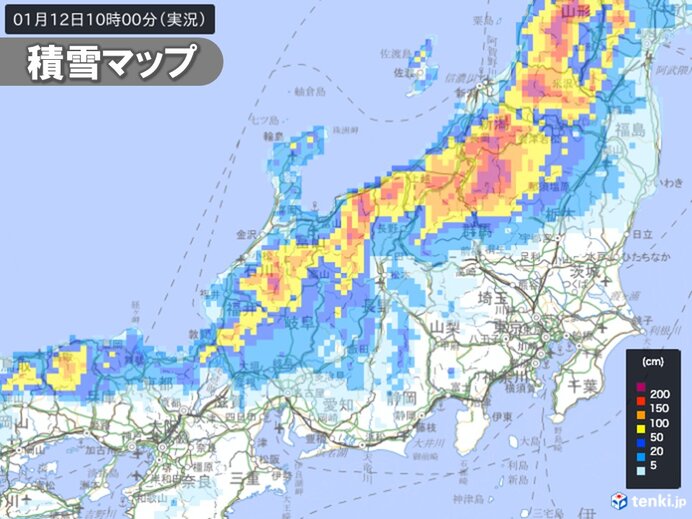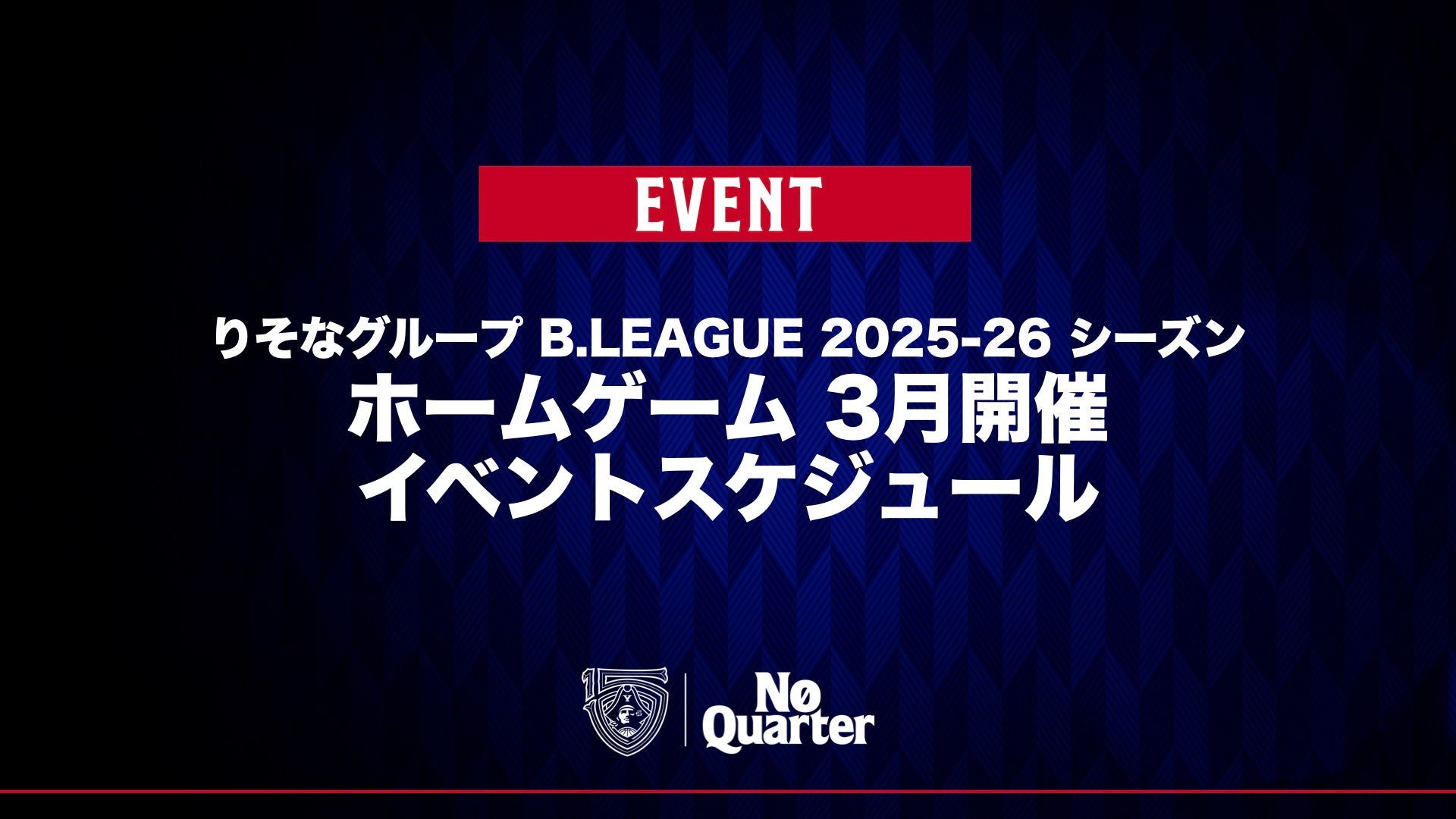「品位」はどこへ 選挙ポスター問題が再燃 新たな規制も限界

20日投開票の参院選では、選挙ポスターの「品位」を巡る問題が再燃した。
5月に施行された改正公職選挙法でポスターの品位を保持する規定ができたが、ポスターの記述で名誉を傷つけられたとして、候補者が別の候補者を刑事告訴する事態に。選挙管理委員会は踏み込んだ対応ができず、規制の限界を示した。
2024年7月の東京都知事選で、政治団体「NHKから国民を守る党」(当時)は関連団体も含めて候補者24人を擁立し、掲示板の枠を確保した。
Advertisement一定額を寄付した人に枠を譲る計画も発表し、候補者以外の人物や動物のポスターが大量に張られた。中には風俗店の広告もあり、大きな問題になった。
こうした事態を受け、与野党の各党は公職選挙法の改正に合意。ポスターに「品位を損なう内容を記載してはならない」とする規定ができ、特定商品の広告や営業宣伝をした場合は100万円以下の罰金が科される。
「選挙が機能しなくなる」
改正後初の国政選挙となった今回の参院選。宮城選挙区に立候補したNHK党新人の前田太一氏は公示日の3日、立憲民主党現職の石垣のり子氏のプライバシーに関する内容を記したポスターを張り出した。
石垣氏側はすぐ、名誉毀損(きそん)容疑で宮城県警に告訴した。改正公選法は、他の人や政党の名誉を傷つける内容の記載を禁じており、代理人弁護士は「このような行為を許していたら、選挙は適正に機能しなくなる」と批判した。
前田氏は取材に「党の指示で掲示したが、張ったのは自分。刑事処分が下されるなら、甘んじて受ける」と話した。
一方、兵庫選挙区に立候補した、NHK党党首の元職、立花孝志氏は「トランプ」と大きく記載する一方、自身の名前は小さく書いたポスターを掲示した。
改正公選法には「候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならない」とする規定がある。
選管は「判断できない」
ただ、地元の選管はいずれも静観の構えだ。
宮城県選管の担当者は「何も対応することはない。具体的な罰則や行政処分は定められておらず、選管が判断することはできない」と説明する。
罰則が設けられているのは営業宣伝に関する規制だけで、他人の名誉や名前の見やすさに関する規定には、罰則がないのだ。
さらに、過去の判例も根拠となっている。埼玉県加須市長選を巡り、選管が候補者のポスターに記載された同和事業に関する言葉の削除を求めたことの是非が争われた民事訴訟で、最高裁が1976年に出した判決だ。
判決は「選管は、ポスターに記載された候補者の主張に関係する文言については当否を審査し、取り消しや修正を命ずる権限を有しない」と判断。その上で、削除を求めた選管が選挙の自由公正を著しく阻害したとして、選挙を無効とした。
宮城県選管の担当者はこの判例に触れ、「内容を良い、悪いと判断すると、候補者の主張にも踏み込む形になる。形式的な部分は指摘できるが、中身については何も具体的な対応を取れないのが現実だ」と説明。「品位」についても「人によって見方が異なるので、行政機関が線を引くのは難しいと感じる」と話す。
兵庫県選管も品位保持規定について「あくまでも、候補者に自覚を促していくという趣旨だ。公選法に違反するかどうかは捜査当局の判断だ」とする。
「品位のあり方、議論を」
公選法に詳しい拓殖大学の岡田陽介教授(政治学)は今回の問題について「どういったものが品位保持規定に抵触するか明確になっておらず、想定された事態だ」と指摘。その上で「明らかに度を越しているものがあれば警察が取り締まるべきで、品位に関する前例もできてくるだろう。ただ、取り締まるだけでは窮屈な選挙となってしまう。有権者側や国会が品位や選挙のあり方について議論を重ねていくことも必要だ」と語る。【五十嵐隆浩】