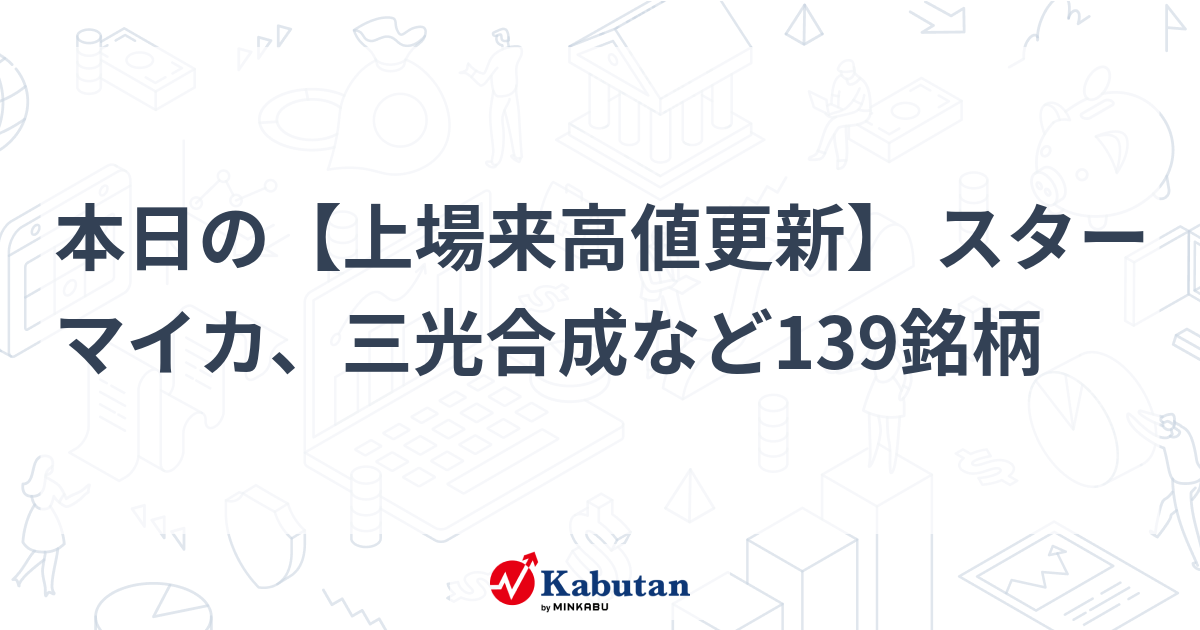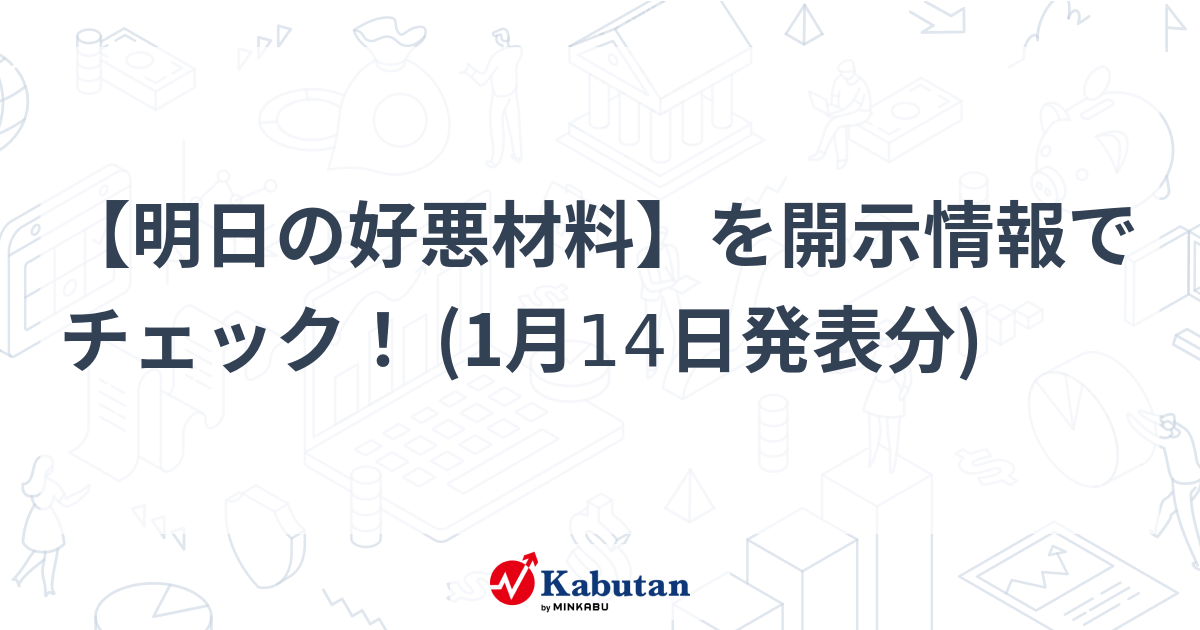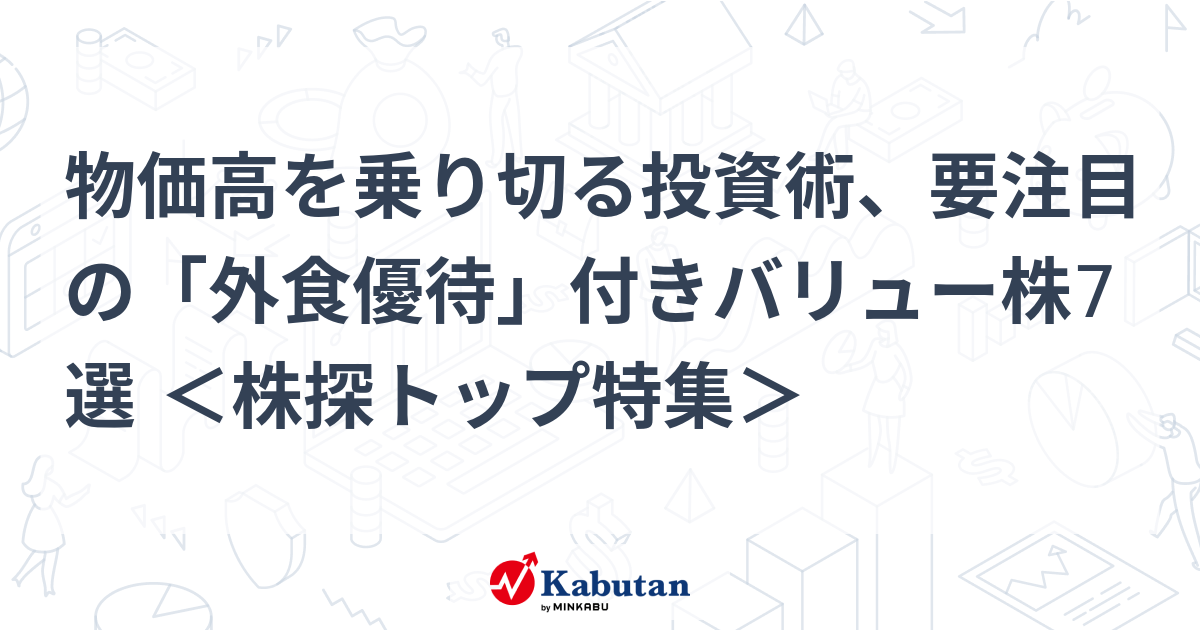【コラム】過熱する金相場、波に乗るには遅過ぎる-カイザー

ポッドキャストを聴くたびに金の宣伝が流れ、資産運用会社によれば顧客は金に夢中だ。友人からも購入の相談が相次ぐ。チャートを見なくても、金価格が急騰し「取り残される恐怖(FOMO)」が広がっていることは明らかだ。
実際のところ、金価格が1968年に自由に変動し始めてから、今年の金相場は最大級の上昇を見せている。予想通り、グーグル検索で「金の買い方」は過去最高の件数を記録。モーニングスターによると、米国の金関連投資信託および上場投資信託(ETF)への純流入額は9月末までに350億ドル(約5兆3500億円)を超え、9カ月間としては少なくとも2005年以降で最大となった。
では、投資家は金を保有すべきなのか。人気資産を売り込む好機を逃さないウォール街が、そう考え始めたのは間違いないだろう。米モルガン・スタンレーのマイク・ウィルソン氏は、従来の60対40の株式・債券ポートフォリオのうち、債券の半分を金に振り向け、60/20/20の株式・債券・金の構成に再編するよう提案している。
一見するとこれは有利なポートフォリオに映るかもしれない。だが、金を組み込んだポートフォリオがS&P500種株価指数と米国債・社債で構成される60/40ポートフォリオのパフォーマンスを上回った分は、1968年4月から今年9月までで年率0.7ポイントという計算になる。配当も込みだ。
しかし、細部に落とし穴がある。まず、金と債券は置き換え可能ではない。過去60年間、年率標準偏差で測ると金のボラティリティーは債券の3倍以上に上る。同期間の金の年間リターンは8.5%で、リスク(ボラティリティー)の高さを考慮しても債券を2.1ポイント上回った。つまり、債券を金に替えればリターンの向上は見込めるものの、変動はそれだけ激しくなる。
リスクの観点から見れば、金は債券よりも株式に近い。ただし、株式の方がパフォーマンスは優れている。1968年以降、金のボラティリティーはS&P500種より約20%高く、年間でパフォーマンスは2.3ポイント低い。従って60/40ポートフォリオに金を加えようとする投資家は、代わりに株式の比率を増やすことで、同等かそれ以上の成果を得られる可能性がある。
株式には金に対するもう一つの利点がある。それは、より安定したパフォーマンスだ。大半の投資家にとって60年という投資期間は現実的ではなく、短期的な動きの方が重要になる。ここで金の輝きは色あせる。
過去10年単位の移動平均では、株式と債券がほとんどの期間で金を上回ってきた。株式や債券と違い、金は長い停滞期を経験している。2007年の金価格は、ほぼ30年前の1980年と同水準だった。こうした停滞は、時として現在のような短期の急騰で流れが変わる。この点で、金は伝統的資産というよりデジタル資産の代替である仮想通貨ビットコインに近い。
もちろん、誰もが冷静な計算で金を買うわけではない。多くの金愛好家が動機とするのは恐怖心だ。株式より値動きの激しい金属が「安全な避難先」として広く信じられているという不思議な事実はさておき、過去の「恐怖による金買い」がどのような結果をもたらしたかは振り返る価値がある。
過去20年間で、金ファンドへの資金流入は、2008年の金融危機や2020年の新型コロナウイルス流行時などに急増した。いずれのケースでも、不安が和らぐと金の上昇は失速し、最近の上昇を考慮しても、株が最終的に金と同等かそれ以上のパフォーマンスを維持した。
今回の金高騰の背景には、多くの投資家が関税によるドル下落とインフレ上昇を懸念していることがある。しかし債券市場は、少なくとも現時点ではそうした懸念は共有していない。今年、米国債利回りは低下しており、インフレ期待は依然として米連邦準備制度理事会(FRB)の目標である2%前後にとどまっている。
現在の金上昇を支えている懸念はやがて沈静化し、上昇相場もそれとともに終息すると筆者は見ている。もっとも、金を買いたいなら止めはしない。ただし、大きな利益を期待すべきではない。そのチャンスは、この上昇が始まる前にあったのだ。
(ニール・カイザー氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。このコラムの内容は編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を必ずしも反映するものではありません)
原題:The Gold FOMO Trade Is Too Late: Nir Kaissar
(抜粋)