特集 - 株探ニュース
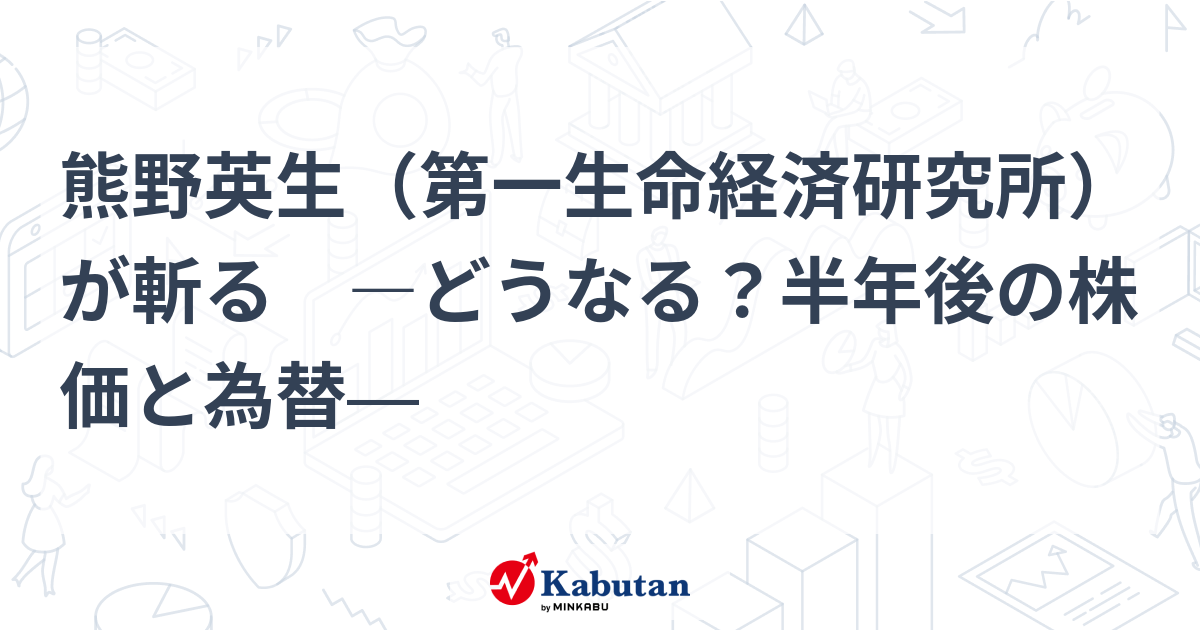
熊野:私は半年後の日経平均株価を3万8000円程度だと考えています。トランプ関税は、いずれ企業業績を悪化させ、まだ株価を3万円程度まで下落させる可能性があります。半年後のダウ工業株30種平均は4万3000ドル程度だと予測しています。実体経済の悪化が顕著になれば、半年間に底値が3万5000ドル程度になるまで下がることもあり得ます。
図1 NYダウ(週足)―― 日経平均株価は3万円程度まで下落する可能性があるとのことでしたが、トランプ政権の高関税政策の悪影響はいつまで続きそうですか。
熊野:4~6月期は世界の株式相場にダメージがあるでしょう。日本や欧州だけでなく、米国の自動車メーカーにも悪影響があります。フォード・モーター<F>やゼネラル・モーターズ<GM>など米自動車大手はメキシコから部品供給を受けているため、完成車の値上げを迫られ、現地生産車も北米に輸入すると販売価格の引き上げを余儀なくされるでしょう。
図2 日経平均株価(週足)―― トランプ氏は高関税によって自国メーカーや経済を守ると主張していますが、そもそも関税率を引き上げることで米国の自動車産業が復活するとは思えません。
熊野:経済学では、当面は国家が保護しなければ国際競争に耐えられない「幼稚産業」を保護するには高関税が有効とされます。一方で鉄鋼、自動車など成熟化した産業について関税で守っても衰退するばかりです。高関税に頼って衰退すると、4年後にも高関税を撤廃できなくなるリスクすらあります。
―― トランプ政権は関税政策以外にも懸念材料が多くあります。
熊野:大きな懸念の1つが雇用問題です。米政権が連邦政府の職員の大幅な削減を進めているからです。4~6月は非農業部門の雇用者数の前月比の増加数が大幅に鈍化するとみられます。これに加えて、関税政策が自動車業界などの業績に悪影響を及ぼせば、人員削減などのリストラにもつながります。移民政策が厳格化されているとはいえ、リストラされたホワイトカラーの人々が、国外追放した不法移民の仕事をするとは思えません。雇用のミスマッチがますます大きくなるでしょう。
―― 米国では物価の高騰も家計の生活を脅かしています。しかし、トランプ政権は、さらなる物価上昇につながる利下げを強く望んでいるとされます。
熊野:市場関係者の間では、FRB(米連邦準備理事会)はインフレが落ち着いた後に利下げをするとの見方が一般的です。しかし、私はむしろFRBのパウエル議長はまず利下げを2回ほど(合計で0.5%程度)実施し、物価動向を見極めるのではないかと思っています。景気が過度に悪化する前に「予防的利下げ」をする形です。―― そうなればインフレが加速するのではないでしょうか。
熊野:その通りです。米長期金利は上昇しています。これは物価上昇と景気停滞が同時に進む「スタグフレーション」の予兆に見えます。関税の引き上げは、輸入物価を押し上げます。そこでFRBが利下げすればインフレが後押しされ、FRBはどこかで利下げを停止せざるを得なくなります。スタグフレーションのリスクは高まると思います。
―― 為替レートはどのように推移するでしょうか。
熊野:円高が進んでいます。不気味なのは、米長期金利が上昇しても、ドル高(円安)になりにくくなっているところです。株売り・債券売り・ドル売りのトリプル安の圧力が水面下で働いて、ドル安・円高に向かっているのだと思います。
半年後のドル円レートは1ドル=135円程度まで行くリスクがあるかもしれません。FRBが利下げをして、ドル安圧力を強めることもあります。 図3 ドル円(週足)―― 市場関係者の間では、貿易赤字を問題視しているトランプ大統領が、米ドル安誘導を目的に「第二次プラザ合意」を目指すとの憶測が出ています。1985年のプラザ合意では米ドルは急激に切り下がり、円相場は急騰しました。第二次プラザ合意に現実味はありますか。
熊野:可能性はゼロではないと思います。もともと私は、トランプ大統領であってもそのようなことは絶対しないと思っていました。しかし、相手国の立場を無視した関税政策を見て、第二次プラザ合意もやりかねないと思うようになりました。
もっとも、仮に第二次プラザ合意をやろうとしても、具体的な手法は見当がつきません。日本もEU(欧州連合)も米国のドル安政策に決して協調しないでしょう。 それに、対抗措置として中国など多くの国々が自国通貨を切り下げ、通貨安競争になるリスクもあります。最悪の場合、過度な金融緩和によりマネーが溢れて世界的な悪性インフレが発生するでしょう。―― 予測では日米の株価は夏以降、持ち直すとのことだったかと思います。株価が反転上昇するきっかけは。
熊野:7~9月期からプラス要因としてFRBの利下げがあると見ています。この時期にはトランプ大統領も、翻意する可能性があります。米国では26年秋に中間選挙を控えており、トランプ政権も26年春までの景気浮揚ができなければ選挙に負けてしまうので、それがトランプ大統領を翻意させると私は考えています。今秋または年末くらいには現在の関税などの方針を修正または転換するのではないかと思います。法人税の引き下げや規制撤廃なども株価を押し上げるでしょう。
一方、米国株を支えてきた半導体大手のエヌビディア<NVDA>などのハイテク株、ビッグテックの立ち直りは容易ではありません。これまで株価が過度に上昇してきたことに加えて、中国の格安AI(人工知能)「DeepSeek(ディープシーク)」の登場が、米ハイテク株などへの楽観的な見方に冷水を浴びせたからです。このため、2月以前のような楽観的な見方には戻りにくいと思います。ハイテク株の影響力の大きいナスダック総合株価指数は、上値は抑えられるでしょう。日経平均株価は、ハイテク株中心につれ高となっていただけに、リバウンド力は限られると思います。
―― 注目するセクターを教えて下さい。
熊野:トランプ政権が関税率を引き上げても、したたかに業績を伸ばす日本の自動車や電機メーカーがあると考えています。現在は自動車や電機などの株価は軒並み下落していますが、米国に工場の多い企業には恩恵もあるでしょう。関税の価格転嫁も、競争力が強く、それができる企業の株価は急激に回復する可能性があります。こうした企業に注目します。自動車・電機以外のセクターにもこうした銘柄はあるかもしれません。
(※聞き手は日高広太郎)


