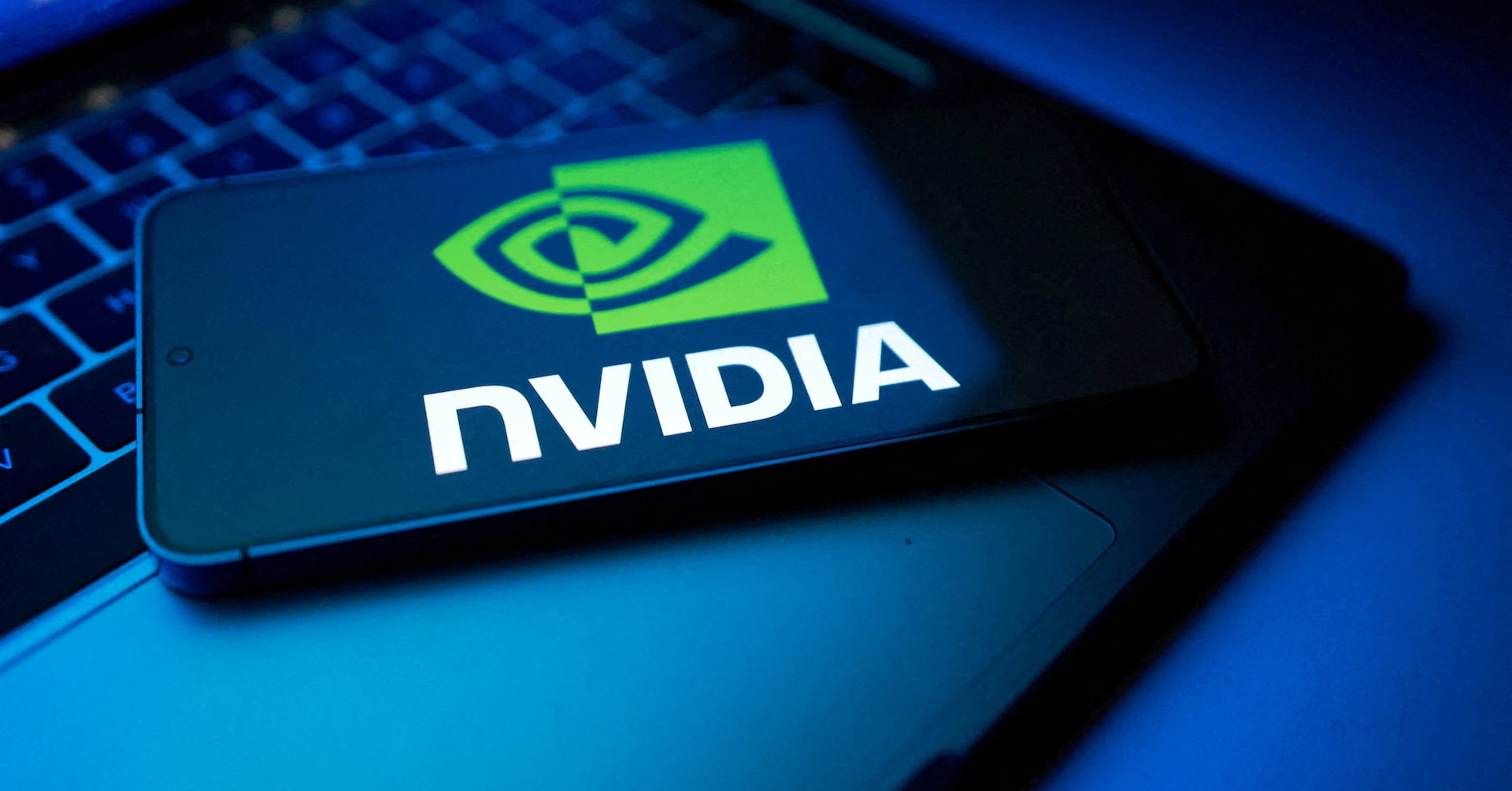「日本一の過密空港」で新滑走路の準備大詰め…2本に増えても、離着陸処理能力は2倍にならず

国土交通省が、福岡空港(福岡市博多区)で整備を進めてきた3月20日の2本目滑走路の供用開始まで1か月を切った。国交省は現在、滑走路に進行方向などを示す目印を描いたり、灯火を設置したりといった最終的な仕上げの工事を進めている。一方、狭い空港の敷地(約350ヘクタール)で2本の滑走路を運用することから、新たなリスクが生じるとの指摘もあり、航空機が滑走路に誤進入するなどの事故を防ぐため、管制官の訓練も行われている。(梅野健吾、中尾健)
福岡空港の2本目滑走路では、作業員が路面に線を描くための測量作業などを行っていた(17日夜、福岡市博多区で)=長野浩一撮影福岡空港の「門限」となっている午後10時を過ぎた今月17日深夜、国交省九州地方整備局博多港湾・空港整備事務所の案内で、2本目の滑走路エリアを取材した。現場では、滑走路に接続する誘導路の中心線を描くための測量作業などが少人数で行われていた。
多くの重機や作業員が行き交って土木工事などが行われていた昨年秋までの熱気は消え、代わりに整然と舗装された滑走路が存在感を放っていた。同事務所によると、滑走路や誘導路などに目印を描く作業は供用開始直前まで継続する。
3月2日には福岡市内のホテルで、国交省などが主催する供用を目前に控えた式典が開かれる。国交省が実施していた飛行検査はすでに終了したという。
2本目の滑走路(左)の供用開始が迫る福岡空港(13日、福岡市で、読売機から)=大金史典撮影福岡空港は、九州や中国地方西部の国際拠点空港としての役割を担うが、滑走路は1本(長さ2800メートル、幅60メートル)しかなく、「日本一の過密空港」と言われる。国交省は混雑緩和などを目的に、現滑走路の西側(国際線ターミナル側)に、2本目の滑走路(長さ2500メートル、幅60メートル)の整備を決め、2015年度に事業着手した。事業費は約1643億円。
福岡空港の増設滑走路一方、滑走路の間隔が210メートルしかなく、航空機が同時に離着陸することはできない。このため、滑走路処理能力は2倍になるわけではなく、「1時間あたり38回」から「同40回」への2回増にとどまる。国交省は、航空機の進入経路変更などで45回まで増やせるとしているが、新たに航空機が上空を飛ぶ自治体の理解を得る必要がある。
また、45回に増えたとしても抜本的な容量拡大にはならないため、地元経済界の一部には「24時間使える海上の新空港建設を目指すべきだ」との声もある。
2本目滑走路の供用開始に向け、航空機の誘導などを行う管制業務も、安全な運用に向けた取り組みが進められている。
国交省は2本目の整備に合わせて、国際線ターミナル側に国内2番目の高さとなる94・2メートルの新管制塔を建設し、昨年12月から業務を開始した。国内線ターミナル側にあった以前の管制塔は31・4メートルだったが、滑走路や誘導路の増設で見渡す範囲が広がることから、空港全体を見ることができる高さを確保した。業務にあたる管制官も7人程度から10人程度に増やした。
2本目滑走路は運用開始後、原則として国際線の離陸用に使用される予定で、離着陸時の航空機の動線も変わる。国交省によると、管制官は運用開始に備え、シミュレーターなどを使って新たな動線を想定した訓練も重ねている。
昨年1月には、羽田空港で民間機と海上保安庁の航空機が衝突する事故も起きており、滑走路への誤進入などは重大事故につながる可能性がある。国交省は「安全で円滑な管制業務の提供に努めていく」としている。
元主任航空管制官の田中 秀和(ひでたか) 氏は「福岡空港は1本の滑走路に集中していた離着陸が分散される点では安全につながるだろう。一方、新たなリスクとして、国際線の着陸機が新たな滑走路を横断しなければならないほか、操縦士が左右の滑走路を誤認する可能性なども考えられる」と指摘する。
そのうえで、「他空港での経験を生かし、想定される危険因子を事前に抽出して航空会社との情報共有や対策の徹底を図ることが重要だ。国際線が多い福岡空港では毎日往来していない路線もあるので、全ての操縦士に対策を浸透させることも大事だ」と話している。