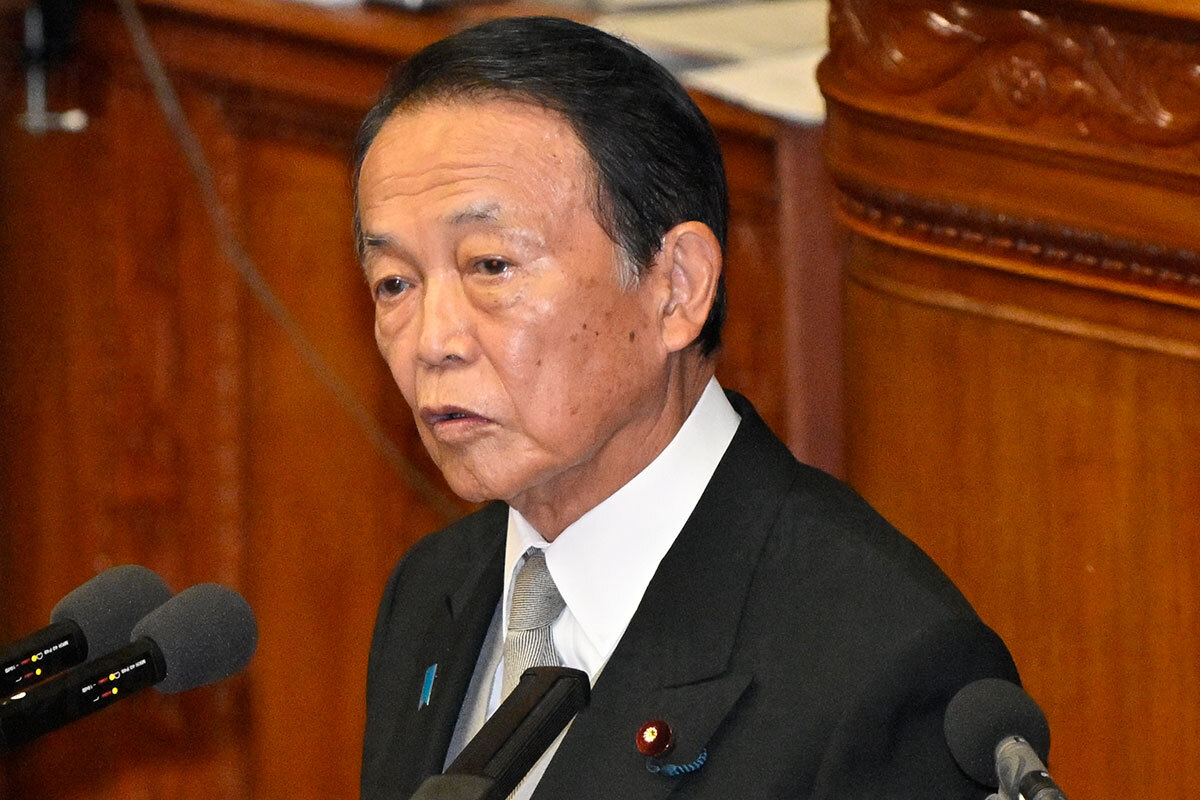飛び石型連休のGW、学校休んで旅行はNG? 教育現場の受け止めは

2025年のゴールデンウイーク(GW)は日の並びが悪く、飛び石型の連休だ。「学校を休ませて家族旅行に行こうか……」。そう考える人も多そうだが、一方で後ろめたさも残る。度々起きる「家族旅行と学校欠席」の議論。教育現場はどう受け止めているのだろうか?
親の責任放棄?
その是非を巡っては、X(ツイッター)などネット上でさまざまな意見が交わされている。
<土日祝日に休めない親もいるし、何の問題もない>
<有給休暇が推奨される時代。子供に休暇があってもいい>
理解を示す声がある一方で、否定的な意見も。
<遊びで学校を休ませるのはどうか>
<先生や他の子どもに迷惑がかかるのでは>
特に、義務教育課程にある小中学生の場合は<教育を受けさせるという親の義務や責任を果たせていない>といった厳しい声も見られる。
Advertisement学校教育法などで「休み」は、欠席(病気や自己都合などが理由)▽出席停止(指定感染症などが理由)▽忌引(身内の不幸などが理由)――の三つに大別されている。「出席停止」「忌引」は欠席日数に算入されないが、通常の「欠席」は病気やけがによる「病欠」と、家庭の都合など体調不良以外の「事故欠」に分けられるのが一般的だ。ただ「欠席」の種類を区別しない学校や自治体もある。
教育現場の受け止め方は?
旅行など家庭の都合で欠席した場合、現場ではどう受け止められているのか。
東京都目黒区教育委員会の担当者は、保護者の仕事などによっては平日しか休めないなど、さまざまな事情があるため「家庭の申し出を学校側が受け入れないことはない」とし、基本的には保護者の意向に委ねているとする。
目黒区教委では、病気も家庭の都合による休みも一律に「欠席」として扱い、欠席連絡がないなど子供の状況や所在が心配な場合を除けば「教員が休んだ理由を深く詮索することはない」という。また、欠席によって生じる学習の遅れについては「子供たちも休んだ日のことは気にするので、申し出があれば、教員や友人と情報を共有し、学びが途切れないようにできる限りのフォローをしていく」とする。事前に休むタイミングがわかれば、教員もフォローしやすくなるそうだ。
受験ではどうなるのか? 都教委によると、都立の高校や中高一貫校を受験する場合、出願時に必要になる調査書に「欠席日数」の記入は不要になった。ただ、私立の場合は独自の様式もあり、記載を求められることもあるという。
「皆勤」以外にも見いだされる価値
公立の小中学校で14年間教員経験のある愛知東邦大の白井克尚准教授(社会科教育)は、議論が起こる背景について「休むことの価値観が社会の中で変わってきている」ためだと指摘。「皆勤賞」が廃止される動きに触れながら「学校を休ませないのは大切だが、休む間の経験も重要。『全部出席することが良い』という考えだけではなくなってきている」と話す。
そんな中で、平日に旅行などで学校を休んでも欠席扱いしない「ラーケーション」と呼ばれる制度を取り入れる自治体も増えている。「ラーニング(学習)」と「バケーション(休暇)」を掛け合わせた造語で、子供が平日に休み、地域や家庭で体験学習などをすることで学びを深めるのが狙いだ。
先駆けとなった愛知県は、公立の小中高校生らを対象に23年から導入した。活動内容の計画を立てて事前に申し出れば、忌引などと同様、欠席扱いしない。年に3日間まで取得でき、受けられなかった授業は各家庭で自習する。
県が制度開始から約半年後の24年3月に取りまとめた調査では、子供の約17%が取得しており、進路に影響が少ない小学校低学年ほど取得率が高い傾向があった。
このほか大分県別府市や沖縄県座間味村、茨城県や熊本県なども同様の制度を導入している。別府市は申請が前日でも可能で、市民に好評だったため、取得日数の上限を23年9月の開始当初から2日間増やし、25年度は年間5日間まで拡充した。ちなみに、隣の韓国では小中高校生を対象に、国の法律施行令などでラーケーションを「校外体験学習」として制度化しており、家族との海外旅行も認められている。
「格差」助長の懸念も
白井准教授は、ラーケーションは保護者が平日に有給休暇を取得する「働き方改革」や地域経済の活性化にも貢献できるほか「休むことの価値や可能性を広げる」と評価する。
一方、休んだ子供の給食停止の手続きや個別連絡など教員の負担が増えたり、社会の維持に不可欠なエッセンシャルワーカーなど保護者の職種によっては制度を利用しづらかったりするなどの課題も少なくないという。
愛知県の自治体では、名古屋市のみが導入を見送った経緯がある。「『休み方改革』の趣旨は理解している」としつつも「家庭の事情で取得できる子とそうでない子の間で不公平が生じる」として「格差」助長への懸念が大きな理由だったという。
名古屋市教委によると、保護者から旅行や外出などで休む申し出があった場合は、従来通り「家事都合」による欠席扱いとするが「休んだ理由によって、子供をとがめるようなことはない」という。
ただ、学習の遅れへの対応については「できる範囲で配慮はするものの、他の子と同じ対応は難しい面もあり、理解をいただいている」と説明する。
自習では補えない友達同士で進める授業や学校行事がある日に欠席するかどうかは、家庭で総合的に判断する必要がありそうだ。
議論にどう向き合うか?
今のところ地域や職種によって温度差や賛否もあるラーケーションが全国的に広がるかは不透明だ。「家族旅行を理由に学校を休んでもいいのか?」。この議論に、どう向き合えばいいのだろうか。
白井准教授は「学外の『学び』のあり方も多様であると捉えることが重要だ」と指摘する。旅行や外出だけでなく、子供によっては家で手伝いをすることや、家族と交流することも学びの体験になり得るし、休息し何もしないことが「学び」を続けるための切り替えになる子供もいる――。子供によって「学び」の形はさまざまであると考えることで、罪悪感を感じなくなるともいう。
「学外でなければ得られないような有意義な学びができるどうかを判断の基準にするのも一つの手ではないでしょうか」【稲垣衆史】