秋元康でもつんく♂でも島田紳助でもない…テレビで最初にアイドルプロデュースを大成功させた意外な人物 「曲のヒット→高視聴率番組」という方程式を作った
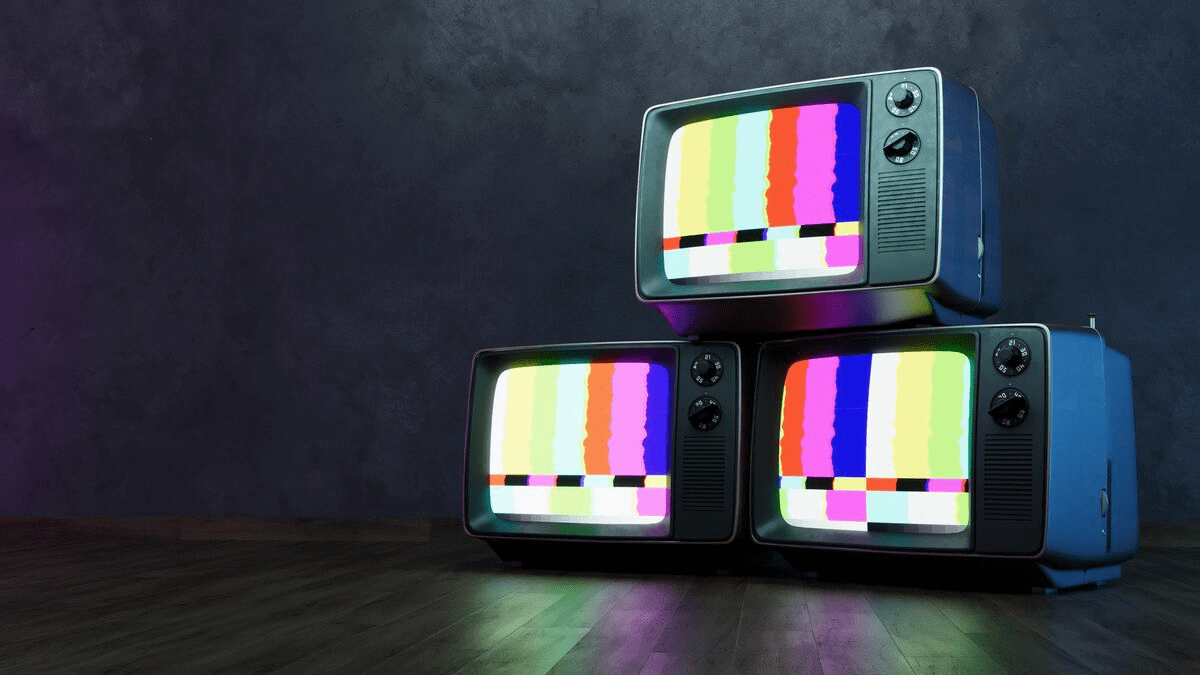
コメディアンの萩本欽一さんはどこがすごいのか。社会学者の太田省一さんは「アイドルプロデューサーとしての側面は見逃せない。番組の出演者が出すレコードを単なる企画ものに終わらせず、レコードの売り上げも視聴率も獲得した手腕は評価されるべきだろう」という――。(第2回)
※本稿は、太田省一『萩本欽一 昭和をつくった男』(ちくま新書)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/Mustapha GUNNOUNI
※写真はイメージです
ミュージシャンでも作詞家でもないのに成功したワケ
「アイドルプロデューサー」と聞いて、誰を思い浮かべるだろうか。モーニング娘。をプロデュースしたつんく♂、あるいはAKB48や乃木坂46をプロデュースした秋元康。そのあたりの名前を答えるひとがきっと多いに違いない。だがつんく♂や秋元康よりもいち早く、アイドルプロデューサーとして大成功を収めたのが、ほかならぬ萩本欽一だった。
ではミュージシャンでも作詞家でもなかった萩本が、なぜアイドルプロデューサーとして成功できたのか。アイドルプロデューサーの先駆けとなったのが、作詞家で『スター誕生!』の審査員でもあった阿久悠である。
代表的なのは、爆発的ブームを巻き起こしたピンク・レディー。「非日常性のエンターテインメント」「歌のアニメーション化」というトータルコンセプトを考え、プロ野球の女性投手を主人公にした「サウスポー」や宇宙人との恋愛を歌った「UFO」などファンタジー色の濃い歌詞と大胆な振り付けで、従来にない斬新な曲を歌い踊らせた(阿久悠『夢を食った男たち』208頁)。
その阿久は、『スター誕生!』の審査にあたり、「できるだけ下手を選びましょう」と他の審査員に提案した。歌の技術の巧拙ではなく、「未熟でも、何か感じるところのあるひと」を選ぼうとしたのである(同書、43頁)。
こうして「アイドル」が誕生した
それは、歌の上手さが歌手にとって絶対的な基準だった当時にあっては、画期的な考えかただった。テレビ時代が到来するなか、未熟であるがゆえに醸し出される親近感が歌手になるための新たな条件になる。
そして『スター誕生!』出身のそうした若い歌手たちは、桜田淳子や山口百恵をはじめとして「アイドル」と呼ばれるようになる。素人ならではの魅力を持つ人材の発掘は、繰り返すまでもなく萩本が最も得意とするところである。
しかもコメディアンである萩本欽一には、自分のバラエティ番組を企画して出演もするという、ほかにはない強みがあった。番組の設定を考え、直接素人の魅力や個性を引き出すことができる。
そしてそこで練り上げられたイメージを活用して、出演者を歌手デビューさせる。後年、島田紳助が『クイズ!ヘキサゴンII』から羞恥心やPaboをデビューさせたのも、まったく同じ手法だ。そのパイオニアこそが、萩本欽一だった。
Page 2
3人のパフォーマンスでは、いまで言うエアバンドの要素が盛り込まれていた。実際に楽器を弾かず、曲に合わせて弾いているような振りをする。
イントロのメロディに合わせて、山口良一と西山浩司が向かい合わせになってそれぞれキーボードとドラムを演奏しているまねをする。その途中に打楽器の音が入る。すると山口は西山の頰をビンタする振りをする。それに合わせた西山のビンタされたリアクションも絶妙だったのだが、これはレコーディングの際、山口と西山が手持無沙汰なのにまかせて遊びでやっていたのがそのまま採用されたものだった(『昭和40年男』35頁)。
こうして、お茶の間向けバラエティと最先端のテクノサウンドを融合させた、それまでのテレビから流れる歌謡曲とは一線を画す曲とパフォーマンスが生まれた。
番組人気との相乗効果もあり、曲は大ヒット。オリコン週間シングルチャート7週連続1位、累計売上160万枚を記録。音楽ランキング番組『ザ・ベストテン』では8週連続1位に。いずれも驚異的記録である。イモ欽トリオの3人は瞬く間にトップアイドルに躍り出た。
なぜソロではなく3人組だったのか
ここに萩本欽一は、どうかかわったのだろうか。むろん、出演時の3人のキャラクターがベースなので、番組の企画者である萩本の承諾なしに歌手デビューは実現しない。
最初レコード会社からのオファーは、長江健次のソロデビューという話だった。当時長江は17歳になったばかり。コントの際、セットの居間から出ていくときに発する「な!」というセリフがウケていた(「ハイスクールララバイ」もセリフ入りで、この「な!」が使われている)。
見た目も童顔で可愛らしく、一番アイドル的な人気があった。だが萩本は首を縦に振らなかった。「一人はまずい。やるなら三人だね」と返答した(同誌、32~33頁)。
ここにも“番組優先主義”の考えかたが表れている。個人の人気という点では長江が突出していたかもしれないが、ソロデビューになってしまえば3人のバランスが崩れる。それはひいては、コント、そして番組全体のバランスの崩壊につながる。
そうした折、別のレコード会社から新たにオファーがあった。フォーライフレコードからである。今度は「三人で」という話だった。それでも最初は断っていたのだが、あまりに熱心だったので根負けした(同誌、33頁)。



