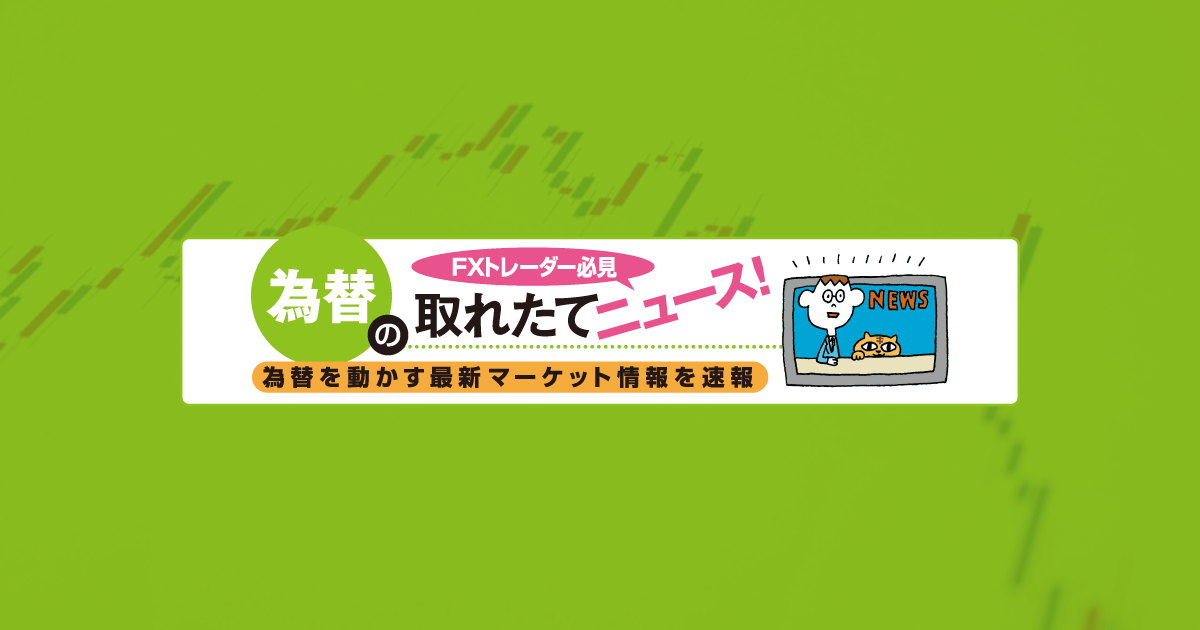コラム:マウントを取りたがる人とどう付き合うか、トランプ関税対策を考える=熊野英生氏

[東京 21日] - あなたの周辺には、何事につけても自分の優位性を誇示して、自分本位に仕事をするような人はいないだろうか。近頃は、こうした行動を「マウントを取る」という言葉で表現するようだ。
困ったことに、トランプ米大統領は各国に対してマウントを取ろうとしている。それも、同盟国・非同盟国を問わずマウントを取ろうとし、世界は混乱のるつぼに放り込まれたような状態に陥っている。さて、日本はこの4年間をどうやり過ごせばよいのだろうか。
会社員なら次の人事異動まで待つことが一般的だろう。だが振り返ると、トランプ1期目に設けられた中国向けの追加関税は撤廃されなかった。バイデン前政権は、弱腰とみられるのを嫌って自由貿易の世界に戻せなかったのだ。トランプ現政権の後も、トランプ関税と同じような措置を強いられないためには、貿易取引のインセンティブ構造を見直すことが肝要である。
目下、トランプ関税に対して潜在的不満を抱いている国々は数多くある。それらの国々と日本は、自由貿易のアライアンスを組むことが得策であろう。例えば、欧州連合(EU)や韓国との間で「環太平洋連携協定(TPP)」参加を呼びかける。トランプ政権からの妨害はあるかもしれないが、自由貿易を脅かす米国の対応にカウンターパワーを徐々に作って、自由貿易の枠組みから米国が孤立することへの不利益を感じさせていくのはどうか。
<孤立主義のデメリットを意識させる>
トランプ氏の狙いは、トランプ関税をかけることを脅しに使って、1対1で交渉しつつ有利な取引条件を相手から引き出すことにある。日本からは1兆ドルの対米直接投資を約束させた。コロンビアは、不法に米国に入国する者の送還を受け入れさせられた。デンマークは、グリーンランドの所有権を放棄しなければ、米国への輸入品に高関税をかけると脅された。今やトランプ政権は、関税政策を武器化して、自国への利益誘導を追求する迷惑な存在と化してしまっている。米国に輸出する相手国は、輸出を「人質」に取られているのだ。
ひとつの作戦は、「人質」の価値を低下させるために、米国向け輸出を減らし、それを肩代わりする輸出先を別に探すことだ。東南アジア諸国連合(ASEAN)や韓国などは米国以外に、中国向けの輸出が多い。日本もそうである。トランプリスクに対して、アジア諸国は複数の国々が連携して中国への輸出シフトを促す流れをつくるだろう。だが今のところ中国の景気は悪く、十分な受け皿になれそうもない。中国自身もトランプ関税による打撃を受けて、米国以外への輸出シフトを願っているはずだ。
少し時間はかかるだろうが、中国がアジア諸国との貿易連携を主導していく可能性はある。もしもそうなれば、トランプ政権は慌てて、孤立リスクを感じるのではないか。そうなると、関税政策を武器化することのデメリットをトランプ政権は意識していく。アジアの貿易アライアンスに、日本がどうコミットしていくかは今後の課題となる。
<マウント攻撃への返し技>
トランプ氏の手法は、優越的地位を乱用して、自国への利益誘導を図ろうとするものだ。それに対処する上手な「返し技」を身につけることが、迷惑行為をかわすために求められてくる。
2月7日の日米首脳会談ではその一例を見ることができた。それは、日米間でウィン・ウィンの関係をつくることだ。対米投資の拡大は、米国経済にも日本企業にもメリットがある。将来的に米国に進出した日本企業が低い法人税の適用を受けられるという好条件を引き出せれば、本当にウィン・ウィンの関係が得られるだろう。
オーストラリアのターンブル元首相は、トランプ氏と付き合う方法として、米国にメリットがある対案を主張すると、トランプ氏はそれに乗ってくると述べていた。トランプ氏はビジネスマンなので、利があるとわかると前言をひっくり返してでも合意しようとするらしい。有効な返し技とは、「これをすれば米国にも利益がありますよ」と対案を出すことだ。トランプ氏の良い点は、前に発言した内容にこだわらず、良い結果を導ければそれで良いと考えるところだ。この点は日本の政治家も学んでよいと思う。
<為替政策も課題に>
トランプ関税から逃げる方法はいくつかある。10%の関税をかけられたならば、通貨を10%切り下げれば痛みをいくらか緩和できる。仮に、トランプ関税をかけられたとき、10%の報復関税を米国にかけ返して、さらに通貨を10%切り下げると、米国の輸出価格は1.21倍に跳ね上がる。それが対抗措置の効果を上げる。
それを防止するためにベッセント財務長官は、為替操作や非関税障壁も考慮しながら相互関税を検討すると述べている。日本がいま為替介入を行ったとしてもその目的は円安防止になるので、通貨安誘導には該当しない。それでも、日本の低金利が円安を促していることが問題視される可能性はある。そう考えると、今後、日本が為替介入を使いにくくなる分、日銀はもっと積極的に金利正常化に向けて利上げを進めることになるだろう。
各種のトランプ政策は、いずれドル高を招くと筆者はみている。日本に対しては、さらなる円安圧力となっていくだろうから、日銀の利上げの到達点は多くの人が考えているよりも高い水準になるだろう。
<自由貿易体制の見直し>
トランプ氏の関税政策に各国ともノーを言えない状況は、過去、国際連盟が第二次世界大戦を止められなかったことに似ている。すでに世界貿易機関(WTO)がトランプ氏の暴走に歯止めをかけられていないことからも、国際協調の枠組みが弱すぎることを感じさせる。もっと自由貿易のルール違反に対して、強いペナルティーを課すことのできる自由貿易のための同盟を築かなくては再発防止はできないだろう。トランプ大統領の在任期間中は、そうした新しい枠組みについて議論することは難しい。
本来、バイデン前政権が第1次トランプ政権の後に、重大なルール違反を取り締まるための仕組みづくりを始めておくべきだったと筆者は考える。バイデン氏は経済安全保障を軸にして、中国を封じ込める政策に重点を置き、広範な秩序づくりまで考えが及ばなかった。米国任せの考え方に限界があったことも原因だろう。
編集:宗えりか
(本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています)
*熊野英生氏は、第一生命経済研究所の首席エコノミスト。1990年日本銀行入行。調査統計局、情報サービス局を経て、2000年7月退職。同年8月に第一生命経済研究所に入社。2011年4月より現職。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab