マイクロプラスチックをめぐる最新の研究:2025年10月に最も読まれた10本のストーリー
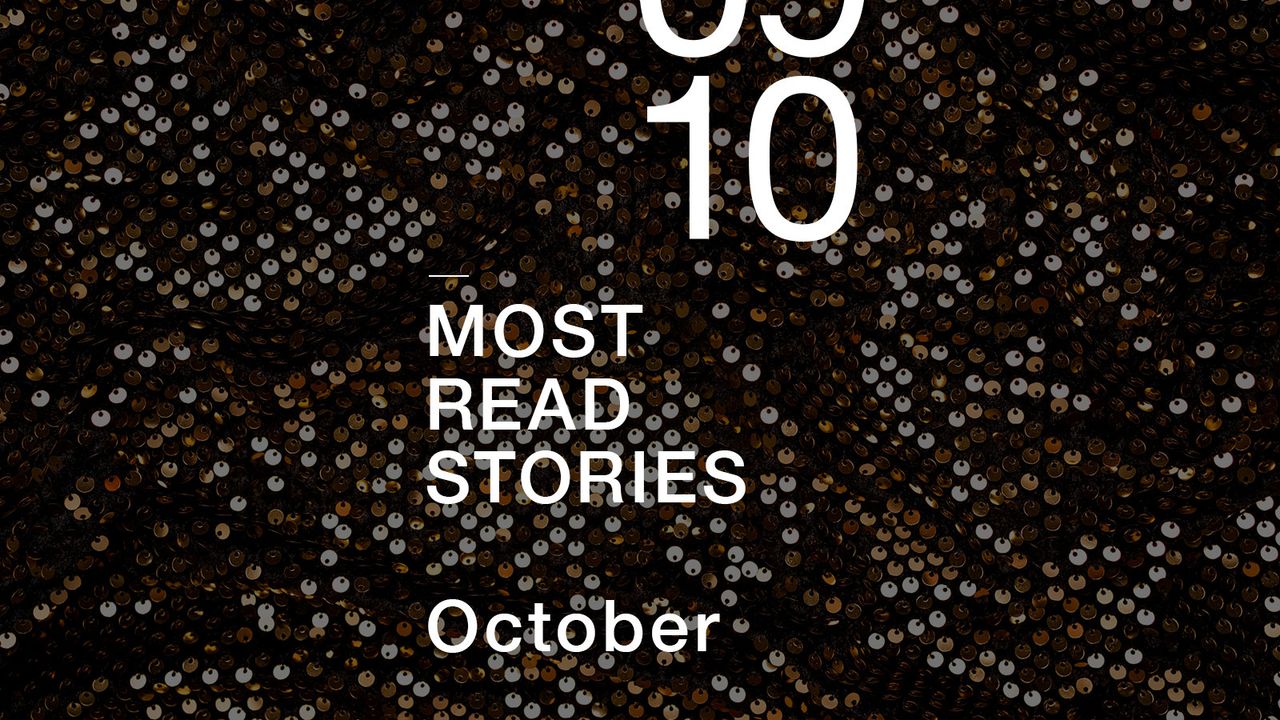
この10月は、ペットボトルの飲料水から人々が日常的に摂取しているマイクロプラスチックに関する記事がよく読まれた。飲料水を通じて人体に直接入り込んだプラスチック粒子は、臓器やホルモン系へ悪影響を及ぼしかねないほか、がんとの関連性が指摘されている。一方で、検査体制や測定手法の確立は進まず、長期的な影響は謎に包まれたままであり、ペットボトルを規制する法整備の遅れも問題視されている。課題は山積しているが、環境へのインパクトだけでなく、公衆衛生や人権の視点でも、ペットボトル依存からの脱却を社会全体で考えるべき時期に差しかかっているのではないだろうか。
関連記事:ペットボトルの水を日常的に飲む人は、マイクロプラスチックを年間90,000個も多く摂取している
このほか、アーティスト米津玄師へのインタビュー記事への関心も高かった。インタビューで米津は、子どものころから社会性の欠如を自覚していたからこそ、逆説的に社会性を強く求めてきたという自身の創作姿勢について語っている。さらに宇多田ヒカルとのコラボレーション曲を軸に、そこで感じた共通性や対照性に触れながら、自身の内側にある「わからなさ」と理性を衝突させることで生まれる“火花”こそが、音楽のセンスであるという哲学も明かした。
関連記事:米津玄師が語る、自己と他者が散らす“新たな火花”が生み出すもの
ここからは、10月にWIRED.jpで公開した記事を中心に、最も読まれた10本を紹介する。
01. ペットボトルの水を日常的に飲む人は、マイクロプラスチックを年間90,000個も多く摂取している
ペットボトルに入った飲料水には、目に見えないほど小さなプラスチック粒子が無数に含まれている。最新の研究によると、日常的にペットボトルから水を飲む人は、水筒などを利用する人よりも年間90,000個も多くのマイクロプラスチックを摂取しているという。>>記事全文を読む
02. モアイ像が“歩いて”移動したことを、研究者たちがついに証明した
イースター島に点在する巨大なモアイ像は、どのようにして運ばれたのか──。1世紀以上にわたる謎が、ついに解き明かされた。モアイ像が“歩いて”移動したという説が、どうやら正しかったようなのだ。>>記事全文を読む
03. ニューヨークで発見の「SIMファーム」、市内の通信網停止も可能な規模だった:米当局
米シークレットサービスは、約300台のサーバーと10万枚のSIMカードを備えた大規模「SIMファーム」のネットワークを発見し、解体したと発表した。専門家は、通常はサイバー犯罪に使われる施設だと指摘する。>>記事全文を読む
04. 史上3番目の恒星間天体「3I/ATLAS」が大量の水を放出:研究結果
NASAの宇宙望遠鏡の観測により、彗星型の恒星間天体「3I/ATLAS」が太陽から遠く離れた場所で「全開の消火栓」並みの水を放出していることが明らかになった。>>記事全文を読む
05. 地球誕生から46億年、ついに太陽が世界のエネルギーを賄うときが来た
この2年、ほぼ誰も気づかないうちに、太陽光発電は世界のエネルギーシステムを根底から覆し始めている。>>記事全文を読む
06. 結局、サトシ・ナカモトは誰なのか──“謎”の核心に最も近づいた男ベンジャミン・ウォレスが語る
「名前は知っているけれど、どんな功績があるのか実は知らない」「ポツポツ知ってはいるけれど、体系的には理解していない」……。サトシ・ナカモトに対する解像度は、おそらく多くの人がそんなところだろう。そのギャップを埋めてくれる書籍『サトシ・ナカモトはだれだ?: 世界を変えたビットコイン発明者の正体に迫る』が発売された。著者ベンジャミン・ウォレスが、本書執筆の経緯を語る。>>記事全文を読む
Page 2
恒星間天体「3I/ATLAS」は、驚きに満ちた天体であり続けている。これまでに観測された恒星間天体としては3つ目となるこの彗星が、水の存在を示すヒドロキシルラジカル(OH)の発光を起こしていることが、新たな分析によって明らかになった。この発見は、アラバマ州オーバーン大学の研究チームによってNASAの「ニール・ゲーレルス・スウィフト天文台」を用いて行なわれたもので、その成果は学術誌『The Astrophysical Journal Letters』に掲載された。
OHは紫外線に特徴的な発光を示すため検出が可能だ。しかし地球上では、多くの紫外線波長が大気によって遮断されてしまう。そのため、研究者たちは地上の干渉を受けない宇宙望遠鏡であるニール・ゲーレルス・スウィフト天文台を使用する必要があった。
水は太陽系内で観測されるほぼすべての彗星に存在しており、水の化学的そして物理的反応は、彗星を測定、分類、追跡し、太陽熱への反応を理解するための基準として利用されている。3I/ATLASで水の存在が確認されたことは、通常の彗星と同じ尺度でその特性を研究できるという意味をもつ。さらに、この情報は将来的に、ほかの恒星系から来た彗星の形成過程を研究するうえで有用なデータとなる可能性がある。
「恒星間彗星から水、あるいはそのかすかな紫外線の痕跡であるOHを検出するということは、別の惑星系からのメッセージを読んでいるようなものです」と、研究に携わったオーバーン大学の物理学者デニス・ボーデウィッツは声明のなかで述べている。「それは、生命の化学に必要な要素がわたしたちの惑星系に特有のものではないことを教えてくれるのです」
彗星とは、岩石、ガス、塵が凍結した塊であり、通常は恒星の周囲を公転している(これまで発見された3つの恒星間天体は例外である)。恒星から遠く離れているとき、彗星は完全に凍結しているが、恒星に近づくと太陽放射によって内部の氷成分が加熱され、固体から気体への変化である「昇華」を起こす。このとき、恒星のエネルギーによって彗星の核から一部の物質が放出され、「尾」が形成される。
しかし3I/ATLASの場合、収集されたデータは予想外の事実を示していた。すでに太陽から地球の3倍以上離れた地点──通常であれば氷が容易に昇華するほどの温度にはならない太陽系の領域──において、すでに彗星がOHを生成していたのだ。この距離で3I/ATLASは毎秒約40kgの水を放出しており、研究チームによるとその流量は「全開の消火栓」に匹敵するという。
この発見は、太陽系内の彗星で通常観測されるものよりも、はるかに複雑な構造をもつことを示唆している。例えば、彗星の核から小さな氷の断片が剥離し、それらが太陽光の熱によって蒸発し、彗星の周囲にガスの雲を形成している可能性が考えられる。このような現象は、これまでにごく少数の極めて遠方の彗星でしか観測されておらず、3I/ATLASの起源に関する重要な手がかりを提供するかもしれない。
「これまで観測された恒星間彗星は、どれも驚きの連続でした」と、この発見の共著者でオーバーン大学の研究者であるズーシー・シン(邢澤曦)は声明で述べている。「『オウムアムア』は乾燥しており、『ボリソフ』は一酸化炭素を豊富に含んでいました。そして今度は『アトラス』が、予想外の距離で水を放出しているのです。どの発見も、わたしたちがこれまで考えてきた惑星や彗星の形成理論を書き換えるものになっています」
(Originally published on WIRED Italia, translated by Eimi Yamamitsu, edited by Mamiko Nakano)



