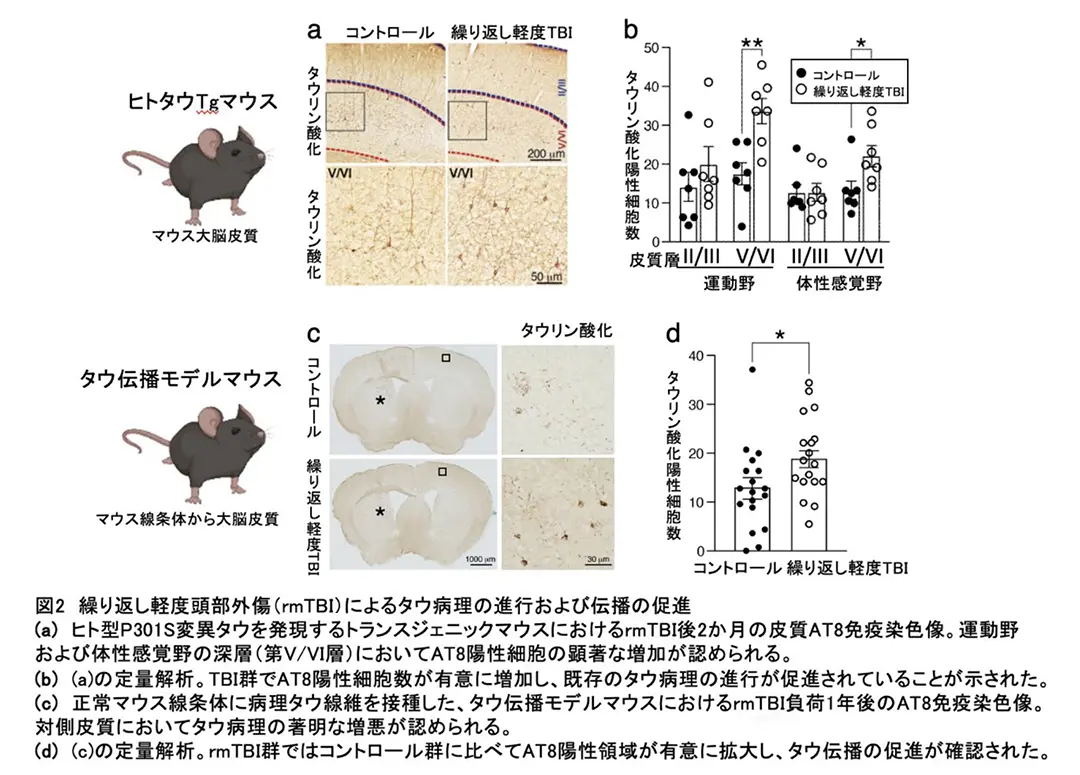認知症予防のカギはポリフェノールを多く含む食べ物を。第一人者のおすすめは「コーヒー」「シークヮーサー」「みかん・柚子」

人生100年時代とも言われ、認知症予防は本人のみならず家族にとっても最大の関心事。認知症研究者の第一人者・杉本八郎さんは、「認知症は生活習慣病の一つ」だからこそ、「認知症にならないような生活習慣を身につけることが大事」だとする。
著書『82歳の認知症研究の第一人者が毎日していること』(扶桑社新書)から、認知症予防につながる食べ物について複数あるうちの3つを、一部抜粋・再編集して紹介する。
活性酸素が老化などの原因に
認知症予防には主にどういう作用のある物質が効くのかについてお話ししておきましょう。
私たちの体内では、「活性酸素」が常に発生しています。
「活性酸素」は呼吸で取り込まれた酸素の一部が化学反応を起こすことで生まれる強い酸化力をもつ物質で、細菌から体を守るなど重要な役割を担う一方、増えすぎると細胞に強いダメージを与えます。
それが老化の原因となるのみならず、血管が傷つくことによる動脈硬化やそれを原因とする脳梗塞や心筋梗塞、さらには内臓疾患やがんなど、ありとあらゆる病気を引き起こしてしまうのです。
もちろん私たちの体にも、細胞を酸化ストレスから守る「抗酸化システム」は備わっているのですが、活性酸素があまりにも増えすぎてしまったり、加齢などによって抗酸化酵素の産生が少なくなったりすると、その処理が追いつかなくなってしまいます。
それを助けてくれるのが抗酸化作用を持つ物質です。
抗酸化作用で「老化」が抑制
体の外から取った抗酸化作用が高い物質の力を借りれば、増えすぎた活性酸素を無毒化することができるので、老化が抑制され、健康な血管を維持することもできます。
そうして生活習慣病を予防すれば、認知症を遠ざけることができるでしょう。
また、脳に十分な血液が送れるよう血行を良くするには、末梢の血管を広げたり、血管の弾力性を高める作用のある物質や、血中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)値を下げたり血液の凝固を抑えたりする、いわゆる「血液サラサラ作用」のある物質も欠かせません。
また、アミロイドβやタウタンパク質、α-シヌクレインの凝集を抑制するという素晴らしい作用のある物質もあります。
そのような物質はアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症を予防するための強い味方になってくれるでしょう。
注目はポリフェノール
認知症予防に効く物質として注目しておきたいのは、ポリフェノールです。
ポリフェノールとは、多くの植物が持つ、紫外線や害虫、有害微生物などのストレスから身を守るための「抗酸化物質」の総称で、高い「抗酸化作用」のみならず、その多くにはアミロイドβの凝集抑制作用があることも確認されています。
つまり、ポリフェノールは、「抗酸化作用」と「アミロイドβ凝集抑制作用」という認知症を予防するための2つの重要な働きを併せ持つ、極めて優れた物質なのです。
一口にポリフェノールと言っても、自然界には5000種以上ものポリフェノールが存在します。
そして私たちの身近にある食品にも良質なポリフェノールを含むものがたくさんあり、どれも優れた抗酸化作用をもつので、日々の食事に積極的に取り入れていくといいでしょう。
なお、「ポリフェノールの抗酸化作用によってアミロイドβの凝集が抑えられる」と書かれた記事が散見されますが、厳密に言うとそうではありません。
抗酸化作用によって血管が丈夫になり、脳の血行が良くなれば、脳の活性は上がります。
それによってアミロイドβの排出が促進される効果が期待できるのは確かですが、アミロイドβの凝集抑制効果というのはそれとはまったく別の作用です。
抗酸化作用はあくまでも活性酸素を除去する作用のことであり、アミロイドβの凝集抑制作用ではないことは覚えておいてください。
おすすめの食品:コーヒー
実は赤ワインに負けないくらいポリフェノールの含有量が多いのがコーヒーです。
コーヒーの苦味や褐色、香りのもとになっているのは「クロロゲン酸」で、「コーヒーポリフェノール」ともいわれるこのポリフェノールは体の中でその大半がフェルラ酸に代謝されます。
つまり、フェルラ酸の作用は、コーヒーを飲むことでも期待できるというわけです。
コーヒーの特徴的な成分であるカフェインにも高い抗酸化作用があり、2015年に発表された国立がん研究センターや東京大などの研究チームによる報告によると、「コーヒーを一日3〜4杯飲む」人が狭心症や心筋梗塞などの心臓病で死亡する危険性は、「ほとんど飲まない」人に比べて36%低く、脳内出血や脳梗塞などの脳血管病で死亡する危険性は43%低いことがわかったそうです。
これは、クロロゲン酸やカフェインの両方がもつ高い抗酸化作用や抗炎症作用の相乗効果によるものではないかと考えられています。
健康的な血管を維持することに役立つことは間違いないので、それが認知症予防にもつながる可能性は高いと言っていいでしょう。
1日3杯以上飲むと…
それを示唆するのが、新潟大学大学院の中村和利教授らの研究グループが新潟県村上市、関川村、粟島浦村に住む40〜74歳の人たち1万3757人を対象に行った疫学研究の結果です。
コーヒーを一日3杯以上飲むグループの認知症の発症リスクは、まったく飲まないグループの約半分だったことがわかったのです。
カフェインには記憶力を高める働きがあることもアメリカのジョンズホプキンス大学の研究結果などから、近年明らかになっているので、じゃあもっとコーヒーを飲まなくてはという気になるかもしれませんが、問題はカフェインを取りすぎると別の弊害が起きることです。
日本ではカフェイン摂取量の目安は特に定められていませんが、欧州食品安全機関(EFSA/European Food Safety Authority)の基準を参考にするなら、一日あたり400mg(妊婦の場合は一日200mg)までを上限にするのがよさそうです。
ドリップコーヒー100mlに含まれるカフェイン量は60mgくらいなので、1杯を150mlとするならば一日3杯くらいであれば健康を害する心配はないでしょう。
眠気覚ましを目的とするエナジードリンクのたぐいは、大量のカフェインが含まれているものもあるので注意が必要です。
おすすめ食品:シークヮーサー
野菜や果物は全般的にポリフェノール類を多く含むので、健康維持や認知症予防のために積極的に取りたい食品です。
含まれるポリフェノールの特徴や、ポリフェノール以外の健康成分について、有効成分を効率的に取るコツも合わせて順に紹介していきましょう。
長寿の里として知られる沖縄県大宜味村(おおぎみそん)特産の果物として知られるシークヮーサーには、「ノビレチン」というポリフェノールが含まれています。
実はこのノビレチンには、神経細胞の突起を伸ばす作用や記憶障害の改善に重要な働きをもつ伝達分子を活性化する作用があることが東北大学の研究によって判明しました。
マウスを使った実験では、ノビレチンにはアミロイドβが溜まるのを抑え、さらにはすでに沈着したアミロイドβを減らす作用があることも明らかになっています。
アルツハイマー病と似た症状を示すマウスにノビレチンを投与すると、投与せずアルツハイマー病が進行したマウスより、有意にすくみ行動が回復し、記憶障害が改善されていることもわかったそうです。
さらにノビレチンには、がん細胞の増殖や血糖値の上昇を抑制する働きがあることも示唆されていて、慢性リウマチの予防効果も期待されています。
ノビレチンはほかの柑橘類にも含まれていますが、シークヮーサーの含有量はずば抜けていて、温州みかんの約10倍にもなります。
果実の入手は難しいかもしれませんが、果汁100%のジュースを飲んだり、原液を炭酸やお酒で割って楽しむといいのではないでしょうか。
ノビレチンは果皮に多く含まれるので、マーマレードジャムにするのもおすすめです。果皮を乾燥させた陳皮を煎じて飲んだり、粉にして料理に使うという方法もあります。
おすすめ食品:みかん・柚子
みかんや柚子はノビレチンの含有量はあまり多くないものの、皮の内側や薄皮、筋などにヘスペリジンという別のポリフェノールを多く含んでいます。
ヘスペリジンには抗アレルギー作用があることが知られていますが、それは毛細血管を強化して血流を改善する働きによるものだと考えられています。
だとすれば、高血圧や動脈硬化などの生活習慣病の予防効果も十分期待できるでしょう。また、高い抗酸化作用を持つビタミンCの働きを高める作用もあります。
ヘスペリジンも果皮に多く含まれるので、マーマレードジャムや陳皮にして利用するといいでしょう。また、みかんや柚子を食べるときには、薄皮や筋を除かずに食べるのもポイントです。
杉本八郎薬学者、脳科学者。主な著書に『世界初・認知症薬開発博士が教える 認知症予防 最高の教科書』(講談社)、『認知症研究の第一人者がおしえる 脳がよろこぶスープ』(アチーブメント出版)