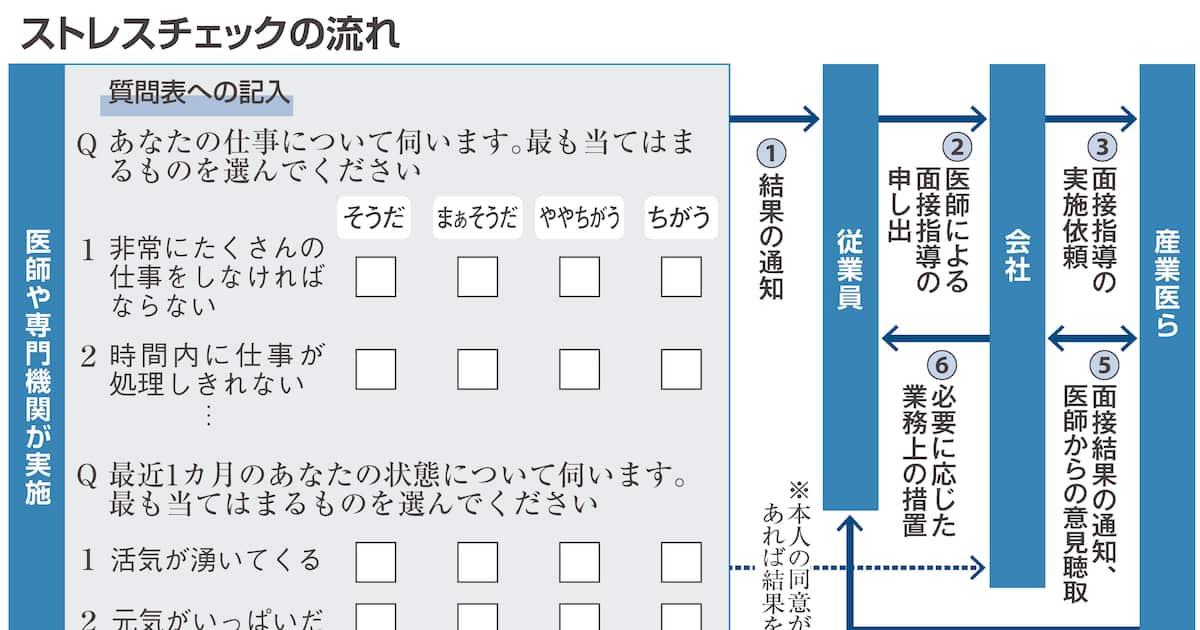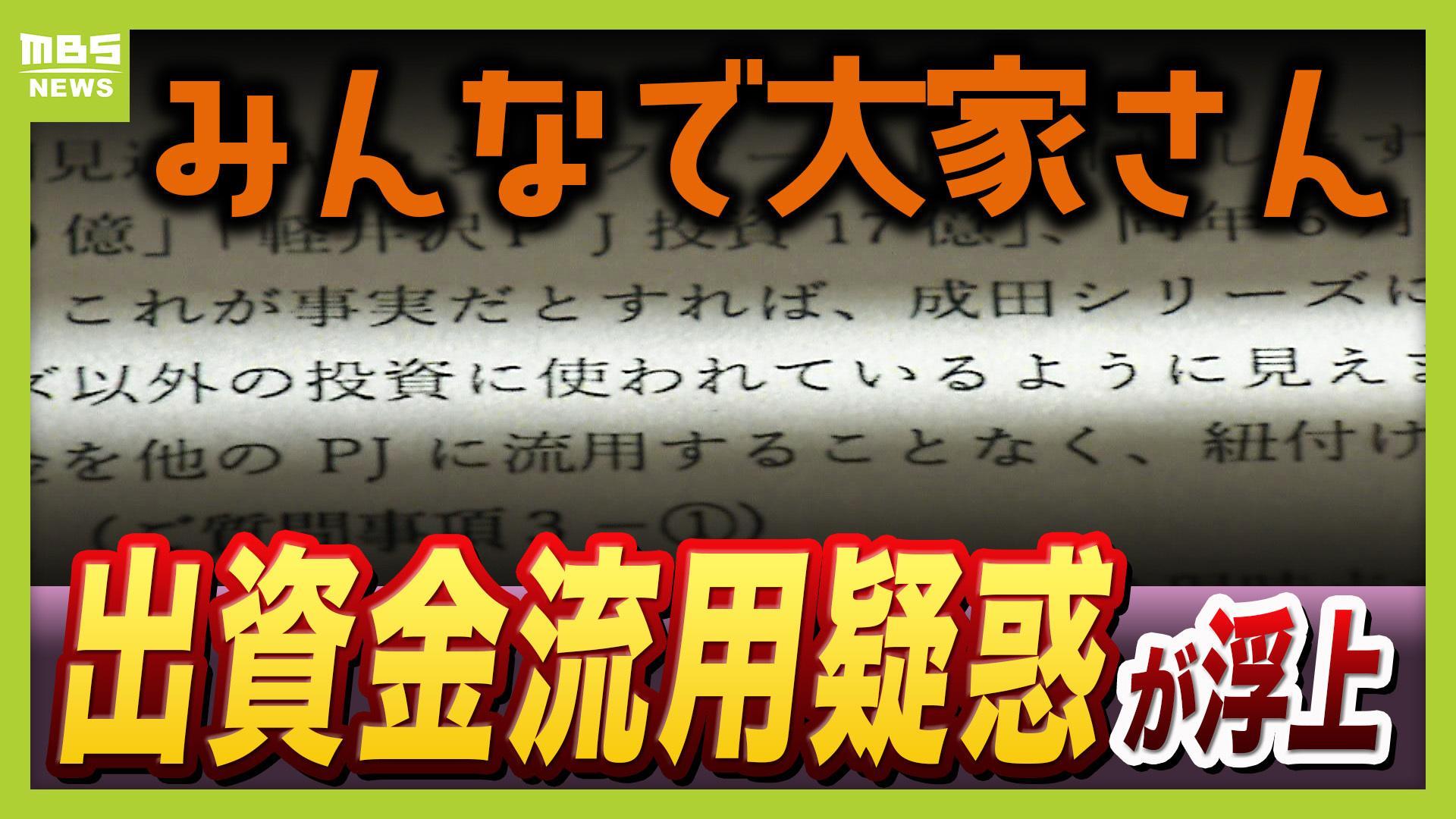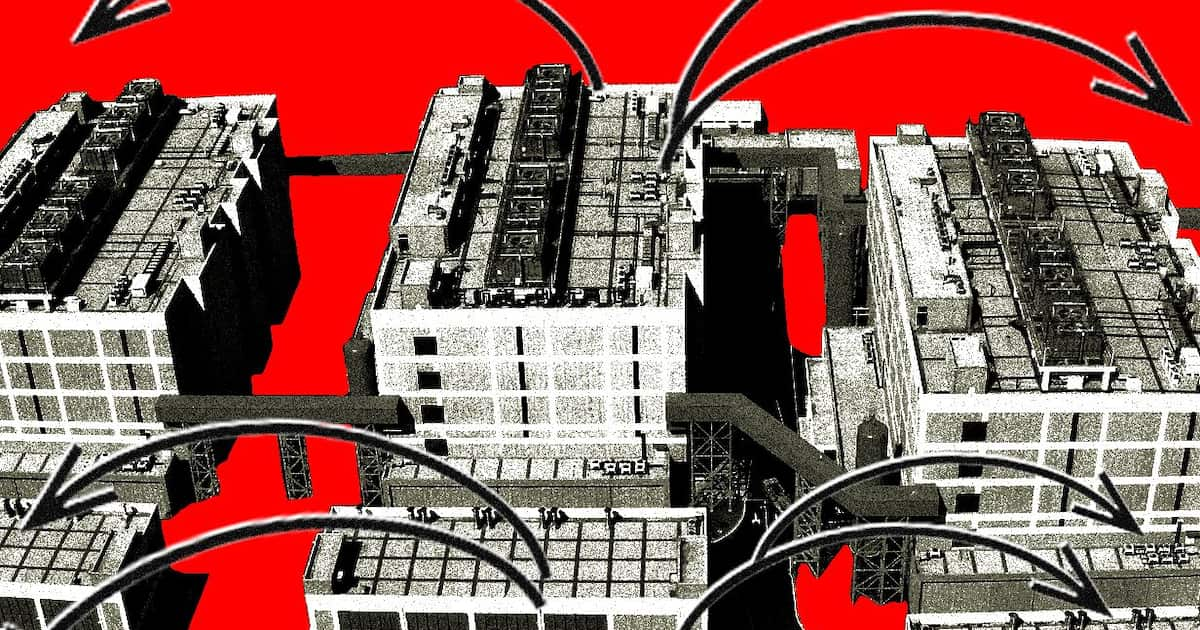「日本だけ」値下げのPS5、Steam新ハードに見るゲームビジネスの大きな変化【西田宗千佳のイマトミライ】

ゲーム機の世界に変化が起きようとしている。
といっても、いわゆる「次世代機」が出るわけではない。各社各様に最適なビジネスを模索する動き、と言えるだろう。
今回は、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)にマイクロソフト、Valveの3社が公開した新しい動きがどのような背景に基づくものなのかを解説していくことにしよう。
まずはSIEからだ。
11月12日、SIEは、日本向け製品として「PlayStation 5 デジタルエディション 日本語専用」を、11月21日から発売すると発表した。
この製品は、光ディスクドライブを搭載しない「PlayStation 5 デジタルエディション」を、国/地域を「日本」に設定したPlayStationアカウントでのみ使える、日本国内専用製品。これまで販売されていた製品は72,980円だったが、「日本専用」とすることで価格を55,000円に抑えている。
ハードウェア仕様にはほぼ変更はなく、別売のディスクドライブを取り付ければ、パッケージ版ソフトやBlu-ray Discなどの再生も可能だ。
こうした製品が企画される理由は明白。日本での販売価格を下げて普及を促進したい、ということだ。
任天堂も「Nintendo Switch 2」では日本国内版(49,980円)を用意し、多国語版(69,980円)から価格を下げていた。アメリカでの販売価格は449.99ドルなので、消費税を勘案すれば多国語版の価格が「海外での販売価格」と考えていい。
「なるほどSIEは任天堂を真似たのか」と言われそうなところで、実際その通りではあるが、背景はもう少し複雑だ。今回起きたのは「リージョンロックの再発明」と言えるものだからだ。
*リージョンロック:地域ごとに製品やサービスを制限すること
ここ数年、日本国内でデジタルデバイスを売る会社は「海外転売対策」に苦しんできた。
円安を背景に、各種製品は日本で販売価格が上がっていた。しかし、日本の国内市況が好調であるわけではなく、価格を単純に為替反映すると売れ行きが下がる。だから、プラットフォームビジネスが絡む製品では、「戦略的に価格を抑える」ものが少なくない。2020年前後からこの傾向はあり、話はゲーム機だけにとどまらない。
だが、そうすると海外との間で価格差が生まれるため、海外へ転売すると利益が生まれる。ゲーム機だけでなくiPhoneなどにも転売ニーズは多く、各社は流通コントロールに苦慮している。
SIEは2023年にPS5の価格を海外水準に上げ、収益が海外に出ていくことを阻止した。
同時にその際、「日本のアカウントでアクティベーションされた場合にのみ、PlayStationストアのクレジットの形でキャッシュバックする」というキャンペーンを行ない、国内値上げ分を短期的に和らげる、という策を採ったこともある。
一方で任天堂は、Switch 2でデバイスに「国内専用」という制限をかけることで、デバイスが海外に転売されないような対策をした。
その関係か、Switch 2は日本国内で好調な売れ行きを示しており、現在も「店に行けばすぐに買える」という状況にはない。これに対し、海外では店頭在庫はすでに正常化し、店に在庫はいつでもある。
SIEは今回、任天堂の施策を真似た形になった。ただ、これは任天堂の発明というより、「ゲーム機が過去の形に戻った」、ある種の再発明というべきかもしれない。
2010年代まで、家庭用ゲーム機は国ごとに「リージョンロック」がかかっていた。海外のソフトは日本のハードウェアでは動かず、逆もまたしかり。色々な抜け穴はあったが、「国ごとに境界がある」のが当然だった。
それがなくなっていったのは、ゲームが「配信」されるものになり、流通上のハードルが邪魔だったから、という部分はあるだろう。
だが、「円安」という状況の中で、高価になった家庭用ゲーム機を売るには、転売などの邪魔な要素をうまく排除していかなくてはならない。
そこで、「アカウント」という決済と利用のベースとなる部分でリージョンロックをかけ、ハードウェアが国別に売られる仕組みを、「日本限定」ではあるが、再度持ち込んだ。
それが今回の変化であり、値下げの背景である。
20年前までは、主に半導体コストの低下によってゲーム機の価格は次第に下がっていった。だが現在は、半導体製造技術の進化に伴うコストダウンは限定的で、ゲーム機は「ライフサイクルを通じて価格が下がりづらいもの」になっている。その背景は以前連載でも書いた。
今後の値下げが難しいのは、任天堂も同様だ。
家庭用ゲーム機が安くなければならない、と決まっているわけではないが、5万円を大幅にこえる価格のままでは、やはり普及には不利である。
だからこそ、リージョンロックを復活させて価格コントロールをするようになった……と理解するのがいいだろう。
ゲーム機のビジネスは、「巨大なヒット作が生まれる」だけでなく、「会員制サービスを含めたネットワークサービス収益」も大きな柱だ。それを長期的に維持するには、利用者の数とアクティブユーザー数、両方が必要であり、その中で日本市場をどう考えるのか……ということでもある。
ここから気になるのは、こうしたリージョンロックが他の地域でも展開される可能性があるか、という点だ。
現状筆者は「導入されないだろう」と予測している。そのくらい、日本での事情が特殊だから、ということなのだが。
もう一つ、「ゲーム機」として注目の動きがある。
PC向けのゲームストアで大きなシェアを持つValveが、2026年に新たなハードウェアを発売するという発表をしたのだ。
新コントローラーの「Steam Controller」、VRヘッドセットの「Steam Frame」もあり、これらも分析しがいのある存在ではあるのだが、今回は小型ゲーミングPC「Steam Machine」にフォーカスして解説する。
Steam Machineは、ハード的にはAMDの独自プロセッサーを使ったミニPCなのだが、OSとしてWindowsではなくLinuxベースの「SteamOS」を使い、その上に互換レイヤーである「Proton」を搭載することで、Windows向けに作られることの多いSteam向けゲームが動くようにしたものである。
同様のコンセプトとしては、2022年に発売されたポータブルゲーム機「Steam Deck」がある。こちらのテレビ接続版がSteam Machine、と考えていい。
コンパクトで4Kテレビにつなげられるハードウェア、という意味では家庭用ゲーム機に近い印象を受ける。
ただ、これが「家庭用ゲーム機を駆逐する存在」と考えるのは早計だ。
というのは、その性質上、プレイするのはPCゲームであることに変わりはなく、設定や操作方法などで、家庭用ゲーム機ほど洗練されてはいない部分が多い……と考えられるからだ。
逆に言えば、「PCゲームの自由さをそのまま引き継げる」のが利点でもあるし、「いざとなったらWindowsをインストールしてPCとして使えばいい」という話でもある。
Steam Deckも面白いポータブルゲーム機だが、Nintendo Switchのような気軽さはないし、Switchとは違うから存在意味がある。
Steam DeckはハードウェアとしてはPC、と言われるが、その辺は本質ではない。PS5やXboxだってハード的にはPCに極めて近い。また、ハードウェアとして独立性の高いSwitch 2も、「汎用性の高いプロセッサーに今日的なCPU命令+GPU」という組み合わせで見れば、構成はそこまで変わらない。性能の話はさらに(極論してしまえば)枝葉末節だ。
ゲームの開発はPCで行なわれ、そこから各ハードウェアにポーティング(移植)されて出荷されるので、重要なのは「PC的か否か」ではなく「メーカーが定義したプラットフォーム」という存在なわけだ。
では「メーカーが定義するプラットフォーム」とはなにか。
それは「ゲームはこの範囲で作ってください。そのための開発サポートをします。さらには流通もサポートするので一緒にビジネスをしましょう」ということなのだ。
ソフトウェア、特にゲームのように自由度の高いものを動かすのは大変だ。「どんなハードウェア・OS構成でも動く」のは理想だが、それをサポートする側はたまらない。
だから「この内容で開発を」という線引きの存在が、ゲームの産業的な供給にとっては重要になる。
そして、家庭用ゲーム機に重要なのが「プラットフォームを維持するためのマーケティング活動」だ。このゲーム機ではどんなゲームができるのか、このゲーム機を買うとどんな楽しいことがあるのか、ということを、お金をかけてしっかり周知・宣伝して人々を惹きつける努力が必要だ。
それには多額の費用が必要になり、多数のノウハウも必要になってくる。
過去にも、家庭用ゲーム機に参入しようとする企業や、クラウドゲーミングなどを展開する企業は多数いた。だがそれらがうまくいかなかったのは、「持続的で大規模な、家庭用ゲーム機としてのマーケティング」を持続できなかったからでもある。
ValveはPCで圧倒的なシェアを持つが、一般向けに他社のようなマーケティングをしているわけではない。家庭用ゲーム機と同じ市場を目指すなら必須のことだが、そこに乗り出す、と考えづらいところがある。
実は「Steam Machine」というハードウェアは過去にもあった。2015年、複数社にハードウェア仕様を公開して製品を発売したのだが、PlayStation 4やXbox Oneに対抗することはできなかった。当時の技術制約による互換性問題も大きかったが、なにより、他社のような大々的なマーケティングを行なったわけでないため、広がることはなかった。
ValveはSteam Deckにおいても、狙うのは「家庭用ゲーム機」ではなかった。PCゲーマーへの選択肢拡大であり、PCゲーマーが家庭用ゲーム機を選ばなくていい、という部分が大きかったように思う。
そして、Steam Deckの存在は「PCゲームはこのくらいの性能で動くべき」という、緩やかな線引きを生み出した。
新Steam Machineが狙うのは「据え置きならこのくらい」という線引きであり、Steam Deck同様に「PCゲーマーを惹きつけ続ける」ことであるはずだ。
同時にこのことは、ゲームという市場が「ゲームを販売し、プレイヤー同士をつなぐプラットフォーム」こそが本質である……ということを示している。
Steamは特定のハードウェアに依存しないプラットフォームである一方、任天堂やSIEは「ハードウェアとサービスが一体になったプラットフォーム」を展開している。その結果としてどういう体験が提供できるか、という点がプラットフォームの選択を決める。
現状、PCゲーマーは確実に増えている。一方で、PCにつきものの複雑さ(正確には「複雑に見える」こと)を嫌い、シンプルにゲームを楽しみたい人々も多数いる。今はまだ後者が多く、家庭用ゲーム機というプラットフォームを支える基盤になっているわけだ。
そこに、マイクロソフトは別の戦略を採ってきた。
Xboxというハードウェアを展開する一方で、Windows PC向けのゲームでも、ストアとXboxアカウントによる連携で「Xbox」ブランドを推している。
先日はWindows 11搭載のポータブルゲーミングPCに「Xbox」ブランドをつけて販売、独自ハードウェアだけにこだわらない姿勢を見せた。
そして、ここに来てマイクロソフトは、ゲーム専用機である「Xbox」の開発とパブリッシングに関する資料を、特別な契約なく閲覧可能な形で公開する選択をした。
Unlocking Access to Game Publishing Documentation for All Developers
家庭用ゲーム機の開発には「開発者登録」が必要で、その内容は守秘義務契約で守られてきた。
2000年代までその契約はとても厳しいもので、公の場で開発情報を語ることすら難しく、小規模なゲーム開発者(いわゆるインディー開発者)が関わるのは難しかった。
それが少しずつ緩やかになり、現在は多くの開発情報が公開され、個人開発者でも家庭用ゲーム機からソフトを出すことは可能になっている。
しかし、開発情報が完全に公開されるのはあまり例がない。マイクロソフトにとっては大きな展開と言える。
開発者情報がオープンになっていったのは、PCでのゲーム開発があたりまえになり、開発効率向上には、一般的なPCソフトと同じく、ノウハウの公開と共有が必須であるという判断が広がったためだ。
特にマイクロソフトは過去から、インディー開発者に対して門戸を開くことに積極的であり、ある意味今回の動きも、そんな歴史につながる部分はありそうだ。
ただ、これでXboxの利用者が増えるか、というとそうではない。結果としてゲームが増えることが重要である。
現状、マイクロソフトにとっての競合は任天堂やSIEというよりも、Valve=Steamという部分が強くなっている。
だとするならば、Valveと同じ土俵に立つためにも、Xboxというハードウェアの情報を公開し、「XboxのゲームをPCでも専用ハードでも」という流れにしていく必要があったのかもしれない。
繰り返しになるが、ゲームビジネスにおける本質は「販売プラットフォーム」にある。それを生かすためにハードウェアを使うのは必然であり、そこには各社それぞれの戦略がある。
任天堂には任天堂の、SIEにはSIEの戦略があり、さらにマイクロソフトやValveも、それぞれの判断に合わせて最適化戦略を採っているということなのだ。