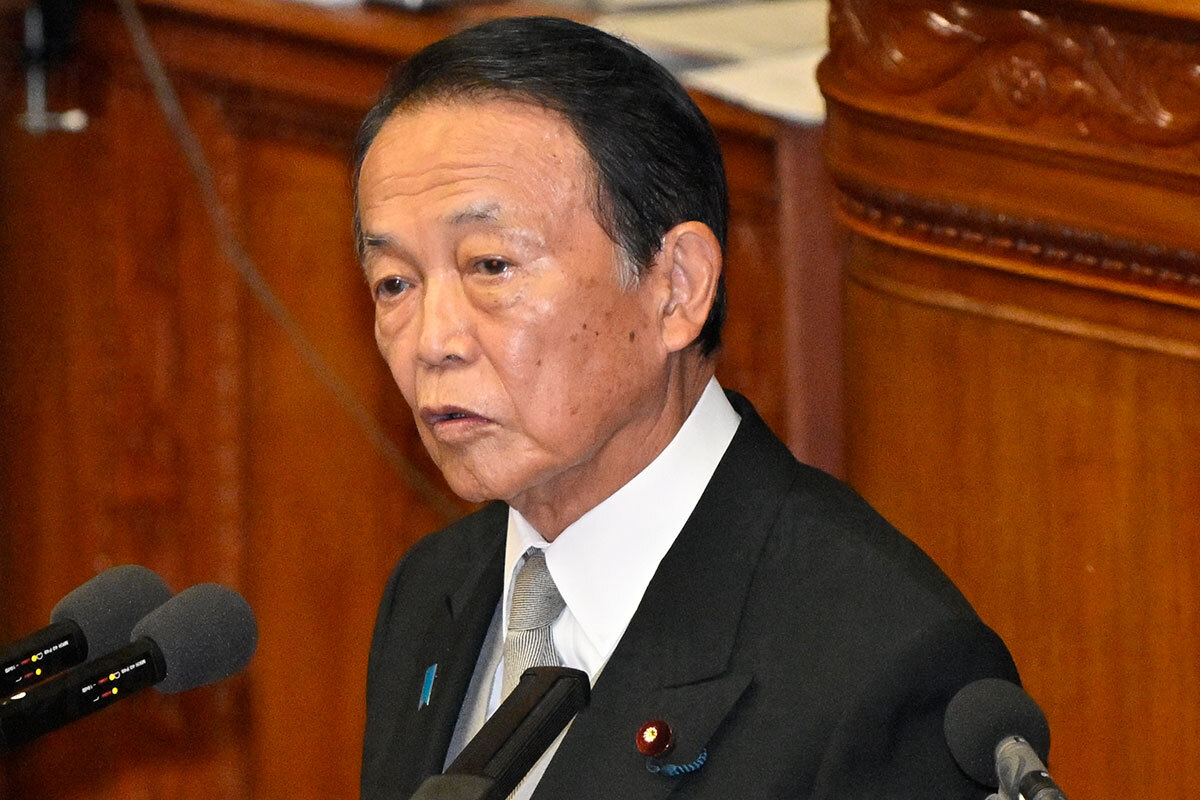【南海トラフ地震】「想定よりも早まる可能性も」 専門家の間で浮上する「2035年説」vs「2038年説」…死者数29万8千人の現実味

近年、全国各地で立て続けに発生している地震。大きな揺れに直面するたびに頭をよぎるのが、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの大規模災害だ。「近い将来に必ず起こる」と言われるこれらの巨大地震では、どんな被害が想定されているのか? 正しい情報を得るために必要な心構えを専門家に聞いた。AERA 2025年9月8日号より。
* * *
今年1月、政府の地震調査委員会が南海トラフの「新被害想定」を公表した。その中で30年以内発生確率が「70%から80%」から「80%程度」に引き上げられたことも記憶に新しい。
6月から発生している鹿児島県・トカラ列島の群発地震では、フィリピン海プレート全体が活発化している可能性があるとも指摘されている。南海トラフとの関係性を不安視する声が上がったが、実際はどうか。日本地震予知学会会長で東海大と静岡県立大の客員教授の長尾年恭さんは言う。
「南海トラフの発生が想定より早まる可能性はあります。専門家の間では2035年説と2038年説の二つが出ています」
かつて南海トラフのプレートが動いた1707年の宝永地震と1854年の安政東海地震、1946年の昭和南海地震の三つの巨大地震のデータをさかのぼりプレートの跳ね返りを調べると、その2説にたどり着くという。
「ただし、30年以内の発生確率は20%だという論文もあり、学会のなかでも意見が分かれているのが現状です」(長尾さん)
フィリピン海プレート縁辺部では、火山噴火やそれに伴う軽石の大量流出といった異常活動が相次いでいる。こうした動きが南海トラフの発生を早めるトリガーになる可能性は否定できないという。
東京湾にある「地震の巣」
南海トラフと並んで気がかりなのが、首都直下地震だ。東京都、茨城県、千葉県などの南関東地域で30年以内に70%の確率で起こると言われている。それぞれの特徴に応じた対策が求められるが、特に首都直下ではインフラやライフラインの老朽化が懸念の一つだ。長尾さんは言う。
「千葉県北西部では、10年に一度ほどの頻度で深さやマグニチュード、震度がほぼ同じ地震が発生しています。ところが、規模は同じなのに、水道管の破裂件数は増えているのです」
Page 2
東京湾北部には、深さ60~70キロメートルの場所に「地震の巣」と呼ばれる震源密集地帯がある。ここでは体に感じない小さな揺れも含め、月に100回ほどの地震が起きている。建物の崩壊に加えて上水道や下水道が破裂すれば、生活の立て直しに影響が出ることは避けられない。
死者数29万8千人と6148人、避難者数1230万人と299万人、建物被害235万棟と19万4431棟……。南海トラフと首都直下の被害想定を改めて比較すると、その様相が見て取れる。
AERA 9月8日号より木造密集度もチェック
「南海トラフでは津波により命を落とす人が多い一方で、首都直下では火災による被害が甚大です。防災や発災時の対応も含め、正しい情報と正しい判断が重要になってきます」
そう説明するのは、東洋大学社会学部教授で災害情報論が専門の中村功さんだ。津波の際は高台に避難するという知識は普及しているが、道路が塞がれて身動きが取れない可能性もある。東日本大震災では各所で渋滞が発生し、津波に巻き込まれたケースもあった。一般論を強調しすぎるのではなく、現地の状況に合った判断をその都度していくことが不可欠になってくる。
どうすれば正しい情報を得て、判断できるのか。
「まずはハザードマップをしっかり確認し、津波や土砂災害、浸水区域を知ってください。東京には多くの木造住宅密集地域があるため、自宅周辺の火災危険度を調べておくと心構えができます」(中村さん)
ハザードマップは見たことがあっても、木造密集度まで調べたことがある人はそう多くないのではないか。東京都の公式サイトでは、木造密集度や道路の狭さ、延焼リスクなどを反映した地域別マップが公開されているのでチェックしてほしい。
また、大阪府や神奈川県などの密集市街地の多い地域については、国交省の「地震時等に著しく危険な密集市街地」を集めたデータも活用できる。生活範囲のリスクを自分ごととして捉えることが、防災への第一歩だ。中村さんは続ける。