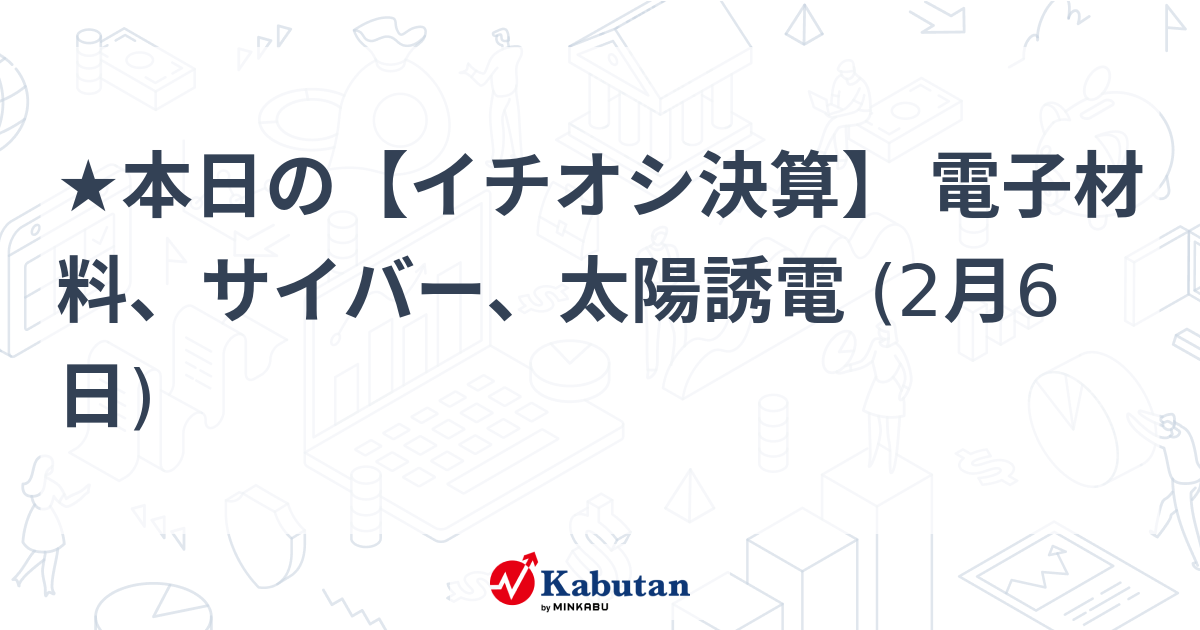メルカリ「スキマバイト」撤退 なぜ登録者1200万人でも終了?

メルカリのスポットワーク(スキマバイト)事業である「メルカリ ハロ」が、12月のサービス終了を発表し、話題になっています。
2024年3月のサービス開始後、登録者数は1200万人に達したにもかかわらず、なぜ撤退してしまうのでしょうか。背景を探ってみました。
サービス開始から1年半で撤退、先行するタイミーに追いつけず
スポットワークでは面接や履歴書なしにアプリで短期の雇用契約を結び、すぐに仕事に就けることが特徴です。長期雇用への引き抜きもOKとなっていることから、新たな採用手段としても注目されています。
メルカリ社内ではかなり前からアイデアとしてはあったようですが、2023年11月の正式発表後、2024年3月にサービスを開始してからわずか1年半で撤退する形になりました。
8月の通期決算説明会では「スポットワーク業界で確固たるポジションを確立する」との中期方針を掲げたばかりでした。それから約2か月後となる10月14日の取締役会にて、サービス終了を決定したといいます。
8月時点では、以前に比べて表現はトーンダウンしたものの、スポットワーク事業についての中期方針を示していた(メルカリの決算説明会資料より、筆者作成)サービス終了の理由については「市場環境の変化やサービスの利用状況などから総合的に判断した」(メルカリ広報)と、詳細は明かしていません。
事業としてはどういう状況だったのでしょうか。通期決算では「調整後コア営業利益」の数字として、スポットワーク事業の有無で59億円の差があったと開示しています。単純計算では1年間で59億円の赤字が出たと考えられます。
ただ、サービス開始当初は事業者向けの利用料を無料としており、4月から「有料化」しています。収益を計上できたのは実質3か月しかなく、先行投資の時期が長かったことを考えれば、まさにこれからという時期でした。
登録者数は6月時点で1200万人を突破しており、他社に比べて数倍の急成長といえます。一般に、新しいアプリが会員を集めるには広告などのコストがかさむところですが、メルカリは月間2300万人が利用する自社アプリから誘導できるという強みがありました。
メルカリのアプリには「はたらく」タブが用意されている。働き始める際にはメルカリのアカウントを利用できた(メルカリのアプリ画面より、筆者作成)ただ、これはあくまで「登録した人の数」であり、キャンペーンのポイント目当ての人やタイミーを中心に使っている人も含まれていると考えられます。決算資料などでも、実際に稼働していた人の数は開示していません。
またパートナーの拠点数は全国チェーンを中心に2025年1月末時点で15万店舗に達していたものの、実際にアプリに掲載されている求人数はタイミーに比べてまだまだ少ないという声がありました。
求人を出す事業者側としては、仕事に不慣れな人が来ることを前提に作業の切り出しやマニュアル化を進め、安全面にも配慮するなど、スポットワークの受け入れ体制を整える必要があります。
その点、タイミーは全国に700人以上の営業担当者を展開して支援にあたっているといいます。メルカリはフリマ内にストアを出店できる「メルカリShops」を通じて全国の中小事業者と接点を持っていたとはいえ、まだ生かし切れていない印象がありました。
それに加えて、2番手以降の事業者にとって不利に働く「参入障壁」をタイミーは挙げています。それは複数のスキマバイトアプリを併用した場合の労務管理の問題です。
メルカリ ハロでは、同一企業からの報酬を月間8万円以下とするなどいくつかの制限を設けることで、社会保険への加入を不要としています。タイミーもほぼ同じ仕組みです。
しかし複数のアプリを使えばこの制限を超えることができるため、雇用する側は労働時間を合算するなどの労務管理が必要になります。そうした手間やリスクを避けるには、業界No.1のタイミーだけを使うのが合理的となるわけです。
タイミーの見立てが正しいとすれば、メルカリはタイミーと同じ事業者向け利用料(30%)の引き下げや、タイミーが手薄な分野を開拓するなどの競争を仕掛けることで、何らかの形で業界No.1を目指す必要があったのかもしれません。
スポットワーク業界では厚生労働省がワーカー保護の動きを進めており、メルカリも9月1日には利用規約の改定やシステム仕様の変更を実施。同時期にキャンセル時のペナルティも変更しており、こうした業界ルールの変化も影響した可能性があります。
今後は勤務履歴の確認などのため、サービスへのログインは2026年4月まで提供する予定とのこと。サービス終了に伴う業績への影響については「軽微と考えている」(メルカリ広報)としています。
経済圏の拡大効果も期待されていたが
メルカリがスポットワーク事業に参入した狙いとして、フリマや決済事業との相乗効果が期待されていました。
家の中にある不要品をフリマで売ってお金にすれば、欲しいものを買えます。これに対してスポットワークは、余っている時間やスキルを売ってお金にする仕組みといえます。
フリマの売上金に加えて「給与」が入ってくれば、メルカリ利用者の懐が潤います。そうすればフリマでの買い物やメルカードの支払いに充てる余裕が生まれるというわけです。
スポットワークによる「給与のCash-in」が期待されていた(メルカリの2024年8月に公開した決算説明会資料より)アプリには銀行口座に振り込まれた給与をメルペイにチャージする導線が用意されています。将来的には給与デジタル払いにより、メルペイで直接給与を受け取れるようにする構想も明かしていました。
こうした経緯を踏まえるとスポットワーク事業からの撤退は残念に思うところはあります。メルカリ経済圏の拡大につながるような新たな一手は出てくるか、引き続き注目しています。
(やまぐち けんた)1979年生まれ。10年間のプログラマー経験を経て、2012年にフリーランスのITジャーナリストとして独立。日経クロステック(xTECH)やASCII.jp、ITmedia、マイナビニュースなどの媒体に寄稿し、2021年からは「Yahoo!ニュース エキスパート」として活動しています。