SNSで見聞きする「ハイヤーセルフ」について心理師がスキーマ療法の視点から考えてみた。(ヨガジャーナルオンライン)
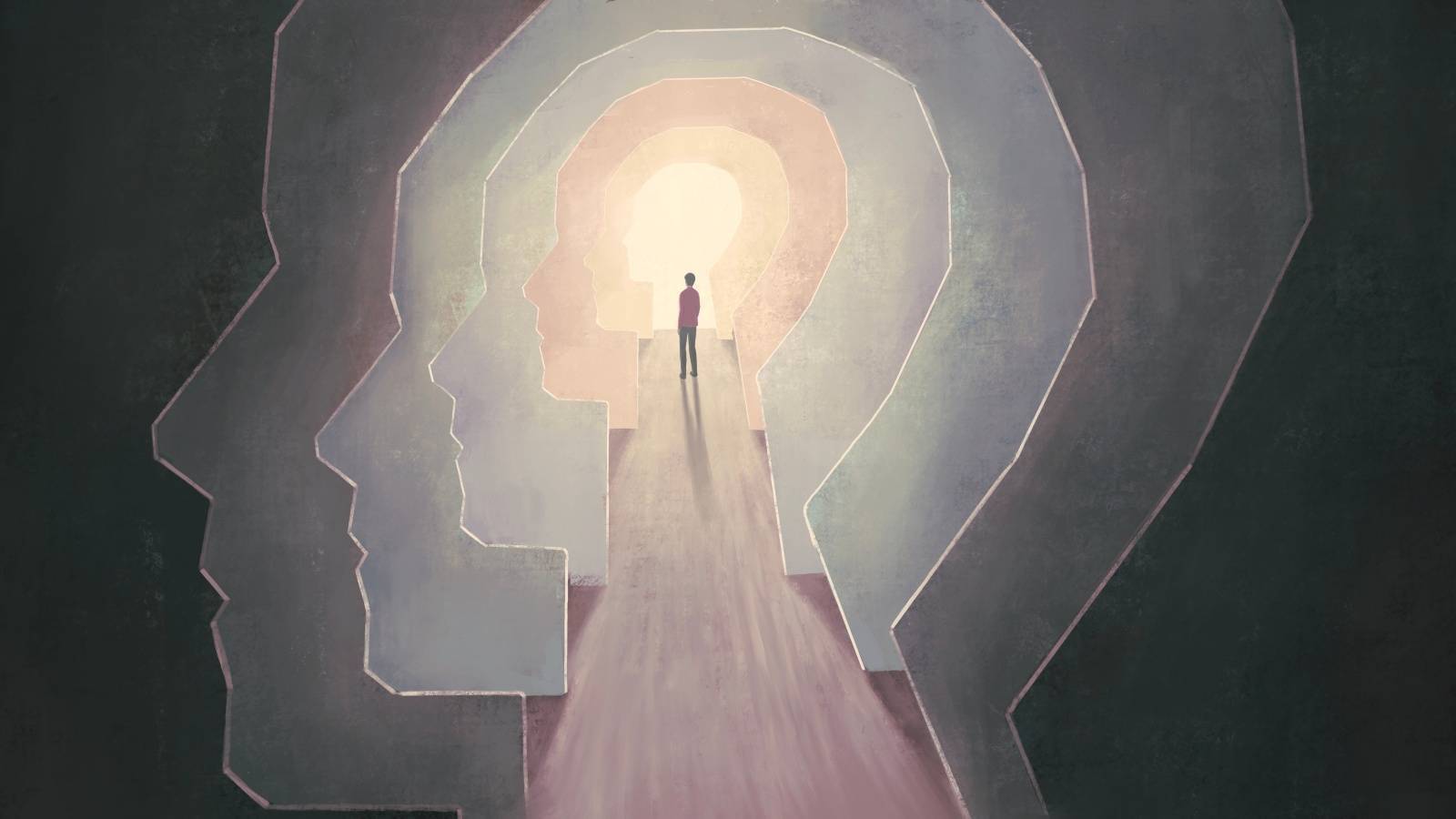
「ハイヤーセルフ」という言葉を聞いたことはありますか? SNS等で見聞きした人もいるのではないでしょうか。今回はスキーマ療法という心理療法の視点から検討してみました。 〈画像〉SNSで見聞きする「ハイヤーセルフ」について心理師がスキーマ療法の視点から考えてみた。 ■ハイヤーセルフってなに? ハイヤーセルフは、直訳すると「高次の自分」。スピリチュアルな本や動画などでは「魂の声」「直感の源」「大きな自分」と表現されることがあります。ここでは心理学、とくに認知行動療法が発展してできたスキーマ療法という心理療法の考え方から、このハイヤーセルフをどう理解できるのかを見ていきます。 ■スキーマ療法と心のモード スキーマ療法では、私たちの心の動きや振る舞いを「モード」という言葉で整理します。私たちが仕事をしている時は、仕事モード、家にいるときはリラックスモードのように私たちは普段さまざまなモードを自然と使い分けています。そのモードの中でも、生きづらさやストレスと関連するモードがあります。例えば、「傷ついた子どもモード」は不安や寂しさを感じているとき、「批判的な大人モード」は「ダメなやつだ」と自分を厳しく責める声として出てきます。逆に、つらさから逃げるために必死に働いたり、考えるのをやめたりするのは「コーピング(対処)モード」の一つです。 ■ヘルシーアダルトという存在 そんな中で大切なのが「ヘルシーアダルト」というモードです。これは心の中の“健康で成熟した大人”の部分。いろいろなモードのバランスをとり、不安なチャイルドモードの気持ちを安心させたり、自分を責める声をやわらげたりします。そして、そのときの感情に流されず、長い目で見て自分にとって大切な選択をすることができるのです。スキーマ療法の目標の一つは、このヘルシーアダルトを育てていくことにあります。 ■ハイヤーセルフと重ねてみる この視点から考えると、ハイヤーセルフとは「特別な霊的存在」というよりも、心理学的には「ヘルシーアダルト」とよく似ていると感じます。不安な気持ち等に巻き込まれず、大きな視点から自分を見守り、必要なときに優しく声をかけてくれる“内なる大人”。スピリチュアルでは「ハイヤーセルフとつながる」と表現されますが、それを心理学の言葉に置き換えれば「ヘルシーアダルトを強める」ということになるでしょう。 ■心理学の別の考え方ともつながる 実はこのアイデアは、スキーマ療法だけのものではありません。ユング心理学では「セルフ(自己)」という概念があり、意識と無意識を含んだ本当の自分の全体像であり、まとまりある「ひとりの人間」として成長させようとする働きがあります。また、マインドフルネスでは「観察する自己」という視点が大切にされます。自分の考えや気持ちに巻き込まれずに、それを一歩引いて見守る立場のことです。どれも「狭い自分を超えて、広い視点を持つ」という点で、ハイヤーセルフと重なる部分があります。 ■ヘルシーアダルトを育てるには では、ヘルシーアダルトモードをどう育てればいいのでしょうか。まずは、自分が今どんなモードにいるか気づくことです。「いま私は子どものように不安になっているな」「自分を厳しく責めているな」と気づくだけで、少し距離が生まれます。次に、その子どもの部分に優しい言葉をかけてみましょう。「大丈夫だよ」「怖かったね」と、いたわるように。さらに、自分を責める声が出てきたら、それに対抗する現実的で思いやりのある言葉をかけます。例えば、「完璧じゃなくても、今の自分で十分だ」と言ってあげることです。こうした積み重ねが、ヘルシーアダルトを少しずつ大きくしていきます。 ハイヤーセルフという言葉は、心理学に置き換えると「ヘルシーアダルト」や「セルフ」「観察する自己」といった考え方に近いと言えます。誰の中にももともと備わっていて、育てることができる機能です。ヘルシーアダルトを少しずつ育てていくことで、より生きやすい心の土台をつくっていきましょう。 ライター/石上友梨(臨床心理士、公認心理師)
石上友梨



