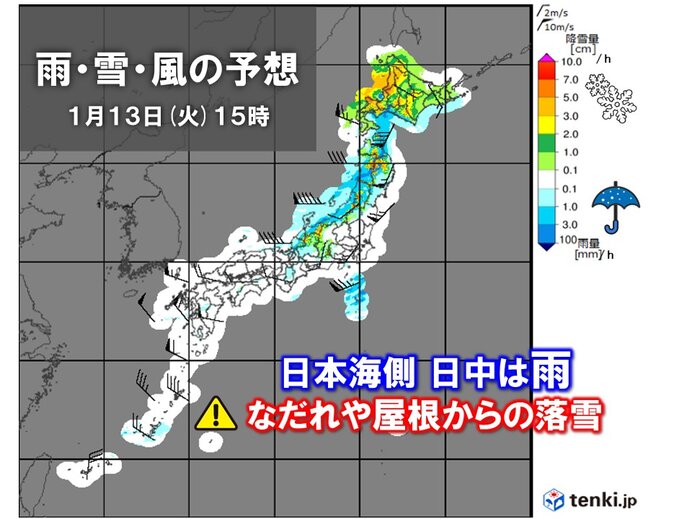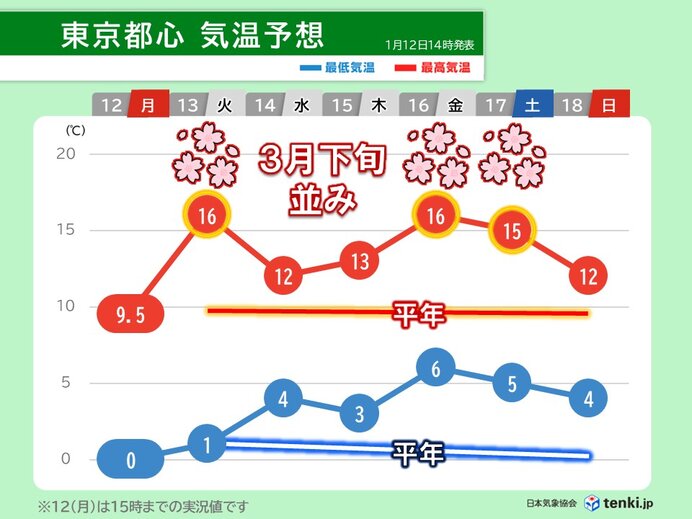能登半島地震の被災家屋、公費解体に「待った」…貴重な建物や独特の景観「失う恐れ」

能登半島地震で被災した約4万棟の家屋の公費解体に「待った」をかける動きが、行政や建築家らの間で広がっている。修繕すれば十分住める物件までが解体申請され、「このままでは能登地方の貴重な建物や独特の景観が失われかねない」という危機感が背景にある。(金沢支局 高倉正樹)
竹の塀「間垣」の景観が残る七浦地区で進められる公費解体(27日、石川県輪島市で)=桐山弘太撮影石川県が策定した「公費解体加速化プラン」では、今年10月末までに被災家屋3万9235棟の解体を目指す。このうち約半数にあたる2万78棟の解体を3月上旬までに終了した。
県や市町によると、解体申請の中には全壊物件だけでなく、直せば住めるのに「自己負担なしで解体できるから」と申請された物件も少なくない。自治体担当者は「息子や娘が地元を離れた世帯にとって住宅が『負の遺産』になっている」と語る。
2月6日、輪島市 七浦(しつら) 地区の住民会合に出席した浅野大介・県副知事は「解体を予定する人も少し立ち止まって、家を残して生かす道を考えてほしい」と訴えた。七浦は、日本海から吹きつける風を防ぐ竹の塀「 間垣(まがき) 」の景観で知られる。「古民家じゃないから」と遠慮する住民に、副知事は「古くなくても価値はある。この町並みを残すことが大事なんです」と強調した。
県が活用を呼び掛けるのが「留保」という仕組みだ。申し出れば、申請した解体工事の手続きを停止し、建築士ら専門家の無料調査が受けられる。希望に応じてリフォーム業者や民泊事業者にもつなぐ。県は修繕費用の助成も検討している。
Page 2
独居の母が暮らした築55年の一軒家が七浦にある金沢市の男性(53)は「愛着のある家がなくなるのは寂しい。壊さずに済むなら直そうか」と考え始めた。公費解体は申請済みで、業者から今月の作業開始を打診されたが、「もう少し検討したい」と断った。
県の呼び掛けもあり、輪島市は3月末としていた公費解体の申請期限を5月末に延長した。「迷っている住民は多い。柔軟に対応したい」と担当者は話す。
風を防ぐ竹の塀「間垣」の景観が残る七浦地区(2月27日、石川県輪島市で)=桐山弘太撮影県内の建築家や設計士らでつくる一般社団法人「能登復興建築人会議」も、市町と連携し、3月11日から現地調査に着手した。伝統的な建物から一般住宅まで約6000棟を調べ、残すべき建物を選別していく。会議のメンバーで金沢工業大の竹内申一教授は「建物は景観を形づくる貴重な資源。(解体完了の10月までに)どれくらい残せるか、時間との闘いだ」と語る。