子どもだけじゃない!“大人の食物アレルギー”の実態は?当事者「以前は食べることができたが…」「ご飯の誘いは基本的に断る」
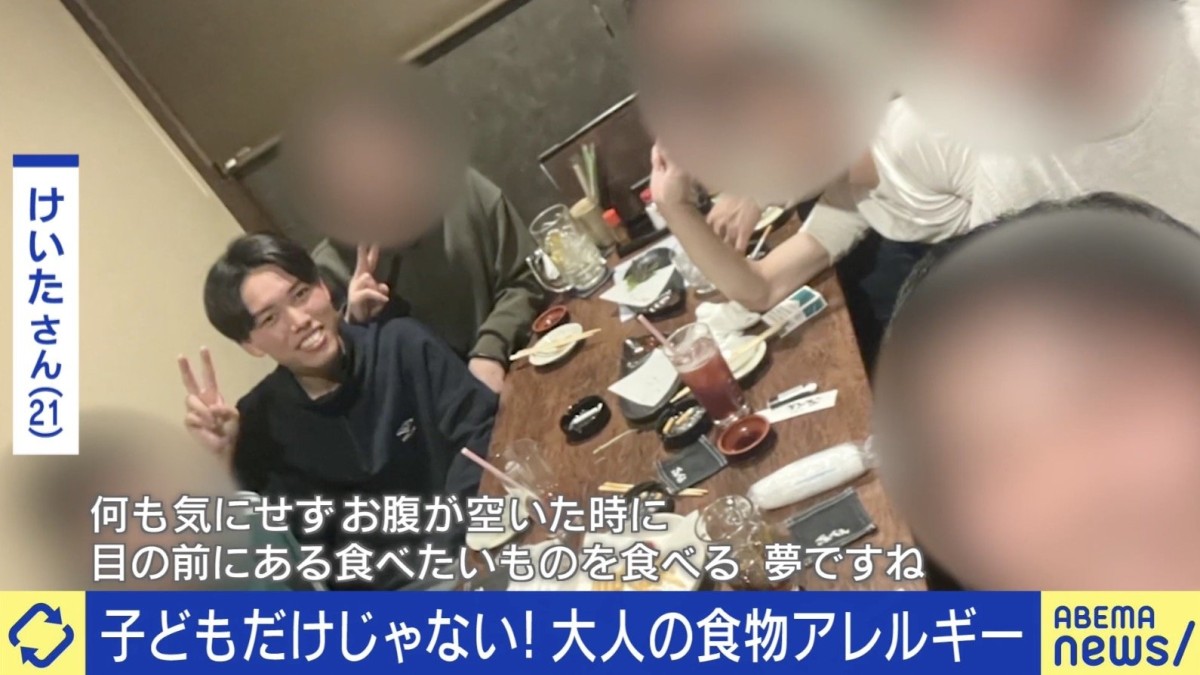
1
小学4年生のレイ君と2年生のラン君。2人の母・あずささんが作った夕飯はミートスパゲティだが、ランくんはミートソースをかけたご飯を食べている。あずささんは「ランは乳製品・卵・小麦にアレルギーがあるので、パスタが食べられない」と明かす。
【映像】背中からお尻まで…“大人の食物アレルギー”症状(実際の写真)
ランくんは特定の物を食べたり触れたりすると症状が現れる「食物アレルギー」。本来、栄養になるはずの食物を体が受け付けず、蕁麻疹や腹痛、嘔吐などの症状が起こるというもの。重症化するとショックを起こし、最悪の場合、命に関わる可能性もある。
あずささんは「生後5カ月のときに離乳食をあげたときにアレルギーがわかった。口に入れてすぐ顔がパンパンに腫れて、掻きだしてぐずりだして、嘔吐が止まらなかった」と振り返る。摂取量や症状のあらわれ方は人それぞれ異なるが、ラン君の場合は牛乳1滴でも危険が伴う。一方で、卵料理や麺類が大好きなレイ君。自宅では調理器具を分け、違う色の食器を使い、ラン君の誤食を防ぐよう気をつけている。
食物アレルギーは乳児期に発症し、多くは成長と共に治るとされているが、少量食べただけでも反応する子どもは、大きくなってもアレルギーが続きやすく、治らない人が増えているという。増加傾向にある“大人の食物アレルギー”に必要な治療や対策はあるのか。当事者と専門家とともに、『ABEMA Prime』で考えた。
■食物アレルギーのけいたさん(21)
現在、大学4年生のけいたさん(21)は、0歳から小麦や卵、乳製品、ナッツ類や果物など、数多くのアレルギーがあった。「最初に離乳食を食べたとき、顔に蕁麻疹が出てきたことが最初のきっかけだ。病院で血液検査したら、他にも見つかった」。
中学生になると、「以前は食べることができた梨やリンゴなどの果物を食べると、喉がイガイガしてきたり、唇が腫れたりする症状が出始めてきた。1番最近だと、高校生のときにイチゴが食べられなくなった」。
現在の生活では、「サークルの後、ご飯食べに行こうみたいなのは基本的に断る。そこでノリ悪いとか思われたりしないか心配ではある」と弊害を感じている。
チェーン店であれば、ホームページで原材料を公表しているところも多く、事前に確認できるが、「屋台など基本的にアレルギー表示がないので、直接『何が入ってますか?』って確認するが、秘伝の味や企業秘密という形で、教えてもらえないところもあった」。
飲み会では、「居酒屋だとメニューが結構あるので助かる部分はあるが、酔いすぎて食べれないものを食べてしまったりするので、気を張ってしまう」と明かした。
■食物アレルギーの症状
国立病院機構相機原病院臨床研究センター長の海老澤元宏氏は、食物アレルギーについて、「僕らの体の中には、IgE(免疫グロブリン)抗体という物質が作られる。それによって起きる現象の1つで、蕁麻疹や皮膚の症状が最も多いが、息苦しくなる、あるいは強烈な腹痛などのような症状が起こる」。
代表的な食物アレルギーのタイプは3つあり、食事から2時間以内に蕁麻疹・痒みなどの皮膚症状や呼吸器症状などがみられる「即時型」。特定の食物摂取後の運動負荷によって、アナフィラキシーが誘発する「食物依存性運動誘発アナフィラキシー」。 花粉にアレルギーを持った人が果物や野菜を食べ、口の中に痒みや刺激を感じる「花粉-食物アレルギー症候群」。
海老澤氏によると、最近では「子どものときに発症して、大人まで続いてしまう方は、卵や牛乳でもいるし、花粉に関連してのアレルギーや、木の実類も多くなっている」という。「卵、牛乳、小麦は比較的治りやすいと言われていて、小学校に入るまでに大体7〜8割は自然に治る。ただ、ピーナッツや木の実類は、約1割しか自然には治らない」。
けいたさんの症状については「スギやヒノキではなく、ハンノキ花粉があるのではないか」と推測。「リンゴ、梨、イチゴは全部バラ科だが、その果物とハンノキ花粉は形が似た物質がある。それによって、僕たちの体は70パーセントぐらい似た物質だと区別がつかなくなる。本当は花粉に反応するが、口の中に生の果物が入ってくると、体が誤作動してしまう」と解説した。
さらに、「今、日本ではスギ花粉に対して反応する人は、若い世代だと40〜50パーセントぐらいになっている。昔に比べて、最近は国民の半分ぐらいがアレルギー体質状態。1度そういう体質が出てしまうと、世代から世代へ移っていく」と付け加えた。
■大人の食物アレルギーの課題
けいたさんは、アナフィラキシーの症状が表れた際、「エピペンを太ももに打つ」という。「エピペン」とは、医師の治療を受けるまでの間、症状の進行を一時的に緩和しショックを防ぐための補助治療剤(自己投与が可能なアドレナリン製剤)で、「アレルギーが重めだったので、小学生ぐらいから常に持ち歩いてる」。
今までに使用した回数は、「2回あって、1回はお母さんに打ってもらって、2回目は自分で打った」。周りには「知っててもらいたいから、アレルギーがあることも、エビペンを持ち歩いてることも伝えているが、(エビペンの)使い方までは言ってない」と明かした。
アナフィラキシーは周りの人に分かるのか。海老澤氏は「食物の場合だと、皮膚の症状が結構多く出る。あとは息がしづらい、咳き込みがひどい、強い腹痛が来たとか、そういうものの組み合わせで判断する」。周りの人ができることは、「エビペンを持ち歩いていて、自分で打てないような状況だったら、周りの人が打ってあげることはできる」と答えた。
大人の食物アレルギーの課題については、「専門知識を持つ医師が少ない」「何科を受診していいか分からない」ことから、海老澤氏は「なかなか治らない。今、経口免疫療法というアプローチや、アメリカだと抗体製剤の治療もできる。抗体製剤等の治療のオプションも日本に入ってきたらいいなと思っている」と話す。
また、「日本の子どもの食物アレルギーの診療のレベルは世界で1番」だが、「移行期・成人期の食物アレルギーの診療体制は非常に脆弱で患者さんが行くところがない状態を早く改善したい」と述べた。
(『ABEMA Prime』より)



