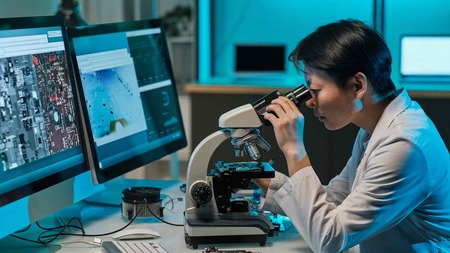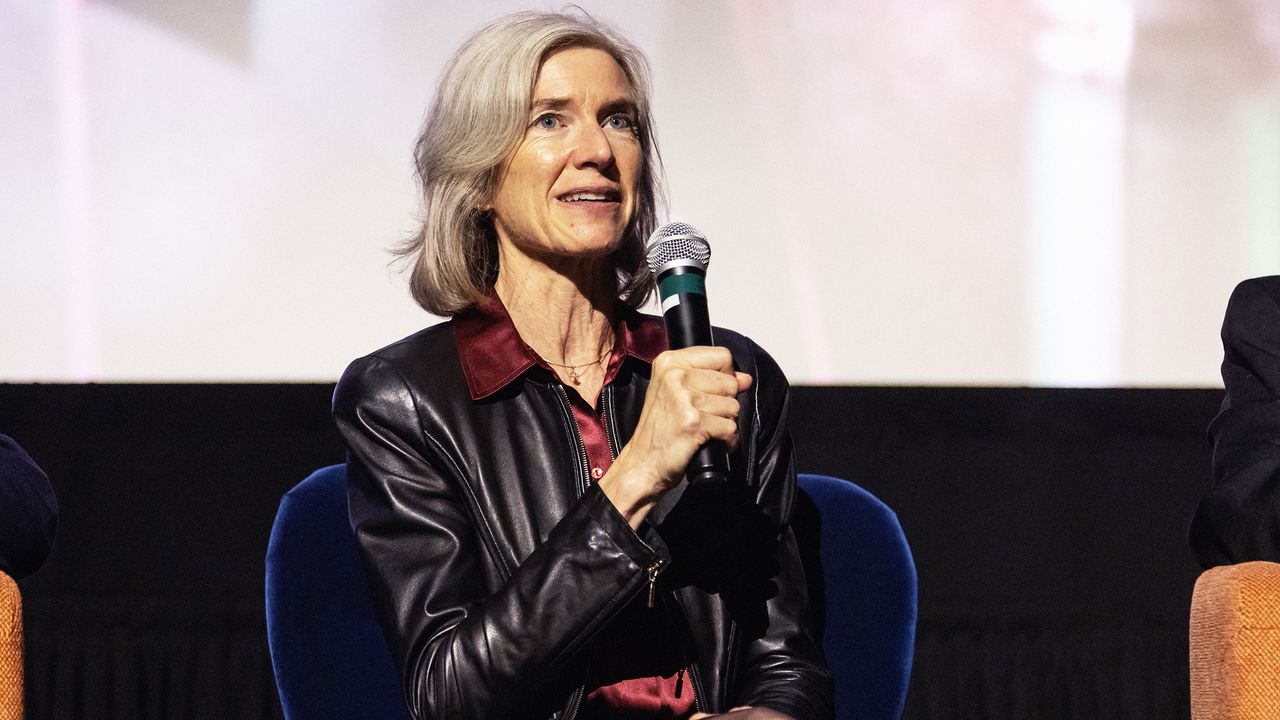「配属先ガチャ」で腐る若手がバリバリの仕事人間に…優秀な上司が「まずは下働きを」と言わずにかける言葉 失望は「仕事への期待」の裏返しでもある

仕事なんだからやって当たり前だという思いもあるでしょうし、言おうと思っても、いざとなると抵抗を感じてしまうことかもしれませんが、
「いつも○○してくれてありがとう」 「がんばってくれて助かっているよ」
そんなことがさりげなく言えるようになると、部下も嬉しく思うでしょう。そして「この人のために頑張ろう」と思ってくれたり、やりがいやモチベーションを持てるようになると思います。そして、繁忙期の対応を求められたり、難しい課題につきあたっても、「上司を喜ばせたいから一肌脱ごう」という気持ちになってくれることもあるでしょう。
やりがいを感じられる要素には、給料や職種、仕事上のステータスだけでなく、最終的には人間関係も大きいのではないでしょうか。
ただし忘れてはいけないのは、感謝の言葉はただ言えばいいというものではなく、心がこもっていなければ、意味がありません。Z世代は本音で言っているかどうかに敏感です。
部下が働いてくれること、毎日会社に来てくれることを当たり前だと思わずに、感謝の言葉やねぎらいの言葉を照れずに伝えられるようにトライしてみてください。
写真=iStock.com/itakayuki
※写真はイメージです
「話が違う」と感じてしまう配属ガチャの問題
配属先や転勤の有無など、かつては希望通りにならないことも多かったですが、今はだいぶ変わってきています。しかし、必ず思い通りになるとは限りません。
配属先などに関しては、思い通りにならなかったりすると、拙著『Z世代をモンスターにしない言葉』(ビジネス社)の1章で紹介した「親ガチャ」ならぬ、「配属先ガチャ」という言葉があるほどです。
上司のギモン②
「面接のときに言われたことと違う」と、今の仕事に不満のようです。「まずは与えられた仕事をこなしましょう」と言っているのですが、どうも自分がやりたいことばかりに関心が向いてしまい、どのように説得したらよいか迷ってしまいます。
会社は必要な人員に対し、適性や経験値に応じて配置を決めるわけですが、たとえば最終に近い面接などの席で、会社が抱えているメインプロジェクトが話題にのぼり、「ぜひ力になってください」みたいな話があったりします。
そんなふうに言われたら、きっとその部署に配属されるのだろうと、その社員は期待するでしょう。でも、その後配属されたのはプロジェクトとはまったく関係がないところだったり、そうであっても新人は下働きをさせられたりします。あるいは、入社と同時に出向を命じられたり、しかも業種すら違う場合すらあるのは、実際にある話です。
Page 2
そして、きちんと役割を果たしたことで、助かっていることを伝えることも欠かせません。
「○○さんがきちんと計算してくれたおかげで、無事に納品できたよ」
当たり前のことだと思うかもしれませんが、納期や決まり事を守って達成したことで最終的な商品やサービスにつながっていること、自分の働きがそこに役立っていることを、しっかりイメージできるように伝えるのです。
成果や実績だけでなく、プロセスを積み上げることはとても大事ですし、関わりのある人の名前を挙げて、「◯◯さんが助かってると言ってたよ」と伝えることでもいいでしょう。
会議や打ち合わせの際にきちんと発言ができたなら、「君の発言したあの一言がヒントになったよ」とか「重苦しい緊張が和らいだよ」ということでもよいのです。「あなたのしたことには意味があった」と伝え、理解してもらうことが重要です。
誰でもそうした声がけをされたら嬉しいものですが、社会人になって日の浅いZ世代には、視野を広げてもらうことにつながります。
所属する部署だけでなく会社全体、そして取引先も含め、自分の関わったことが大きな流れにつながっていて、そこには自分の役割がきちんとあることをわかってもらうのです。
そうすれば仕事の楽しさに気づくこともできますし、上司はそれを伝えるための声かけが大事になります。
失敗したときこそサポートする姿勢を明確に
中には頑なな人やネガティブな人もいるでしょう。仕事がうまくいったときにも、「たまたまですよ」とか、「運がよかっただけです」などの反応が返ってきたり、ほめたり評価していることを伝えても、斜に構えた態度が返ってきたりすることもあります。それでも、上司の側がそこで引いたりせず、態度を変えないことも大切です。
また、成果があったときだけでなく、うまくいかなかったときの声がけも欠かせません。日本人は「きっと本人が気にしているから、そのことには触れずにおこう」と考える場合もありますが、きちんと言葉にして、
「次はきっとうまくいくよ」 「もしわからないことがあったら、経験豊富な○○さんに相談するといいよ」
励ましや今後のためのアドバイスも一緒に伝えるとよいでしょう。仕事の全体像をつかみ、長いスパンを考えられるように導くとともに、「困ったときはきちんとサポートするよ」と明確に伝えるのです。
もうひとつ、単純なことにもかかわらず、意外とできていないのが、上司から部下に対して「ありがとう」の言葉を伝えることです。取引先には言えるのに、身近な部下には言えないのもおかしなことです。
Page 3
しかし、部下のほうは「プロジェクトを一緒にやろうと言われたのにこんなことをさせられて……」と不満が募るばかり。どんな話だったのかにもよりますし、いきなり新入社員がそんな華々しい仕事ができるはずもないでしょうが、「話が違う」という思いになるのも無理もありません。
ボタンの掛け違いがあるなら話し合いが必要ですし、目の前にやらなければいけないことがあるなら、部下のほうも考えを改めるしかないのかもしれません。
配属の話はさておき、個人にとっての仕事とはどんなものであるかを分けると、3つのカテゴリーがあり、「好きなこと」「できること」「やるべきこと」に分けられます。
仕事を選ぶとき、どんな観点で選んでいるでしょうか。
自分で仕事を選ぶ場合、「好きなこと」=「やりたいこと」が、「できること」と重なっていればやりがいにもつながりますし、なるべくなら両者が交わる部分が多いものを選ぶのがよいでしょう。
仕事なのですから「やるべきこと」という観点も忘れてはいけません。
上司であれば部下に仕事を割り振るときに、与えられたミッションにふさわしいのは誰か、部下一人ひとりの個性や適性を考えるでしょう。もちろん仕事ですから、成果を出せること、経験を積ませることを考慮して決めることになるでしょう。
「好き・できる・やるべき」の交点を探す
そうした判断をするには、日頃から部下と話す機会を持つ必要がありますし、部下が何を望んでいて、どんなことを得意としているのかリストアップしておくこと、あるいは部下本人と話し合って、すりあわせることが大事です。
写真=iStock.com/vm
※写真はイメージです
この3つは、アメリカの組織心理学の専門家であるマサチューセッツ工科大学のエドガー・シャインが提唱する理論の中で「3つの問い」と呼ばれます。仕事を選択する際に、最も大切にする価値観を「キャリアアンカー」と呼び、そのもとになるのがこれらの問いだというわけです。自分の好きなこと(WILL)、できること(CAN)、やるべきこと(MUST)はそれぞれどんなことか、というわけです。
この3つがたとえバラバラでも、どこか共通項を見出したり、あるいは近づけていくことが重要です。
私も仕事のお話をいただいたりすると、自分にとってどうかを考えます。そこで思うのは、自分がやりたいことというよりは、社会的にニーズがあって、提案をいただいたことが自分にできることであれば、求められたことをやるというのが正攻法なのではないかと考えます。
中には「好きなこと」でないとダメだというように、それを重要視する場合もあると思いますが、それでやっていけるなら、それに越したことはないと思うのですけれど、現実的にはそうはいかないこともあります。