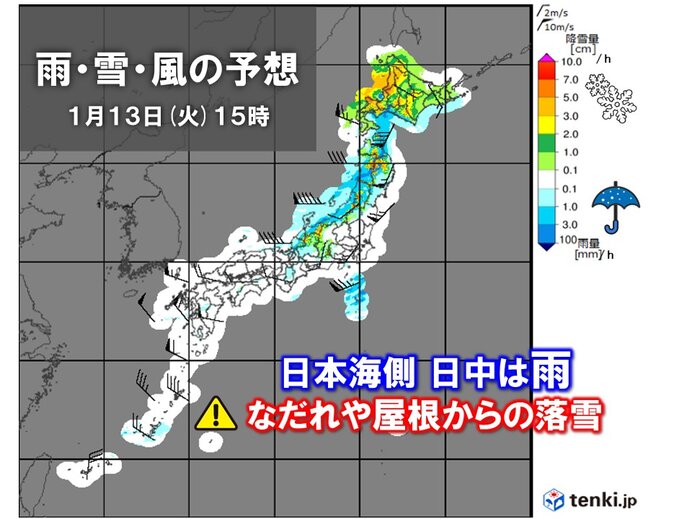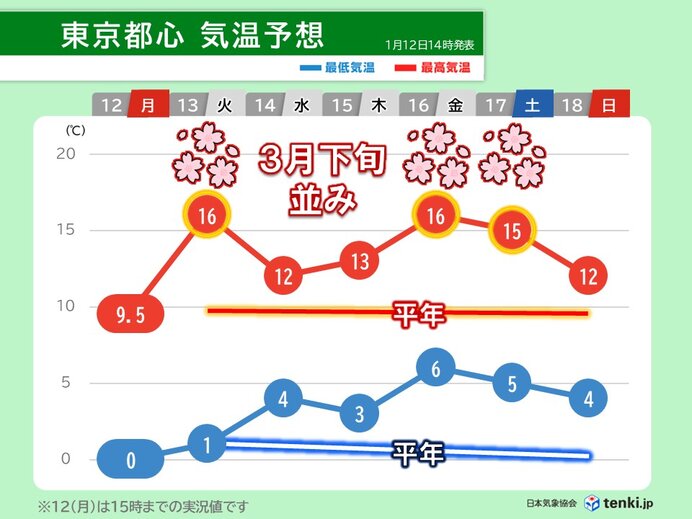自社さは「3:2:1」でも失敗 連立政治に「正解」はあるのか

55年体制が終わり、日本政治は大きな転換期を迎えています
。2012年から続く現在の自公政権も、少数与党となり、限界が見えつつあります。今後の連立政治の「正解」は何なのでしょうか。中北浩爾・中央大教授に尋ねました。
平成の政治改革の内実
日本の連立政権を考える際に起点となるのは、1993年に細川護熙政権が誕生し、38年間続いた自民1党支配の「55年体制」が終わったことです。
これ以降、一つの政党が、衆参両院で過半数の議席を獲得することが困難になりました。
日本は議院内閣制であるために、衆参両院、特に、予算や首相指名などで優越する衆院の過半数の議席を安定的に確保しないと、内閣の存立は厳しく、連立が不可欠になりました。
日本の連立政権のあり方を決める上で重要なのが、細川政権の下で行われた94年の「平成の政治改革」です。
その中心は、衆院に小選挙区制を中心とする選挙制度を導入したことでした。
「勝者総取り」で有利な作戦とは
例えば、比例代表制が中心のドイツでは、政党が別々に選挙を戦い、結果を受けて連立を組みます。
それに対して、日本の小選挙区比例代表並立制は、「勝者総取り」の小選挙区で候補者を一本化して戦う方が有利です。
従って、連立の枠組みは、基本的に選挙前に形成されることになります。
選挙協力に加えて重要なことは、安定した政策調整の仕組みを構築することです。
特に、首相を出す政党がジュニアパートナー(連立内小政党)に譲歩することが、連立政権の持続力を高めます。
非自民・非共産8党派による細川政権は、首相が一任を取り付けるトップダウンで運営され、突然の未明の記者会見で発表した「国民福祉税」構想を契機に、連立が分解していきました。
自民が譲歩した
その反省から自民、社会党、新党さきがけの「自社さ」政権は、政策決定に関わる議員の割合を「3:2:1」にするなど、自民がかなりの譲歩を行いました。
しかし、選挙協力がうまくいかず、…