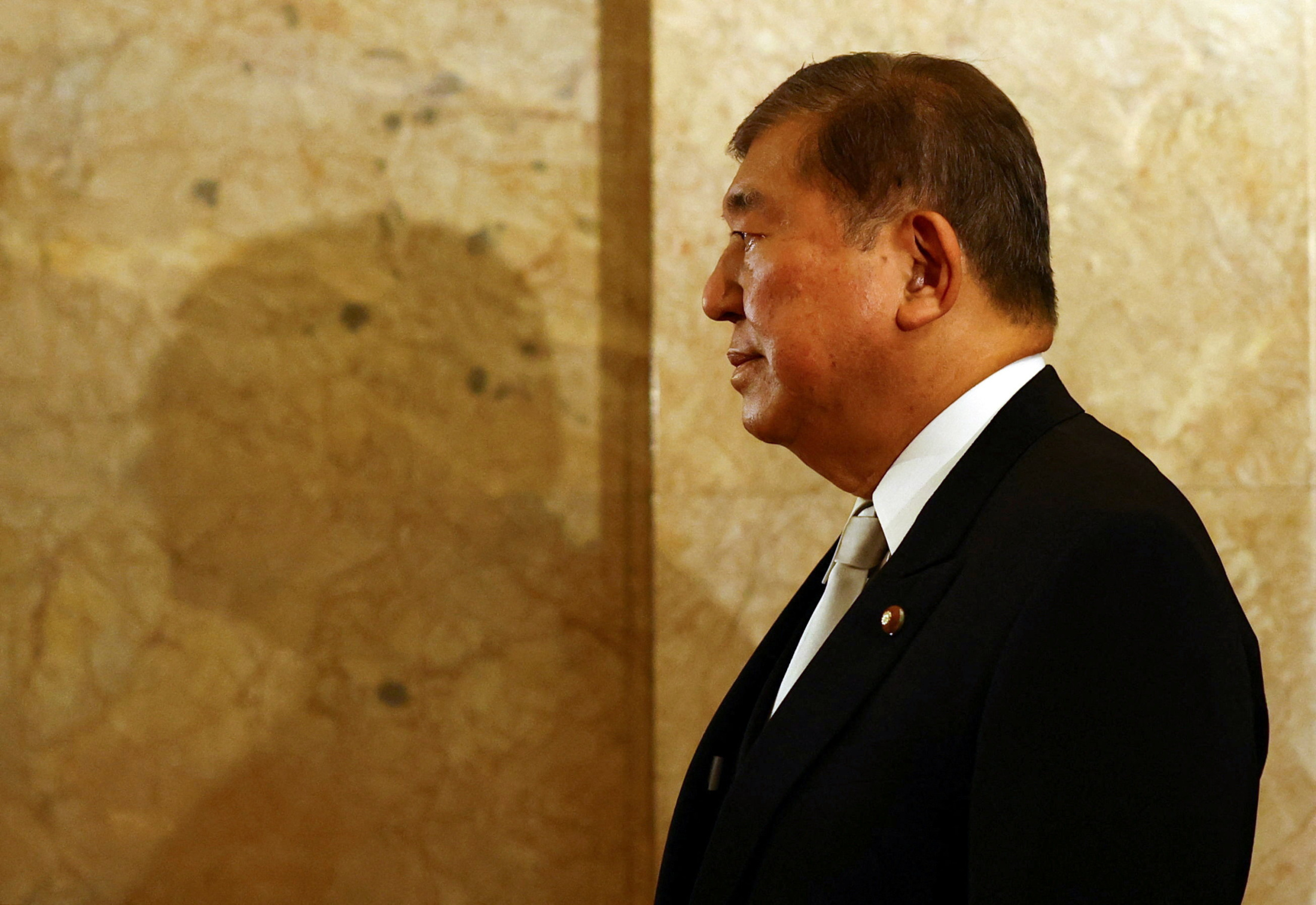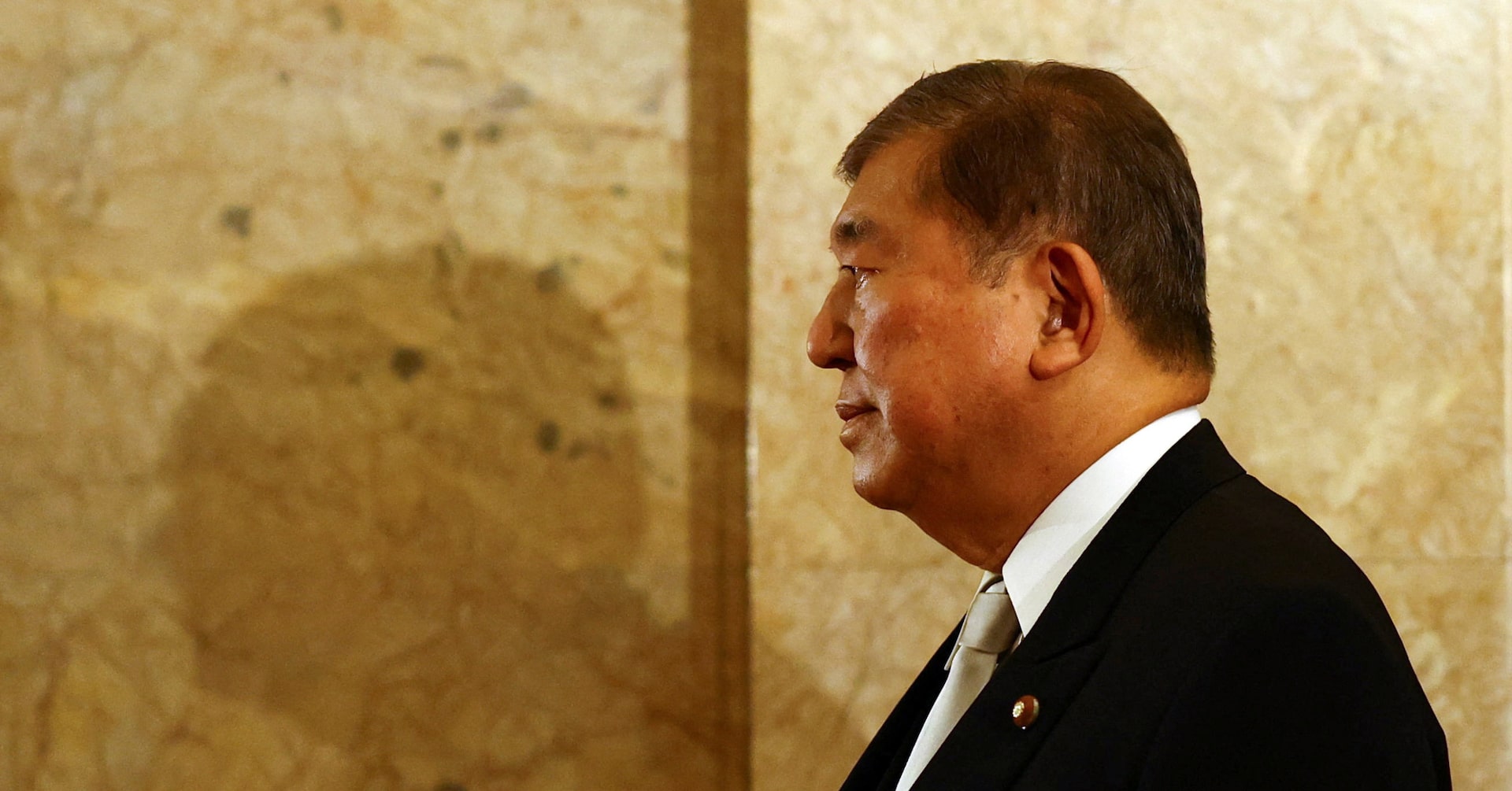世界で行われた核実験は過去80年で2000回超、各地に今なお残る爪痕

マーシャル諸島で行われた核実験の水中爆発によって立ち上るキノコ雲と水柱=1946年7月25日/Pictures from History/Universal Images Group/Getty Images
(CNN) 米ユタ州ソルトレークシティーで1950~60年代に育ったメアリー・ディクソンさんは当時、隣のネバダ州で核実験が繰り返されていることを知らなかった。住んでいた街は、大気圏内核実験による放射性降下物の多くが流れてくる風下地区にあった。
ディクソンさんは甲状腺がんになった。姉は全身性エリテマトーデスを患って40代で亡くなり、妹は最近、腸のがんが別の部位に広がっていると告知された。めいたちも健康上の問題を抱えている。
数えてみると、子どものころ近所に住んでいた人たちのうち54人が、がんや自己免疫疾患を発症したり、子どもの先天異常や流産を経験したりしているという。
がんの直接的な原因を特定することは難しいが、医学界では一般に、放射線にさらされると被ばく線量に応じて発がんリスクが上がると考えられている。
ネバダ核実験場の周りのアリゾナ、ネバダ、ユタ、オレゴン、ワシントン、アイダホ各州に住んで放射線にさらされた人々は、「風下住民」と呼ばれている。
ディクソンさんは劇作家で、核実験の被害者を代表する活動家でもある。がんが再発した友人も多いと話し、「精神的なダメージは消えない。しこりを見つけたりどこかが痛んだりするたび、再発におびえて生涯を送ることになる」と訴える。
「私たちにとって冷戦は終わっていない。今もその影響を抱えて生きている」
核の時代は80年前の第2次世界大戦末期、米軍が広島と長崎に原子爆弾を投下したことで始まった。原爆の死者は直後だけで11万人に上った。ここから動き出した冷戦期の核軍拡競争で、米国とソ連、英国、フランス、中国が強力な核兵器の開発を競い合った。
45~96年に実施された核実験は2000回以上。各国で確立された核抑止力が、現在に至るまで世界の安全保障を支えているのか損なっているのかは、見方によって異なる。
日本では45年以降、被爆時の負傷や関連する病気で数十万人が死亡したように、核実験は近隣住民の命と健康、土地に被害を及ぼした。
その後インドとパキスタン、北朝鮮も核実験を行ったが、一連の国際条約で実験はほぼ完全に禁止された。21世紀に入っても北朝鮮だけは核実験を続け、最近では2017年に強行したものの、大気圏内の実験は1980年以降、実施されていない。
とはいえ、「これは過去の問題ではない」。そう強調するのは、米カーネギー国際平和財団のノンレジデント(非滞在)フェローとして核政策を研究するトグザン・カッセノワさんだ。
カッセノワさんはCNNとのインタビューで、「核兵器が爆発してから数十年過ぎた今も、多くの人がその代償を払っている」と述べた。
「同じ物語を共有している」
初期の核保有国は、人口の少ない遠隔地とみなす場所で核実験を実施した。人口が集中する主要都市からは遠く離れた、海外領土などが多かった。
米国は主にネバダ州と、中部太平洋のマーシャル諸島。ソ連はカザフスタンと北極海のノバヤゼムリャ列島。英国はオーストラリアと、インド洋の環礁、クリスマス島(現キリスィマスィ島)。フランスは北アフリカのアルジェリアと、南太平洋の仏領ポリネシア。中国は新疆ウイグル自治区の砂漠にあるロプノールで実験を行った。
ソ連はカザフスタンのセミパラチンスク核実験場で、49~89年に450回以上の核実験を実施した。核実験のために極秘の街が建設されたが、近隣住民は「全体像をよく知らなかった」――そう語るのは、「核の正義」とジェンダー平等の専門家で、カザフスタン住民の核被害を訴えるNPO「カザク・ニュークリア・フロントライン・コアリション(QNFC)」の共同設立者でもあるアイゲリム・シチェノバさんだ。
「親族の多くは私が子どものころに亡くなった。なぜ40代や50代で死んでいくのか、私にはわけが分からなかった」と振り返る。
実験場をめぐる長年の秘密は、やがて長年のタブーとなった。しかしシチェノバさんは最近、カザフスタンの核遺産が女性たちに与えた、世代を超える影響を扱うドキュメンタリー映画を制作した。女性の主体性を取り戻そうと努めたその経験は「癒やしの過程」でもあったと、シチェノバさんは語る。
この映画は日本語に訳され、今月広島で上映された。シチェノバさんはこの時、「カザフスタン国民だけの特異な経験ではない」ことを実感したという。
シチェノバさんは「私たちは仏領ポリネシアやマーシャル諸島、オーストラリアからの同じ物語も共有している」と語り、「私たちこそが、核兵器による人道的影響の専門家だ」と強調。欧米の科学者たちが専門家を自認する一方で、「実体験がある人々の声はまともに取り合ってもらえない」と訴えた。
核実験による影響の全容はなかなか把握できない。健康上の問題についてひとつの原因を特定したり、地域社会への幅広い影響を測ったりすることは難しいからだ。
米国立がん研究所(NCI)が97年に実施した研究では、ネバダ州で51~62年に実施された地上核実験による甲状腺がんの過剰生涯症例(生涯にわたるがん発生の増加分)は1万1300~21万2000例と推定された。さらにその後の見直しで、この数は推定値の下限に位置すると結論づけられた。
セミパラチンスク実験場の周辺での研究によると、核実験が集中的に繰り返された49~62年のがん死亡率と乳児死亡率は、いずれもカザフスタン国内のほかの地域より高かった。
NCIがマーシャル諸島で実施した別の研究は、48~70年の期間に住民ががんにかかった症例のうち、0.4~3.4%は放射線被ばくが原因と推定している。「キャッスル・ブラボー」のコードネームで知られる54年の核実験で放射性降下物が雪のように降り注いだ環礁、ロンゲラップとアイリンギナの住民82人の間では、この割合が28~69%に跳ね上がる。