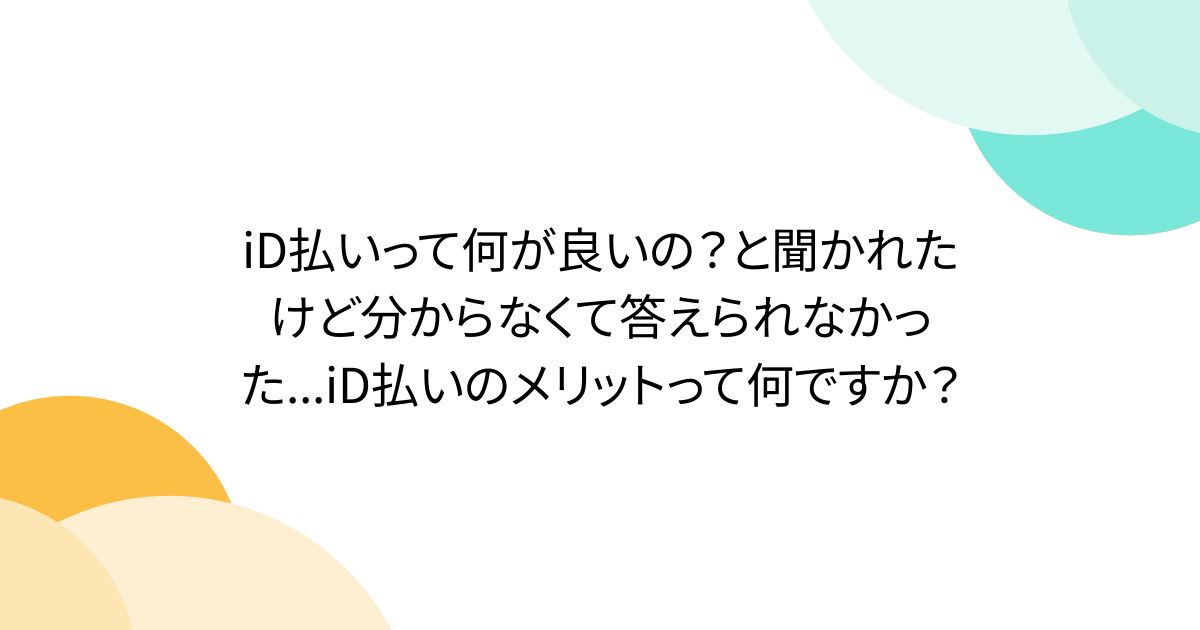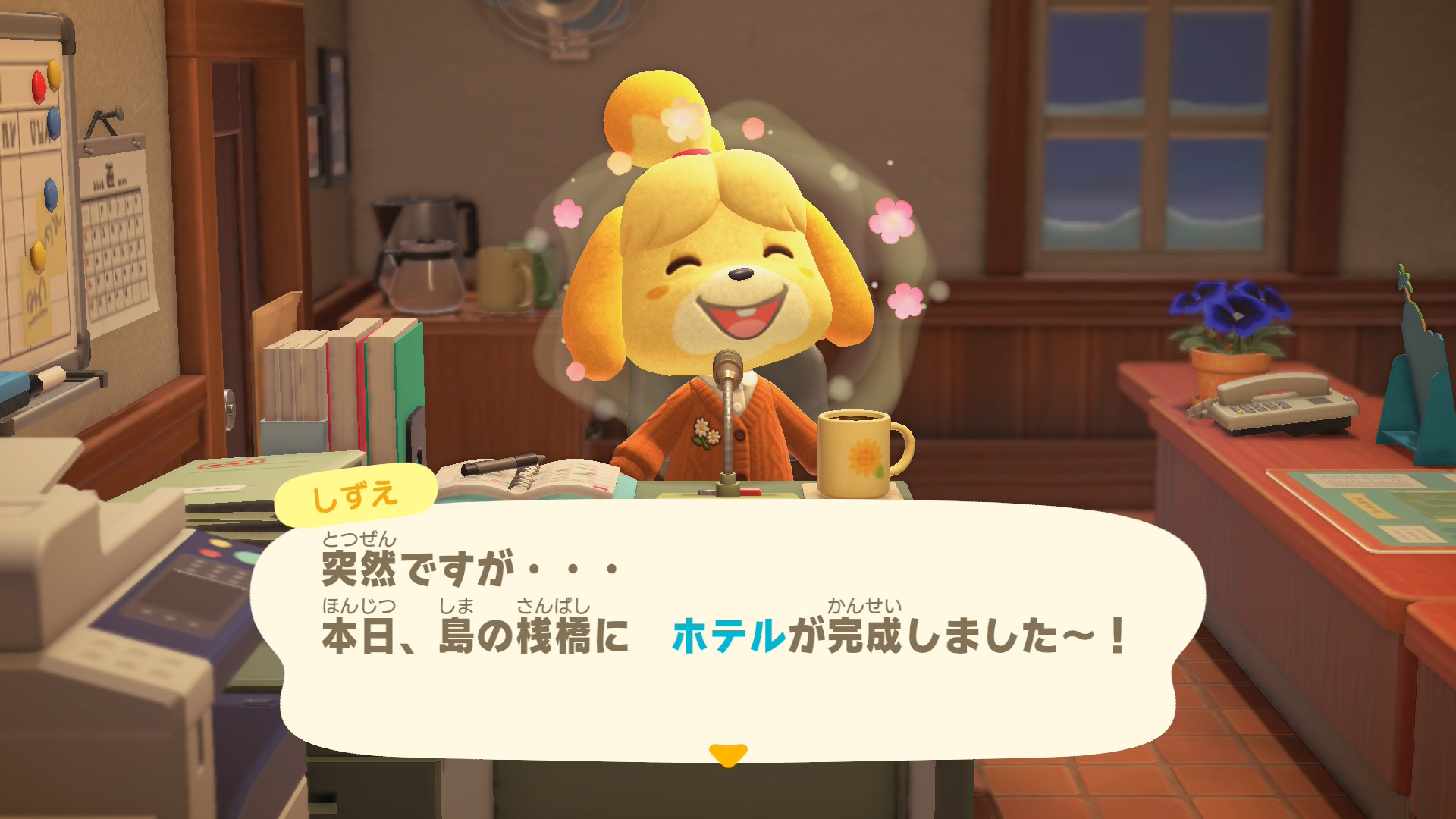「いい大学→いい会社」は本当に幸せなのか…大企業のエリートが「不安だ」「苦しい」と悲嘆する事情 会社も社員も成長できないジレンマを抱えている

なぜなら、人間はもともと危険や苦痛から逃れようとして進化してきたのに、「いい会社」になればなるほど、会社側が若手社員の苦痛や不満を少しでも軽減しようと努力し、実際そのような環境や仕組みを実現してしまうからだ。
黎明期のベンチャーのような、優しい上司も、望ましい環境も、充実した研修も、明確な仕事の役割分担もなく、少人数であらゆる業務をこなさなければ会社が回って行かないような、いわばブラックな環境に置かれたほうが、短期間で圧倒的なスキルと経験が身に付くこともある。
こうしたジレンマに対して、何かできることがないかと考えた私は、2023年の秋に「経営マンダラ」を作り、中小企業から上場企業の社長、医師、教師、弁護士、政治家などが参加する実践会を立ち上げた。
「経営マンダラ」とは、2600年続いている仏教教団(キリスト教よりもイスラム教よりも古く、世界一永続している組織とも言われている)の組織運営法と、世界一永続している会社と評される数々の日本伝統企業の永続経営の秘訣を分析して、その要素を9つのマンダラ形式にまとめたものだ。
「経営」とはもともと仏教用語
私自身、このマンダラに基づいて複数の事業を創業し、10年で事業承継し、コロナパンデミックを経てなお、それらの事業が自立的に成長している。
こんなことを書くと、「僧侶が経営?」と眉をひそめる人もいるかもしれない。
しかしあなたはご存知だろうか。「経営」とはもともと仏教の言葉である。
経営の経は、お経の「経」と書く。経とは縦糸のこと。経典にはブッダの教えが記してある。
ブッダの教えは真理だ。真理とは、「時代が変わっても場所が変わっても変わらぬ原理原則のこと」。
この真理の縦糸に、創意工夫の横糸を絡ませて、美しくて丈夫な布地を永く織り続ける営みが、「経営」なのだ。