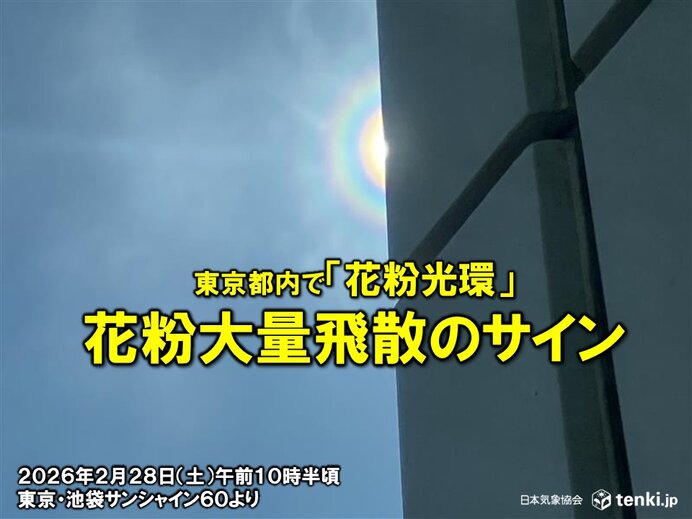塩分量の目安で続く論争、日本人はWHO値の約2倍を摂取、影響は

人間と食塩との関係は複雑だ。私たちの体が機能するためには少量の食塩が必要だが、ほとんどの人は1日の推奨摂取量をはるかに超えた量を摂取している。(Photograph by Jozef Vaclavik, Getty Images)
[画像のクリックで拡大表示]
食塩は、愛すべき、どこにでもある、なくてはならない調味料だ。必要不可欠な栄養素でありながら、取りすぎると深刻な病気を引き起こす。しかし、どれくらいの量を取れば過剰なのかについては、科学者の間でも意見が分かれている。
健康な成人の食塩摂取量について、世界保健機関(WHO)は1日5グラム未満、米国心臓協会(AHA)は1日5.8グラム以下に抑えるよう勧めている。さらにAHAは、高血圧の人には、その約3分の2にあたる3.8グラム以下を推奨している(編注:厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では男性は7.5グラム未満、女性は6.5グラム未満、高血圧および慢性腎臓病の重症化予防のためには男女とも6グラム未満を目標量としている)。
一方、米国人は1日に平均で8.6グラム、世界全体では東アジアや中央アジアの国々が数値を押し上げていることもあり、10.78グラムの食塩を摂取している(編注:厚労省の2023年「国民健康・栄養調査」によれば、日本人の食塩摂取量の平均値は9.8グラム)。
塩分の取りすぎが血圧によくないことに異論を唱える科学者はいない。しかし、どのくらい摂取すると過剰になるのかをめぐっては論争があり、基準が厳しすぎるという意見もある。WHOが2023年に発表した報告書では、データが得られた国のうち、1日の食塩摂取量がWHOの推奨する5グラム未満に収まっている国は1つもない。(参考記事:「悪玉コレステロール、「減らしすぎは悪影響」は本当か」)
塩分が体に及ぼす影響
食塩は主にナトリウムイオンと塩化物イオンからできている。そのうち、健康上の問題になるのはナトリウムだ。ナトリウムは体の水分バランスを保つ役割を担っているが、取りすぎると高血圧を引き起こすおそれがある。
ナトリウムを多く取ると、体はナトリウム濃度を一定に保とうとして水分も増やすので、血液量が増え、血圧が上がり、血流も速くなる。すると血管壁にかかる圧力が高まり、血管が硬くなる。腎臓も、血液中の余分な塩分をろ過して尿として排出するために、必死に働かなければならない。
これらすべてが心臓と腎臓に負担をかける。長期にわたる塩分の過剰摂取は、腎不全、心臓病、脳卒中を引き起こすおそれがある。また、胃潰瘍や胃がんにもなりやすいことが知られている。(参考記事:「子どもの糖類過多、悪影響は生涯に、高血圧や糖尿病になりやすく」)
塩分をめぐる論争
一部の研究者は、食塩摂取量の目標が厳しすぎると主張し、健康増進のための減塩運動に批判的だ。2013年に米国医学研究所(現在の米国医学アカデミー)がAHAの定める上限値について評価を行い、この厳しい上限値はエビデンス(根拠)に欠けていると報告した。AHAは、医学研究所が重大なエビデンスを見落としていると反論した。
スイス、ベルン大学医学部教授のフランツ・メッサーリ氏は、現在の推奨される摂取量を守るのは難しいと言う。さらに、食塩と血圧の関係は、その人の病歴やストレスレベル、職業(炎天下で働く屋外労働者かデスクワーカーかなど)、生活習慣(運動は血圧を下げる)などの影響を受けるため、単純に論じることはできないと指摘する。
メッサーリ氏らは、食塩摂取量と心血管疾患にかかるリスクとの関係はJ字型のカーブを描いていて、塩分が少なすぎても多すぎても健康被害が生じると考えている。ただし、こうした議論には反論もある。