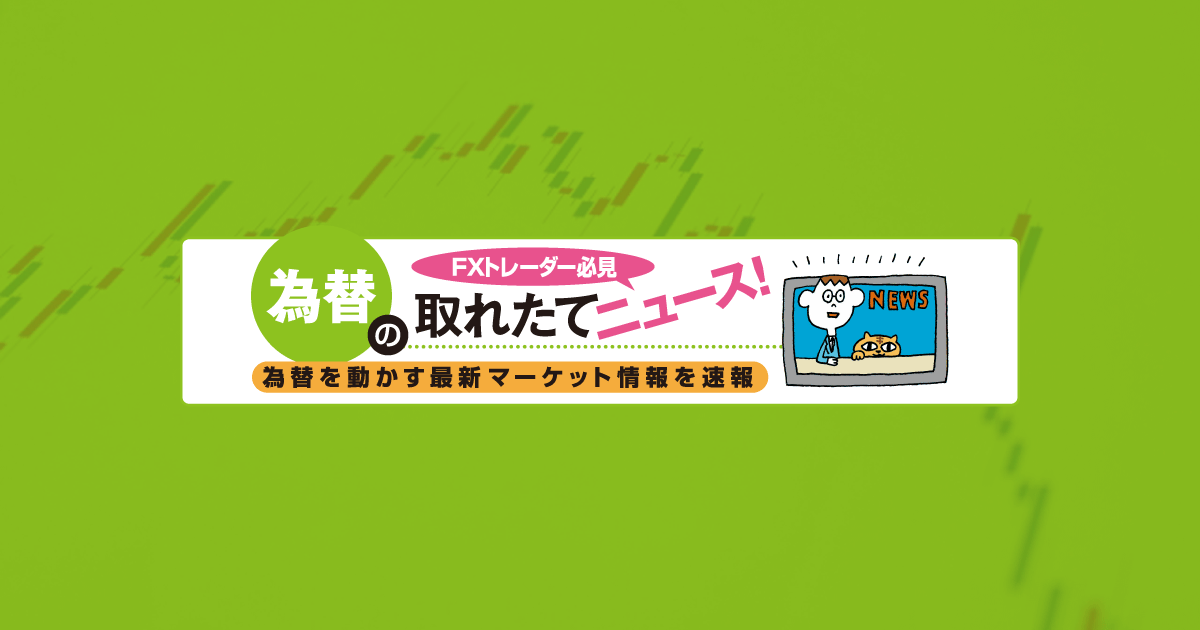日本経済は6期ぶりマイナス成長へ、高市政権の積極財政方針を後押し

日本経済は7-9月期に失速し、6四半期ぶりのマイナス成長に転じたと大半のエコノミストは予想している。「積極財政」を掲げる高市早苗政権にとって、大規模な経済対策の策定を促す材料となる可能性がある。
内閣府が17日発表する実質国内総生産(GDP)速報値は、ブルームバーグのエコノミスト予想(中央値)で前期比年率2.4%減と、2023年7-9月期以来の落ち込みが見込まれている。13日時点で22人中19人がマイナス成長を予想。前期比は0.6%減を見込む。米関税に伴い輸出が減少、住宅投資や設備投資が低調だったとみられている。
政府は「景気は緩やかに回復している」との認識を維持しているが、物価高の影響でGDPの過半を占める個人消費は力強さを欠き、生活向上を実感しにくい状況が続いている。「強い経済」の実現に向けて月内にも経済対策を取りまとめる高市政権にとって、マイナス成長に陥れば積極財政を正当化する要因となり得る。
明治安田総合研究所の小玉祐一フェローチーフエコノミストは、景気は拡大基調にはあるものの、7-9月は「全体的に少し弱めの推移が続いた」と指摘。マイナス成長は高市政権にとって「大型の景気対策を打ち出す理由付けにはなるだろう」との見方を示した。
ブルームバーグ調査によると、輸出から輸入を差し引いた外需寄与度はマイナス0.3%。設備投資は前期比0.1%減と4四半期ぶりのマイナス、個人消費は0.1%増と前期(0.4%増)から鈍化が予想されている。住宅投資は、4月の建築基準法・省エネ法改正前の駆け込み着工急増の反動による影響で大幅なマイナスになったもようだ。
新家義貴シニアエグゼクティブエコノミストは11日付リポートで、住宅投資は前期比11%減でGDPの前期比年率を1.5ポイント押し下げると予想。住宅投資の悪化は一時的で、輸出も反動減などの要因があるため、7-9月のGDPを過度に悲観視する必要はないが、実体経済は力強さを欠くことを再確認するとみている。
焦点は規模
市場では経済対策の規模に焦点が移っている。強い経済の構築を目指す高市首相は所信表明演説で「戦略的に財政出動を行う」考えを表明。自民党の小林鷹之政調会長は11日、経済対策について「相応の規模」にしたいと述べた。
経済財政諮問会議の民間議員に起用された第一生命経済研究所の永浜利広首席エコノミストは、12日開催の同会議への提出資料で、経済対策は昨年度の約14兆円を上回る規模でなければ、積極財政への期待が低下する可能性があるとの見方を示した。
関連記事:経済財政諮問会議の民間議員に若田部氏や永浜氏ら-リフレ派を起用
石破茂前政権が昨年11月に策定した総合経済対策では、財政支出の規模は21兆9000億円。財源の裏付けとなる24年度補正予算は一般会計で約13兆9000億円だった。
小林政調会長は12日の定例会見で、経済対策について来週中に党内で政審・総務会を開き、閣議決定を目指したいとの意向を示した。
明治安田総研の小玉氏は、「積極財政というからには、昨年を上回らないと市場は拍子抜けということになる」と指摘。「良いか悪いかは別として、市場はやはり大型の景気対策を期待している」と語った。
ブルームバーグが先月実施した調査によると、補正予算の規模についてエコノミストの予想中央値は15兆円だった。
利上げシナリオ
7-9月期のGDPがエコノミストの予想通り縮小しても、日本銀行は経済見通しをほぼ据え置くとみられている。日銀は先月公表の経済・物価情勢の展望(展望リポート)で、25年度のGDP見通しを0.7%増と、従来の0.6%増から引き上げた。
大和総研の神田慶司シニアエコノミストは、プラス成長が続いてきたためやや一服感が出ているが、「景気が後退するということではない」と分析。むしろ物価高が続いていることなどを踏まえると、日銀は「12月あるいは1月に利上げするというスケジュールは変えないのではないか」と述べた。